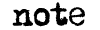「乙葉旭は!?」
「心配しなくていい」
栞子を背に乗せた焔は、公園で一番高い木のてっぺんの上に舞い降りた。
「見ろ、あそこだ」
木立が円を描いて囲むその中心に小さな池があった。公園の砂場くらいの大きさだ。黒く濁った水面から何十本という蔓が這い出して、旭の方へ向かっていく。このままでは全身に絡みつかれ、あっという間に池に引きずり込まれるだろう。
旭は構わず進んでいく。
「あぶない!」
焔の白い毛を栞子の細い指がきゅっと掴んだ。
「いってえな」
「ごめんなさい。でも」
「まあ見てろよ」
蔓の先端が旭の爪先に触れた。
その瞬間、まるで電気を帯びたかのように蔓はびくりと震えて停まった。戸惑うように揺らいだあと、進路を変えて再び走り出す。
次々に向かってくる蔓が、旭を避けていく。
木のてっぺんにいた栞子には、まるでそこに見えない壁でもあるかのように、旭の前に空間ができていくのが良く見えた。
旭は未だ、足を止めてはいない。ゆっくりと歩いていく。
「どういうことなのでしょう」
「あの程度のあやかしなら、旭には触れることすらできないだろうな」
「あれが、乙葉旭の力……」
賞賛とも驚きともつかない溜息が栞子から漏れた。
「あんなもんじゃない」
そう呟いた焔の声音には、旭を誇らしく思う気持ちと同じ大きさで、畏怖の念も含まれていた。
旭はまっすぐに池に向けて歩いていった。
雨はどんどん強くなり、シャワーを浴びているかのような状態だった。
前髪はぴたりと額に張り付き、流れをつくる。ダッフルコートはずしりと重みを増した。
豪雨のために視界は霞んでいたが、その先には確かな気配があった。
一歩進む毎に、それは濃くなった。
肌を圧迫するくらいに、強い想いだ。全身を打ち付ける雨からも感じる。
憎い。
忌まわしい。
厭わしい。
何かに強く反発する想いが旭の中に流れ込んでくる。
遊歩道を逸れ、木立の中を進んだ。
池はすぐそこにあるはずだ。
標的をなくした蔦は、公園をすっぽりと覆うあやかしの結界内で行き場をなくし、絡み合い、黒々と積み重なっていく。
池の縁で立ち止まると、旭は腰をかがめた。
手を伸ばして池から這い出す蔓の一部に触れる。
「もういいよ」
たった一言、囁くように言った。
それだけだった。
何十杯ものバケツの水をひっくり返したような音が公園に響いた。
さっきまで地を覆っていた蔓は、一瞬で形を失い、水となり崩れ落ちた。
あまりの水量に、結界に包まれた公園全体が踝まで浸かる巨大な水たまりと化した。
「何をしたの?」
栞子が興奮した声で言った。
「願っただけだ」
「願う? 何を?」
栞子の問いに答えはなかった。
そのとき、ドーンという地響きとともに、池から水柱が上がったのだ。
まるで竜のごとく空へ駆け上がった水柱が旭に襲いかかる。
真正面から受けた旭の体が突き飛ばされた。
巨大な水たまりを、旭の体が滑っていく。灌木の植え込みにバキバキと埋まる形で止まった。
「旭!」
焔が叫んだ。
旭は手だけをあげて答えた。
「大丈夫。繋がったから」
体を起こし、灌木の枝の中から抜け出した。
むき出しの手や顔に小さな傷がついたが、構わずに再び池の縁に立った。視界を遮る濡れた前髪を掻き上げる。雨は未だ降り続き、池の水面はちゃぷちゃぷと音をたてながら苛立つように揺れている。
その色は墨に染まっていた。
憎しみの色だ。
「悲しい、辛い、苦しい」
旭が言葉を紡ぐ。
黒々としたさざ波の中にわずかな蒼が見え隠れする。
「寂しい、悔しい、淋しい」
水を通して旭の中に流れ込んでくる想いを、言葉にする。
旭は今、あやかしの心を読んでいた。
あやかしは、動植物よりはかなり人に近い。
意思を持ち、欲望に従い生きる。
人間とあやかし。
一つの世界に二つの支配者がいればどうなるか、それは誰の目にも明らかだ。互いに自分たちの身を守ろうとする。結果、奪い合う。だからこそ、昔から人との接触は途絶えなかった。
けれど旭は知っていた。
焔というあやかしとともに暮らしながら、彼らにも心があるということを学んだ。違うのは、その価値観であることに気づいたのだ。
彼らの想いを聞きたい。
力で封じる前に、彼らの声を聞きたい。
幼い頃から望んだその願いは、能力となって現れた。
旭は、あやかしたちの小さな声を聞く耳を得た。
少女のかじかんだ指先に気づくのと同じ心で、旭はあやかしたちの叫びを聞く。
池に住み着いたのは、かつてここにあったという屋敷の子供だった。
人があやかしとなったのではなかった。元々、屋敷に住んでいたのが、人間のふりをしたあやかしたちだった。彼ら一家は、人に交じり、のんびりと暮らしていた。
ある日突然、手柄を狙う退治屋の一人が屋敷の気配を嗅ぎつけ、一家を襲った。
家族の一人は退治屋に消された。
二人は逃げた。
一人だけ、逃げ遅れたものがいた。
まだ子供だった。
彼は池の底に姿を隠した。
そして待った。
退治屋が戻ってくる日を。
復讐を遂げるその日を。
池の底で眠りながら、もう二度と会えないだろう家族を夢見て、待っていた。
やってきたのは、まだ幼い退治屋二人だった。
「それから……会いたい」
一番最後に現れた、一番強い想いが旭の唇から紡がれる。
震えていた池の動きが止まった。
旭は池の縁に屈んだ。
そっとのぞき込むと、遠く暗い水底で小さな子供が旭を見上げていた。必死に旭を睨んでいた。
「ずっと一人でがんばってきたんだね。きっと会えるよ。今度はぼくが君の家族を探すから。約束するよ」
小さな子供は、今にも泣き出しそうな顔で、唇をぎゅっと結んだ。
その心が水面を小さく振るわせる。
旭の手のひらが、子供の頭を撫でるように優しく水面に触れた。
「もういいんだよ」
膨らました袋が破裂するような乾いた音とともに、暗く淀んでいた空がはじけ飛んだ。
公園を覆っていた渦巻く雲はもうない。眩しいくらいの冬晴れの青空が広がる。水浸しだった公園は元に戻り、池はきらきらと陽光を弾いている。
池の水は澄んでいた。
底はどう見ても三十センチ程度の深さしかなく、小さな子供の姿は消えていた。
代わりに、水底には小さな鯉が円を描いて泳いでいた。
「終わったか」
旭の隣に音もなく焔が舞い降りる。
その背から栞子が飛び降り、池の底を覗いた。
「あの小さな錦鯉が妖怪の正体でしたの。あなたは一体、何をなさったのですか?」
旭は恥ずかしそうに小さく「何も」といった。
「でもあやかしは大人しくなりましたわ」
「俺が説明してやる」
さっきの続きだと、焔が話を始めた。
「人間は人間から生まれるが、あやかしは違う。光や闇、水、風、土、火、植物、動物、あるいは人の作った物から生まれる。生まれたときからあやかしだったものや、なにかが変化してあやかしになったもの、神や人があやかしに成り果てたものなど、その成り立ちは多数ある。これがあやかしの定義だ。旭は元の姿に還れと願う。それだけだ」
「そんな闘い方が……」
「闘うんじゃない。さっきも言っただろう? 旭は闘わないって」
「ぼくには闘う手段はないです。イレブンの修行でもいつも落ちこぼれだった。栞子さんのように能力を具現化することはできません。ぼくにできるのは、彼らの声を聞くだけ。聞いて、それに答えることだけです」
栞子がひどく驚いたように、猫のように大きな目をさらに大きくして旭を見た。
「あなたはこの妖怪の言葉を聞いたというのですか?」
正確には、あやかしの心や記憶を感じ取るのだが、説明が難しいのでこくんと頷いて肯定する。
「元々、ここにあったお屋敷に住んでいたんです。退治屋に家を焼かれて、家族と離ればなれになって、そんなふうにしたぼくら退治屋を恨んでいたみたいだ」
「じゃあ退治屋の力を持つ私たちがここへやって来たことに気づいて襲ってきたというのですね。これがもし普通の人間だったら、何もしなかったのでしょうか?」
「そうじゃないかな。たまたま感受性が強い人にはこの子の姿が見えて、噂になったんだと思う」
「つまり襲ってくるには理由があったってことですわね」
「うん」
旭が笑った。
とても嬉しそうに笑った。
栞子が初めて見る旭の笑顔だった。
「で、どうするんだ?」
「この子の家族を探す。風の便りに京都の方にいるらしいってのまではわかっているんだって」
「どうやって探すんだよ。京都往復するだけで、どんだけ金かかんだよ」
「それは、焔がひとっ飛びってことで」
「おれは新幹線じゃねえ」
「いたたたっ! 痛い痛い、噛まないで!」
旭と焔がじゃれている間、池を見ていた栞子が「あら」と声をあげた。
「この鯉の模様」
「え?」
「背びれの付け根に三日月のような模様があるでしょう?」
「あ、ほんとだ。気がつかなかった」
「三日月のついた鯉が京都のお寺の池にいるって、話題になったことがありましたの」
栞子が帯の中から携帯を取り出して、調べようとした。
「電源が入らないわ」
「あれだけ濡れればね……ぼくのもダメだと思うな」
不思議と公園は乾いていたが、旭と栞子は全身ぐっしょりのままだった。
二人で携帯の真っ黒な画面に視線を落とす。
「家に帰ったらパソコンで調べてみるよ」
旭は携帯をコートのポケットに戻した。
「乙葉旭」
「はい」
「私が調べてもいいかしら? 私の家は神戸なのです。京都ならそんなに遠くないですから、実際に行って確認してこれますわ。近くまで行けば妖力があるかもわかりますし」
「それはすごく助かるけど……でも、どうして? 昨日は妖怪は敵だって言っていたのに」
「それは……」
「……さまあ〜……お嬢様〜!」
突然の乱入者によって、栞子の声は遮られた。
「ああ! こんなにびしょぬれで! 何があったんですか!」
「あら一条。今までどこに?」
一条は手に黄色のリボンを握りしめていた。
「あらではございません! めくらましの術まで使ってお嬢様がお逃げになったので、後をつけさせていただいたのです。公園の外で様子をうかがっていれば、突然、結界が現れて中に入れず、外からずっと叫んでおりました! リボンだけが風に乗って飛んできたときには、もう息が止まるかと!」
「ちょっと遅いんじゃないか? 護衛なんだろ?」
いつのまにか人型に戻った焔がにやにや笑っている。
「入りたくても入れなかったんだ!」
「その程度だから、使われるしか能がないんだよ、おまえは」
「おまえだって乙葉の犬になったんだろうが。その札!」
一条が焔の胸のあたりに指を突きつける。そこには銀の識別子が下がっている。
焔はにやりと笑って、突きつけられた一条の手首を掴んだ。
「あ! 離せ!」
一条の抵抗を無視してスーツの袖をまくり上げる。出てきたのは銀の腕時計――否、その文字盤には識別子が埋め込まれていた。
「一条さんって、もしかしてあやかしだったんですか!?」
旭が驚きの声をあげる。
「しかもその昔はおれの眷属だったんだぜ」
「つまり狐ってこと?」
そうそう、と焔はにやにやと笑う。
「あれは仕方なかったんだ!」
「あら、そうでしたの。だからそんなに仲が良いのね」
「お嬢様、それは大きな勘違いです!」
乾いた空に、焔の笑い声が響いた。
「っくしゅん」
「お嬢様! このままでは風邪を引いてしまいます! すぐに帰りますよ!」
一条は栞子を抱えると、挨拶もなしに慌ただしく去って行った。
妖狐というのはみな、過保護な性質なのだろうかと、旭はふと思った。
「乙葉旭! また会いましょう! 私、諦めませんから! 必ずあなたを夫にしてみせますわ〜」
「……だってさ。どうする? 旭」
「別にどうにもしない。結婚だなんて早すぎるし」
「あ、おまえ、もしかしてあいつのこと、気になるんだろ〜」
いつもなら軽く流すか、完全否定するだろう旭が、小さく微笑んだのを焔は見逃さなかった。
旭の瞳は、栞子たちの消えた方を見ている。
「……悪い人じゃないよ。蝶みたいで綺麗だ」
「は?」
焔が口をぽかんと開けたまま旭を見下ろした。
「くっしょん!」
急に寒気がやってきたのか、旭は両腕で自分の身体を抱き込んだ。
「帰るぞ。おまえが風邪引いたら、とうちゃんに殺される」
「だから、お父さんはそんな人じゃないって」
「おまえが知らないことは、まだまだいっぱいあるってことだ。乗れ」
「新幹線は嫌なんじゃなかったの」
「どのみち、そのかっこじゃ電車は乗れないぞ」
一瞬で白狐に変化する。
その背にしがみつくと、焔はすぐに地面を蹴った。
風を切って跳んでいるはずなのに、不思議と寒くはなかった。
旭は太陽の匂いのする白銀の毛に、顔を埋めた。
【Beginning - 蝶は真冬に舞い降りた(5)エピローグへ続く】