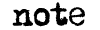期末試験最終日を明日に控えた夜。
「中間テストがないって喜んだことを訂正する」
居間の卓袱台に広げた教科書とノートとプリントの海に旭は突っ伏した。
「昨日もあんまり寝てないのに、世界史とか範囲広すぎてもう無理」
「なにを今更焦ってんだよ。毎日の授業と鬼のような課題をこなしてれば自然と頭に入るだろうが」
しれっと言い退けたのは畳の上に寝転がって余裕綽綽とハードカバーの本を読み耽っている焔だ。
白峰学園高等部一年B組出席番号一番。
学年一のモテ男は、十八歳だけど英国からの帰国子女なので高一に編入しました〜、というのが表向きの設定だが、その真の姿は五百歳の妖狐である。もちろんクラスメイトは焔の正体を知らない。入学式初日から焔に群がる彼女たちは、彼の溢れる妖力に知らぬままに魅せられているに過ぎない。
「いいよねえ焔は。モテモテな上に、一度見たものはぜ〜んぶ覚えちゃうんだから」
一方、一年A組に属する乙葉旭は正真正銘十五歳の人間男子で、クラスに沈み込んだ凡人である。
「できない方がおかしいだろ」
「普通の人間はそんなことできないの。妖怪と一緒にするな」
旭の投げた消しゴムを易々と片手でキャッチした焔は、読んでいた本をぱたむと閉じて諸手を上げた。
「わかったよ、付き合ってやるって。そんなに眉間に皺寄せてると取れなくなるぞ」
「焔が原因なのわかってる? 自分だけゴロゴロしてさ。試験中なんだよ? 学生なんだよ?」
ただの八つ当たりだとわかっているが止められない、そして止める気もなかった。それは焔の役目だ。
「はいはい、わかりました。まずは夜食からな。腹が減ってるからイライラするんだぜ。すぐに用意してやるから待ってな」
顰めっ面の旭の頭を軽くくしゃりと撫でて、焔はキッチンへ向かう。
五分と待たずに漂ってきたのはバターの匂いだ。
進まない試験勉強のせいで腹立ちまぎれに焔に当たってしまったというのに、旭の顔には小さな笑みが生まれていた。
焔が触れた前髪を摘まんで引っ張っている。
また少し伸びてきている。五月の連休中にあまりの暑さに自分で切ったのだが、長いところと短いところが入り乱れてざんばらだ。長い方はすでに鼻先まで届いていた。
「少しは戻れたのかな」
旭の髪をくしゃりとするのは焔のくせのようなものだ。
こんな風に自然に焔が旭に触れたのは、いつのことだったろうか。
ある出来事をきっかけに、旭は妖怪退治屋という家業から逃げ出し、普通の高校生としてどうにか新しい生活を始めたのは、この春のことだ。それまでの一年間、自分の中に深く閉じこもっていた旭が高校に行けるようになったのは、焔と、この家を提供してくれた紫葉栞子、二人のおかげだった。
しかしその出来事の爪痕は深く、旭は人に触れられることをひどく嫌った時期があった。そんな旭を気遣い、焔がふと伸ばしかけた手を握り込んで止めるのを、旭は幾度も見てきた。その度に胸の奥がちくんと疼くのをどうすることもできなかった。
焔の触れた額の辺りには、まだ少しその指の感触が残っている。
「ほんとに久しぶりなんだ」
はふうと息を吐いて床に寝転んだ。
にやけてしまう口元を隠すように腕で覆う。
躊躇いなく焔が触れてくれた。たったそれだけのことが心を震わせる。
いつのまにか、自分で張り巡らせたバリアは解けていた。明確なきっかけなど、恐らくなかっただろう。あるとすれば、それは時の流れだけだ。
ゆっくりと穏やかに、時に賑やかに過ぎていく時間の中で、焔はずっと待っていてくれた。
旭が元の場所に戻ってくる日を、決して疑うことなく。
ずうっと。
「こら! 潔く教科書、放棄してんじゃねえよ」
寝転がったままの頭を軽く蹴られた。気づけば、盆を片手に持った焔が真上から旭を見下ろしている。
「ちょっと! 痛いんだけど!」
「おまえがアホ面してるからだ。何、にやついてたんだ?」
「っみ、見てたの?!」
旭が慌てて起き上がる。
「お〜、見てた見てた。きゃ〜っどうしようっ好きな人に好きって言われちゃった〜て感じだった」
「言われてないし」
「お、好きなやつはいるんだ?」
「いるよ」
「え?」
持っていた盆を卓袱台の上に置いたところで、焔が固まった。いつもの旭なら「そんなのいるわけないし」と冷たくあしらうところだ。
「いるよ」
「え?」
「ずっとそばにいてくれた人。大好きで、大切な人だよ」
「えっと、それって誰かな?」
焔の顔が微妙な色に染まる。
「アホ面は焔の方だ」
「だから誰だよ、まさか栞子か?」
焔の狼狽え方がおもしろかったので、しばらくこのままにしておこうと思った。
「あ! ホットケーキだ! 美味しそう。トッピングは?」
「メイプルシロップとホイップクリームとバニラアイスですが……って誰だよ!」
「教えな〜い。いただきま〜す」
五段に積まれたホットケーキの優しい色合いに思わず目を細めた。
焔の手料理はいつでも温かく優しい。終わりの見えない試験勉強も些末なことに思えてくるから不思議だ。
口の中でバターとシロップとバニラアイスのハーモニーがじわりと広がると、焔が髪に触れたときのように、胸の辺りが小さく震えた。
これも妖力だというのなら、それでもいい。
幸せな気持ちを厭う人はいないのだ。
焔を取り囲むクラスの女子たちの気持ちが、少しだけわかった気がした。
「ウマイか?」
問い詰めることを諦めたのか、焔もホットケーキをつまんでいる。
「美味しいよ……ありがとう」
心のままに伝えたら、なぜか焔が真っ赤になった。
旭は小さく笑いながら、「食べ終わったら、世界史の山当ててよ。もうお手上げ」と我が侭を言ってみたら、赤い顔のまま頷いた。
広い庭からじーじーと虫の鳴く音が聞こえる。
夏の音だ。
試験は明日まで。
夏休みはもうすぐそこまで来ている。
(了)