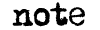平凡な下校途中に起こった出来事は、まるで突然の嵐に巻き込まれたごとく、旭を激しく疲弊させていた。
暗い湖底へと沈み込んでいく心に引きずられるように、重さを増すばかりの身体は、辛うじて焔にしがみついた状態で家にたどり着くや否や、自分の意志では動かすことができなくなっていた。
旭はベッドに倒れ込んだまま、沢山の蝶が羽ばたくのをぎゅうと閉じたその瞼の裏で感じていた。蒼い鱗粉をまき散らし、ばさばさと音をたてて飛び立っていく何千という蝶が、旭の少女への行為を責めているようだった。
制服がシワになると、瞼を落とした旭の傍で焔が言っていたけれど、応える力もなかった。
どうせ明日から、冬休みだ。
制服がシワになろうが構うものか。
旭は無意識に手足を縮込めた。
ただ眠りたかった。
眠って、忘れてしまいたかった。
いとも簡単に、人を殺そうとしたことを。
そんな力を自分が手にしていることを。
適うことならば、乙葉旭であることさえも忘れて、妖怪とも退治屋とも関係のない普通の中学生として生きてみたかった。
けれど、旭の中に流れる血の一滴までもが、それを許すはずもないことを、嫌というほど理解していた。
あやかしは存在する。
太古から、日本に変わらずに存在するあやかし、あるいは妖怪。
人に害をなすそれらを処理するための特殊機関がある。国家公安委員会第十一特別外局、通称【イレブン】。
そこでは、あやかしを制御する特殊な力を持つ人々を【士】と呼ぶ。年齢に関わらず、その能力を発した時点でイレブンに登録される。その数、全国に約五千人。大抵の場合その力は、親から子へと血によって受け継がれる。
活動の特殊性ゆえに、イレブンの存在は公にされていない。東京のどこかにその本部があるといわれるが、その場所を知る者は、そこへ入ることを許された士と、日本という国の中枢にいる数人だけである。
そして、乙葉旭もまた、両親から受け継いだ血によって、イレブンに縛られ、学業の傍らその任を務める者の一人なのだ。
幾夜、眠り続けようとも、その血に刻まれた定めが消えるはずもなく、旭は昨日の旭のまま、目を覚ました。
すでに夜はすっかり明けて、カーテンの向こうは陽の光に溢れているようだった。
時計を見ると八時を少し回った辺りだった。
のろのろと身体を起こす。
学ランだけは焔が脱がせてくれたのだろう。椅子の背にかけてある黒い上着を見つけた。
制服のシャツとズボンは案の定シワシワだったけれど、このままクリーニングに出そうと脱いだものを丸めて袋に突っ込んだ。
冬休み一日目。
本来ならば、クリスマスと正月を迎えるこの季節、浮き立つ心地の一つや二つあるはずだが、旭の中に住み着いた憂いは、眠っている間に冷たい氷の結晶となって深々と突き刺さっていた。
「おはよう、旭」
重い身体を引きずってようやく居間に入ると、旭の祖母・日向が食卓でコーヒーを飲んでいた。
「おはよう、おばあちゃん。今日も仕事?」
日向はすでに身支度を調えていた。白髪一本もない髪を綺麗に結い上げ、グレーのスーツに身を包んでいる。きっちりとメイクされた顔は、中学生の孫がいるようには見えないほど若々しい。
「社会人は学生と違うんですよ。今週いっぱいはまだ仕事です」
旭の両親は二人ともイレブンの士である。
父は、東北の退治屋の一族の出身で、家業の古本屋を営むために単身、東北の地に暮らしている。もちろんただの古本屋ではない。本はあやかしを捕らえるために使うのだ。母は、乙葉家の一人娘で、エース級士として全国を飛び回っていてほとんど家にいない。この冬休みは、久しぶりに父と過ごすために早めに休みをとって父の元へ行っている。
そんな家庭で旭を育てたのが母方の祖母である日向だった。
日向はイレブンの創立に携わり、旭が小学校に入った頃からイレブン局長を務めている。家でも外でも厳しいので有名だ。それは日向の立ち居振る舞いにも現れている。
「ばあちゃん、迎えの車、来たみたいだよ」
キッチンから人型に変化した焔が出てきた。
ぼさぼさの茶髪に、よれよれのTシャツ、穴の開いたのジーンズといういつもの格好だ。黒のカフェエプロンが良く似合っている。
祖母が忙しい日には、食事を作ってくれる。
「ありがとう、焔。ごちそうさま。いってきます」
「いってらっしゃい」
「帰りは遅くなるから、夕飯は先に食べなさい」
「わかった」
「それから、焔、あれは図書室に出しておきましたから」
「サンキュ、ばあちゃん」
祖母と焔のやりとりをぼんやりと聞き流しながら、旭は自分の席についた。
「旭、目玉焼き食うか?」
黄色い黄身が軽い吐き気を誘発したので、首を振って不要の意志を伝えた。
普段から大食いするタイプではないが、今朝の旭にほとんど食欲はなかった。
「じゃあスープだけでも飲めよ。今日はおまえも仕事だろ? 腹が空いてたら、いざってときに体が動かなくなるぞ。妖怪退治は体が資本だからな」
まるで自分が妖怪であることを忘れているかのような焔の発言に、ほんの僅かだけ笑みがこぼれた。
そういえば任務があったと、ついでのように思い出す。
すでに士の資格を持ちイレブンの任務についているが、見習いのため調査活動がメインだ。
ネットの掲示板などに書き込まれた超常現象を洗い出し、情報調査の担当者が本物っぽいものを発見すると、旭のような見習いが実際にその場所に行き調査する。もし超常現象が妖怪によるものであれば、改めて大人の士が送り込まれ、しかるべき処置を行うしくみだ。
「今日は何の調査だ?」
キッチンから声がした。
仕事の指示は、昨日の朝、携帯のメールアドレス宛に届いていた。
焔から問われて内容をきちんと覚えていないことに気づき、旭はポケットに入れていたスマホを取り出した。
「本町駅の公園にある池がターゲット」
「電車で二駅か。そんなに遠くないな。で、何が出るって?」
「池は底無しだとか、池に落ちて行方不明になった子供がいるとか、覗くと底の方で子供が眠っているのが見えるとか、そんな感じ」
「底無しなのに、底で眠ってる子供? なんか矛盾してるな」
「都市伝説なんてそんなものだと思うけど」
携帯で指示メールを確認していた旭の前に、湯気の立つスープの椀が置かれた。透き通ったスープの中に、色とりどりの角切り野菜とソーセージが入っている。立ち上る湯気に混じる匂いをかいだら、急に空腹を覚えた。
用意されたこの温かいスープは、昨日の昼過ぎからベッドから出てこなかった旭を、彼がとても心配している証だろう。
妖怪である焔が、妖怪退治屋であるこの家にいるのは、すべては旭のためだ。
正確には、乙葉旭の魂のためだ。
かつて焔は、山神として人に崇められる白狐だった。
人を守る存在であった焔が、あやかしと成り果てたその原因となった魂を、焔は再び相見えるためだけに探し続け、何百年とこの世界を彷徨い続けた。そしてついに十五年前、その魂を持つ乙葉旭という存在を見つけたのだった。母親の子宮の中で小さくその命が芽吹いたばかりだったという。
旭はそのことを知っていた。幼い頃に母親から聞いたのだ。
焔が全力で旭を守ろうとするのは、旭の魂。
だから。
「ありがとう」
こんな僕を、心配してくれて、ありがとう。
一言に込めた気持ちが彼へと届いたかのように、「ちゃんと食えよ」と焔が笑まう。
スプーン一杯の汁を口に含めば、優しい味に尖った心は緩やかに溶け始める。
いとも簡単に旭をコントロールする焔のそれは、あやかしの力でもなんでもなく、十五年間という月日の積み重ねの結果だ。
留守がちな家族に代わり、家族の一員として過ごしてきた焔を人間と錯覚することさえ少なくない。
昨日のことは、まさにそういう油断が旭の方にあった所以だと、一夜を置いて理解した。
『使役妖怪には識別子をおつけなさい。さもないとまた間違われて消されてしまいますわ』
昨日、少女の言葉が甦る。
妖怪退治を営む者は、捕らえた妖怪を自分の手足として使役することがある。
その場合はイレブンへの申請が必要となる。その者が使役できる力量を持っているかを調査されるのだ。合格すれば識別子として札が与えられる。使役妖怪はその札をつけていれば、他の士に退治されることはない。そういう仕組みだ。
焔を乙葉家の使役妖怪として登録したのは旭の祖母だった。旭が生まれた直後のことだと、祖母から聞いている。これまで焔が他の士から狙われるようなことはなかったから、ルールを知っていても札をつけることなど考えたこともなかった。
けれど、昨日みたいなことが起こらないとは限らない。
もっと力の強い士によって焔が攻撃されたら、今度はどうなるかわからない。
焔も、自分も、焔を傷つけたその相手も、取り返しのつかない事態に陥る蓋然性は決してゼロではない。
唯一、識別子という札を用いる以外は。
札をつける――それは支配されているという証だ。
犬に首輪を付けるように、焔に札をつけることはできない。
旭にとって焔は従僕ではないのだから。
たった一つの解決策は、旭の前で大きな障壁となっていた。
野菜スープをスプーンでかき回しながら考えに沈んでいると、がちゃりとドアの開く音がした。
視線をあげると、いつの間に部屋を出たのか、焔が居間に入ってくる。
「どこ行ってたの?」
「図書室」
図書室とは乙葉家の一室で、本棚とそれを埋め尽くすたくさんの本に囲まれた部屋だ。日向の仕事部屋であり、旭の勉強部屋でもある。読書好きな焔も陽の当たる縁側の次に、気に入りの場所だ。
焔は手に持っていた銀色のものを首にかけた。チャラリと金属のぶつかる音がする。銀の鎖の先にぶら下がる楕円形の札に旭の視線が吸い寄せられる。
「それって」
「識別子。昨日、ばあちゃんに頼んで出しておいてもらったんだ」
昨夜、遅く、日向と焔が話し込んでいたのを旭は知っていた。
魘されては目を覚まし、幾度かそんな波を繰り返したとき、旭の部屋のドアの外で話し声を聞いたのだ。昼間のことを話していたのだろうとは思っていたが、それが識別子こととは思いもしなかった。
「映画に出てくる米兵のタグみたいでかっこよくないか?」
札を持ち上げて見せる焔は普通に笑っている。
焔ほどの妖力の強い妖怪にもなれば、人に使役されるなど我慢ならないだろう。たとえ自分の意思で妖怪退治家にいるのだとしても、家来の位置にいることを許すはずがないと旭は思っていた。ましてやそれを見せびらかすかのような札をつけるなどあり得ない。だから今まで、焔だってつけなかったのだ。
あの少女が進言したくらいで、心が変わったりはしないだろう。
ならば……
「どうして?」
わかっていて旭は問うた。
今の自分には焔が紡ぐだろうその言葉が、絶対的に必要だから。
「俺はおまえの前から消えたりしない。おまえに誰かを傷付けさせるようなことは絶対にさせない。もう二度と」
いつものように焔の長い指が、旭の柔らかい前髪をくしゃりと撫でて離れていった。
焔はどこにも行かない。
銀の札はその証となった。
従僕ではなく、約束の証だ。
そしてようやく、落ちた淵からそろりと這い上がる。
その手に、その言葉に、幾度、助けられてきたのか。
壊れそうになると、縋る。
縋れば、助けてくれる。
わかっていて、手を伸ばす。
焔はそれを、決して、拒まない。
「僕は、狡い。でも」
俯いて、唇を咬む。
それが乙葉旭という人間であり、焔が命を賭して守る魂の、現在の使用者である。
それでも僕は、焔が必要なんだ。
こんな力を持って生まれた自分が、人間として生き続けてゆくには、あの優しいあやかしの手がどうにも必要なんだ。
キッチンから届くへたくそな鼻歌と洗い物の音が、溢れ出した旭の弱さをそっと隠した。
「旭、ちゃんとぜんぶ食ったか?」
「うん、ごちそうさまでした。美味しかったよ」
空になった器を確認することを忘れない焔に、どこまで過保護なんだかと、それを強要していることを知りつつ旭は苦笑した。
「俺はまだ片付けあるから、先に図書室行ってていいぞ。今日の調査の下調べするんだろ?」
焔から差し出されたミルクティの入ったカップを受け取り、席を立つ。
任務の前に下調べをするのは、いつものことだった。
ネットでの実際の書き込みを読んだり、イレブンのデータベースから似たようなケースを調べたりすることで、現場での仕事をしやすくするためだ。そうすることで、妖怪の知識もつく。これも士としての修業の一つだった。
誰が調べたのか、ネットの中には本町の公園の過去についての詳細な書き込みもあった。
『公園のあった敷地は、昔、大きなお屋敷があったんだってさ』
『お屋敷の庭に池があって、高そうな鯉が沢山いたとか』
『火事になって焼け落ちたんだよな、あの家。放火だったみたいだけど』
『四人が住んでたらしんだけど、焼け跡からは誰も見つからなかったんだって。四人の消息も不明。当時、かなり騒がれたよね』
『住む人がいなくなったから、公園に作り替えられたのよね。三年前だったっけ』
『池だけが、なぜかそのまま残された。なぜだと思う?』
「――住人は鯉に姿を変えて、今もあの池で放火犯が来るのを待っている、あの池の底で眠りながら……と。ふーん、いわく付きなんだな」
「焔」
旭の後ろからノートパソコンの画面を覗き込む。
「火の無いところに煙りは立たないってな」
「やっぱりいるのかな」
「さあな。まあ、いたとしても大物じゃないだろ。この辺りのあやかしなら一応、把握してるからな。何が出てきたとしても、おまえのことは俺が守るから大丈夫だ。おまえにかすり傷でもつけようもんなら、俺が乙葉家に消されるからな」
「おばあちゃんやお母さんなら、容赦なくやりそうだね」
「いや、乙葉で一番怖いのはおまえの父ちゃんだ」
「え? お父さん、ぜんぜん怖くないよ? 病弱だし」
「そりゃ、おまえは大切な息子だからだろうが。ホントのあの人は怖いんだよ。あの笑顔の下で何考えてるかわかんねえとこがな」
「お父さんはそんな人じゃないよ」
たまにしか会えないが、いつでも和やかで、どこか儚げな雰囲気を持つ父しか旭は知らない。
「いいんだよ、おまえは知らなくて」
旭が生まれる前、焔は旭の父、太郎の元にいたという。旭が知らないことを知っているのだろう。
「そろそろ出るか? 調査なんて面倒な仕事、さっさと終わらせようぜ」
図書室を出て玄関へと向かう焔を追いかける。
急かされるままにダッフルコートを羽織って玄関の戸を開けた。
冷たい空気の中に、黄色い蝶がいた。
「おはようございます。乙葉旭」
黄色地に様々な色で描かれた蝶をあしらった着物姿の少女が、白い息を吐きながら立っていた。
焔のおかげで少しばかり浮上したつもりだったが、昨日発生した問題は何一つ片付いていないことを思い出した旭だった。
【Beginning - 蝶は真冬に舞い降りた(3)へ続く】