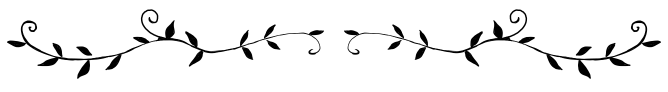辺り一面に広がるバルティゴの凪いだ海。ふいに吹くやわらかな潮風が、黒いコートの裾をはためかせている。
シルクハットの前鍔をつまむサボの笑顔は、いつも通りの明るさで、これから敵地へ赴く気負いはどこにも見当たらない。
「それじゃ、行ってくる」
気楽な声で言うサボに、ナマエもまた頷いて返した。
「どうかお気をつけて」
「ナマエもな。体に気を付けろよ」
「ありがとうございます。といっても、私は当面任務もないので……」
首を傾げたナマエに、サボが「そうじゃねェよ」と小さく笑った。
「近ごろ冷え込むからな。お前こういうとき、真っ先に倒れるタイプだろ」
「まさか……大丈夫ですよ」
サボの予言めいた言葉に、首筋がひやりとする。確かにナマエの体は気怠さを訴えていた。
それでも、まさか。さすがにそこまでは酷くはならないだろう。
◇
そのまさかだった。
兵舎の私室。こじんまりした部屋のベッドの上で、ナマエは何度目ともしれぬ寝返りを打った。
全身がうだるように熱い。厚手のブランケットを幾重にもかさねたミルフィーユ状の最下層、汗ばむ体は確かに火照っているのに、身体の芯では凍えるような寒気を感じる。
襟元から体温計を引き抜いて、目盛りを見た。三十八度五分。
立派すぎるほどの風邪である。
「ナマエちゃん、いいかな?」
ドア越しの声に「どうぞ」と返せば、開いたドアの隙間から、ぴょこんと金茶色の頭が覗く。コアラだった。
彼女は片手に持ったトレーを傾けないよう気にしながら、ベッドサイドへ歩み寄ってきて、横たわるナマエの顔を覗き込んだ。
「ごはん、食べられそう?シェフが野菜スープ作ってくれたんだよ。栄養満点だって、ほら!」
そう言って見せられたトレーの上には、湯気立つスープボウルがのっていた。薄黄色のスープのなかにはよく煮込まれたニンジンやタマネギ、ブロッコリーがごろごろと入っている。
ふうわりと鼻腔をくすぐるあたたかな香り。さぞや美味しいのだろう。……けれど。
「ごめんなさい、ちょっと、食べられないかも……」
今は香りを嗅ぐだけで、胸がいっぱいだった。
「そっか……。もうずっとなにも食べられてないから、少しでもって思ったんだけど……」
「ほんとうにごめんね……。せっかく作って貰ったのに」
「ううん!ナマエちゃんはなんにも悪くないよ!熱は?測ってみた?」
「うん」
頷いて、手元の体温計をコアラに示す。
「三十八度五分。また上がっちゃった」
「八度六分?!」
驚いて体温計を見たコアラが、「ほんとだ!」と悲壮な声を上げる。
「寝込んでからもう五日も経つのに、ずいぶん頑固な風邪!これじゃあナマエちゃん辛いね……私が代わってあげられたらいいのにな」
そう言うコアラの顔があまりにも真剣で、ナマエはあたたかい気持ちになって微笑を漏らす。
「幹部のコアラちゃんが寝込んじゃったら、それこそ大変だよ。みんな頼りにしてるんだから。むしろ私でよかったくらい」
「そんな!ナマエちゃんのことだってみんな頼りにしてるよ!すっごく!」
「うん、ありがと。……頑張って早く治すね」
笑いまじりに返した声はけれど、思ったよりも弱々しく響いてしまった。
そんなナマエの様子をじっと見つめたコアラが、もう一度「やっぱり代わってあげたい!」と、今度は拗ねたように言うので、ナマエは声をたてて笑ってしまった。
ほんとうにやさしいお姉さんなのだった。
とにかくたくさん眠ること!あとでまたお薬持って見にくるからね。なにかあったら声、かけてね。
そう口早に言って、コアラが退室していく。何度も名前のほうを振り返りながら。
途端にしんとする室内。自分の呼吸ばかりがやけに大きく聞こえる。
あたりには充満するコンソメスープの香りと、さきほどのコアラの言葉が余韻のように残っていた。
どちらもやさしくあたたかいものだから、ナマエはふと微笑んで、それからそっとため息を吐く。
ベッド脇の壁にかけられたカレンダーを見上げれば、左隅に大きく書かれた11の数字。
あれから半年、とナマエは思う。
サボと付き合い始めてから、もう半年も経つ。
「ナマエが好きだ。付き合ってくれ」
星空の広がるバルティゴの白い夜。共用のバルコニーで眼下の景色を眺めていたナマエに、サボは突然そう告げた。
なんの前触れもなかった。
つい数分前までしていたのは、他愛のない話だったし、昨日も、その前の日だって、サボはそんなそぶりは一度も見せたことがなかった。
それだからナマエは、すぐにはその言葉を飲み下せなかった。
「えっ」と、喉に詰まった声をひとつだけこぼし、目を大きく開いてサボを見る。
サボの凪いだ瞳は確かに、ナマエだけを映していた。
「お前が好きだ。……これっぽっちも気付いちゃいねェだろうと思ったから、言うことにした」
言うことにしたって、言われても。
言葉もなく見つめ返せば、向き合うサボが、コツリ、靴音をたててこちらへと歩み寄る。ナマエは思わず肩を揺らした。
サボは今もなお、ナマエだけを見つめている。
「返事くれよ。おれじゃ駄目か?そんなふうには見れねェか」
「そんな、ことは……」
あるはずもなかった。
だって、ナマエもサボがずっと好きだった。もしかするとサボよりも先に、ずっとずっと好きだった。
コツリ。サボがもう一歩ナマエに近付いて、その大きな手のひらでナマエの頬を包み込む。革手袋をしていないサボの手は、とてもあたたかい。
鼓動が爆発するかのように高まるのを感じた。サボに触れられた肌が、痺れるように熱い。
「ナマエ」と、己を呼ぶサボの低い声にうながされるまま、ナマエはただサボを見つめた。瞬きを忘れた瞳が、じんと潤むのを感じながら。
「私もずっと、総長のことが……」
そうしてナマエはサボの恋人になった。
ふいにくらむような頭痛がして、ナマエは双眸を伏せた。こめかみの奥が疼くようだった。熱が上がったのだろうか。
重たい腕を上げて、額に手を当ててみる。……よくわからない。額はもとより、手のひらすら馬鹿みたいに熱く、とても測れそうにない。
(総長の言うとおりになっちゃったな……)
思って、ナマエはブランケットへうずめた唇を引き結んだ。ナマエが風邪で倒れたのは、サボがバルティゴを発った直後のことだ。
もとより不調は感じていた。何日も前から、夜になると体が妙に気怠くなることが多く、ナマエも違和を覚えていたけれど、単に疲れているだけだと油断していた。
いよいよこれは、と思ったのは、サボが発つ前日の夜のこと。
「そう長くはならねェはずだ。一週間かそこらか、そのくらいで片付けて帰ってくる」
サボの私室。壁際に据えられたソファに二人並んで身をうずめながら、サボがそう言った。
ナマエが横目に見たサボは、いかにも申し訳なさそうな顔をしている。
「……悪ィな。なかなか二人になれる時間作れなくて」
「そんな……気にしないでください」
あわてて返しながらも、ナマエは内心残念だった。
付き合って半年経つけれど、ナマエとサボは恋人らしいことをしていない。革命軍で重役をになうサボは、休む間もなく西へ東へ飛び回ってばかりだった。
もちろん、仕方のないことだとわかっている。わかっているから、いつも通りなんでもない顔で笑った。
「こうしていられるだけで充分ですから」
それも、本当のことだった。
「ありがとな」
サボは目元を和らげると、手を伸ばしてナマエの手に触れた。ぎゅっと握られてしまえば、ナマエの心臓はばくばくと音をたてて、にわかにその存在を主張してくる。
息を呑んでサボを見れば、彼はもまた真剣な顔でナマエを見つめた。
キスをされるのかも、とナマエは期待した。
「……じゃ、そろそろ寝るか。部屋まで送るよ」
気のせいだった。
すっくと立ち上がったサボに従い部屋をあとにすれば、すぐ私室についてしまう。ナマエはサボに礼を言ってから、ドアを閉めた。そのドアへ背をもたれさせ、ため息をひとつ。
(また今日も総長とは、手を繋ぐだけで終わっちゃった。それも幸せだけれど……)
とぼとぼとベッドへ歩み寄りながら、ふと、身体が妙に熱いことに気がつく。それになんだか、全身が重たい。
一度、軍医にかかったほうかいいのかもしれない。
着替えを済ませるとナマエは、部屋のランプを消し、倒れ込むようにしてベッドに横になった。
結局その気怠さは、翌朝になってもなお付きまとい、羽ばたくカラスの背に乗るサボの姿が遠くの空へ消えた瞬間、ナマエの体は地面へと強く縫いつけられたのだった。
高熱を出し続けるナマエは、しかし暇だった。
やることといえば寝るしかなく、それも数日も続くと眠りたくても眠れない。
そんなナマエができることといえば、考えることくらいだ。そのせいで、ナマエは今日もまたしみじみと、サボとの関係について考えていた。
(総長は私に、何もしようとしない……)
半年。いくらすれ違いばかりの交際といえ、半年ともなれば、もう少し進展していてもよい時期だと、ナマエは考えていた。
それどころか、人によっては深い肉体関係を持っていてもおかしくない……らしい。
以前、恋愛ごとに詳しそうな兵士がそのように話すのを、ナマエは耳にしたことがある。
一方のサボとナマエといえば、先日のような手繋ぎがせいぜいだ。それ以上にはまるで進みそうにない。
(私からして欲しい、と頼めばいいのかもしれないけれど……)
何度もそう思ってみたものの、そうする自分を想像するだけで、ナマエはいっそう熱が上がるような心地になる。とてもできそうにない。
(総長は、私になにも感じないのかな。私に魅力がないのかな。それとももしかして、私がなにかがっかりさせるようなことをしてしまって、それで、もしかすると……)
────冷められてしまったのかも。
なんてネガディブな考えだろう。
ナマエの冷静な部分はそう判じていたけれど、一度考えてしまえば、その言葉は何度だってナマエの頭に浮かんだ。
ぐらり、と視野がかすむ。
やはり熱が上がっているようだ。頭を占めていたネガテイブな考えすら、体のすみずみまでを満たす熱にどろりと溶けていく。
重くなった双眸を閉じれば、すぐに意識が遠のいていった。全身がシーツへと染み込んでいくような、不思議な心地。まどろみへ沈むなか、ナマエはうっすらと想った。
……総長に会いたい。
ぷつり。そこで意識が途絶えた。
◇
夢を見ていた。
ふわふわの雲に抱かれる、静かな夢。体は相変わらずどこもかしこも熱くて、息も苦しかった。夢の中なのに変に生々しいのが、ナマエにはなんだかおかしかった。
ふと、熱に汗ばんだ額にかかる前髪を、誰かの指先がそっと掻き分けてくれる。それから、囁くような低い声。
「……やっぱりな。なんだか妙だって気はしてた」
「そうなの?私は全然わかんなかった」
返す声はコアラだろうか。こちらも囁くようなちいさな声だ。
「確証はなかったけどな。でもこいつ、昔っからこの時期体調崩してたし、気をつけて見てたんだよ」
「ふうん。大事にしてるんだ?」
「当たり前だろ」
間髪を入れず言ったサボに、コアラが忍び笑いをこぼす。
ピチャン。ふいにたった水音を前触れに、ナマエの額へひんやりとしたものが乗せられた。とても気持ちがいい。力の入らない指先がさらに弛緩する。
「それじゃあ、私はそろそろ行くけど。サボ君、ほんとうに看病できる?」
「できる。あのな、お前おれをなんだと……」
「もちろん、常日頃から手のかかる参謀総長殿です。……でも、そうだね。その様子なら大丈夫そうかな」
椅子の脚が床を擦る音。
「なにかあれば声、かけて。……変なことしちゃ駄目だからね」
「するかよ、馬鹿。早く行けって」
「はいはい」
足音が遠ざかっていって、あたりはしんと静まり返った。傍らには変わらずサボの気配。それも、耳をすませばわずかな呼気すら聞こえる。ほんとうに生々しい夢だ。
と、ふいに頭へなにかが触れた。
それはかすめるほどの密やかさで、ナマエの髪を撫でてくれる。
うっすらと目を開けてみた。すぐ横に人らしき輪郭がある。白いもやに遮られたような視界だが、それは確かにサボだった。霞がかった彼の顔が驚きに染まる。
「起こしちまったか」
ナマエは返さない。というより、声が出そうにない。そういう夢は過去に幾度か見たことがある。今回もそうなのだろう。
「欲しいもんあるか?そこに水とリゾットがあるぞ。……あー、リゾットは冷えちまってるな。食うなら温めてくるよ」
言いながら立ち上がろうとするサボに、ナマエは嫌だな、と思った。離れて欲しくない。
意識するよりも先に手が伸びて、サボの服の裾を握っていた。白い輪郭が振り返る。
「どうした?」
伝えたい言葉がある。
なんとか声を出そうとしても、朦朧とした思考はまたどこか遠くへいく。視界はもはやなにも映さず、薄れる意識のなか、ナマエはそれでもかすかに唇を動かす。
なにを言ったのか、それが声になったのかすら、わからないまま。
意識を手放す直前、服の裾を掴む手が、なにかあたたかいものに包み込まれたような、そんな気がした。