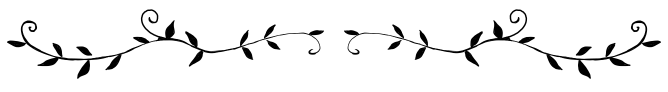目の前の彼女はそう言っておれを見つめた。それもとびきりの不機嫌顔で。
総本部の食堂で差し向かいに座るナマエが主張したそのとき、おれはエビがごろごろと入ったパエリアを食っていたところで、それも両頬にパンパンに詰めていたものだから、すぐには返事ができなかった。
そうしたらナマエはますます顔をしかめて、やっぱり同じように「恋人らしいことがしたい」と拗ねたように唇を尖らせる。
おれはそこでようやく、ごっくんと口の中のもんをぜんぶ飲み下して、「恋人らしいことなァ」などと首を捻ってみた。
「そうは言ってもな。休みの日にはお前の買い物付き合ってるし、手ェ繋いでキスして……ほかに何するんだよ」
あげつらってみるといかにも甘ったるいことをしている。なんでおれはこんなプライベートな話をこんなところでしているんだろう。おれの後ろにいるコアラの耳はきっと今、ダンボみてェになってるに違いない。
じわじわと恥ずかしくなってきて、切り上げるように席を立った。テーブル上の皿を盆ごと持ち上げて、名前に向かって顎をしゃくる。
とりあえずおれの部屋へ行こう、という無言のサインをナマエはきちんと汲み取ってくれた。おれはついでに空いてるほうの手でナマエの盆も持ち上げて、食器の返却口へと向かった。
部屋に着くなり、おれの胸に寄りかかって背中に腕を回してくるナマエを見下ろしながら、とりあえずおれも抱き返した。
ナマエの髪からはいつものようにシャンプーの甘ったるい匂いがする。近頃はそれにも慣れてきたが、このほとんど男所帯の総本部では珍しいものだったので、通路や室内ですれ違うたびに香るそれに、昔のおれは彼女から色濃い「女」を感じていた。
それだからおれは彼女から告白されたとき、なんとなく、気が付いたら、首を縦にしていたのだ。
「サボくん、あのね……」
腕の中のナマエがそう言って見上げてくる。キスをしろということだろう。両手でナマエの頬を包むようにしてもっと上に向かせる。てかてか光るぷっくりとした唇へ、おれの唇を重ねる。
啄むようなキスを何回か交わしてからナマエの唇を舌でつついて開かせた。ぬらりとした彼女の舌がすぐに応えるようにおれの舌を吸う。
おれはナマエの腰をぐいと引き寄せながら、ゆっくりとベッドへ押し倒す。湿ったようなリップ音を残して唇を離せば、瞳を潤ませたナマエが女の顔でおれを見る。
ほら、こういうのだってお前の求める「恋人らしいこと」だろ。ナマエのシャツの胸ボタンをひとつ、ふたつ片手で外しながら頭の中で呟く。それを声にしない代わりにナマエの耳朶に唇を這わせて、その輪郭に沿うようにじっとりと舐めあげれば、あ、とため息にも似た甘ったるい声をこぼして、ナマエが身をよじった。
あとは言葉なんかいらない。真っ白いシーツを彼女の指がしわくちゃに乱して、互いの汗を滴るがままにまじえる、いたって単純で獣のような行為に没頭するだけだった。
情事の声やシャンプーの匂いと同じくらい、ナマエは甘ったるい女だった。さすがに人目のある場所でひっついてくるようなことはなかったが、それでも時折寄越してくるまなざしには、確かに上司と部下以上のものが込められていた。
休みの日の過ごしかたもそうだ。いかにもカップルです、というようなものをおれに求める。たまたま立ち寄った島の、どこで調べたんだと聞きたくなるような小洒落たカフェで、これまた小洒落たもんを食ったり。
服屋で「ねえこれ似合う?どうかな?」とおれの意見を求めたり。しかもおれの「こっちがいいんじゃねェか」という返事をさらりと流して、結局別のもんを買うんだから、おれはあの時間が正直苦手だ。
こうしてみればおれとナマエの相性はいいとは言えない。むしろ悪いほうだ。それでも別れないのは、これといって決定的な不利益が今のところないということと、ナマエとの貪るようなセックスが何度しても飽きがこないせいだった。
一度コアラにこんなことを話したら「うわっサボ君最低!女の敵だよ!うわあ……」とあからさまに引かれたので、それからは人に話さないようにしている。
だからといってけっしてぞんざいに扱っているつもりはない。付き合う以上は大事にしたいと思っているし、実際におれにできる範囲でそうしている。
そんなわけなので、こうして情事を終えたあとのナマエに腕枕をしながら、その乱れた髪を撫でてやるのも、おれの彼氏としての義務のひとつだった。
それにしても、恋人らしいことか。
「こいつはいったいなにが足りねェんだろうな……」
目が覚めたら今度はもう少しちゃんと話を聞いてやろう。そう思って、おれはつかの間のまどろみに沈むナマエの髪をもう一度撫でた。
◇
ここしばらく任務に明け暮れていた。武器、とりわけ火器製造に関わる組織が潜伏している可能性があるという国へ赴き、そのまま組織を壊滅。いざ帰るぞと思った矢先、そのまま別の国へ斥候として潜入することになった。
そうやって日々忙殺されて過ごすうちに、おれはすっかりナマエのことを忘れていた。カラスの背に乗って本部に帰る道すがら、きらきら光る海の水面を眺めているときに、「なんだか名前のあのテカテカした唇に似てんなァ」とふと思って、そういえば……とようやく思い出したのだった。
「やっべ……」
「どうかしたか?」
呟きに反応したのはカラスで、おれの斜め下にある黒い頭を少しだけ捻っておれを見上げた。
「いや……ナマエにたまに連絡してくれって頼まれてたんだけどよ。すっかり忘れちまってた」
「……それは少し面倒な事になりそうだな」
なにかと拗ねがちなナマエの性質をカラスは知っているらしい。
「謝るしかねェか……」
おれはシルクハットの前鍔をぐいと下げた。
意外にもナマエは拗ねていなかった。
おれが帰ってくるらしい、とコアラあたりからでも聞いたんだろうか、彼女は玄関口前で両手を組んだまま立っていて、おれがカラスから降りるなりタタタタ、と小走りする勢いのままこの胸に飛びこんできた。おれはそれを難なく受け止める。
「ナマエ、悪ィな。一度も連絡できなかった」
「ううん。……それより、サボくんが無事でよかった」
心配したんだからね。
おれを見上げながらそう笑った彼女は目の淵に涙をため込んでいて、それが太陽の光にきらきらと輝く。うわっ零れちまいそう。……なんて心配しているうちにナマエは両手を拳にして、それからおれの胸板を力いっぱいポカポカと叩き始めた。なんでだよ。
「……なあ、痛ェ」
「心配かけた罰だもん」
「そんじゃドラゴンさんのとこ着くまでな」
暴れるナマエをひょいと肩に担いでツカツカと歩き出す。通路ですれ違った何人かの兵士達がギョッとしたように振り返ったが、おれとしてはそれよりもナマエに叩かれる背中のほうが気になった。
こいつの弱っちい力じゃ痛くもなんともねェし、そんなことはナマエだって百も承知のはずだ。それなのにこいつときたら飽きずもせずにおれの背中をポカポカポカとやっている。
「……そんなにおれが心配だったかよ」
ため息しながら訊くとナマエのポカポカ動きが緩んだ。
「……当たり前だよ」
「あのな、おれは強ェぞ。そうそう怪我もしねェし軍での模擬戦だって今んとこ負けなしだ。お前も知ってるだろ」
「それは、そうだけど……」
「それじゃ、もう少し肩の力抜け。……おれが任務で出るたんびにそれじゃ、お前だって疲れちまう」
ナマエはとうとう動かなくなった。拗ねているのか疲れたんだか、まったく判断がつかない。
肩の上でしんなりしているナマエを片腕で支え直しつつ、歩くスピードを早めた。あの角を曲がってすぐがドラゴンさんのいる指示室だ。
事の要点だけなら電伝虫で既に報告してあるものの、その際に省いた委細は山ほどあった。それをどの順番でどう伝えるか。頭の中で組み立てていく。
「ナマエ、そろそろ降ろすぞ。まだおれに言いてェことがあるなら後で聞く。部屋で待ってろ」
指示室のドアの前でそう声をかけると、ナマエはやっぱりしんなりとしたままおれの肩の上でモゾモゾした。返事ねェけどこのまま降ろしちまうかな、おれがそう思っていると「全部わかってるもん……」すぐ耳元で呟き声がした。
「わかってるけど、それでも心配なんだもん。……だってわたし、ただ待つしかできない」
そう続けたナマエの声はとても小さかった。小さいが、これもやっぱりおれのすぐ耳元に落ちた言葉だったので、ばっちりと聞こえていた。
ナマエはまた少しモゾモゾして、ずるりとおれの肩を降りる。
「……今日はゆっくり休んで。また明日ね」
言うなり、返事を待たずにナマエは走り去って行った。おれはそんな彼女の背中をぼんやりしながら見送る。
いったいなんだ、この気持ちは。
呼吸が喉元に張り付いちまったような、ナマエの顔や声を今さっき初めて知ったような。頭の中で組み立てておいたはずのあれこれがバラバラになって、おれの足下らへんに散った。
◇
それからのおれは変だった。
どう変かというと、たとえば気がつくとナマエの姿を探している。ナマエの横顔を見ているとつい頬がゆるゆるするし、他の男と話していると正直面白くない。
デート中、街の雑踏のなかからおれを見つけ出したナマエが、顔をぱっと明るくして笑顔でおれに歩み寄ってくるところなんて、何度見てもいいもんだなあ……としみじみ思うようになった。
じっさい、ナマエはかわいいほうだ。革命軍内でもそれなりに人気がある。
おれは今まであまり気にしてなかったが、とにかくそうなんだとなぜかニヤニヤしているコアラから教えられた。
そのときおれはうれしいような、なんだかもやもやするような、なんとも言えない複雑な気持ちになった。
おれのそんな変化にナマエは困惑しているふうだった。まァそうだろうなと思う。おれは今までよりも自分からナマエを探して話しかけるようになったし、ベッドのなかでだって、前よりもずっと繊細な注意を払って抱くようになった。
だから、
「サボくん、なんか変わったね。どうしたの?」
と、おれの部屋のソファに座るナマエが訊ねてきたことも、当然のなりゆきだった。
彼女の座るこのソファはなかなかにふわふわしていて、今も名前のやわらかい体をしっかりと包み込んでいる。おれは名前に紅茶の入ったマグカップを手渡しがてら、自分のコーヒーをずずずと啜った。
「やっぱりナマエもおれが変わったと思うか」
「そりゃあ……前よりずっと優しくなったし。バニー・ジョーだってそう言ってたよ」
「ふーん……」
そこで他の男の名前を出すのかよ。面白くねェな。
どすり、とナマエの横に腰を下ろして、ふわふわのソファに身を沈める。
このソファは「忙しいうえに無茶ばかりする総長のために」と構成員の連名でおれにプレゼントされたもので、殺風景なおれの部屋においては珍しく洒落たデザインをしている。
隣に座るナマエの腰に腕を回し、おれはまたひと口コーヒーを飲む。やたら苦いが目が冴える。便利な飲みものだ。
「おれは前から優しかったろ。お前のこと大事にしてるつもりだったし」
「それはもちろんそうだけど……でも」
と、ナマエが迷うように視線を泳がす。どうした、と問えば彼女は眉尻を下げてすこし困ったように笑った。
「サボくん、わたしのことそんなに好きじゃなかったでしょ? もちろんそれでもいいって思ってたよ……でも最近のサボくんはそうじゃなさそうで」
わたしのことちゃんと好きなのかなって、勘違いしちゃいそうになるの。
そう続けたナマエはやはり微笑んだままで、長い睫毛をそっと伏せながらおれの肩に頬をすり寄せた。
「だからちょっと戸惑ったけど、でもすごく嬉しい。すごく幸せだよ」
まただ。また、胸をわし掴まれた心地になる。
おれはナマエの手からマグカップを奪う。それをサイドテーブルへ置きがてら、上半身をよじってナマエに向き合った。きょとんとした顔のナマエがおれを見る。おれもじっと見つめ返して──…、そのままやわらかそうな両頬を指でぐーっと左右に引っ張った。思ったよりよく伸びた。
「おお……すげェな、ナマエ、お前のほっぺたやわらけェ」
「はほふん、いひゃい!」
「ははは! 悪ィ悪ィ」
指を離して笑い続けるおれをナマエは恨みがましそうに睨んで、両頬を手でさすった。そんなナマエを見ながら、やっぱりおれは変わったんだな、と改めて思った。
ひとしきり笑い終えると、室内は急にしんとして、おれとナマエの息遣いだけをくっきりと浮かび上がらせる。ナマエが期待顔でおれを見ている。キスをしろということだろう。いつものことだった。
それなのにおれときたら、おれの唇を待つナマエの表情に釘付けで動けなかった。あれだけさんざんしてきたのに、キスなんかよりずっと生々しい行為だって数えきれないほどにやってきたのに。それなのにおれは動けない。ナマエの少し上気した頬や潤んだ瞳がどうしようもなくかわいい。
「サボくん……?」
また困ったようにナマエがおれを見るので、なんとか誤魔化そうと、彼女の頭をおれの胸に押しつけるように抱き寄せた。そのつむじに顎をのせれば、甘ったるいシャンプーの匂い。猫のようにふわふわしてやわらかい髪の毛。
おれの肺はその甘ったるさに溺れていて、けれどそれを幸せだなと感じてしまう。
まいったな。
「おれさ。ナマエのことだいぶ好きみてェだ……」
すっかりお前にまいっちまったらしい。
呟くと、ナマエはおれの腕のなかでびくりと身を揺らした。どうかしたのかと顔をうかがえば、さっきよりもずっと顔を赤くしたナマエがぱくぱくと口を開けたり閉じたりしている。
「……なんだよ」
ふいに照れ臭くなって言うと、ナマエは頬にえくぼを作って笑った。たくさん見てきたナマエの笑顔のなかでもとびきりのものだった。
そうして彼女はそのピンク色の唇を開く。ほんとうはね、サボくん。
「ずっとその言葉が欲しかったの」
笑みを深める彼女の瞳がまたきらきらとしだしたので、おれはそのまなじりに唇を落とした。
もう一度、今度はもっとしっかりした声で「好きだ」とおれが言うと、とうとうナマエのまつげがぽろりと涙をこぼした。恋人らしいことってそういうことだったのか。
ああ、やっぱりこいつ、すげェかわいいな。
そうたまらない心地になって、さらうようにナマエを抱きしめた。