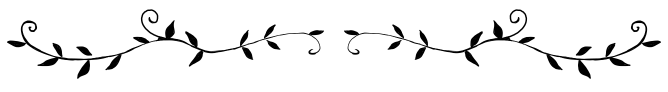いや、きみは存外忘れっぽい奴だから、もう覚えていないかも知れないな。まあともかく、鶴ってのはそういう生き物なんだ。
だから、俺がきみについていくことをどうか許して欲しい。追いかけていって三途の川で落ち合った途端、帰れ、だなんて言われちまったら、さすがの俺も立ち直れんからなあ。
いやいや、なにもきみを束縛する気なんざない。ただ側にいたい。それだけさ。
構わないだろう? だって俺はきみの刀だ。何十年もきみと共に在った。それも永年近侍を賜った腹心中の腹心だぜ。そりゃあ、黄泉路を共にする権利くらいあると自惚れもするだろう。
……黙りかい。死人に口なしってのは、まさしくこのことを指すんだろうなあ。ま、断る口がないのもひとえにきみの運だ。沈黙は了承の意と捉えさせてもらうぜ。
それじゃ、少しばかりそこに座って待っていてくれ。ちょいと支度に時間がかかりはするが、なあに、すぐに追いついてみせよう。また後でな。
……
…………
もしかして、きみ、俺を待つあいだ退屈してるんじゃないか?
それならひとつ思い出話でもしようか。いい退屈しのぎになる。ま、本当はただ俺が話したいだけなんだがな。ははは。
さて。俺ときみが初めて出会った日を、きみは覚えているかい。降るような蝉時雨が鼓膜を劈く真夏日のことだった。きみは政府の役人とかいう、小綺麗な中年男に手を引かれやってきたな。
きみは小さかった。ほんとうに、小さくて……そうだな、背の丈は三尺かそこらだったんじゃないか?
ちっぽけなきみは、ひどく怯えた目をしていた。きみは一言も喋らないまま、役人の言葉に唯々諾々と従って、あっという間に俺たちの新しい主になった。
正直に言おうか。俺はきみを歓迎しちゃいなかった。前の主を失って、まだ半月も経っていなかったんだ。……突然死だった。前触れなく訪れた不幸を飲みくだすには、いささか時が足りなくてな。
それにきみときたら、俺が何をしてやったって目を輝かせて大喜びしただろう。ありゃあ駄目だ。どうしたって堪らなくなる。
ん? 待てよ。当時のきみは幼かったからな。覚えていないか。たとえば……そうだな。まだきみが来て間もない頃の話だ。
あの頃のきみは、いつだって寂しそうだった。
見知らぬ男ばかりがひしめく本丸の隅っこで、所在なさげに肩を丸めてばかりいた。
今でこそ社交的なきみだが、幼いきみは少々人見知り気味だったんだぜ。嘘なんかじゃあない。ほんとうさ。
まあそれでだ。ある日、ぽつねんと縁側にたたずむきみの背中が、急に哀れに思えた。
きみを主にいただくことこそ抵抗があれども、しかし、きみだって好きで本丸に来たわけじゃない。そんなことくらい、ちゃあんと解っていた。解ったうえで見て見ぬふりをしたことへの、後ろめたさもあったんだろう。
悩んだすえ、俺はきみに花冠をくれてやることにした。
きみも知ってのとおり、裏庭を少し行った先に、花畑があるだろう? 花はそこで摘んできた。作りかたは短刀たちに教わってな。自慢じゃないが、はじめてにしてはうまくできたんだぜ。
作ったばかりの白詰草の冠を手に、俺は縁側に座るきみの背後へ回った。忍び足で近寄って、その愛らしいつむじを見下ろしながら、すとん……と、きみの頭上へ花冠を落っことしたのさ。
きみは最初、俺に何をされたか解らないふうだった。不思議そうに俺を見上げて、恐る恐る頭上に手を伸ばし、それでようやく気がついた。
うん、ありゃあいい驚き顔だったな。今でもさっき見てきたことのように思い出せるぜ。
ともかくそれで、きみはそのまあるい頬っぺたを真っ赤にして、ありがとう、と笑ったんだ。
はじめて、きみが俺の前で笑った。
……そのときようやく、俺はきみの笑顔を想像したことすらなかったのだと、気がついたんだ。
それからのきみときたら、まるで雛のようだったな。
俺のあとをちょこちょこと追っかけてくるようになった。俺が立ち止まれば、一瞬遅れてきみもぴたりと止まった。俺が小走りすれば、その短い足でまろびながらも懸命についてこようとした。
俺はきみのそんな姿がかわいくて、かわいくて、愛おしくて……そしてなにより、憎らしかった。
きみへの愛着がつのるほど、前の主との絆が薄れるような、思い出を削り取られるような、そんなやるせなさを感じてやまなかった。
ただの刀だった時分に、さんざ、主を転々としてきたのになあ。刀として、もの言わぬ道具として、もの分かりのいいつもりでいたんだが。
この肉の器を得てからというもの、どうにも感情に引き摺られやすくなっちまったらしい。
いずれにせよ、きみになんら罪がないのは確かだが。
俺はきみから離れようとした。
しかしきみはめげなかったな。俺がどれだけきみを避けようが、邪険にしようが、お構いなしだった。
そして、俺はそれが嫌じゃなかった。……いや、嬉しかった。他の刀には目もくれないきみが、俺にだけ妙に懐いてくるんだ。
愛らしさと憎らしさとで、頭がぐちゃぐちゃになったんだぜ。まったくきみときたら、罪深いにもほどがある。
ひと月だ。ひと月、きみからの熱烈ならぶこおるとやらを受け続けた俺は、とうとう根負けしたふりをして、きみを受け入れることにした。
他の刀達が少しずつきみにちょっかいを出すようになったのも、ちょうどその頃だったな。
きみを受け入れること。それは決して前の主への不義にはならないのだと、ようやく心の整理がついたんだろう。
あの本丸じゅうにきみと俺たちの笑い声が響くようになるまで、そう時間はかからなかった。
……
…………
よいしょ……っと。ああ、すまんすまん。物音が気になるかい?
なに、きみのもとへ向かう前に、いくつか野暮用を済ませると言っただろう。身支度以外にもまあ、いろいろとな。
ちとうるさいかもしれんが気にしないでくれ。きみとこうして話す程度の余裕はあるからな。なにも心配はいらないさ。
で、どこまで話したんだったか? ああそうだった、きみの幼少期の話を終えたところだったな。
……そんなふうに親交を深めながら、一年、五年、十年。あっという間に時が流れていった。
俺にとっては瞬きするほどの短い時間でも、きみにとってはそうじゃない。
審神者として前線で俺たちを指揮するかたわら、きみは目まぐるしい経験に翻弄され、ときに挫折しながらも、しかし立派な主に成長したな。
内面ばかりじゃない。見目だってそうだ。
きみは美しい女になった。繊細な花びらが幾重にも重なったつぼみが、やわらかな陽射しにうながされ、ゆるやかに綻ぶように。
きみという一輪の美しい花が咲いた。
あんなにちっぽけだったきみがなあ。その事実に気がついたときは、そりゃあ驚いたもんだぜ。
光坊の奴には、「鶴さんってときどきすごく鈍くなるよね」……なあんて揶揄われたもんだが。
そしてきみが俺のことを好きだと、顔を真っ赤にして告白してくれたのも、ちょうどそのぐらいのことだった。
季節は春だった。
満開の桜が風に揺れて花びらを散らすなか、きみは俺を上目に見て、震える声で「好きです」と、ただひと言を絞り出すように言った。
かつて幼子だったきみが向けてきた、あの無邪気であけすけな好意とはまったく別のものだ。
俺がなんと答えたかは、さすがに覚えているだろう?
……立ち去るきみの頬に涙がこぼれ落ちるのを、俺はただ眺めることしかできなかった。
時はさらに流れ、きみは結婚した。
婚儀の日はめでたくも雲ひとつない晴天で、きみの着る白無垢が青空によく映えていたのを覚えている。
きみはいつもより鮮やかな紅をさし、はにかむように微笑んでいたな。そしてきみの隣には人間の男がいた。
きみの伴侶としてふさわしい、人間だった。