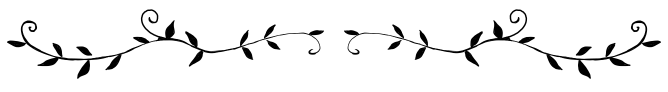日めくりカレンダーの端をつまみあげ力を込めれば、今日という日がちいさな悲鳴をあげて、あっけなく終わりを迎えた。
凝り固まったこめかみをもみ込みながら、執務室の壁かけ時計に目をやる。時刻は0時ちょうどだ。本丸は今や隙間のない深い眠りに覆われている。
まどろみに痺れる指先で、今しがた生まれたばかりの日付をそっと撫でた。四月一日。真白の紙に黒字で書かれたその日付を、なんどもなんども、頭の中で繰り返す。しがつついたち。言葉は淡い毒となり審神者のなかに染み込んでいく。
「鶴丸国永は、ひどい刀だ」
呟いて、審神者は執務室をあとにした。
翌朝の審神者を叩き起こしたのは、いつものアラーム音ではなかった。
悲鳴である。それから床板を軋ませながら疾走するいくつもの足音。夢うつつに浸る頭が、すこしの時間をかけて「始まったか」と答えを弾きだす。
朝支度をすませ大広間へ向かう廊下を歩くなり、すれ違う刀達はみな一様に審神者に注意を呼びかけた。
いわく、「鶴丸殿にお気をつけください」「あいつは今年も全力だ」「ボクさっそく騙されたちゃった」「庭の池にピラニアがいるのは嘘ではなかったぞ」「あいつの処罰は俺にお任せを」……。
予感を裏切らない、賑やかな一日だった。
かの白い刀は本丸中を飛び回り、ときにはふと微笑みたくなるような、あるいは仕込みを駆使した大掛かりな話を、虚実交えて話し歩く。
「俺はこの日に一年分の嘘を吐いて、吐いて、吐き切っているからな。だからこの日以外では嘘をつかないだろう?」というのは、いつだか審神者に向けられた鶴丸の言である。
「君はいいね。主だけだろう、毎年彼の四月馬鹿に巻き込まれずに済むのは」
黄昏時、夕餉の仕込みを手伝う審神者にそう零したのは歌仙だ。燭台切と共に大量の野菜を刻む姿はいつになく疲れきっている。
「主君たる君への礼節を弁えている点は評価してもいいが。ならば僕のことも、この騒ぎから除外してもいいだろうに」
「鶴さんがごめんね……。歌仙くんって反応がいいから、彼を喜ばせちゃうんだと思うよ」
苦笑して返した燭台切は、牛蒡を乱切りする手を止めて審神者へ視線を流す。
「でも、そういえばそうだね。どうして主にだけ嘘をつかないんだろう? 悪戯はよく仕掛けているのに」
「さあ……」
審神者は曖昧に笑ってみせたが、実際のところは違う。鶴丸は審神者にも嘘をつく。毎年同じ嘘を、飽きもせずに。
ぎこちない笑みを貼り付けたまま、眼差しを手元へ落とす。まな板の上には玉ねぎが中途半端に刻まれたまま転がっている。包丁を握り直して再び玉ねぎに刃を入れた。さくり。
まな板を叩く単調な音に没入するにつれ、審神者の意識は過去へと飛んでいく。
審神者はいつも日付が変わる時刻を区切りに執務を終えていた。
0時五分前にもなると、書類で散らかる文机を整頓し、机の端にある日めくりカレンダーを手に取って一枚破る。破った紙をくずかごへ捨てる。それから、きっかり0時になったのを確認して執務室をあとにする。
特段意味があるわけでもない、長年勤めるうちに身についた癖のひとつ。
例年、鶴丸が審神者に構うのは決まってこのタイミングだった。
鶴丸は気楽そうな様子で執務室へ踏み入ると、まず審神者を労わり、次にその日の武勇伝について嬉々として語る。そうしてひと通り審神者を楽しませたあと、一日の締めくくりとばかりに嘘をつくのだ。
そのどれもが陳腐なもので、疑うまでもなく嘘だった。
「そんなのじゃ騙されたくても騙されないよ」と困る審神者に、当の鶴丸は「だってこんな日だ。どうせ何を言っても信じちゃ貰えないだろう?」と、からりと笑ってみせた。
裏庭にスカイフィッシュがいた、伽羅坊の龍が実体化した、実は俺は女なんだ。
次々にうそぶく鶴丸はいつも同じ文句で話を結ぶ。
「この俺、鶴丸国永は、男としてきみを愛しているんだ」
ひどい刀だ、と思う。
あからさまな嘘と共にこの言葉を並べるものだから、一瞬だって信じることができない。陳腐な偽りのひとつとして扱われている。
鶴丸は人間と刀に愛が芽生えるなどあり得ないと思っているのだろう。結論するたび、目眩のような絶望が審神者を襲う。
「また、そんなあり得ないことを言って」
唇を震わせそう返せば、鶴丸は微笑んで小首を傾げ、審神者の肩を叩く。
「さあもう日付が変わっているぜ。寝室まで送ろう」
そんなやり取りを、もう幾度も繰り返している。
刻んでも刻んでも、目の前にうず高く積まれる玉ねぎは一向に減る気配がない。玉ねぎの集団はアルミ台の上に無造作に並んだまま、審神者の手で切り刻まれる瞬間を行儀よく待っている。
包丁はよく研ぎ澄まされている。薄透明の身に刃先を滑らせ圧を込めれば、すとん、小気味好い音がして断面が見えた。
こんなに傷付けられても抵抗すらしないなんて。彼らも、傷付けられる痛みに慣れてしまったのだろうか。
馬鹿な考えだ。玉ねぎは血を流さない。傷だらけのまな板には、半透明の白い断片だけが散らばっている。
「主、大丈夫? 泣いてるじゃないか……玉ねぎ切るの、代わる?」
夕餉と湯浴みをすませた審神者は、まだ湿る髪を肩に下ろしたまま、中断していた書類の仕上げをすべく机に向かっていた。
集中してしまえば瞬く間に時は過ぎ、もう十数分もすれば日付が変わる。じきに始まる儀式から審神者は逃げる気がない。そんなことはあり得ない。
正座続きで痺れた足はじんと痛み、時計の針が進むごとに増す息苦しさに何度も深呼吸しながら、それでも焦れる思いで彼を待っている。
たとえ偽りでも、偽りであるからこそ、あのひと言にすがってしまうのだった。
「よっ。どうだい、捗っているか?」
見計らったかのようにかかる声。振り返らずとも誰のものかは明白だ。
返事を待つ気はさらさらないらしく、鶴丸は軽快な足取りで机を挟んだ審神者の対面へ歩み寄り、腰を落とした。流れるような仕草で机上の書類をひとつつまみ上げ「ほう」と口の端を上げる。
「もう終わらせたのかい。毎晩遅くまで頑張って、きみは偉いなあ」
「仕事だからね。普通だよ」
「しかし、よそじゃ近侍に丸投げするような審神者もいると聞く。ところがきみは、極力己の力のみで片付けるようにしているだろう。見上げた努力家じゃないか! きみのような主を持てて、俺は運がいい」
「あ……、ありがとう……」
緩む頬を必死に引き締め、「それで」と審神者が切り出す。
「今年はどんな嘘を? 歌仙に仕掛けたドッキリは聞いたけれど」
「ああ、唐の古墨のやつだな! あれは仕込みからこだわったんだぜ。偽記事の載った新聞を自作したりな。そうだなあ、他には……」
一度口火を切ってしまえば、あとはとめどなかった。瞳を爛々と輝かせ身振り手振りで語るさまはいかにも好ましい。
話のすきまを縫うように審神者が相槌を打てば、鶴丸はそのたび嬉しそうに目を細めた。
「……ま、今年はこんなものだな!」
白い袖を揺らし大きく伸びをする。
「あとはいつものやつだ」
「やっぱりやるんだ。もう騙す気もないくせに」
じとりと半眼になる審神者を見、鶴丸が肩をすくめた。
「すっかり恒例になっちまったからなあ。これをやらんと落ち着かん。さあて、さくさくいくぜ。……実は俺は、白玉の付喪神だったんだ。あと一昨日宇宙人と茶を飲んだ。鶯丸はなんと宇宙人とメル友になったぞ。それから。
この俺、鶴丸国永は、男としてきみを愛している」
胸が、燃えるようにあつい。
流暢に動く鶴丸の薄い唇から、やっとの思いで目を逸らす。熱を吸った心臓がけたたましく鼓動している。息が苦しい。
審神者は懸命にそしらぬ顔を装い、すがるように机の隅のカレンダーを手繰り寄せた。白紙に黒字の四月一日。つまみ上げ破こうとして……、やめた。
ふと思い立つ。今日を終わらせる前にひとつだけ嘘をつこう。
そう、これは嘘だ。手の中の日付が、まだそう呼ぶことを許してくれる。
「私も……あなたが好き。いち、女として」
目も合わせず言い切って、今度こそカレンダーを一枚引き破く。胸がすくようだった。本当はずっと、こうして伝えてしまいたかったのかもしれない。
「なんて。ねえ鶴丸……」
エイプリルフールだよ。そう続けるつもりで顔を上げた審神者だったが、鶴丸の顔を見るなり口を噤む。
真っ赤だった。
白皙のかんばせが、今や暁の空のごとく熟れている。けぶるような白銀の睫は大きく上下に開かれ、そのなかの一対の琥珀がまっすぐ審神者を射抜く。
なにより審神者を動揺させたのは、その瞳だ。
鶴丸のこの目を審神者は知らない。こんな、熱に浮かされたような。焦燥にも似たその色は、けれどむさぼるような欲に濡れていて、より艶かしい。
――――これは、なに。
想像とまるで違う反応におののく。審神者の知る鶴丸であれば、冗談だろう、とか、やり返されてしまったなあ、とか、軽く笑い流すはずだった。
「きみ、それは本当かい?」
「えっ。……えっ?」
「……否定しないんだな。そんな顔をされると、期待してしまうんだが」
ざり。畳を擦る音。鶴丸が立ち膝のまま審神者ににじり寄る。
「期待……? でも、だって。鶴丸のはいつもの嘘で」
ざり、ざり。二人の距離はもう、息が触れるほど近い。
「嘘をつくのは四月一日だけだと、前に言ったろう? きみに愛を伝えるのはいつも、日付を跨いでからにしていたんだぜ。今もな。……気がつかなかったか?」
微笑みながら伸ばされる腕を、審神者は拒まない。なにしろ頭が追いついていない。されるがまま鶴丸に抱き寄せられ、白檀の香る肩口へ頬をよせる。
鶴丸の体はどこもかしこも硬く、男そのものだった。その事実がどうしようもなく審神者の羞恥を煽る。
「待って」と、やんわり抵抗を試みたところで今更すぎて、頭上から降ってくる忍び笑いに黙殺されてしまう。
いよいよ眦を濡らす審神者のこめかみへ、やわらかな感触が落ちた。
見上げた鶴丸の唇は蕩けるように淡くほころび、審神者の耳朶を食む。
「好きだ。―――いとしい、俺の主どの」