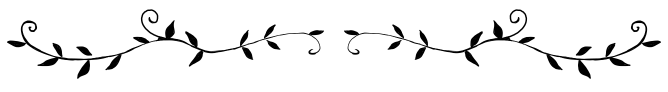唐突に目覚めたナマエは、明瞭な頭でそう思った。熱が下がったようだ。
室内にはうっすらと朝の気配が漂っている。もうまもなく日が昇り始める頃合いなのだろう。薄明に染まる空気がそう予感させた。
起きるにはまだ早い気がして、ナマエはブランケットの下の身をぐいとよじらせた。よじろうとして、失敗した。
寝返りを打ちたかったのに、背中にかかる圧がそれを阻む。
「あれっ……」
と、声をあげてからようやく、ナマエは自身の下腹と腰回り、それからを背中全体を包み込むおおきなぬくもりがあることに気がついた。そのぬくもりは、あろうことか、ナマエの耳元ですやすやと寝息をたてている。
首をよじればすぐ、ナマエの頬をくすぐる、癖のあるイエローブロンド。鼻先に迫る秀麗な顔立ち。
間違えようもなく、サボだった。
「そ、そ、そ、総長っ……?!!」
病み上がりのうえ寝起きとあっては、叫んだつもりでもたいした声が出なかった。
背中のぬくもりは「ううん」と鼻にかかった呻きを吐いて、またすやすやと心地よさげな寝息へと戻っていく。
ナマエは焦って、自身のへその前で組まれたサボの両腕を掴み、小刻みに揺さぶった。
「総長、起きてください……!いったいぜんたい何事が……?!」
「……んあ、眠ィ……わり、あともうちっとだけ……」
ナマエを抱くサボの腕がさらに力を込める。ひえ、ナマエは息を吸い込んだ。
「総長、だめです、起きてください!今すぐに!ねえ、総長ってば……!」
「……なんだよ」
ようやく語尾のしっかりし出したサボの声に、ナマエはほっとした。少しだけ力の緩んだ腕のなかで身をよじらせて、サボに向き合う。
見上げたサボはいかにも眠たげだったけれど、ナマエを視認した途端、その目を大きく見開いた。
「ナマエ?!」
「……はい。あの……おはようございます」
「お、おう。……いや、待て、この状況は……」
そう聞かれても、ナマエにもわからない。だんまりしたままサボを見返す。
混乱したのは一瞬のことだったようで、サボはすぐにいつもの冷静な表情に戻った。顎に指を当てながら、「そうか」と呟く。
「思い出した。昨日、ナマエがおれの服の裾を離さなくて」
ぎょっとした。確かに覚えがある。けれど、それは夢のなかでの話だった。……そのはずだった。
思索に耽るサボはそのまま続ける。
「それからお前は、寂しいって言った。離れないで、やだ、寂しいって俺に頼むから、そうしたんだが」
これは記憶にない。けれど意識を失う寸前、ナマエは確かに唇を動かしていた。それはこんな言葉だったのか。
顔がどんどん熱くなっていく。
「……それで、あー、このあとはおれが悪ィ。任務から帰った直後だったもんだから、お前のこと看病しながら眠くなっちまって。部屋に帰ろうとも一応は思ったんだが……」
ちら、とサボがナマエを見る。
「そうしたくねェな、と思った。で、目の前にはシングルとはいえベッドがある」
あとは言わずもがなだ、と事もなげに言って、サボは状況説明を終えた。
それからいつも通りの笑顔を浮かべ、名前の額を手のひらで覆う。
「熱、ずいぶん下がったんじゃねえか?昨晩よりずっと顔色よくなったな」
「……あ、はい、それは……たぶん」
「よかったよ。安心した」
話しながら、サボのもう片方の腕はナマエの背中に回ったままだった。鼻先にあるサボの胸板は、清涼な男性らしい匂いがする。
腕の中で気まずくもぞもぞとするナマエを見下ろして、サボが忍び笑う気配がした。ナマエが見上げるよりも先に、サボの顎が名前のつむじに乗っかる。
「なあ」と、頭上から響く声に、どうしたらよいかわからず、ナマエはなされるがままに耳を傾けた。
「寂しい思いさせちまってたろ。……ごめんな」
「そんなことは……」
「ない、とは言わせねェ。前からわかってたことだ。ナマエのやさしさに甘えちまってたのは、おれの責任だ」
「それでも」と続くサボの声は、どこまでも真摯な響きをしている。
「おれにはやらなきゃならねェことが山ほどある。だからナマエには悪ィが、これまで通り、時間を作るのはなかなか厳しいと思う」
「……はい」
とっくに了解していたことだ。
さみしい、そう思う気持ちはやはりある。けれどそうして忙しくしているところも含めて、サボという人なのだった。
つむじに乗せられていた重みが消えた。
サボはまた、ナマエを見下ろしている。彼の寝乱れたイエローブロンドが、その意志の強い瞳を遮るように、ひらりと双眸へかかっている。それから、くつろげられた首元のシャツから覗く、鎖骨や首筋。
はっきりいってとても色っぽい。ナマエの心臓は、いよいよ爆発しそうだった。
サボはそんなナマエの心中をつゆとも知らぬ様子で、小首を傾げた。
「やっぱりお前、まだ熱あるんじゃねェか?」
ナマエはぶんぶんと頭を横に振った。
「大丈夫です!気にしないでください!」
「おいおい。ずいぶんだな、その勢い」
「今朝はむしろ身体が軽いくらいです。熱だって下がったんじゃないかって」
「ふーん。……そのわりに顔、だいぶ赤ェけど」
誰のせいだと……と返そうしとして、ナマエは口を噤んだ。からかわれていると気がついたからだ。
ナマエを見る青い双眸は、今や、いたずらに細められていた。
「……総長、意地が悪いですよ」
「仕方ねェだろ。ナマエがすげェかわいいからよ」
「……か、かわいいって……」
どもりながら呟くと、サボが笑みを深めた。
「そりゃ、ナマエが。すげェかわいい。そうやっておれがいるとすぐ顔赤くすんのも、キスして欲しそうな物欲しげな顔も。ぜんぶかわいくて仕方ねェ」
「物欲しげな顔……?!」
「してるだろ?おれといるとき、いつも」
あんまりかわいいもんだから、つい焦らしちまうんだよな。
笑い含みの声に、ナマエは呆然とする。穴があったら入ってしまいたい。ただただ恥ずかしかった。
すっかりしおれているナマエに、サボが声をたてて笑う。それから、「顔、上げろよ」という優しい声。
ナマエは唇をとがらせた。
「……いやです」
「なんだ、拗ねたか?」
「別に、拗ねてなんかないです」
「悪かったって。からかい過ぎた」
「別に……」
と繰り返そうとして、できなかった。
ふいに額に落ちたやわらかな感触。ナマエははっと息を呑む。
────今、総長が……?
突然のことにナマエが硬直していると、サボは指先でナマエの前髪をかき分け、もう一度、ナマエの額へ唇を落とした。ちゅ、と響くリップ音。
腰から首筋までが、ぞわりと粟立った。口をぱくぱくとさせるしかないナマエに、サボはふ、と微笑を零して、その緩んだ唇のまま、額からこめかみ、眦、鼻先、頬……と、次々に口付けていく。羽根で撫ぜるようにそっと。
気がつけば顔を上げていたナマエの唇を、サボの親指がゆっくりとなぞる。背中がぴりぴりとした。もうわけがわからない。
サボの顔が、吐息が、あまりにも近い。
「……目、閉じなくていいのか?」
おれはどっちでもいいけど。
囁くような声だ。それがあんまり甘くて優しい響きだったから、ナマエは夢見心地になって、そっと瞼を伏せた。
長く待った気がする。けれど、ひと呼吸ほどの短い瞬間。やわらかいものが唇に触れた。
目を開くと、間近にある澄んだ海の色。そこに映る自身の顔。ナマエはなんだか、泣きそうだった。
サボの指が、ナマエの眦をそっとなぞる。
「泣くなよ。ほんとかわいいな」
もう泣いていたらしい。
サボはまた、ナマエの唇へ唇を重ねて、それから満足そうに笑い、ナマエを抱きしめた。大きな手のひらが、ナマエの背中をゆっくりと撫でる。
「これからはさ」
と、耳元へ落ちる声はやっぱり、溶けるように甘い。
「こうして一緒に寝るか。どれだけ任務が忙しかろうが、寝るときくらいなら時間はある。そうすりゃ少しは一緒にいられる時間も増やせるだろ。……言っとくが、別に下心から言ってるわけじゃ……」
よどみなかったサボの言葉が、そこで詰まった。
どうしたのだろう、とナマエが伺い見たサボは、不自然に目を泳がせていた。
「ねェ、とは言い切れねェ……おれも男だ。こればっかりはな」
「え。総長、私のことそういう」
思わず訊ねると、サボが呆れたふうに顔をしかめた。
「そりゃそうだろ。これでけっこう我慢してんだ。……今だって。ただお前、いつもすげェ緊張してるから、ゆっくりでいいと思ってたんだよ」
そうだったんだ。
胸の奥でわだかまっていたものが、ゆっくりとほどけていく。
ナマエは破顔して、サボの胸に頬をすり寄せた。
「……総長」
「ん?」
「大好きです……とっても」
思い切って言ってしまえば、サボも腕に力を込めて応えてくれる。
「おれもだ。おれも、ナマエが好きだ」
サボの厚みのある胸板からは、とくとくと穏やかな心音がする。
ナマエは今、つま先から頭のてっぺんまで、幸せでいっぱいだった。
◇
ある朝。
背中にぬくもりを感じて、ナマエは目を覚ました。明け方だ。室内へ射し込む朝の光はまだあわく細い。
自分の胸の先、全身を抱き込むようにゆるく組まれたサボの腕に、そっと触れてみる。思ったとおり、あたたかかった。じんわりと頬が緩む。
昨夜、ナマエが目を閉じたときサボはまだいなかった。夜遅く、デスク前で書類にむかっていた横顔がナマエの見たサボの最後で、そのあと、彼はどこかで執務を切り上げて、このベッドへ入り込んできたのだろう。
ナマエが眠るとなりへ、いつものように。
「……ナマエ?」
声がした。吐息が首筋をかめる。
くすぐったくて身をよじると、サボの腕がぎゅうとナマエの動きを封じ込める。そうしてうなじへ落とされる口付け。
「……くすぐったいですよ」
「ん。……もう朝か……」
あんまり眠たげな口調なので、ナマエは微笑んだ。
「まだ少し早いです。今朝もいつもの時間でいいんですよね?時間が来たら起こしますから」
「……んー」
サボがナマエの肩に鼻先を擦り付ける。髪の毛のやわらかい感触。ナマエはそれをやんわりと撫で、それからサボの頬にも触れようと手を動かした。
はたと気がつく。サボの頬がやけに熱い。
「総長、ちょっと」
断ってから身をよじり、サボの正面に向き合う。
とろとろと瞼を閉じるその顔にあらためて触れれば、間違いなく、その肌は平素にはない熱をはらんでいた。薄闇のなか浮かぶ白い肌も、こころなしか上気している。
「もしかして、熱があるんじゃ」
あわてて立ち上がり、サイドテーブルの引き出しから体温計を取り出す。寝ぼけ眼のサボへ手渡すと、サボはおとなしくそれを脇に挟んだ。
数分後見た体温計の目盛りは、三十八度をさしていた。ナマエは愕然とした。
「やっぱり!どうしよう。きっと私が風邪うつしちゃったんです……」
「おー。すげェ、けっこうあるな」
体温計を片手にサボがからりと笑う。
「総長が風邪なんて……あの馬鹿みたいに体の強い総長が……」
「……お前、今だいぶ失礼なこと言ってるぞ」
「あっ、……すみません」
「まァいいけどよ」
言って、布団のなかでごろりと寝返りを打つ。
「お約束のパターンだな。ま、すぐ治るだろ。……溜まってる書類をコアラに押し付けるチャンスか」
「……うう。コアラちゃんにも申し訳ない。私にもなにか、できることがあれば……」
あるだろうか。
サボもコアラも、平の構成員であるナマエよりずっと責任ある仕事をこなしている。
ベッドへ浅く座りながらうんうんと唸り声をあげていると、
「あるだろ」
サボが平然と答えた。
「おれの看病してくれよ。お前が世話してくれるんなら、それこそすぐによくなる」
な? いいだろ。
言って、サボはナマエの手を取り、その手のひらへ唇を落とした。伏せた睫毛の隙間から青い瞳がナマエを見上げる。
サボとの触れ合いには慣れてきたつもりのナマエだったけれど、こうした瞬間、どきりとしてしまうのは相変わらずだった。
さっと耳先が赤くなるのを感じながら、こくりと頷く。
「それは、もちろん。責任は取ります」
「責任って。そこは恋人として、だろ?」
サボが喉元で笑う。それからその腕でナマエの腰をぐいと抱き寄せる。
あ、と思う暇もないまま、サボの腕にすっぽりと包み込まれた。されるがままに身をあずけながら、ナマエはこのあとのことを考える。
ドクターに頼んで薬を貰って、コアラちゃんやハックさんへの報告もいるし、滋養のある料理は、できれば私自身の手で作ってあげたい。少しでも早く元気になって貰わないと。
……決意しながらも、ナマエはもう少しだけ、とサボの腕のなかにいる幸せに身を浸した。
サボのぬくもり。それが背中にある。
とても幸せだった。
耳元でサボが笑う気配がする。総長も私と同じ気持ちならいい、そう思って、ナマエは静かに目を閉じる。
窓から差し込む光はやわらかく、もうすっかり朝の眩さをのせて、寄り添うふたりを照らし出していた。
(背中に愛がある)end.