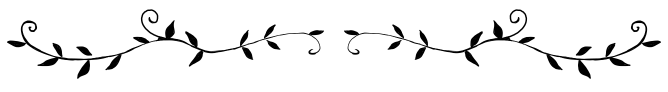現実逃避だった。親に決められた習い事を淡々とこなす日々の、その虚しさからの逃避。
近所の図書館で借りた本は、どれも角が擦り切れていたし、表紙も日焼けしていた。それでもおれには、その本たちがどれもピカピカに輝いて見えたものだ。
この中には本物の自由が詰まっている。窮屈さで溺れそうなおれにとって、何よりも欲しいものが。
「その頃はまだエースと知り合ってねェし、周りにいる奴らとは、馬が合わなかったしよ。そんなだから余計、読書に傾倒していったんだよな」
「サボくんそれ、今話すことかな?!」
真横を走るナマエが、ぜいぜいと息を切らしながら叫んだ。ずいぶんと苦しそうだ。
アスファルトを蹴る足を緩めて、背後を振り返る。街灯の連なる夜の町。おれが抜け出してきた屋敷はもう見えない。
追手はなさそうだった。
「案外、バレねェもんだな。パーティーの主役がいなくなっても」
笑いながら言ってみたものの、返事がない。見れば、ナマエは地面にしゃがみ込み肩で息をしていた。
「大丈夫か?」
「……キツい。ちょっとは加減して」
「悪かったよ。ここからはゆっくり行くか」
ほら、と差し出した手をナマエが握り返す。
引っ張り上げたナマエの体は羽のように軽い……とは言えず、つい「重いな」と呟けば、容赦のないゲンコツがおれを襲った。
「女の子になんてこと言うの」
「でも軽くはねェだろ、実際」
「……もういいもん」
拗ねるナマエを横目に、おれ達はぽつぽつと歩き出した。
静かな夜だった。通りに人影はなく、聞こえるのは、遠くのほうで響く車のクラクション音。それからおれ達二人の足音だけだ。
通り過ぎる家々から漏れ出る明かりを、なんとはなしに目で追っていると、くい、と小さく腕を引かれた。
「本当によかったの? あんなにちゃんとしたパーティーなのに、抜け出しちゃって……」
ちゃんとしたパーティー、という言葉につい、渋い気持ちになる。
確かに今日は、屋敷でおれの誕生日パーティーが開かれていた。母が直々に手配したのだという催しは、例年の如く豪勢な、上っ面ばかりを取り繕ったつまらないものだった。
上流階級としての見得。コネクション作りの社交場。実態はそんなもので、誰一人としておれを心から祝う奴なんていやしない。
そんな実状をよく分かっていないナマエは、いかにも不安げにおれを見つめている。
パーティーから抜け出す手引きをしたことを、引け目に感じているのだろう。
おれはいたって気楽に答えた。
「構わねェさ。ひと通りの顔見せ程度はしておいた」
「……でも」
「大丈夫だって。それによ」
正面にコンクリート作りの校舎が見えてきた。おれ達が二年前に卒業した中学校。目的地だ。
おれは立ち止まって、ナマエの目をしっかと見る。黒目がちの瞳は子供の頃からずっと変わらない。
「せっかくナマエ達が祝ってくれるっていうんだ、おれとしてはパーティーなんかよりそっちのがずっと行きてェよ」
おれの言葉に、ナマエは照れたようにはにかんだ。繋いだ手をぎゅっと握って、「サボくん、あのね」夜風に乗せて囁く。
「お誕生日おめでとう」
屋敷から抜け出す手伝いを、エースでもルフィでもなくナマエに頼んだのはきっと、彼女からのこの言葉を何よりも聞きたかったからなのだろう。
今ではそれがよく、わかっていた。
「ああ。ありがとな、ナマエ」
◇
3-Dの教室の扉を開くなり、けたたましい炸裂音が火花とともに頭上へ降り注ぎ、おれを驚かせた。
「やってくれるなァ!」
髪に絡まる赤や黄色の紙テープを、指先でつまみ上げながらそう言えば、得意げな顔がみっつ。三人は顔を見合わせて「成功だな!」などと、ゲラゲラ笑いながらハイタッチしている。
もちろん、ナマエとルフィとエースだ。
空になったクラッカーを放り投げながら、エースがおれの肩を叩く。
「駆け落ちに不備はなかったかよ、お姫様?」
「抜かりはねェさ。ルフィ、今のは凄いな! 驚いたぞ!」
「そうだろー? ししし、大成功だな、エース、ナマエ!」
満足げなルフィの手に目をやって、ぎょっとした。一人でクラッカーを三個も持っている。
「なあ、クラッカーの数凄くねェか?」
「一人ひとつじゃサボくんは驚かないだろうからって、エースくんが」
「な? 驚いたろ?」
「まあな。ご覧のとおりだ」
肩を竦めるおれに、「それだけじゃないからね!」、ナマエが声を弾ませた。両腕を大きく広げながら、教室中を示すように、その場でぐるりと回ってみせる。
「じゃーん! 見て見て、この飾り付け! いい感じにできてるでしょう?」
「サボ! ケーキもあるぞ! それから肉!」
「アー……肉はルフィのせいでちィっと減っちまったがな……」
「美味かった!」
「そーかよ。ルフィ、一応言っとくがこのあと少しは遠慮しろ」
「う……がんばる」
「頑張ってルフィくん!」
賑やかなやり取りを聞きながら、改めて教室内を見渡した。
普段は均等に並べられている数十もの机や椅子は、五つを残してすべて後方に退けられていた。壁一面には造花やバルーンがいくつも飾り付けられており、これはナマエが担当したのだろう。
室内の中央には、五つの机を合わせた上に、フライドチキンやピザやサラダやらの料理と、ろうそくの灯ったケーキが乗っている。
胸の底がじんわりとあたたかくなる心地がして、思わず頬が緩む。最高の誕生日祝いだ。
辺りを見てだんまりするおれの腕を、ルフィが掴んで揺すった。
「なあサボ! 早くしろよ!」
「ああ……」
うながされるままに椅子に座る。
ナマエの手によって教室の照明が落とされ、ろうそくの炎が室内を薄赤く染めるなか、おれは三人の顔を見渡した。
窮屈な日々を溺れるように生きていたおれにできた、大事な兄弟達。
天井まで積み上がるほど読んだ、どんな冒険の本よりも、こいつらと共に過ごす時間は自由に満ちていた。
「エース、ルフィ、ナマエ」
「なんだよ?」
「ん?」
「なに?」
三者三様の返事に、おれは笑いかける。
「お前達と兄弟になれて……おれは幸せだ」
言うなり、ふっ、とろうそくを吹き消した。
一面の暗闇のなか、目蓋の裏に残る炎の赤が眩しくて、おれは目尻に浮いた涙をそっと拭った。
◇
「それにしても中学か……懐かしいな」
「だろ? しかも、3-D」
「おれ達三人の組だ」
「サボ達はずりーよなー、おれだけ学年ちげェんだもん」
「すまねェなルフィ……心はいつもひとつだ……!」
「サボ……ブラコンはいい加減卒業しろ」
「エースくんもたいがいブラコンだと思うけどなあ」
「おれは違ェ!」