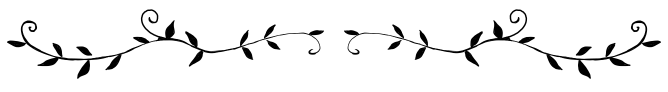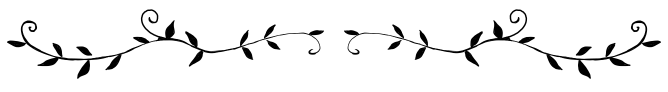何か困り事があると、なんであれこころよく力を貸してくれた。あるいは重い荷物を運ぶとき。探しものが見つからないとき。
さまざまな場面において、彼はいつだってここしかないというタイミングで現れるのだ。
金色の隻眼に覗き込まれ、「どうしたの?」とやわらかな声で尋ねられると、それだけでどんな不安も吹き飛んでいくから不思議だった。
「燭台切さんは凄いですね」
作業台に向かい、絹さやのヘタを取っている最中のこと。ふと思い立ったままそう告げると、燭台切さんがきょとんとした顔で私を見た。
厨には他にも鯰尾くんと骨喰くん、歌仙さんがいたが、皆忙しなくあたりを行き来していて、私の声に反応したのは目の前にいた彼ただ一人だった。
「急にどうしたんだい」
「いつも思ってるんです。気遣い上手で、頼りになるなって。……お料理もうまいし」
話しながら、私も燭台切さんも手は止めない。ひとつ、ふたつ、処理済みの絹さやをボウルへ放り込む。
ふたりで休みなく作業したおかげで、山のようだった未処理の絹さやも残りわずかだ。今晩はこれを鶏肉とあわせて卵とじにするのだという。
「ありがとう。主にそう言って貰えるなんて光栄だな」
「お世辞だと思ってる? 本気で言ってるからね」
「大丈夫。わかってるよ。……いきなりだったし、ちょっと照れるけどね」
そう言ってはにかむ姿は、一片の隙なく整っている。いい男というのは、絹さやを持つ姿さえ様になってしまうらしかった。
「私も燭台切さんを見習わないとな」
「主は今のままで充分だよ。主が僕達のことを道具としても人としても大切にしてくれてること、みんなちゃんとわかってるから」
ほら、やっぱり。
こうした相手を思い遣ることばを、いつも与えてくれる彼だった。
「そういうところが凄いなって思うんだよ」
「うーん。そうかな?」
首を傾げる彼に、「そうだよ」と相槌する。だってほんとうにそうなのだ。
ふいに沈黙が落ちた。燭台切さんが無言で作業をするので、私も彼に倣って作業に集中することにした。ぱきぱきり。ヘタを折るときの小気味のよい音だけが、私たち二人の隙間を埋めていく。
「下心がある……と言ったら、どうする?」
静かな声だった。
雑音に呑まれそうなほど小さな音。かろうじて拾ったものの、その意味まではわからずに、私はただ彼を見ようと顔を上げる。
琥珀の瞳は私をとらえながら、どこか挑発するかのように、ゆっくりと瞬いてみせた。
「今、なんて?」
「いつも主が困っていないか探してる。他の誰でもなく、僕だけを頼って欲しいから。……案外狭量だろう?」
落ちついたバリトンの響きは私を安心させてくれるものだったのに。今はこの心臓をこんなにも煩くさせる。
私が呆然としていると、燭台切さんは小さく笑って私の耳元へ唇を寄せた。
「これがどういう意味か、今度考えてみて」
耳朶にかかる吐息はやけに甘ったるくて、目眩がするようだった。
「さあ主。続き、しないとね」
身を引いてほほえむ燭台切さんはもういつも通りだ。私は喉の奥に棘を残したまま、目の前のかごへと手を伸ばした。
かごのなかの絹さやはもう間もなく無くなってしまう。この作業を終えたあと、私はいったい彼にどんな顔を向ければいいのか。検討もつかなかった。
せめて、意識するほど熱を帯びる、この頬の色に気づかれませんように。
祈るような想いを知らない彼の指が、最後のひとつをていねいに処理するさまを、そっと眺める。その繊細な動きとはうらはらの、骨ばった指。
それは私とはまるで違う、男のひとの手をしていた。
(燭台切光忠と下心 )end.