恋人のキスをして
午後の授業はレオナ先輩の出席率が悪い。
昼食を食べ終わった後で腹も膨れれば眠気が襲う。それはレオナ先輩でなくとも同じだ。
しかも場所は日当たりのいい、ポカポカした温室。
草木が生い茂り、この草花の感触も匂いも、故郷のジャングルを思い出して至極居心地のいい場所ではある。
一緒に温室で昼食を食べ終わった後、レオナ先輩の腕の中にとじこめられながらスリスリと頬を擦り合わせられて、こちらも同じ様に擦り合わせた。
そうなるとレオナ先輩はいつものように、私の耳に舌を這わせてグルーミングを開始する。
温かい腕の中で耳の毛をグルーミングされれば、うとうとしてしまうのは仕方のないことだと思う。
これが夜だったり、休日だったらこの行為を受け入れて、一緒にうとうとしてしまうのだが、今はダメだ。
これから午後の授業があるというのに、一緒になって眠ってしまえば一緒にサボってしまいそうだ。
「レオナ先輩…眠くなるので、やめてください」
「眠ればいいだろ」
当然のように魅力的なお誘いをしてくるが、誘惑に負けてはいけない。
私は先輩と違って授業をサボったことなどないのだから。
「ダメです。午後の授業、ちゃんと行かないと」
「お前もサボれ」
耳のグルーミングに加えて、後頭部を優しく撫でられる。
レオナ先輩と恋人同士となり、こうしたスキンシップに漸く最近になって慣れることが出来た。
最初は羞恥心のが勝って、こんな腕の中に居られるわけもなく、心臓はバクバクで緊張で体はガチガチに固まってしまうし、眠るなんて言語道断だったのに。
今ではレオナ先輩の心音すらも心地よく感じて、すっかり安心しきってしまう。
知らない間に尻尾までも絡まり合っているが、それももう慣れた。
「ナマエ」
名前を呼ばれて顔を上げれば、今度は唇が合わさる。
ちゅっと小さく音を鳴らして離れていくのだが、その熱が妙に寂しく感じて自分からもう一度唇を触れ合わせた。
「…キスに慣れてきたな」
「えっと、まあ、そうですね」
以前はキスされるたびに顔を真っ赤にして、緊張で体に力が入ってしまっていたのだが、最近はごく自然にレオナ先輩からのキスを受け入れている。
それに、羞恥心はあるのだが、今の様に自分からキスすることだって出来るようになった。
肩を押されて仰向けにされると、レオナ先輩が私に覆いかぶさる。
さすがにいつもと違う体勢と、狩りの時のような雰囲気に戸惑う。
たまに感じるが、自分も肉食動物のはずなのに絶対的王者であるこの人を目の前にしたら草食動物の気持ちが少し分かる気がする。口が裂けても言わないが。
「あの、レオナ先輩?」
「そろそろ、恋人同士のキスってもんを教えてやる」
「?キスに種類があるんですか?」
「ある」
恋人同士のやり取りなど私には無縁の話しだったし、経験だって一切ない。
キスだって初めてだったし、何なら異性にグルーミングされるのも、抱きしめられたのも初めてだったのだ。
その私がキスに種類があることなど知るわけがない。
私の男性経験というものはレオナ先輩が初めてなのだから。
小さく頷くとレオナ先輩が満足そうに口角を上げた。
レオナ先輩の親指が私の唇をなぞり、少し口を開けばいつものように唇を合わせ…
「んんっ!」
唇を塞がれた後にザラリとした猫科特有の舌が私の口内に侵入してきて、私の犬歯を舐めた後に私の舌に絡み付いてきた。
トラの獣人である私自身もレオナ先輩と同じ猫科。そんな私の舌の感触を楽しむかのように口内で弄ばれる。
「んぅ…ふっ…」
くちゅっと音が聞こえる。この音はなんだか恥ずかしい。
心臓がバクバクだ。苦しいぐらいに。
何だか腰の辺りがゾクゾクしてくる。何故だか腰をもぞもぞと動かしたくなる。
飲み込み切れない唾液が口角を伝っていくのを感じる。
自分が何をされているのか理解しようとも頭が追い付かない。
それぐらい、この“恋人同士のキス”というものが予想外の行為だ。
呼吸の仕方が分からないから苦しいのだが、何だか今まで以上にいけないことをしている気分になってきた。
「はっ、はぁ…っ!」
酸素不足と初めての感覚にぼんやりとしていたが、口角をザラリと舐められて目を見開いた。
唇が熱い。いや、顔も体も、全体的に熱くなっている気がする。
それに心臓が爆発してしまうのではないかと思うくらい、鼓動が速い。
ただ、今まで以上にレオナ先輩と近くなった気がするし、キスよりも抱きしめられるよりも、愛が深まったとも感じる。
はぁはぁと息を切らしている私と違って、レオナ先輩は余裕の表情で舌舐めずりをした。
「どうだった」
「えっと…」
感想を聞かれるとは思っていなかったので、考えるよりも感じたことをそのまま口に出して伝える。
「なんか体が熱くなって…腰辺りが変な感じになりました…。今までのキスよりも…その…変かもしれませんが、気持ちよかった気がします…」
素直にそう伝えたのだが、私の返答が予想外だったのかマズイことを口走ってしまったのか、レオナ先輩は目を丸くした後に顔を顰めた。
「随分と煽ってくれるじゃねぇか」
「あお…?煽る?」
「まぁ、いつか分かる。とりあえず今はまだ、こっちで我慢してやる。ゆっくり進めねぇと、恐怖で逃げられるかもしれねぇからな」
そう言って噛みつくように唇を塞がれ、先ほどと同じ恋人同士のキスっていうものをラギーがレオナ先輩を呼びにくるまでやられ続けた。
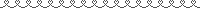
初めて恋人同士のキスをされてから、レオナ先輩のタガが外れてしまったかのようにそのキスばかりされるようになった。
それどころか、以前よりも長く深く、そして回数も格段に増えた気がする。
もちろん二人っきりの場所ではあるが、温室はもちろんのこと、レオナ先輩の自室、空き教室、運動場、私とラギーの部屋。恐ろしいことにサバナクロー寮の談話室でまでやられた時にはさすがに血の気が引いた。
そして、今まさに談話室よりも人に見られそうな場所でされそうになっていて抵抗しているのだが、ここは学園内の廊下。
人の気配が今はなくとも、いつ誰が通ってもおかしくはない。
「っ!レオナ先輩!ここではっ」
「お前が無駄に騒ぐと誰か来るかもなァ」
「っ!んんぅっ」
体格に差がありすぎて、壁際に追い詰められた私は壁とレオナ先輩に挟まれれば逃げ場はない。
レオナ先輩の言葉に思わず口を噤んでしまえば、噛みつくように唇を塞がれる。
そうなれば容易に舌が侵入してきて、後はもうされるがままだ。
レオナ先輩の制服を握りしめ、何とか倒れないようにしがみ付くが足は生まれたての小鹿のようにガクガクになる。
倒れ込むことでこのキスから逃れようとしたが、私の足の間にレオナ先輩の片足が入り込みグイッと持ち上げられると、とうとう完全に逃げ場を失った。
私たち獣人は聴覚がとても鋭い。
周囲の音もそうだが、もちろん恋人同士のキスとやらをされている時のくちゅっという恥ずかしい音もはっきりと聞こえてくるのだが、これがいつまで経っても何回していても恥ずかしい。
「ん、はっ、はぁ…」
ちゅっとリップ音を立てて離れると、レオナ先輩はこのキスの後に必ず私の口角を舐め取る。これも本当にやめていただきたい。
文句を言おうと口を開こうとすれば後頭部をぐいっと掴まれて、顔面をレオナ先輩の胸元に押し付けられた。
「ぶふっ」
「歯止めが効かなくなってきてるな…」
大きく溜息をついて、そう呟くと少し抱きしめる腕の力を抜いてくれて顔を上げる。
私の目を見るとレオナ先輩はまた溜息をついて頬を摺り寄せてきた。
「まだ慣れねぇか」
「慣れませんよ…」
「だろうな…まあいい。どちらにしろ、そろそろ俺が限界だ」
何が限界なのか問いかける前に再び口を塞がれる。
一度こうして塞がれてしまえば、息苦しさからなのかもう何も考えられなくなるし、やっと解放される頃にはボーっとした状態で必死に呼吸をするしか出来ない。
耳を甘噛みされてびくっと体が震えると、レオナ先輩は笑っているのかその振動が私の体に伝わってくる。
「近いうちに、キス以上のことも教えてやる」
「キス…以上…?いいです、今はもう勘弁してください…」
キスに慣れてきたと思えば、今度は恋人のキスとかいうものを教えられたばかり。
このキスだけでいっぱいいっぱいになるというのに、これ以上の濃厚な行為は私の頭が爆発しそうだ。
私がレオナ先輩の鋭い視線から逃げるように目をそらせると、顎を掴まれて覗き込まれた。
「俺から逃げられると思うか?」
答えはノーだ。獲物を見つけたライオンから逃れられるのなんてチーターか豹ぐらいじゃないか?
こちらはトラの、しかも雌なのだから。
「それとも尻尾を巻いて…逃げるか?」
「っ!逃げませんよ。望むところです」
ニヤニヤしながら言われているし、安い挑発ということは分かっているのだが、「尻尾を巻いて逃げる」といわれるとどうしても言い返したくなる。
きっとレオナ先輩はそれを分かっててわざと私にそんなことを言ったのだろう。狡猾なサバナクローの寮長らしい。
キス以上のこととは想像もつかないが、一体何をされるのか。考えるだけでも顔が熱くなる。
「週末、俺の部屋へ来い。ラギーには俺から言っといてやる」
そう言い残して立ち去るレオナ先輩の背中を見送り、私はその場でズルズルと座り込みながら自分の唇を押さえた。
これ以上の何があるのか、未知なる体験が待っていることにワクワクもするが何故だか恐怖も感じる。私の本能だろうか。
ただ、レオナ先輩にされることなら受け入れたいと思う。
恋人同士のキスとやらにも早く慣れないと。
そんな思いを胸に、私は教室へと戻っていった。