わたしだけにキスして
外の任務に新人たちが駆り出されている中、中堅組の3人は揃ってデスクワークをしていた。
私の席の隣には山積みになっている書類で隠れながら、サボって雑誌を読んでいる、レノ。
反対側にはレノとは違い、真面目にデスクワークに励んでいるルード。
ルードのように真面目にデスクワークに励む気力もなく、かといってレノのように時間を潰せるような雑誌を持っているわけでもない。
仕方なく真面目に取り組もうと、パソコンへ視線を戻すと隣から雑誌が放り投げられた。
「お前パパラッチに写真撮られてるぞ、と」
レノの言葉に「はぁ?」っと声をあげて雑誌を掴む。
神羅の英雄、金髪美女とキス。
そうデカデカと書かれた文字を読んで、必死に記憶を呼び起こす。
外ではあまりキスをしていないし、私だって気配には敏感だ。
パパラッチの存在があれば私もセフィロスも気が付くはず。
「まあ、その出版社は反神羅の出してるとこだから揉み消せなかったんだろーな、と」
そんなことをレノが言ってきて、ははっと空笑いして問題の写真を見るためにページを捲り、目に入った途端に息を飲んだ。
まるで頭を鈍器で殴られたかのような衝撃と、戸惑いと悲しみと苛立ちと、色んな負の感情が沸き起こる。
「随分と大胆なキスシーンだな、と」
覗き込んできたレノに対し、雑誌を握りしめて私は呟いた。
「違う」
「ん?」
「私じゃない、この女」
「は?…あー…」
気まずそうな雰囲気になってしまったが、そんなことを気にするほど今の私は余裕がない。
それなのにレノは私に追い打ちをかけるような言葉を吐き出す。
「まあ、あんな全てを持ってる男なら女は選び放題だし…。男の浮気は勲章みたいなもんだぞ、ぐはぁっ!」
雑誌をレノの顔面に叩きつけ、私は無言で立ち上がる。
直接本人に問いただすしかない。
「いって…」
「お前が悪いぞ、レノ…」
ルードの哀れんだ声を背中にタークスの執務室を飛び出した。
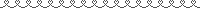
ソルジャーフロアへ向かう為にエレベーターを待つ。
その間にも頭の中は怒りと悲しみでいっぱいだった。
ずっと二人でいようと、わざわざ私の故郷にまで連れていってくれたのに。
こんな裏切り方をされるなんてひどすぎる。
胸が張り裂けそうなぐらい苦しい。
涙を流したら負けな気がしてぐっと堪えて、自分の唇をごしごしと力強く擦る。
私はセフィロスしかしていないし、セフィロス以外とキスなんて考えられない。
あれだけ私を独占して愛してると囁いて、夢中にさせといて…
考えれば考えるほど今までにない感情が私の中で渦巻いていく。
こんな思いをさせられるのなら、いっそのこと…。
その思いが頭を過ったが、嫌なことにそんな時に限ってセフィロスとの楽しい思い出ばかりが頭を駆け巡る。
落ち着かせようとエレベーターに乗り込んでからも深呼吸を繰り返したのに、心は全く落ち着かない。
私にとって異性と付き合うというのはセフィロスが初めてだ。
セフィロスは今までたくさんの人と付き合ってきたのかもしれないが、私は初めてなのだ。そんな初心者に対してこんな裏切りの仕方をされるとは、全く想像もつかなかった。
いや、普段のセフィロスを見れば私だけを愛してると感じさせていたのに。
ソルジャーフロアに到着して、あんなに勢いよく行こうと早足になっていた私はその場で立ち尽くした。
いざ、別れの言葉を口にするのはかなり辛い。
なぜ浮気された側なのにこんな思いをして言葉にしなくてはならないのだ。
「あれ?ナマエ?」
「ザックス…」
立ち尽くしていた私の元にザックスが駆け寄ってくる。
同じ2ndの仲間であり、友達でもある彼はこの事を言えばきっとセフィロスに怒って、私に優しく声をかけてくれるだろう。
今の私に彼の優しさはダメだ。ここまで我慢してきた涙が溢れてしまう。
「何でもない。私帰るんだった」
「へ?まだ午前なのに?」
「うん。ちょっと体調悪くて早退するの」
「あー…確かに顔色悪いな。セフィロスにも言って」「言わなくていい!」
思わず声を荒げてしまってハッとなった。
これではセフィロスと何かあったことを知らせるようなもんだ。
私は誤魔化すように笑って「心配させたくないから」と嘘をつき、ザックスの顔を見ずにすぐに非常階段へ向かう。
とにかく一人になりたい。本当は怒りをセフィロス本人へぶつけたかったが、それもそれで虚しさや悔しさが増すだけな気がする。
階段を降りながらツォンに連絡し、任務が入ったら出るから連絡してとだけ伝え、ソルジャー寮へ駆け出した。
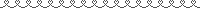
寮に着いてからベッドに倒れ込むと、枕に顔面を押し付けた。
やっと一人きりの空間に来れて安心したのか、堪えていた涙が止め処なく溢れてくる。
あんな別れてやるって怒っていたのに、今はただただ悲しいだけだ。
散々泣いた後、ふと先ほどのザックスのことを思い出す。
心配してくれていたのに何だか悪い態度だったなと反省し、謝りのメールでも送っておこうと携帯を取り出した瞬間、着信が鳴り響いてびくっと体が震える。
「セフィロス…」
電話に出る気になれず、そのまま携帯を放り投げて目を閉じる。
もちろん、携帯はずっと鳴り続けていたが無視をし続けた。
しばらく鳴っていたが、そのうちやっと静かになったと思えば今度はアンジールからの着信。
さすがに無視はできなかった。
「はい」
『おれの番号で出ないとはどういうことだ』
「…」
何となくそんな気もしていたが、やはりアンジールの携帯からかけていたのはセフィロスだったらしい。
きっとアンジールは呆れて溜息をついているだろう。そんな姿が想像できる。
『レノから聞いた。あれは』
「聞きたくない。さようなら」
それだけ言って電話を切り、せっかく止まった涙が再び溢れてきた。
「さようなら」の言葉がこんなに辛い言葉だと思ったのは人生で初めてだ。
だが、これ以上セフィロスから言い訳など聞きたくなかったし、あの写真は起きたことの事実なのだから。
泣き続けたら疲れて眠気が私を襲う。
私は抗うことなく、そのまま意識を手放した。
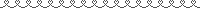
ギシッとベッドの軋む音でハッとなり、すぐにその相手の喉もと目掛けて枕元にあったナイフを向けた。
「っ!」
「その素早い対処は褒めてやる。だが、指導者として欲を言えば侵入してきた時点で気がつくべきだったな」
ナイフを掴んだ手は簡単に掴まれてシーツに押しつけられる。
私の対処に上官らしく、頼んでもいない指導してきたのはセフィロスだ。
ソルジャーの中のトップの実力のある彼の気配を察知できる人間が居るのかは疑問だが、それよりも今の私の気にすべきところはそこではない。
「…泣いたのか」
「泣くでしょうよ。こんな裏切られ方をされれば」
私に覆い被さるようにして見下ろしているセフィロスを睨みつけながら、吐き捨てるように言った。
両手はシーツに押さえ付けられているし、下半身はセフィロスの体が乗っている為動かすことは出来ない。
まだセフィロスと話す心の準備はしてなかったし、目が自然と唇にいってしまう。
「俺は確かにあの女とキスをした」
突然のセフィロスからの言葉に息が止まりそうになる。
私が言葉を失っているとセフィロスは、まるで宥めるように私の額にキスをした。
「あれは2年前のお前と付き合う前だ」
「…付き合う前…?」
「お前と出会ったあの日、俺はお前の事が気になり始めていたのは話したな。手に入らないお前の代わりに、あの女と………キスをした」
キスをしたという前の間がものすごく気にはなるが、付き合う前にセフィロスが色んな女の人と関係を持っていたのはもちろん知っていたし、それを承知で付き合ってはいるのだが。
今回のように直接写真を見てしまうことはなかったから、ぼんやりと他の女の人と絡んでたんだなぁとしか思っていなかった。
だから写真で実際にセフィロスが他の女の人とキスをしているのを見て、生々しくなって…ああ、そうかこれが嫉妬。私にもこんなどす黒い、女らしい感情があったのか。
ソルジャーという男社会に身を置いているからセフィロスが嫉妬することはあっても、私は滅多にすることはなかった。
だからこそ、今こんなにも動揺している。
私が黙り込んでいるのをいいことに、セフィロスは私の顔に小さくリップ音を立てながらキスの雨を降らせた。
「ん、ちょ、ま、やめ、キスやめて!」
「珍しくそんな激しい嫉妬を…くくく」
「…私怒ってんだけど」
「くくく、悪いな」
セフィロスは私の頭を抱きかかえるように片腕を回し、耳元で笑い始める。
ものすごく愉快そうだが、こちらはものすごく不愉快極まりない。
顔を顰めてセフィロスの両肩に手を置いて、なんとか押し返そうと手に力を込める。
「んぐぐぐ」
「ナマエ」
「何よ。いい加減、離れてよっ」
「俺が浮気してるとまだ疑っているのか?」
答えはノーだ。
こんだけ悲しんで悔しがって、別れまで切り出そうとしておいてと思うが、先ほどの優しいキスの嵐で安心してしまっている自分がいる。
「…」
「俺の体に発信器でもつけるか?」
「…それもいいわね」
「満足するまで好きにするといい。それでお前が安心するのなら協力する」
何だかどんどん自分が幼稚に思えてきた。
もちろん本気でセフィロスに発信器を付ける気なんてないし、直接こうして話しをしたら疑いなど消え去っている。
だけども、素直に「付き合う前のことなら仕方がないよね」なんて言えない。そんな心の広い女にはなれない。
「もういい」
「くくく、今度は拗ねるのか」
頬を優しく撫でる手が温かい。
セフィロスが甘やかす動作をするものだから、その手に縋り付いて甘えたくなる。
頬を優しく撫でていた大きな掌が離れて、指先で涙の痕を追う。
少しは罪悪感でも感じてくれたのだろうか。
「お前の悲しむ涙はあまり見たくはないが…俺を思って流す涙はいいな」
「…最低」
ぎしっとベッドの軋む音とともにセフィロスのサラサラな銀色の髪がシーツに流れ、息のかかる距離まで近寄ると唇の触れ合いそうなところで止まる。
「もっとお前から俺を求めろ。この俺をお前が独占すればいい。望みは何だ」
そう囁いて私の唇を塞いだ。
もう今はこのキスで流されてあげてもいいって気になってきた。
私はセフィロスの首の後ろに両手を回し、唇が離れたところで仕返しとばかりにセフィロスに唇を甘噛みする。
「私にだけキスをして」
返事の代わりにセフィロスは私に噛みつくようにキスをした。