
「おれの女になれ」
「はい…」
我ながらなんてバカなことを言ってしまったんだ。
まるで命を救ってやったことを建前に、彼女に断れないような状況で。
ただ、あそこまで体が悪い状態でもおれに頼らなかったことに、名前の中でおれの存在がそこまで小さいのかと感じさせて。
焦燥感、絶望感…何が何でも繋ぎ止めたいと出てきた言葉が「女になれ」だ。
彼女の病室を出てナースステーションで診察内容を記録しながら、大きなため息が出た。
軽い肺炎状態で入院させるのに、内科でなく自分の病棟である循環器に入院させたのは完全なる私情。
まぁ、もともと科に関係なくとも家族が自分の病棟の個室へ入院することはよくあること。
他のスタッフもやってきたことではあるが、まさか自分がそうするとは思わなかった。
しかも、妻でもなく、彼女でもなく、ただのお見合い相手。
「トラファルガー先生。彼女さんの血液データです」
「ああ」
自分の病棟に入院させることで、名前はおれの彼女という位置づけをされた。
別に今となっては正式に彼女になったのだから問題ないのだろうが…
そこで先ほどの後悔の渦に再び頭を侵される。
あれでは彼女はおれに対して“好き”という感情ではなく、命の恩人だから“断れなくて”あの返事だったのだろう。
脅しの様なものだと言われても過言ではない。
だが…もう後の祭りだ。
だったらこの手を利用して一気に攻めて、落とす。
順番は逆になったが、この手はきっかけとして使えばいい。
そうなると気になってくるのは彼女が住んでいたアパートのこと。
あんな安いアパートでセキュリティーもスッカスカで、ましてやあの日鍵をかけ忘れたなど軽くっていたが、あの様子だとたまにやっていそうだ。
つまり、ものすごく危ない。危機感も足りない。
少々強引だが、一番安心するのはおれのマンションへ住まわせることだ。
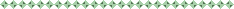
「ラミ、話がある」
「?なあに、お兄ちゃん」
ラムを寝かしつけたあとのラミに声をかけ、おれは名前のことを話すことにした。
「ラムがよく話している名前先生って覚えているか」
「うん?もちろん覚えてるよ。私もお迎えに行くとしょっちゅう話しかけちゃうんだよね、明るくて気さくな可愛い先生」
「おれが今付き合ってる」
「…え?」
口が開いたまま塞がらない。
そんな顔でラミは言葉を失ったかのように口をパクパクさせた。
「ま、まさか…お兄ちゃん…ラムの園の保育士に手を…出すなんて…」
「違ェ。見合い相手だったんだ。別にラムの保育園で口説いたわけじゃねェ」
「そ、そうなんだ…」
「これがラムの父親がおれで、不倫してるんなら問題なんだろうが。生憎おれはラムの父親でもなければ、結婚もしてねェ」
だから別に隠す必要もなく、後ろめたくなる必要もないと思うのだが。
ラミは少し考えた後に腕を組んで唸り始めた。
「そりゃあお兄ちゃんはいいのかもしれないけど…向こうは複雑じゃないかな。一応、園児の家族なんだし」
「関係ねェだろ」
「先生が可哀相だよ。だからお付き合いは隠しておいた方がいいかもね。もしくは名前先生が他の園にうつるかラムが他の園にうつるか…」
「…」
もっと単純に考えていたがそうもいかないらしい。
他の先生は他の保護者も居る手前、簡単には考えられないということか。
どちらにしろ正式に結婚すれば仕事を辞めておれが養ってもいいのだし。
「お兄ちゃん、おれが養ってやればいいとか考えてない?」
「…考えてる」
「あのねぇ…今はそういう時代じゃないのよ。向こうは保育士っていう専門職で資格を手にするために頑張ってきたの。それをおれの都合に合わせて辞めろなんて、私だったら速攻で別れるよ」
ラミのいう言葉が尤もすぎて言葉を失った。
ただ一緒に居たいという理由で縛り付けるのは確かに良くはない。
今後の付き合いについては名前とじっくり話す必要があるな。
…だが、こんな複雑になるんならやっぱり付き合うのをやめると言われたら?
まだ向こうはおれに落ちても居ないし、命の恩人という建前で付き合っているようなもんだ。
そんな関係は障害が出来てしまえばすぐにでも簡単に崩れてしまうのでは、と考えてしまう。
「それで?お兄ちゃんは何を私に言いたかったの?」
「…名前の住んでいるアパートがあまりに酷くて…ここに連れて帰ってきていいか」
「それはまずいわね。他の保護者に見られたら問題になるし」
「ラムは喜ぶと思うが」
「それもまずいのよ。だって名前先生は家でも先生をしなきゃならなくなるのよ?家でもトラファルガー先生、診察お願いしますって言われたらお兄ちゃんならどう思う?」
クソッ。八方ふさがりじゃねェか!
おれは苛々を吐き出すように溜息をつくと、ラミも同じようにため息をついた。
「まぁ…私たちがお兄ちゃんのところから出てけば丸く収まるんだろうけど…それを言ってこないお兄ちゃんには頭が上がらないよ」
「…」
「優しいお兄ちゃんだからグルグルしちゃうんだよね」
確かにそうすれば、ラミの言う通り丸く収まるんだろうがおれには一ミリもそんなこと考えていない。
おれだってラムを可愛がっているし、ラミだっておれを頼りにしてここへ来たのだから受け入れた時点で中途半端に追い出そうなんざ思わない。
医者であるラミは経済力もあるから自分でそれなりのマンションを借りることもできるはずなのに、わざわざおれのマンションへやってきたのはおれを頼りにしているからだ。
そんな妹を無下には出来ない。
「私も何か考えてみるよ。どちらにしろ名前先生には挨拶に行こうと思ってたし。お兄ちゃんの病棟に入院させたんでしょ?」
「おれの病棟の個室にいれた」
「ベッド空いててよかったね」
明日から仕事へ行く楽しみが出来た。
今まではラムの迎えの時にしか顔を見られなかったのに、入院中は毎日見られるのだから。
この機会にじっくり口説かなくてはならない。
アピールして…機会をうかがってまた改めて気持ちを伝え、向こうの気持ちも確認する。
そう考えながら、明日からの仕事のために早めに就寝することにした。
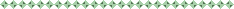
いつもよりだいぶ早く出勤し、真っ先に苗字と書かれた病室へ入る。
ベッドの頭部を上げてテレビを見ている名前がおれに気が付いて、こちらへ顔を向けて頭を下げた。
「おはようございます、トラファルガー先生」
「変わりないか」
「おかげさまでだいぶ楽になりました」
夜勤の記録には特に問題なく、朝のレントゲンも血液データもだいぶ良くなってきている。
「酸素チューブもう取っていい」
「ありがとうございます」
鼻から酸素チューブを取り、にっこりと笑う名前につられておれも頬を緩ませる。
聴診器を耳にかけて目を見れば、察したのか少し頬を赤らめてパジャマの前を開く。
恥じらいながらのその動作は、慣れている医療行為とはいえムラッときた。
女の裸など仕事柄見慣れているが、好きな女を前にすると今の状況は意識せざる負えない。
聴診器を白い肌に当てて肺の音を確認し、背中からも聴診する。
だいぶ音も良くなっているし、経過良好だな。
耳から聴診器を外すと、名前が病衣の前を閉めはじめる。
「問題ない」
「良かった…ありがとうございます」
「いや…何か聞きたいこととかあるか」
「えっと…すごい聞きにくいのですが…」
心配そうに形のいい眉がきゅっと寄せられた。
おれはベッドに腰掛け、名前の頬を手の甲で撫でるとあからさまに体が固まる。
昨日はそんな緊張して体を固める事もなかったというのに。
ああ、昨日までは高熱で意識が朦朧としていたからかと、少し残念に思う。
「大部屋にうつることとか…できます…?」
「…なぜ」
「その…個室代が怖くて…」
てっきりおれがこうして来るのが嫌なのかと思ったが、理由を聞いてくくっと笑った。
「退院手続きもおれがやろうと思ってるし、退院時の清算はおれがする」
「ダメですよ!そんなの!」
「個室じゃねェとおれが口説きにこれねェだろ?」
おれの言葉に驚いた顔をした名前は一気に顔を赤くして口をパクパクとさせる。
そんな表情に胸がキュッと締められて、堪らず後頭部を掴んでおれの胸へ抱き寄せた。
「んな可愛い顔すんな」
「く、口説くなんて」
「つか、お前緊張しすぎじゃねェか?」
「わ、私、基本的に男性が苦手なんです…」
だからこんな体をガチガチに固めていたのか。
今も顔を真っ赤にしておれにされるがままになっている名前。
男慣れしていない初心な感じもおれの胸を高鳴らせた。
「徐々に慣れていきゃいい。とにかく個室から出す気はねェ」
「うう…せ、せめて治療費だけは払わせてください…」
「考えておく」
いまだに緊張している様子の名前の頭を撫でて、前髪を上げ、額に唇を寄せる。
ちゅっとリップ音を鳴らすと、そのタイミングでおれの白衣の胸ポケットから無機質な音が鳴りだす。
「…また、昼に来るからな」
「お忙しいのに」
「おれが来たいだけだ。しっかり休んでろよ」
PHSを片手に立ち上がる前に今度は頬に唇を寄せ、部屋を後にし電話に出る。
要件を終えて電話を切った後、自分のした行動に苦笑したくなった。
こんな甘ったるい行動をおれが起こすとは思わなかったから。
しかも、狙ってやったのではなく、ごく自然と。
名前が愛おしいと思うと自然としてしまった行動。
どんどん名前を好きになっていく。
この気持ちは恋と言わずになんと言うか。
この話しの感想あれば