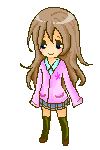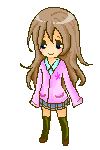まほろばアンカー(♭)
この小説は相互サイトの管理人、りこのオリキャラである瑠璃さんと美優ちゃんをお借りしています。
たたん、と頭上に広げたオリーブグリーンの傘の上で雨が弾ける。朝の予報をしっかり受け止めて昼過ぎから曇りだした今日の空は、夕方になってとうとう霧雨を降らせだした。徐々に強くなるそれを、机に立てた教科書で欠伸を隠しながら眺めていたのが六限目の話。ホームルームの終わりには退屈な授業の終了を照らすかのように一旦止みかけたものだが、先ほど自分が友人と別れて教室を出る頃には、また一層強くなっていた。革靴の先に跳ねた泥を、あ、と気にする間もなく水溜りが溶かして消す。乾いたら薄い跡になるかもしれない。手入れは面倒だ。とはいえ、そんなことは思ってみても雨自体はそれほど好きでも嫌いでもない。片手が傘で塞がるのは少し、億劫ではあるが。
「――――――……」
たん、とまたも滑り落ちた水滴に誘われるように顔を上げて、瑠璃はそのままふっと息を呑んだ。向かいの道沿いの、古びた洋菓子店。その紺と白の縞模様でできた軒の下に、見覚えのある少女が立っている。歩き出す様子のないところを見ると、買い物帰りというわけではないようだ。雨どいから流れ落ちる水を眺めているのか、その眼差しがこちらと噛み合う気配は一向にない。
瑠璃はくるりと手の中で傘の柄を回して、来た道を少し戻り、横断歩道を渡った。ウインカーを出して止まった車のタイヤが濡れて、信号機の青を映す。点滅もしていないのに心なしか歩調が速くなっていくのは、きっと他の何でもない、彼女のせいだ。
「や、何してんの」
「!?」
休まる気配もない雨の中へ、無謀にも今か今かと足を踏み出す機会を窺っている、この彼女の。足早に近づいて声をかければ、雨どいと空中を交互に眺めて躊躇うように足を出したり戻したりしていた彼女は、驚いたように肩を跳ねさせた。そんなにびっくりされると切ないものがある。もうかれこれ一年近く、同じクラスで聞き慣れた声だろうに。
「瑠璃さん」
「ん、奇遇だね。今、帰り?」
「うん、瑠璃さんも?」
「そうだよ」
振り返って顔を確かめれば、ようやく気が緩んだように彼女はふわりと藍色の目を細めた。つられて唇が弧を描く。そっか、と言葉というほどでもなく零される声は、こんな日にも変わらず温かで、周囲の温度を一度上げた気がした。そんな、何とも表現しにくい、けれど悪くない心地。飲み込まれるようにまた一歩近づいて、ああこんなことを考えるためにここへ来たわけではないのだと、我に返って口を開く。
「傘、ないの?」
いわゆる雨宿り、というやつなのだろう。対岸の道で見たときから何となく分かっていたことだが、一応問えば、彼女は困ったように押し黙った。そしてやがて、こくりと頷く。
「……忘れちゃって……、朝、晴れていたものだから」
遅刻しそうになって、慌てて置いてきてしまったみたいで、と。呟くように言って、彼女は髪を直す素振りで、片手を頬に当てた。わずかに染まったそれを見るに、どうやら不注意を恥じているらしい。そそっかしいところのある子だということなど、こちらはとっくに知っているというのに。まあそんなところが彼女のそそっかしさを補って、可愛らしい、の一言で許したくさせるのかもしれないが。
「相変わらずだねえ。はい」
「え?」
「入っていく気、ない?今なら空いてるよ」
ぱたりと瞬くその目の前で、傘を傾けてみせる。冗談めかして手招けば、彼女はぱっと顔を輝かせて、それからすぐに戸惑うような表情を浮かべた。けれどやがて空とこちらの顔を交互に眺め、鞄を抱え直す。
「いいんですか?」
「もちろん」
「ありがとう、瑠璃さん」
軒先から落ちる雨を遮るように傘を寄せて、左側に一人分の隙間を作った。とはいえ、元々こんなものは一人用だ。はみ出した右肩に、雨が落ちて染みる。
「……」
そっと盗み見れば、彼女の左肩も濡れていた。鞄を辿って地面に落ちる水滴は、どちらからともなく歩き出した二人の足跡代わりのように点々ときりがない。
「ごめんなさい、助かりました」
「ん?」
「ホームルームが終わってすぐ、少し止んだからと思って走ってきちゃって。駅に着くまでは平気だと思ったんだけど」
「無茶するね。雲の切れ間、ってやつだとは思わなかったの?」
「……大きな切れ間なら平気かも!と思って、つい」
ぽつりぽつり、声を交わす。その合間にも降る雨は彼女の肩を濡らして、緩やかに癖のついた麦色の髪をそこへ貼りつけた。傘を持つ手に、大きな滴がひとつ落ちる。冷たさがじわりと肌に染みて、響いた。
「美優ちゃん、ちょっと」
「え?きゃ、」
「はいはい、騒がない」
空いた左手を回して、肩を抱くように彼女を引き寄せる。短い悲鳴じみた声が上がって、予想通りの反応に少し可笑しくなった。とん、ともたれるように体温が触れる。たった手のひら一つ分の距離を縮めるのはこうしてしまえば簡単なことで、けれど言葉で頼んでみても、彼女は結局遠慮がちに間を狭めることしかしないだろう。
「あ、あの……」
「何?」
「……分かってるくせに」
「うん、ごめんね」
決死の思いで口を開いたような眼差しで見つめられ、役目を終えてもその肩の上で濡れた髪を絡めて遊んでいた手を、笑いまじりに離した。もう、と目を逸らすその肩に、もう雨は降らない。彼女も俺の行動の意図自体は理解しているのか、ぎこちないながらも、距離を取り直そうとはしなかった。じわりと、腕を伝って滲み出す温かさ。多少の違いはあれど三十六度と三十六度に境界線はなく、こんなふうに長く触れたことなんてないはずだというのに、まるで昔にもこうしていたような安心感がある。心地好い、なんて言ったらわざとらしいと笑われるかもしれないが。それでも、このオリーブグリーンの傘の下。俺達の頭上に降る雨だけを遮るこの空間は、狭くもどこか居心地が良くて、ああなんだか。
「瑠璃さん、濡れてません?ちゃんと入ってくださいね、瑠璃さんの傘なんだから」
「心配してくれるなら、もっとぎゅっと寄ってくれない?」
「え!」
「はは、何赤くなってんの」
なんだか、無性に足を止めてしまいたくなる。うつむいて髪に隠された頬を突いてみたら、触らないでと叱られてしまった。きっと彼女は分かっていないのだ。そんなふうに逃げるような言葉を吐くくせに、この距離を広げて拒むことはしない。その態度が、結局俺をますますつけ上がらせる。なんて、もし分かっていてやっているのだとしたら、両手を挙げて負けに溺れてしまいたいくらいだけれど、そこは自覚がないのが彼女の強みというべきか弱みというべきか。どちらにしても、俺を増長させていることには間違いなく。
「……あんまりからかわないで、って、何度言わせるんですか」
「ごめんごめん、可愛いなぁ。……冗談じゃないけど」
「……へ?」
つまるところ行き着く先は、俺は幸せなことに、見込みのある恋をしているらしい。見開かれた藍色の目に、何かを刻みつけたくてありきたりな笑みを残す。彼女のそれが俺の脳裏に焼きつくように、逆もまた然り、であったら良いのだけれど。
止む気配のない雨の中を、そんなことを考えながら歩くのも悪くない。
「……あ」
「?」
「ごめん、美優ちゃん」
言葉をなくしたようにフリーズした彼女が、再び抗議の声を上げるより早く。俺は思いついたように立ち止まって、口を開いた。
「忘れ物、したみたいだ」
たたん、と雨が小さなオリーブグリーンの傘の上で弾ける。ぱたりと瞬いた無垢な藍色の目、離れることを忘れたような温もり。じゃあ、取りに戻りましょう。彼女がそう口にするまで、時間はかからなかった。礼を言って歩き出す後ろに、駅が遠ざかる。
傘を叩く雨の音は、相変わらず高らかだ。肩の下で揺れる髪についた滴を拭っても、彼女はもう何も言わなかった。