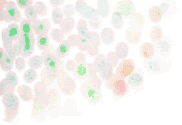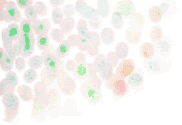
所詮この世なんてそんなもの
「黄瀬先輩っ、はやくはやくっ!!」
「あっ、ちょっと待ってくださいっスよ!名前っち!!」
手を引く青い髪を後ろで一つにくくった少女が女子にしてはありえないスピードで走る。その手に半ば引きずられるようにしている金髪の青年に少女、名前は笑った。
「俺今日休日なんスけどっ!?」
「いいじゃないですか。中学の頃はモデル業ばっかやってて体力落ちてるんだから、少しでも戻しとかないと!!」
そんな言葉を返しながら、彼女は黄瀬にばれないように微笑んだ。
黄瀬の手を引くのとは反対の手に抱えられたバスケットボールがこれから行く場所を示唆していた。
「もう息上がってるんですか?もしかして全然走ってないとか?」
「はっ、はっ、あ、あんたの体力、底なし、っすか」
彼女が短パン、Tシャツ、スポーツ用のシューズであるのに引き換え、黄瀬は動けるもののジーパンにスニーカーだ。黄瀬が久しぶりの休日であると黒子から聞いた名前が、動ける格好で最寄駅に1時間後、と約束を取り付けた結果であった。そして現在は彼女の家の近くにあるストバスコートにいる。
「っつか、青峰っちは、ど、したんすか…?」
「お兄?むだむだ。お兄なんてまだ寝てるしマイちゃんマイちゃん言ってるかと思えば、お前じゃ俺に敵わねえとか言って相手してくれないんだもん。」
口を膨らんで、兄と同じ紺色の髪が風に揺れる。
「で、テツ先輩と火神さんは部活だし緑間先輩は電話しただけで切られた。」
「ま、まあ、想像通りっスね。」
じゃ、早いとこやっちまいますか。
そう言って着ていたジャケットを脱ぐ姿にどきりと胸が高鳴るのは彼女だけの秘密だ。
名前も着ていたジャージを脱ぎ、ストレッチをする。身体が重いのは気のせいだと思った。
名前の動きは青峰に似て素早い。幼い頃からストバスをしていた兄妹の動きはそっくりだ。これなら中学女子では向かうところ敵なしだ、と黄瀬に褒められ名前はえへへ、とはにかんだ。
「そういえば、今年全中はどうなりそうなんすか?」
「んー、男子も女子も予選は余裕ですね。さつきちゃんが調べてくれたし」
名前が用意したタオルで汗を拭きながら、しかし喉渇くっスねーと零した。
「あ、私買ってきますね!!」
「え、あ、いいっスよ!!俺が…」
「無理やり誘ったのは私なんですから、先輩は気にせず座っててください!!」
それだけ言うと彼女は黄瀬の制止を無視して近くにある自販機へ向かって走っていった。
がこん、と音がして飲み物が落ちてくる。出てきたそれを拾い上げると、名前はそれをほっぺたに当てた。つめたいそれが顔の火照りをおさめてくれることはなかったけれど…
「かっこ、よすぎですよ、先輩…」
この想いを告げてはならないことくらい自覚していた。彼は女の子らしい女の子が好きではなくて、自分に好意を寄せる女は馬鹿だと思ってて。でも名前は彼の顔に惚れた訳ではない。モデルだから付き合いたいわけでもない。兄の青峰に憧れてそれを越えようとする黄瀬が好きなのだ。まっすぐ、バスケに打ち込む黄瀬を好きになったのだ。
いや、今となっては彼の全てに惚れ込んでしまっている。
もう、心臓壊れそうだよ、先輩。
そう思いながらもう一度ボタンを押して自分の分の飲み物を購入して戻ろうとすると、彼女の抱えていた飲み物のうち片方がスッと抜き取られた。
驚いて振り返ると、其処にはひとつ違う自分とよく似た顔があった。
「ちょっと、お兄。なにすんのよ。それ、黄瀬先輩のなんだけど。」
「んあ?黄瀬の?ならなおさらいいんだよ。つか、お前、黄瀬となにしてんの?」
「バスケの練習だよ。お兄が付き合ってくれないから。」
ふんと、むくれると、目の前の兄の目が細くなった。普段より数倍悪い目つきに、名前の肩が跳ねる。
「な、なによ。お兄がマイちゃんマイちゃん言って何もしてくれないから誘ったんじゃない!!それに、黄瀬先輩の方が優しいし、ちゃんと教えてくれるし、それに…」
そう言い募っていると、不意に兄に右腕を掴まれ、名前はうっ、と声を上げた。
「お前、今日はもうバスケすんな。」
「いや。試合近いもん。練習しなきゃ。」
離してよ、と手を振りほどこうとするが、昔は大して変わらなかった力も10代半ばになってかなり差ができてしまったため、ピクリとも動かない。
「お前このままじゃ怪我すんぞ。」
「私は怪我なんかしないもん。練習しないお兄と違って!!そんなんじゃ黄瀬先輩にもテツ先輩にも絶対勝てなくなるんだからね!!」
「はあ?いまてめえなんつった」
低くなる青峰の声にも彼女は怯まない。
「才能にかまけて練習しないお兄なんかが勝てるわけないって言ったんだよ!!」
「あ?てめえふざけんじゃねえぞ、ブス」
「さつきちゃんと違って私は本当にブスだもん。それにお兄の妹で美人だったらそっちのかまびっくりだし」
「あ?黙れチビ」
「巨乳好き」
「お前なんか才能ねえんだからバスケやめちまえ」
その一言は、彼女にとって最悪の一言だった。自分が兄ほど才能がないことは自覚していた。自覚もしていたし、男女差もあるからもう勝てないことも分かっていた。けれど、自分が努力で得たプレーはみんな兄の妹だから、で片付けられてしまう。たった一年と数ヶ月早く産まれただけで、兄に才能があるだけで、彼女の力は全て兄のおかげとされてしまうのだ。
そんな悔しさを拭いたいから、人一倍練習して認められようとしているのに。
それを全て潰された気がした。
「お兄なんて、だいっきらい!!」
自分用に買ったアクエリアスのキャップを開けて思いっきり兄に投げつけると彼女は別の自動販売機まで一直線に駆けて行った。
「すいません、遅くなっちゃって。このミネラルウォーターで良かったですか?」
「あ、大丈夫っス。わざわざ探してくれたんスね。ありがとう。」
にっこり笑って水を受け取る黄瀬に少し傷ついた心が癒される。この人もきっと兄の妹として私を見ているのだろう。好きな人にそう見られるのは彼女にとって苦痛で仕方がなかった。
貼り付けていた笑顔が剥がれそうになって彼女は慌ててタオルで汗を拭うふりをした。涙は押し殺した。やっぱバスケは楽しいっスという彼に笑いかけるために。
それでも…
「気づいてお願い気づかないで」
兄の妹なのに弱い私に。
「なんか言ったっスか?」
「あ、ううん、なんでもないですよ?」
そう言って果たして、彼女は笑えていたのだろうか?
▼