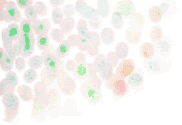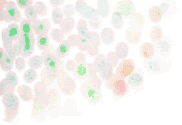
自己暗示さえ効果なし
幼馴染、真太郎が気にかけるのはいつだって私ではなかった。
「お前は大丈夫だろう?」
「うん、大丈夫」
それが私達の会話。
「名前ちゃんはいいなあ。真くんに大丈夫って言われて」
はにかんで笑うあの子は私と真太郎の幼馴染。
やめて。
そんなセリフ、言わないで。私は身体も丈夫、勉強も運動も言ってしまえばできる方。リーダーシップだって、とれる。自惚れではないと思う。だって真太郎は嘘をつかないから。
けど、真太郎と同じくらいあの子のことも大切だから。
「まあね。真太郎に心配されるほど落ちぶれちゃいないよ。それより身体大丈夫?」
「もう、名前ちゃんお母さんみたい」
そう言って笑うあの子は嬉しそうだった。その笑顔を見ていると私も幸せになっていく。
これで、いいの。
だって私は強いから。なんでも出来る。大丈夫。
それが、日頃の呪文になりつつあった。
けれど、あの子に構い続ける真太郎を見るのも、毎日気を張って過ごし続けるのも、そろそろ限界だったようだ。
私とあの子と真太郎は偶然にも同じクラスで、あれは球技大会のクラス練習だった。普段なら得意で失敗することのないバスケのスピンに失敗。その時にあの子を巻き込んで倒れてしまったのだ。
ただ、不幸中の幸いで私の体が反応して彼女の下に腕を滑りこませることができた。
「あたた、名前ちゃん。ごめんね。私が鈍いばっかりに」
「え、あ、ううん。私こそごめん。」
彼女の声に反応するのが遅れたのは別に身体の痛みからではない。倒れる瞬間、真太郎が呼んだ名前があの子のものだったからだ。
ほら、今だって。
駆け寄ってくる真太郎が心配するのは、その目に映るのはあの子だけ。
私なんて眼中にもないもの。
「いいから、保健室へ行くぞ」
きゃあ、と周りから声が上がって、見上げればあの子を抱き上げた真太郎がいた。
心臓が、鋭い痛みを訴えた。
「名前は大丈夫だったか?」
そこで初めて私に気がついたような顔。やめて、見たくない。そう、大丈夫よ。
私は、いつだって、大丈夫。
「大丈夫。だから早く保健室連れてってあげて」
笑えていただろうか?
けれど真太郎が納得したような表情を浮かべたから大丈夫だったんだと思う。
ああ、と短く答えてあの子は真太郎は保健室へ向かって行った。
それを見送りたくなくて、立ち上がろうとした。すると、今更のように腕と足首に鈍い痛みが走って…
はっ、と乾いた笑いが零れた。
大丈夫なんて、嘘ばっかり。
本当は大丈夫じゃない時だってあった。
あがり症だし、勉強だって真太郎の何倍も覚えは悪い。けど、何度も大丈夫を繰り返してなんとかしてきたのだ。
ねえ、真太郎。
私、貴方が思っているほどには強くないわ。
私だって、人間だもの。
痛い時は痛いのよ。
ただ、みんなの前で大丈夫と言った手前何も口には出せず、心配して駆け寄ってきてくれた友人達に笑顔を見せてプレーに戻る。
ずきり、ずきり。
腕が、足が、心臓が痛む。
痛みの中放ったシュートのループはそんなに良くなかったもののゴールに入った。
ねえ、真太郎。
痛みで熱くなる身体のせいで朦朧としてきた意識の中、姿の見えない幼馴染に心の中で問いかけた。
もし、一度でも大丈夫じゃないって言えば、私のことも心配してくれた?
少しは、私のことも見てくれた?
気にかけてくれた?
ねえ、真太郎。
弱い私なら愛してくれた?
「苗字ちゃん!!」
誰かの声と共に逞しい腕に引かれた。
その落ちた先が、誰の胸の中だったのか、意識が途切れた私には分からなかった。
▼