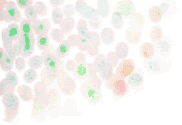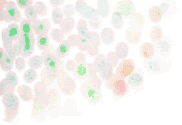
似たもの同士のはずだった
夕暮れの放課後。
近頃は気温が下がってきて過ごしやすくなったが、何処か哀愁を漂わせる。金木犀の甘い香りが鼻腔をくすぐって、無性に懐かしく、泣きたくなった。
教室に入ったら、やたら目つきの悪い青髪の長身男がグラビア雑誌なんぞを眺めていた。とてもシュールな光景だが、こんなのでもキセキの世代エースになれるなんて世も末かもしれないと本気で思った。
「大輝、ほらノート」
「あー、さんきゅー」
毎回毎回テストの度に私やさつきにノートを借りるこのどうしようもない幼馴染は、今日も今日とて堀北マイちゃんに夢中だ。
ため息はもう何度目だろう。
「グラビアも程々に練習でないと、あんた本当に負けるわよ?」
その途端、さっきまでの気の抜けた空気が少しだけ尖る。幼なじみなんて、面倒だ。こんな些細なことすら気がついてしまうのだから。
「いーんだよ。俺に勝てるのは俺だけだ。」
中二病を拗らせたようなセリフも、彼が言えば本当になってしまうのだから恐ろしい。絶対的な自信と期待していた旧友たちとの試合が、彼のこんな空気に拍車をかけてしまった気がする。
「へー、まあいいけど」
そんなどうでも良さそうな風を装って彼の隣の席に腰掛けた。
「とりあえず、追試くらわない程度には勉強しなよ」
今回はわかりやすくまとめといたから、なんて言えば、あー、さんきゅー、と気の抜けた返事が返ってきた。
「つか、お前こそいいのかよ」
「んー、何がー?」
「ピアノ、練習しなくていいのかよ」
どくり、と心臓が音をたてたけど、すぐに見て見ぬフリをする。
「いーのよ。どーせ殆ど初見で弾けるから、次のレッスンの時で」
窓の外を眺めながら答える。
自慢ではないが、私は天才と呼ばれる部類らしい。運動なんてこれっぽっちもできないし、勉強もそこそこだけれど、ピアノを弾くことだけは得意で好きだった。それこそ、五歳の頃から幼稚園や学校の時間、大輝やさつきと遊んでいる時間以外はほとんどピアノを弾いていた。弾けない曲なんてなかったし、新しい曲を覚えていくことが楽しかった。
中学に上がっても部活には入らず、たまにさつきの手伝いに行く以外は音楽室でピアノを弾いた。部活を終えた二人と一緒に帰る、それが日課だった。
けれど、大輝がバスケに失望するのと同時に私もピアノを弾くことに疑問を感じ始めた。
「本当、上手になったわね。私は貴女を教えられて鼻が高いわ」
そんな言葉をもらって、前の初老のピアノの先生とお別れした先で出会った、まだ若い女の先生。その先生に出させられた数々のコンクールで私は賞を総なめにした。そうすればぽっと出のくせにとか、審査員に賄賂を送っただとか陰口を叩かれた。
正直贔屓目なしに見たって私が一番上手かった筈だし、審査員の先生たちはほぼ満場一致だった。
けど、そんなこと言われるためにコンクールに出たわけじゃない。別に誰かに認めて貰いたかった訳じゃない。ただ、ピアノを弾くことが楽しかっただけなのに…
それから、真面目になんて練習しなくなった。先生も変えて、週に一回、先生のところでだけピアノに触る。さつきや、周りの人は残念がったけど、私はこれでいいと思っていた。好きな時に、好きなものを弾く。自分が満足すればそれでいい。
そんな自己満足なピアノを続けてもう一年。
「てめーこそ練習したほーがいいんじゃねえのかよ」
「うっさい。あんたにだけは言われたくない」
結局、元を正せば二人とも同じなのだ。ただ、好きで好きで好きで仕方なかった事がやっているうちに苦しくなって、けど嫌いになんてなれなかった。
だから、余計に苦しい。
それでも、いや、だからこそ大輝には笑ってほしかった。私のように燻っていてほしくなかった。
「大輝、バスケ頑張ってね」
ぽつり、とそんな言葉が零れた。
結局、私が何もしなくても大輝は自分の生き甲斐を取り戻した。
黒子くんと、あと、確か火神くんに、大輝は負けた。あの時、火神くんとの1on1をしている大輝は少しだけあの頃の面影を宿して笑っていた。
そうなることを望んだのは私だった。大輝に、笑顔になってほしかった。そう思っていた、筈なのに。
いざそうなってみれば、置いていかれた気がした。一人に、された気がした。
ずっと、二人で身を寄せ合っていられると心のどこかでは思っていたのかもしれない。
ああ、こうなることは、分かっていた筈なのに。さみしいことは分かっていた筈なのに。
寒い冬空の下、一人ぽつりと呟いた。
「一人で生きたいわけじゃなかったのよ」
一瞬頬を暖かい雫が掠めて、それからすぐそれも冷たくなった。
もう、大輝のそばにはいられない。
何故かそんな気がした。
▼