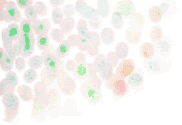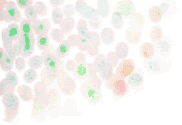
涙のしおり
「ねー、名前ちんお腹すいたー」
「はいはい、もう少し待ちなよ」
そんな会話をしながら歩いた駅前の噴水広場を一人で歩く。暗くなった空に一番星がキラリと光る。
もう、こんな時間に暗くなるのね、と私は一人心の中でごちた。
思えば、もうあれから一年も経つのだ。
「あつしー、かえろー」
私と敦は家が隣の幼馴染だった。小さい頃から、それこそオムツの時からずっと一緒だった。それは中学に上がってからも変わることはなかった。何故か小学校一年生から中学三年生までずっと同じクラス。部活だって、さつきに誘われて行ってみればそこには敦の姿があってビックリしたっけ…
家に帰ってからも、小学五年頃になった時から必ずあいつは私におやつをせがむようになった。そのため私は態々やったこともない料理練習して、ご飯あとのおやつを敦に作ってやるようになった。
こうやって、敦に尽くすのが当たり前の生活を15年間おくったことで分かったことがあった。
そう、私は敦に惚れてしまったのだ。
けど、そんなのは今更すぎて口には出せなかった。
そうこうしている間に中学三年生の夏、すなわち最後の夏が終わった。
帝光の圧倒的勝利で全中が終了。あまり気持ちの良い試合ではなく、テツは部活どころか学校からも離れてしまった。
そうして、秋の色が濃くなってきたある日…
「寒くなったねー」
「うーん、そーだねー」
二人並んで、さっき買った焼き芋を頬張りながら喋る。
帰り道、二人で帰るのは昔からの日課で変わることはなかった。
「あつしー、受験どーすんのー?」
時期的にはごく自然な話題だった。彼にバスケ推薦がきていたのは知っていた。けれど、めんどくさがりの敦が地方を選ぶ訳がないと思って高を括っていたのだ。
だから、声がでなかったのだ。
「あー、秋田のなんだっけ、陽なんとかってとこー。監督美人だったしねー」
周りの音が消えた。
何、それ…
「敦、それ、本当?」
「うん、マジだよー」
愕然とした。
今まで、敦の世話はずっと私がしてきて、これからもずっとそうだと思っていた。いつか、こんな関係に終わりが来ることは知っていたけれど、まさかこんなに早いなんてこれっぽっちも思っていなくて…
握りしめた拳が震えた。
左手にある焼き芋の熱が急激に冷めていくような気がした。
「敦、これあげるから、先、帰ってて。買い物してくるから。」
「はーい、じゃあねー」
おやつよろしくー、なんて大きな手を振る敦。
ねえ、敦…
敦は悲しくないの?
もう、毎日あたしは隣にいないんだよ?
もう、あんたのおやつ作ってあげられないんだよ?
なのに、なんでそんなに平気そうなの?
息が苦しくなるまで駆けて、近くの公園のベンチに辿り着いた。
空を見上げると、一番星がキラリと輝いている。
ああ、なんでこんな報われない恋をしたのだろう。否、私が弱虫だから報われないのかもしれないけれど…
涙が勝手に溢れ出した。
「ひっ、うぇっ、」
無茶苦茶に涙をぬぐった。
ああ、今まで何でも言い合える、そんな関係を敦と築いてきたのに、肝心なことを私は言えなかった。
もし、この思いを告げたなら何か変わったかもしれないのに…
はは、と泣きながら一つ笑い声がこぼれた。
敦相手なのに…
「素直になれないなんて、馬鹿げてる」
自分を嘲笑う言葉は、秋の綺麗な夜空に吸い込まれた。
それから一年…
少しだけ、傷口は痛まなくなった。
夏少しだけ敦は帰省したらしい。私は部活の合宿に行っていて、会えなかったけれど…
「元気に、やってるかなー」
一人ごちたそれは、あの時と同じような秋の空に吸い込まれた。
ウィンターカップは東京だから、見に行こう、なんて事を思って敦の家の前を通り過ぎた。
「ただいまー」
こうして、敦のいない今を私は生きていくんだ。
後ろで玄関のドアが音をたててしまった。
▼