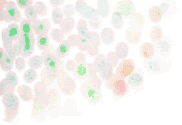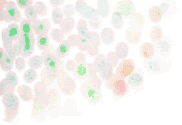
押し殺した心の行方
朝、学校に行ったら下駄箱に靴がなくてまた職員室に行ってスリッパを借りた。
もうこれも慣れた作業だ。
けれど自分で決めて自分で選んだことだから、後悔はしていない。
ただ、イライラはするけれど。
私は帝光中の男子バスケ部マネージャーをしている。
愉快な仲間と美人ぞろいのマネージャーに囲まれて、クラスでは普通に友達もいてそれなりに楽しい中学校生活を送っていた。
けれど中1の後半からこういったイジメが多くなった。
理由その一はクラスのリーダー的存在の女の子にバスケ部NO1と言っても過言ではない青峰を紹介しなかったから。
まあこれはそんな約束をすっかり忘れていた私が悪いとも言えよう。
その二は同じマネージャーのさつきが一軍昇格の時に二軍へ行くのとは逆に、私は一軍から二軍降格の選手の元へ行ってそれを通告するからだ。
勿論、それは私の独断ではなく監督やコーチの指示であるのだが、彼らを恨むことができない分避難は私に集中した。
さつきがバスケ部の光なら、私はその闇の仕事をしているんだと思う。
データの分析をして、それをチームに披露するさつきとは違い私は洗濯などの雑用をし、降格する人に冷たい一言を告げるのだから。
元々自分が監督からその役目をもらった段階でその覚悟はできていたし、最悪強姦などされてもおかしくないかも、とさえ思っていた私にはこれくらい気にすることではなかった。
因みに紛失した上履きを探したことはなく、この前入ったお小遣いで新しいのを買ったのだが、もうなくなったのか。
もったいないな、と溜息をついたけれどまあどうしようもない。
そのまま更衣室へ向かうことなく体育館へ。
鞄から体育館履きをとりだしてスリッパを持ってきた袋の中にしまう。
それから職員室でついでに借りてきた体育倉庫の鍵をあけてボールを出した。
ふと、一個のボールが転がってそれを拾い上げた。
途端に小学校時代が懐かしくなった。
足の故障がなければ、中学でもバスケを続けただろう。
帝光は女子も強いが、一軍に入れない程度ではなかったと思う。
茶色のザラザラしたボールを撫でていたらふと懐かしくなってポーンとゴールの方へそれを放ってみた。
けれど手の力だけでは届く筈もなく、それはゴールに届く前に勢いを失い床へ落ちた。
それが無性に悔しくて、唇を噛んだ。
いや、もしかしたらイジメに対するイラつきだったのかもしれない。
今度はボールを拾ってレイアップを打ってみようとしたが、鈍い痛みに阻まれた。
思わずその場に膝をついて、顔を顰めた。
悔しい、悔しい。
苦しい。
分かっているし、本当に後悔はしていないのだ。
けど、やっぱり、悔しい。
「大丈夫か?」
優しいテノールが響いて、振り返ると真っ赤な髪の彼がいた。
「あか…し…」
「立てるか?」
優しく私を気遣うのは三年生の引退前にしてキャプテンになった赤司征十郎。
バスケ部でない女子たちからは「赤司様」と崇拝されるほどの統率力と全てにおいて頂点に君臨する彼は、本当に優しい人。
だから、純粋に私を心配してくれているのだと思う。
「ありがとう」
差し出された手を取り、逆の手にあったボールを受け取って籠に戻した。
「何か、俺にできることはあるか?」
「あ、大丈夫。部活始まるまでまだ時間あるし」
「いや、そうではなくて…」
彼が言わんとしていることは分かった。
きっとこれも私のことをチームメイトとして本気で心配してくれているから。
だけど…
「大丈夫」
遮った。
多分、私の些細な意地だったんだと思う。
「私はそんなに弱くないから」
自分に言い聞かせるように彼に言った言葉は思惑とは反対に自分の心を抉った。
それから三日後…
彼は本当に強姦されそうになった私を助けてくれた。
「大丈夫。俺がいる。君は弱くてもいい」
正反対のその言葉が、傷つき、疲れた私の心に静かに染みて癒していくのが分かった。
彼に縋り付いて、今まで泣けなかった分沢山沢山泣いた。
▼