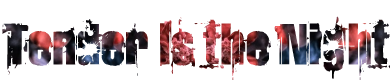いつもの如く気まぐれな猫のように、トリッシュがその日ふらりと事務所に戻って来たのは夏の宵のことだった。
急な来訪に三人分の夕飯の食材を用意していなかったメアは焦り、その様子を案じてダンテは外食を提案した。
「でも私、今はお腹が空いていないのよ」
そう平然と涼しく返す様子も、ますます我が道を行く美しい猫のようだとメアは思った。
結局、折衷案として事務所から徒歩で五分ほどの場所にあるバーに行くことになった。ダンテとトリッシュは酒を片手に和やかに話しながらダーツに興じていた。賑やいだ店内で声を掛けてくる近所の顔馴染みと会うたびにポツポツといくつか言葉も交わしているようだ。
常ならトリッシュの旅先での土産話を聞くのはメアも好きだったし近所付き合いもダーツだって嫌いではない、のだが。
今日は何となく、その二人の輪に加わる気が引けてしまい、カウンター席で一人黙々とタラのムニエルとバターロールをフォークで交互につついていた。
此処は昼でも夜でもマスターがその日市場で仕入れた食材から考えた"本日のメニュー"を一品だけ提供してくれるのだ。それがなかなか評判で味も良く、メアとダンテもたまにふらりと食べに来ることがある。
「口に合わなかったかい?」
苦笑しながらマスターがメアの皿を覗き込んで来たので、ふるふるとかぶりを振った。
「タラの皮目の焼き加減が丁度良いし、バターと香草が効いててとても美味しいです。……ごめんなさい、ちょっと考え事をしてました」
「君にそんな憂い顔をさせるのはどこのどいつだろうな」
マスターの茶化しにも弱々しい笑みを返すことしか出来なかった。
食事を残すのは忍びなく、メアはぼんやりとしていた意識を引きずり戻してムニエルを黙々と口に運ぶが、最初のひとくち目以降、上手いこと味が感じられない。
料理が悪いのでは無いと、はっきり判っていた。問題はメア自身にあるのだ。
それはダンテがトリッシュとマレット島から生還して来て以来、時折ふつりと首をもたげてくるぬめぬめと光る"蛇"にも似た感情だ。
トリッシュのスラリとした背丈や美しいかんばせ、艶やかで豊かなブロンドを見ていると、どうしても事務所の机上に置かれた写真立てが脳裏を過ぎってしまう。
喉元の苦しさを、ひと口分にしてはやや大きすぎるサイズにちぎったバターロールを飲み込むことで胸の底に押しやり、メアは小さく小さく溜め息を吐いた。
「つまりはトリッシュに"嫉妬"しちゃった、ってことよね」
そんなメアのぼやきを相槌交じりに聞いた末に、レディはあっけらかんとそう言い放つ。
「……おっしゃる通り、デス」
"蛇"に似た感情の名前なんてとっくの昔に気がついてた、と頬の内側の肉を噛み締めながらメアは気だるげに、何が掛かっているかも見ないまま透明なハンガーたちを指先で持て余す。
トリッシュは数日間事務所に滞在した後、またふわりと風にさらわれたスカーフのような優雅さでどこかへ出かけて行った。仕事の依頼が重なればもう少し長期の滞在になったのかもしれないが、生憎というか幸いというべきなのか最近の事務所では悪魔絡みの依頼に関しては閑古鳥が鳴いている。
メアもそんな隙を見て、今日はレディと二人でショッピングモールに買い物に来ていた。
秋物の化粧品や夏服のセールを巡り、レディが下着が見たいと言うのでふらりとランジェリーショップに入ったところである。
スポーティーな無地のボクサータイプと薔薇の花のレースがあしらわれたビキニタイプのショーツを渋い顔で見比べながら、レディはそりゃあねえ、と哀れみを含んだ声を上げる。
「気持ちがザワつくのは当たり前よ」
私だって彼氏の実の母親そっくりの女がぽっと現れたら何するか判らないわ、と度々トリッシュとも仕事を共にしているレディの言葉にメアはズキリと胸の奥が痛むのを感じた。
レディは優しいから、そう此方を庇うように言ってくれる。
トリッシュが悪くないのだって頭では判っているのだ。彼女だって、その外見からして初めは利用される為に魔界で生み出されたある種の被害者だ。彼女は強いからそうは思っていないかもしれないけれど、メアがもしも同じ立場に立たされたら正気を保っていられるのかも判らない。
そしてダンテだって何も悪くない。メアの知る限りではトリッシュに懸想をかけた様子もなく、親しい友人として過ごしている。
しかし、その表情が孕む見たことのない色をどうしても、メアは受け止めることが出来ずにいた。不安だった。ふとした瞬間、誰にも向けることの無い心なしか穏やかなダンテの顔を独占できるトリッシュを羨ましく、そしてどこか妬ましく思っている自分が心底醜いと思った。
ただでさえトリッシュを前にするとその怖気が走るほどの美貌に見蕩れてしまうのに、これ以上余計な感情の泥濘にはまってしまったらもうダンテの傍にだっていられなくなってしまうのではないか?
「ねーえ?今、どうしようもないこと考えてない?」
レディにつうと白いロングTシャツの肩の縫い目をなぞられてメアはハッと我に返る。
「ほんと、どうしようもないね」
あはは、と乾いた笑いを浮かべるメアの痛々しい表情を、レディはその左右の色の違う双眸でじっと見つめた。それぞれが異なる上等な宝石のような色を宿した瞳が数度、瞬いたかと思うと、
「もうあのバカに直接聞いてみればいいんじゃない?」
レディが言うところのバカ、とは無論ダンテのことである。
メアはそんな突然の提案に「なっ、んで?」と言葉を詰まらせた。
ぎらり、とレディの瞳が怪しく光る。
「ガバガバに気を緩ませた所でそれとなーく聞いてみれば、男なんてポロッと本音吐いちゃうものよ」
「それでもし聞きたくない答えだったらどうしたらいいの……」
「そうね……蜂の巣にでもしてやれば? どうせあいつ死なないんだし」
そんな無責任な、と思う一方でレディの言う通りいっそ聞いてしまいたい気持ちも確かにあり、メアの心は綱渡りに挑む軽業師の足元のように上下左右へと激しく揺れ動いていた。
"ダンテはトリッシュのことが好きなの?"
レディはそんなメアの横顔を見つめたかと思うと、おもむろにぐいっとロングTシャツの襟ぐりを掴んだ。襟元から中を覗かれ、メアは、ふおっ、と驚きの声を上げる。
メアの装いはいつも通りのシンプルなスタイルで、中はタンクトップと飾り気のない下着、首周りにはアクセサリーの類も無く、ただそれっきりだ。
「……レディ?」
突発的な行動に放心しているメアを頭のてっぺんからブーツの爪先まで眺め下ろし、
「いいこと思いついちゃった」
こっちに来てメア、と手を引かれて近づいて来るのは売り場の一角に華々しく広がる、実用性の薄いセクシーランジェリーのコーナーだ。
レディの考えの一端がおぼろげに掴めたメアは、華奢ながらも銃のグリップに擦れてタコの出来た温かい手の平を、無下に振り払う気にもなれず身を任せるようにぎゅっと握り返した。
「ダンテったら、本当にバカなんだから。大バカ者よ」
そう愚痴を零してからレディはさて、と楽しそうに明るい声を上げると、メアの方へとくるりと向き直った。
"ガバガバに気を緩ませる"とレディは当初表現していたが要するに「色仕掛けでダンテの気を削ぎ本音を引きずり出せばいいんじゃない?」と下着屋での装備一式を購入した後にカフェで休憩を取りながら具体的な作戦の立案をされた。
レディの気炎をあげがちな様子に圧倒され、メアは頷くがままだったが果たして自分はダンテに対して色仕掛けなど上手く出来るのだろうか?そもそも彼に対する今更の"色仕掛け"とは何なのだろう?
かつては父親の手伝いで見知らぬ男たちに散々ハニートラップを撒いていたこともある。けれどそれはメアにとっては何の感情も湧き上がらず至極どうでもいい、凡人たちだ。
そんな輩たちとダンテは、そもそも同じ秤に乗せることすらはばかられる。
そうモヤモヤと考え事をしながら、メアは夜空の色に染まった窓ガラスにくっきりと映る自分の姿に目を向けた。
ジョーゼットシフォンとホワイトレースで膨らんだ淡いピンク色のベビードールをとろりと素肌にまとい、セットで買った履き慣れないオープンクロッチタイプのショーツを身につけている。もはやパンツとしての役割を果たしていないじゃないか、と脱がずともコトに及べる深い切れ目が入った布地を呆れたように見やる。秘めるべきはずの肌に触れる冷たい空気にふるりと身を震わせてメアは一つ息を吐いた。
メアが先にシャワーを浴びたので、きっとダンテはもう暫くしたらいつも通り濡れ鼠で部屋に帰って来てはゴロリとベッドに横たわるのだろう。
似合っているのかも判然としない透けたパステルピンクの胸元を眺め下ろしてから、メアはレディが選んでくれた口紅を慎重に塗る。
自分では絶対に選ばない色だったが、きちんと主張はしつつもメアの肌色と下着姿に合うヌーディーなピンク色だった。
レディは凄いなぁ、とその慧眼に感嘆してからメアはベッドサイドテーブルの引き出しからブラシとレースのあしらわれたヘアゴムを取り出す。
洗面所で乾かす際に丹念に梳いた髪にもう一度ブラシを通して、長いブルネットをうなじで二つに分ける。そうして高めの位置で強く結い上げると、窓ガラスには少し幼げな自分が不安そうにこちらを見つめていた。
レディは「ギャップで誘うのよ」と強く言っていた。ツインテールの髪型もその時に提案されたものだ。
普段着ない雰囲気の下着、つけない色の口紅、慣れない髪型。
こんな砂糖菓子みたいに可愛らしい格好よりもっと際どいデザインの方がいっそのこと気が紛れる、とメアがへなへなと弱音を吐くとレディには「彼女とジャンルがかぶるのはダメよ」とにべもなく一蹴されたのだった。
彼女とはトリッシュのことであり、それも一理あるなとメアは妙に納得してしまったものである。
メアにはレディやトリッシュのようにスラリとした身長や手足もなければ、抜群の美貌もない。胸は少しばかり大きい部類かもしれないが、それだって二人には及ばない。
外へ遊びに行っても人目を引くダンテの周りには気がつけば美女が集まっている場面だってあるし、そんな時は自分がまるで水槽の底に溜まる澱になったような気分になってしまう。美しい魚たちが伸び伸びと泳ぐのをぼんやりと見上げることしか出来ない澱、だ。
そのコンプレックスを取り払ってくれるのは他でもないダンテなのだけれど。彼が愛していると、そう示してくれるとメアは彼の隣に居る自信が持てた。
そんな人を一瞬でも騙して試そうとしているのか、という罪悪感と不安感にチリチリと胸の奥が鈍く焦げる音がした。
"軽い不意打ちのパンチを食らわせて、一つ二つ質問を投げかけてみる。"
ただそれだけのことだ、ちょっと聞きたいことがあるだけなんだ、とメアは自分に言い聞かせながら入り口側のベッドの縁に腰掛けた。
その落ち着きなく揺れるつま先を包むのも、相変わらず履き慣れない十センチヒールのパンプスだ。ベビーピンクのエナメル生地で、ストラップに白いファーが飾られたタイプのデザインをしている。これがあれば沢山背伸びをしなくてもダンテと距離を縮めることが出来るはずだ。
そこでぎし、と階段が軋む音がして、メアはつい息を止めて気配を消した。シーツの中か、はたまたベッドの下やクローゼットにでも隠れてしまいたい焦燥感が強烈に込み上げてくるが、それも時すでに遅しというやつだった。
ガチャリ、とドアが開く。
片手でバスタオルの下の銀髪をかき混ぜるたびに、水滴がぽたぽたと宙を舞っていた。上半身は裸のまま、乱雑に黒いスウェットを腰に引っ掛けただけのダンテが現れ、もう片方の手には冷えて汗をかいたチェリーコークがある。また私のコーラ勝手に飲んでる、とその缶を無意識に目で追うと彼がグッとあおった瞬間にアイスブルーの瞳とバチリと目が合った。
今私はどんな表情をしているんだろう、と顔の筋肉の強ばりすら上手く感じ取れなくなっていた。きっと不機嫌そうに眉をしかめているかもしれない、とメアは幾度か瞬きをすることで緊張を解く努力をする。
「……珍しいな」
ダンテの第一声はそれだった。
無理もない、とメアは思う。
普段好んで付ける下着はセットアップだが飾り気は最小限のものが多かったし、ダンテから特別注文が入ったこともなかった。だからつい着け心地や効率を重視してしまいがちだった。仕事で際どい衣装を着ることはあっても、こんな風に寝室でダンテの為に扇情的な下着を纏ったのは初めてのことだ。
メアは呆気にとられ立ち尽くしているダンテの元にコツコツと歩み寄ると、頭にかかったタオルに手を伸ばしゆっくりと髪を拭く。その距離もいつもより近くてこそばゆかった。
「……変、かな?」
緊張で掠れた喉で尋ねると、ダンテはしげしげとメアの姿を見つめて、
「いや、よく似合ってる」
バスタオルと濡れそぼった銀髪の下から柔らかい光を灯す青い瞳が覗いて、メアはつい目を逸らす。既に心臓が早鐘を打っていた。いつもなら何てことない距離なのに、平静を保つのがこうも難しくなるのは想定外だった。
「昨日レディと買い物に行ってたよな」
「そう……一緒に選んでもらったの」
もたもたと時間を掛けて拭き終わった銀糸を手ぐしで撫ぜてから、メアはダンテの頬を手の平でゆっくりと引き寄せた。風呂上がりで火照っているはずのダンテの肌よりも自分の方が体温が高いことに気がついてしまい、余計に恥ずかしくなってしまう。
反射的に首を傾げて軽く身を屈めてきたダンテの唇の先でメアはねえ、と息を零す。
「私、可愛い?」
「今日は一段と、な」
「?」
「いつだって可愛いさ、お前は」
何を今更?とでも言いたげなトーンと淡白な眼差しにメアは全身に熱が回るのを感じていた。まるで煮えたぎる鍋にでも突き落とされたような気持ちになって、慌ただしく息を止めてダンテの唇を塞ぐ。想定を上回る甘言に思考回路がショートしかけていた。
どうかもうそれ以上は何も言わないで欲しい。
喰らいつくようにキスをすると、唇が開いて肉厚の甘い舌が口内を這う。上顎をくすぐられて痺れが生まれるのを感じ、負けじと舌を伸ばすとゆったりと絡み合い粘膜を擦り合わせる愛撫へと変わって行った。
これほど淫靡な口付けは久しぶりに感じられた。交わり自体が長く途絶えたことはなかったけれど気付かぬうちにマンネリ気味だったんだろうか?とメアはいつもより嬲るような舌の動きをしてくるダンテの瞳の奥を覗き込む。そこにはいつも通り、劣情の火種が燻っているだけだ。
「ねえ、何考えてるの? ダンテ」
「それはこっちのセリフだったんだがな」
腰をひょいと抱き上げられてベッドまで運ばれると、ベッドサイドテーブルに飲みかけのチェリーコークが置き去りにされた。
メアは半身を押し倒そうと肩にかけられたダンテの腕を絡めとり、逆に彼の体をシーツの海に沈める。
「今日は休んでていいよ」
ダンテの爪先から履き潰したルームシューズを引っこ抜いて床に捨てながら、メアはその研ぎ澄まされた体躯の上に馬乗りになる。
へぇ、と笑いながら枕に後頭部を埋め腹の上でふわふわと揺れるベビードールにダンテは指を絡ませた。
「ご奉仕してくれるのか?俺の可愛い天使ちゃん」
「ええ、そのつもりよ。覚悟していてね、マイ・ダーリン」
芝居がかった言葉をかわして、メアはダンテの両手に指を絡めながら首筋に顔を埋めた。白い肌の上でゆっくりと舌を踊らせ、耳朶を食む。
忘れかけていた呼吸を取り戻すと、肺いっぱいにダンテの甘い体臭がなだれ込んで来て目の前がクラクラと揺れた。いつも使っているミント系のシャンプーやボディソープの香料さえもあっという間に包み隠してしまう、ベビーパウダーにも似た甘ったるいムスクのような香りはダンテ自身から放たれるものであることをメアはよく知っている。心地よさを与える時もあれば、情欲を高める時もある麻薬のような芳香。
鎖骨の下に唇を落として薄い肌を転々ときつく吸い上げた。残った赤い花のような痕に満足感を覚えていると、ダンテの喜色を含んだ声が降ってくる。
「くすぐったい」
「我慢して」
いつもは私に散々痕を残すくせに、と胸板も強く食むようにして鬱血の痕を残す。半魔の治癒力で常人より早く消えてしまうものだが、だからこそそこに散る花は儚くて美しいとも思えた。
胸の尖端を舌で擦り、薄く前歯を立てると握った手に少しだけ力がこもるのが判った。舌で淡く色づいた先を転がし、リップ音を立てて吸い上げると、ふふ、とダンテが楽しそうに息を漏らす。
両の胸にそう愛撫を加え、そのまま唇を滑らせる。腹筋の窪みをなぞってから脚の間へと手をかけた。厚手のスウェットと下着越しにも硬い熱が灯っているのが判り、メアはつい心が踊ってしまう。いつだって彼への愛撫に自信がある訳ではなかったが、それでも感じてくれていたのなら嬉しくもなる。
空いた手で頭を撫でられる心地良さに目を細めながら、ダンテの衣服を全て脚から引き抜くと、既に硬さを持った杭がふるりと現れた。
「そのちっちゃいお口でしてくれるのか?」
上半身を起こして枕とヘッドボードに寄りかかりながら、潤んだアイスブルーの瞳が期待に揺れていた。
まじまじと見られるのはいつも恥ずかしかったが、メアはオーラルセックスが嫌いではなかった。直接ダンテ自身が高まって行くのを感じられるのは胸やお腹がじんじんと温かくなって気持ちがよかった。
血管の浮いた鼠径部へと吸い付くキスを落として、メアは割り開いた内腿をじっとりと撫でる。
「口でされるの、好き?」
「そりゃな。お前の腹ん中には劣るけど」
そう言ってするりとベビードールの隙間から下腹部を撫でられてメアはカアッと頬を赤らめた。その様子に白い歯を剥いてダンテが意地の悪い笑みを浮かべる。
ちょっと気を抜くとあっという間に手綱を奪われてしまいそうだ、とメアはムッとサファイアブルーの瞳でダンテの嘲笑を牽制してから、静かに熱塊に指を這わせた。
亀頭に唾液を垂らし滲み出ていた先走りと手の平で混ぜ合わせると、濡れた杭がぴくりと揺れる。それをゆるゆると指で幾度か摩って塗りつけてから、メアは既に膨らんだ杭の先をぬるん、と口に含んだ。
歯を立てぬよう慎重に喉の奥まで槍を飲み込んでも、いつものことながらダンテのそれは収まりきらない。むしろ年々大きくなっている気さえする。
切れ切れに息継ぎをしながら、根元を指で擦りくぷくぷと音を上げて口淫に耽っていると、ダンテの指先がちろりとメアの髪や耳を撫でてくる。
そのこそばゆさに喉の奥でぐっとカリ首を締めるとダンテの眉間に深い皺が寄った。いつもより早いなあ、とメアはのんびりとその様子を上目遣いに伺う。それは吐精を必死に堪えている時の顔だ。
ダンテはフェラチオされるのは好むくせにそのまま最後まで果てるのは嫌いなようだった。
彼から言われた通りに止める日の方が勿論多いが今日は知ったことか、とメアはぐりっと裏筋を舌の先で転がしながら、濡れた会陰部から陰嚢にかけてを手の平や指先でやんわりと撫であげた。
ダンテがメアの弱点を知っているように、メアもダンテの弱点を知っているつもりだ。
"そうだ。そんなことを知っているのだって、私だけのはず。"
胸を締め付けてくる不安をかなぐり捨てながら、弱い場所を攻めてやると、次の瞬間びくん、と槍が幾度か脈打ち、喉の奥に熱い奔流が流れ込んできた。
「っ、ふぅ…あっ…くそっ……」
深く深く息を吐きながら、ダンテはどこか悔しそうに歯を食いしばっていた。
今日もフェラで出すつもりじゃなかったんだろうなぁと思いつつ、メアはほの甘いがそれでも苦い白濁を口内に全て受け止める。
ほとんどダンテのものしか知らないが故にいつも粘度が濃いのが当たり前だと思っていたが、以前読んだポルノ寄りのゴシップ誌で体調や頻度によって粘度は変わると書いてあった。さらさらの精液は上手く想像出来ないなぁ、そんなことを考えながらメアはゆっくりと唾液と精液を口内で混ぜ合わせ、ぐっと嚥下する。
「お前、年々テクニックがえげつなくなってないか……」
「んー?」
「すげえ犯された気分になる……」
温くなったチェリーコークをひと口飲んでから、手の平で目元を覆っているダンテの顔色を伺う。怒っている訳では、なさそうだった。それに口では文句を言いつつも下腹部の屹立はあっという間に硬度を取り戻している。
精液の残滓を舐め取ってから、メアは臍まで反り返っているダンテの槍に黙々とベッドサイドテーブルから取り出したスキンをかけた。
ダンテがため息を吐きながら、腹の上に跨ってくるメアをほのかに赤らんだ顔で見上げる。
「慣らさなくて平気なのか」
オープンクロッチの下着に手を伸ばされ、羞恥に腰が引けたが反応した時にはもう遅かった。しとどに濡れそぼった秘裂を指の腹でなぞられ、へぇ、とダンテが可笑しそうに口の端を歪める。
「大洪水、だな」
「……だから平気なの」
「改めて見ると、すげえエロい下着だな」
受け止める布地が少ないせいで、いつもより殊更溢れ出た蜜がぬらぬらとメアの太腿を汚していた。その蜜をダンテの指先がすくい上げたかと思うと、ぐりっと花芽を押しつぶすように塗りたくられる。突然の刺激に息を飲みながら、メアはぶるりと腰を震わせた。
「やだぁ……触ったらダメっ……」
あまり弄ばれたら意識がぐずぐずになってしまって目標が達成できない。それだけは避けなくちゃいけない。
悪戯をしたくてしょうがない様子で彷徨うダンテの両腕を彼の胸の前でえいやっと、やんわり縫い止めると、その薄い唇に笑みが浮かぶ。
「どうした? 今日はやけに頑固だな」
「……そんなことない」
空いた片手でダンテの硬く尖った槍を蜜口にあてがうと、メアはゆっくりと腰を沈めた。
ショーツのピンクよりも鮮やかな花弁がじっとりと綻んでいく。
体の中に焼けるように熱い異物を受け入れる形容しがたいこの感触は、きっと永遠に慣れることがないのだと思う。それでもダンテの形をしっかりと覚え尽くしたメアの胎内はぴったりと寄り添いながら、吸い付くようにその槍を根元まで飲み込んだ。
尖端が最奥に行き着いた瞬間、蜜襞が震え、メアはお腹の底でずっと燻っていた熱たちがいとも容易くぱちん、と弾けるのを感じた。
「んんんっ、ふっ……!」
口を押さえ、ぶるりと体を痙攣させながら涙を零すメアの様子におー、とダンテが頬に手を伸ばす。
「そんなに頑張んなくてもいいんだぜ……」
「別に頑張ってなんか、ないっ」
眦から伝い落ちた涙をダンテに拭われながら、メアは息を荒らげてゆっくりと腰を上下に動かし始めた。
「お前、奥弱いだろ」
「よわくない」
「いつもは止めてって泣きじゃくるくせに」
「ないてない」
どういう訳かお腹の奥が敏感すぎるメアは騎乗位を滅多にすることがなかった。どうにか出来たとしても酷く疲れてしまうので、あまり得意ではない。それでも時折するとダンテが喜んでくれるので、それが唯一の救いだったのだ。
ダンテの厚い胸板に手をそえ、唇を引き結びながらメアは尻を揺らして抽挿の動きに没頭した。結合部から響くちゅぷちゅぷという淫靡な水音がどんどんと大きくなっていく。
暫くは何もせず、悩ましげなメアの表情と透けたシフォンの下でふるふると揺れる双丘を楽しげに眺めていたダンテだったが、おもむろにベビードールの胸元へと手を伸ばした。
リボンを結んで留めるだけのフロントオープンタイプの下着だと気がついたようで、ダンテがプレゼントの包みを開くようにリボンの端をしゅるりと引っ張る。はらりと胸の前があられもなく空気に晒され、メアは小さく悲鳴を上げながら腕で体を覆い隠した。
「もうほとんど見えてるみたいなもんだっただろうが」
「そ、そうだけどっ、勝手に解いちゃヤダ……」
ダンテは寝そべっていた上半身を素早く起こすと、メアの腰をぐっと抱き寄せた。ずるり、と浮かせていた腰が沈み込んでしまいメアはまた一つ悲鳴を上げそうになる。
ぎゅうと強めに胸の膨らみを揉まれ、ダンテが低い声で囁いた。
「そろそろ俺にも触らせてくれよ」
「うう……待って、ダンテ……」
唇に吐息がかかり、その隙間からちろりと舌が差し出される。メアは無視する訳にも行かず、その餌に自ら食いついた。舌を絡ませ、丹念に歯列をなぞられ浮ついた声が漏れてしまう。次第に鼻で呼吸するのも難しいような乱暴な口付けが続き、メアは心拍数がどんどんと上がって行くのを感じていた。
そこには興奮だけじゃなく、不安も混ざっている。
"もしかして、ダンテ怒ってる?"
うっすらと目を開くと相変わらず劣情が揺らぐ瞳と目が合うが、イマイチ何を考えているのか判らなかった。
"私、何か失敗した?"
あともうちょっと気持ちよくなってもらった隙に、ちょこっとだけ聞きたいことがあった、それだけのはずなのに。
噛みつくような口付けは首筋へと伝い降り、メアの頸動脈の辺りにガリッと強い痛みが走った。ダンテに歯牙を立てられたことに気がつき、メアはその逞しい二の腕に爪を立ててしがみつく。ほのかにぬるりとした感触が伝い落ちている気がしたけれど、それが血液なのか唾液なのかそれとも汗なのかすら判らない。けれどそれだってどうせすぐに治る、と身を委ねているとダンテの手の平がもったりと今度は穏やかにメアの乳房をすくい上げる。
「俺一人で良い気分になってもしょうがないんだよ」
どこか拗ねたような表情でダンテがそう呟く。
メアがその言葉の意味を考えあぐねてぱちくりと目を瞬かせていると、不満げに尖った唇が乳暈をすっぽりと飲み込んだ。
「あっ、う……」
尖端を強く搾るように扱かれたかと思うと、音を立てて吸い上げられてメアは背筋を震わせた。
それとほぼ同時に空いた片方の手が、ほとんど露わになった白いメアの尻臀をぱちん、と軽く叩く。痛みこそなかったが反射的にひっ、と喉を鳴らしてダンテの首に縋り付くと、そのままベッドの上に押し倒されていた。繋がったまま腰骨をぐりぐりと押し当てられて、甘い疼きが下腹部をぞぞぞ、と妖しく這い上がって行く。
メアは半ばパニックになりながら、ダンテの胸板を押し返そうと躍起になった。
「ダメ、やだっ、ダンテ……!今日は休んでていいって最初に言ったじゃん!」
「もう充分休んだし堪能させてもらったけどな」
汗ばんだメアの額を撫で上げて、ダンテはすっかりリップが薄れた唇をなぞる。
「……もし言いたいことがあんなら、さっさと吐いちまえば? 何か隠してんだろ、お前」
その不意の言葉にメアはぴくり、と体を強ばらせた。
目の前で冷静に光るアイスブルーの瞳が今はひどく怖かった。体だって深い所で繋がっているはずなのに、心だけが突然引き千切られて宙に放り捨てられたような思いになってメアは呆然と目を見開く。
その表情にダンテも一瞬驚いた顔をしてから、怪訝そうに眉根を寄せると、
「あー……もしかして、もっと深刻な話だったのか?」
「なんだと、思ったの……?」
「いや、俺とのセックスで気に入らないことがあってやけくそになってんのかと思って。ちょっと、イラついた」
そう気まずげに囁かれてメアはなるほど、と首を傾げる。あまりにも不器用すぎたのだ。それでダンテを不愉快にさせてしまった。
「俺はいつもメアと一緒に気分良くなるのが好きで居たつもりだったんだけど、もしかしてメアはそうでもなかったのかなって」
別にセックスに限った話じゃねえんだけどさ、と呟いてダンテはメアの頬や目蓋に何度かキスを落とした。
「だったらごめんな」
その言葉に、胎内で張り詰めたままのダンテの杭を思わずきゅうう、と締めつけていた。
「うっ、ちょっ、……はっ?」
「ちがうの、ごめんね、ダンテ、ごめんなさい」
溢れそうになる涙を飲み込んでメアはダンテの腰にヒールが刺さらぬよう脚を絡ませた。
何てひどい女なんだろう、とメアは自分自身を呪った。こんなに好きな人を勝手に疑い試そうとして彼を振り回した自分はやっぱり醜い女だ、とメアは罪悪感の波に苛まれ手の平に顔を埋めて大きく息を吐く。
「あー……今日はもう休むか?」
メアの動揺ぶりを見た故の問いかけに、イエスともノーとも返さずに呟く。
「一個だけ、言ってもいい?」
「何」
「……今だけは、私のことだけ見てて欲しいの」
その欲に塗れたメアの本音にダンテは一瞬眉をひそめたかと思うと、おやっと顔色を変えて苦笑いをする。
「もしかしてお前、トリッシュのことが引っかかってた、のか……?」
どうして判ったの、と言わんばかりについ目を見張ってしまい「やっぱりな」とダンテが息をつく。彼の前だと全てが顔に出てしまいがちになっている自覚があり、メアはああもう嫌だ、と喚きながらダンテの首にしがみついた。
「私本当にバカなの!ごめんなさい……」
「いや、俺の方がバカだった、な」
ぎゅう、と抱きしめられて後頭部を手の平であやす様に撫でられると、どうにかねじ伏せたはずの涙がまた溢れだしそうになってしまう。
ダンテは幼子のようにぐずるメアを宥めようと頬を穏やかな手つきで撫ぜながら、サファイアブルーの瞳を真っ直ぐ見つめて囁く。
「トリッシュはただの友人」
嗚咽が零れそうになってメアが強く下唇を噛み締めると、その引き結んだ唇にダンテは困ったように軽いキスを落とす。
「まあ、落ち着けよハニー。俺みたいなダメ男の世話してくれながら十何年もずっと飽きずに一緒に居てくれてさ、そんなクソ野郎の周りの女に可愛いヤキモチ妬いたり、こんな必死にいじらしい格好して尽くそうとしてくれる、そんな最高の女は世界中どこ探したってお前たった一人だけなんだ。……なあ、メア、愛してるよ。多分さ、お前や、もしかしたら俺自身が考えているよりももっと、俺はお前のことを愛してると思うんだ」
伝わった、か?と不安げに問いかけられて、メアは結い上げた髪が肌を打ち音を上げるほど首を縦に振った。
普段どちらかと言えば口数が多いとは言えないダンテが真摯に紡いだ気持ちも、自分がバカみたいなことで悩んでいたのも痛いくらい理解出来ていた。
「もういいですぅ……判った……判ったからもうだいじょぶ」
「ほんとかよ」
そう笑いながら呼吸を奪うように唇を攫われて、体の奥がずくずくと爛れたように燃え落ちていく心地がした。
甘いチェリーコークの名残りが香る舌の粘膜を擦り合わせながら、ダンテの無骨な指先が首筋をくすぐり、メアの柔らかな双丘を解していく。
「んっ、はうっ……」
殺しきれない声がまろびでてしまい、メアの耳が羞恥に赤く染まった。どこもかしこもすっかり敏感になってしまっていて、乳頭を指の腹でこねくり回されるたびに蜜襞がダンテの雄槍をきゅうきゅうと締め付けてしまう。
メアが普段より歯止めの効かない体をもどかしく思っていると、
「いつもより反応がいいんだな」
ダンテは眉をしかめて苦しげに堪えながらも、嬉しそうにメアの汗ばんだ下腹部を撫でた。その表情を間近で見せつけられてメアは静かに息を吐く。
トリッシュにしか見せないダンテの表情がもしもあるのだとしたら、今のダンテの表情だってきっとメアにしか見られないものなのだろう。
そうだ、それでいいや、とメアは笑ってダンテの左手を手繰り寄せると、その大きな手の平に頬を埋める。
「今度は急に笑い出すのか……」
「気がついちゃったから」
「何に」
「ナイショ」
ふぅんと鼻を鳴らすと、ダンテは思い立ったようにメアの体を抱き、ゆるゆると抽挿を始めた。
「ひゃあっ、んっ、待って、ダン、テ」
「俺にしてはだいぶ待ったから、もう無理だ、な……っ」
動き出した途端に内側を満たしていた蜜がとろとろと零れ落ちてシーツを濡らしていく感触があった。ダンテの鏃の尖端で掻き乱されては子宮口まで真っ直ぐに突き上げられ、メアは声も無く背を弓なりに反らせた。
時折ぐりぐりと最奥を擦りあげられたかと思うと、ダンテが唾液に濡れた指の腹でメアの秘裂に隠れていた花芽をくるりと突く。
「ん、あああ……っ!」
強すぎる刺激に一瞬で視界が白く染まった。蜜襞がダンテの昂りを食いしめ、思い切り収縮する。
「はっ……きつ……っ」
苦しげに笑いながら、ダンテは二、三度震えて達したばかりのメアの腰を容赦なく抱え込み突き上げた。蜜壁を余すことなく蹂躙され、増していく速度にじゅぶじゅぶと攪拌された愛液が淫猥な音を立てる。
メアの朦朧としかけた意識も、更なる刺激により強引に引き摺り戻されてしまう。
「やぁっ、だぁ……むり、ダンテぇ……」
「本当に可愛いよな、お前。……全部見てるよ。ちゃんと見てるから、心配すんな」
絡みつく媚肉を引き剥がすように穿たれる熱い楔に、メアは内ももをひくつかせながら泣き喘ぐことしかできなくなっていた。そんな声すらもダンテの舌先がすくい上げキスで塞いでしまう。
蜜路の果てを痛いくらいに攻め立てられ、再びメアの胎が切なく引き絞られていく。その圧を堪能していたダンテもそろそろ限界が近付き、いっそう強く腰を打ち付けた。
「んあああっ、ダンテ……ダンテぇ、またイッちゃう、イッちゃうよぉ……ひああっ、」
「っ、は……メア、ッ……」
夢に魘されでもしたようにお互いの名前を呼び合いながら、先にメアが高みに昇りつめた。搾り取るように食らいついて離さない蜜襞に誘い込まれ、ダンテは数度腰を叩きつけたのちに最奥に白濁を注ぎ込む。スキン越しでもドクンと強く脈打つ熱い感触を下腹に受け止めながら、メアは肌を包むぬるま湯のような幸福感を確かに感じていた。
体内からダンテの杭がずるん、と抜け落ちて行く感覚に打ち震えていると、
「メア」
甘い余韻の中で名前を呼ばれてとろりと目を向けると、ゆったりと体を抱きかかえられる。お互いに未だ火照った体と汗ばんだ肌が擦れ合い、ダンテのうなじに頬をよせれば甘ったるい芳香がメアの胸を満たしていく。
メアの頬に伝った涙の後を寂しげに指でなぞってから、ダンテは啄むような口付けを数度メアの唇に落とす。どこか罪悪感の残るその仕草に「ねえ、ダンテ、」とメアは汗に濡れた銀糸に指を差し込んだ。
「一緒にもっかいお風呂入ろ……?」
ダンテは大きく目を見開いたかと思うと、すぐにメアの体を抱き上げてベッドから立ち上がった。
「喜んで、マイ・ハニー」
まだ夜も長いしな、という嬉しそうなダンテの呟きに、メアはそっと頷きを返した。