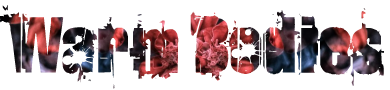事務所のドアを荒々しく開ける音にメアはふっと読みさしの本から視線をはね上げた。
読書に集中していたことと、ご機嫌にロックを吐き出しているジュークボックスの音に遮られ、いつの間にか外で土砂降りの雨が降っている事に気がついていなかった。
暗闇の中をばちばちと水滴が弾ける音が響き、帰ってきたダンテがコートを脱ぐと冷たい夜気を吸った雨水が飛び散る。
「おつかれさま、仕事どうだった?」
「まあまあ、かな」
今日のダンテは朝からエンツォの依頼で悪魔狩りの仕事に出掛けていた。夕方頃には帰る、と言っていたのだが日はもうとっぷりと暮れている。手こずったのだろうか、と濡れそぼった銀髪からポタポタと雨水を垂らすばかりの彼の静かな表情を伺おうと近付く。と、ダンテはするりとメアの脇を通り抜け、ソファにコートを放り投げると、
「……シャワー、浴びてくるわ」
浴室に消えていった。疲れているのだろうか、と脱ぎ捨てられたコートを衣装掛けに吊るすと、ぬるりとした感触が手の平に広がった。粘性の強い、薄い紫色をした液体だ。悪魔の体液の類だろうか、とメアは慌ててキッチンで手を洗い、コートのそれをタオルで拭き取る。
何か厄介なことに巻き込まれていないといいんだけど、とメアは溜め息を吐きながら本に意識を戻したが、幸か不幸かその予感は的中してしまったようだった。
浴室から出てきたダンテが肩で息をしている気配を振り返ってメアは思わずぎくり、と固まってしまった。蒸気の中で霞む、その腕や顎の一部分が中途半端に魔人化していたのだ。白目の部分が黒く反転し、普段のアイスブルーの瞳は黄金色に染まっていた。肘から下が赤く硬い爬虫類のような鱗に覆われ十指の先で鋭い爪が濡れて光る様を見つめながら、そのただならぬ様子にメアは歩み寄りそっと尋ねる。
「大丈夫?ダンテ……」
「あんまり」
仕事先で遭遇した悪魔に油断した隙に何やら気味の悪い液体をかけられ、その時は特段ダメージを感じなかった、とダンテは気だるそうにゼーゼーと息を切らしながら話した。あの紫色のぬるっとしたやつかな、とコートの付着物を思い出す。
「しばらくしたら魔力が飽和状態になって来て、このザマだ。上手く制御出来ねえ」
開いた手の平の上でパチパチと白い魔力が弾けた。しんどい、と零す上気した頬とひどい汗を見てメアはうーんと唸る。と、おもむろにダンテの腕にひたりと触れてみた。パチン、と肌を刺した魔力の流れを意識して掴み、自分の内側に引きずり込む。
魔力を食われる、とダンテはいつも表現するが、飽和状態なんだとしたら消費してやればいいだけの話では?とふと思ったのだ。
そのメアの行動にダンテはきょとん、と目を丸くする。
「ちょっとは楽になったりする?」
「あー……閃いた」
爪をメアの肌に立てぬよう両腕を掴むとダンテはふっと笑って、
「"食う"の、手伝ってくれないか」
ベッドの上でメアはやけくそ気味にパジャマ代わりのオーバーサイズのTシャツと下着を脱いで裸になりながら顔を赤くして文句を言う。
「手伝うのはいいんだけど、えっちする必要ある?!」
汗みずくの肌からズボンを引き抜きながら、ダンテはじっと据わった目で仕方ねえだろ、と口の端を下げた。
「戦闘時以外だと精液が一番魔力を乗せ易いんだよ……!」
「な、なるほど」
「この雨の中、外で俺とドンパチすんのとどっちがいい」
そんな事言われたらダンテのサンドバッグになってボロボロのミンチにされるのがオチである、とメアは想像しただけで背筋を薄ら寒くしながらかぶりを横に振った。
「こっちがいい」
「……でも、気乗りしないなら無理しなくてもいいぜ」
そんな事ない、と返しながら実際苦しそうなのは明白だったので自分に出来ることならなるべくしてあげたい、とメアはダンテのいつもより熱い背中に体を寄せた。胸板を撫でおろして首筋に頬を埋める。
「……ちゃんとえっちしたいよ?」
少し安心したように息をつくダンテをシーツの上に引きずり込むと、そのまま押し倒される。その拍子で引っかかった爪の先でメアの二の腕が薄く切れて血が滲むのを見て、ダンテが苦い顔をした。
「悪い」
「へいき」
血をぺろりと舐めとると、すでに傷口は塞がっている。自身の治癒、という面ではメアはもう魔力を使いこなせていた。
既に足の間で硬くいきり立っているダンテの杭に目をやりながら、メアは首を伸ばして口付けをし鋭く並んだ歯列に舌を潜り込ませた。獣のような口蓋をなぞると血の味がする。きっと口の中のどこかが切れたんだ、と思いながらも躊躇わずダンテの舌を捕まえた。
ちゅぷちゅぷと粘膜を擦り合わせ鉄臭い口付けをしながらダンテの丸い頭蓋を撫で下ろす。いつもより荒い息を吐き赤い顔をしたダンテが可愛らしく思えた。頬の赤みのせいで精悍で整った顔立ちがいくらか幼く見えるのだろう。
ピリピリと舌の上を走る魔力の心地良さを感じながら、舌を絡ませ合う。
魔力が体の中に流れ込んで来ると鳩尾の辺りがふわふわと温かくなる、とダンテに話した時、俺の感覚とは違うんだなと彼は興味深そうにしていた。ダンテの場合、魔力は全身にみなぎるものであって普段は意識の外にあるが使う時には熱くも冷たくもなる、そんなようなことを言っていた。私はダンテの魔力の"味"しか知らないから温かさしか判らないのかもしれない、とふとそんな事を思った。
離した舌が血の色をした唾液の糸で繋がるのをぼんやりと見ながら、メアはダンテの額に浮いた汗を手の平で拭う。苦しげにしかめられた眉間のしわを撫でてから、
「もう入れたい、よね……?」
「……まあな」
メアは体を起こすとサイドテーブルの引き出しからこの前ダンテがふざけて買って来たローションのチューブを取り出した。イチゴの香りがする、パッケージがけばけばしいピンク色のそれを自分が一番最初に使うことになるとは、とメアは下唇を噛む。
心臓が恥ずかしさで騒がしかったがどうにか無視して枕に体を預けると、薄いピンク色のジェルを手の平に出す。ダンテの腕がこんな状況なので、いつもは彼の指がしてくれるほぐす準備を今日は自分でやるしかない。
足の間にとろりと垂らすと冷たさで身が竦んだ。まだほんのりとしか濡れていない秘裂に馴染ませながら、ぬぷりと中に指を埋めていく。
その様をダンテの金色の瞳にじっと見つめられてどくどくと心臓が耳元で鳴りだす。瞳の色が違うせいか違う誰かに見つめられているような居心地の悪さに襲われた。
指で内側をかき混ぜ、入口を擦り上げるたびにふるふるとメアの体が震えた。いつもされて心地良いと感じるダンテの指の動きを思い出しながら、指を二本に増やしていく。
「今、何考えてる?」
思考を読まれた気がしてメアがムッと眉を潜めると、ダンテはおかしそうに笑った。
甘いイチゴの香りを胸に吸い込むたびに頭の芯がとろとろとアイスクリームのように崩れ落ちていくような感覚に陥る。
怖々とした手つきで髪を撫でながら、メアの涙で蕩けたサファイアブルーの瞳にダンテがそっとキスを落とした。その唇が耳朶から首筋に滑るのを感じながら、メアはぐちゅ、と秘所が熱く溶けていく音を聞く。
「っん……は、あ」
どうしても物足りなさがあってお腹の奥がじんじんと切なく疼いたが、今はそれでいいんだった、とメアはちゅぽ、とローションと愛液でしとどに濡れた秘所から指を抜いた。薄桃色に色づいてほぐれた秘裂を指で開き、ん、と喉を鳴らす。
「はい、どうぞ。……もう平気だよ」
その姿に「っ、」と短く呻いてダンテが頬を染めて顔をしかめた。
「どうしたの?」
「……なんでもない。本当、無自覚だよなお前」
苦い顔をしたまま硬く勃った尖端をメアの入口に宛てがう。避妊具越しだと魔力を吸収出来ないので、触れ合うそこは素肌の感触だった。それだけでぞくぞくと腰骨の辺りが期待に粟立ってしまう。
ダンテが腰を落とす動きに合わせてメアもゆっくりと息を吐いて力を抜いた。
体の中にずくり、と潜り込んで来た塊はいつもより硬く大きかったが、柔らかく蕩けたメアの内側は穏やかにダンテの杭を受け止めた。お腹の奥にこつん、とつき当たる感触を上から撫でながらメアは目を細める。
「ダンテの凄くあっついね……」
「っ、は……」
ピリピリと伝わってくる微弱な魔力の刺激に意識を集中し、くいっと手繰り寄せると、狼狽える声が上がった。
「ん、メア、ちょっと待っ、」
顔をしかめてダンテが体を折ると、ビクンと杭が内側で脈打った。吐き出された熱にじんわりとお腹が温かくなるのを感じながら、ありゃ?とメアが目を丸くする。シーツを掴んでダンテは苦い顔をした。
「くっそ……とんだ早漏野郎になっちまった」
「ごめんね、急に刺激したから」
いや、とダンテはメアの頭を撫でてすっと目を細めた。
「もういいよ、全部好きにしてくれ」
体を抱き寄せられて、ダンテがゆるゆると腰を動かし始める。いつもより穏やかな動きなのに、開いたままの魔力の流れが肌に染み込んで来て快感が何倍にも膨れ上がっている気がした。それはダンテも同じようで些細な弾みですぐに達してしまうのを堪えているようだ。全部吐き出して楽になっちゃえばいいのに、とメアは苦しげなダンテの頬を撫でてきゅう、と下腹部に力を込めた。
「っ、う、あ」
掠れた声を耳元で漏らしながら、とぷり、と溢れたダンテの精液の熱と魔力にお腹の真ん中がぽかぽかと温かくなっていく。
戸惑うように眉をひそめているダンテの姿にメアはふっと笑って、
「今日のダンテ、可愛いね」
「……るせぇ」
恥ずかしそうに首筋に顔を埋めながら、ごり、とお腹の奥を突き上げられてメアはひゃっ、と小さな悲鳴を上げる。早められた律動で接合部からぐちゅぐちゅと濡れた音が響いた。精液と愛液とローションの混ざった液体が泡立ち、二人の白い肌を汚していく。
「あっ、んあっ、ダンテぇ……っ」
「っ、くっ……」
いつもより深く強くお腹の奥が疼いて苦しい、とメアは明滅する視界の中でただ声をあげることしか出来なくなっていた。ぱちゅん、ぱちゅん、と濡れた音が響き、ダンテの腰の律動が早くなっていく。
ピクピクと射精の前兆で震える杭を中に感じて、何とかメアは魔力を吸い上げる。
"食われる"感触ってどんな感じなんだろ、とふと気になった。彼の反応からして不快なものではなさそうなのが幸いなことだろう。
ダンテは二重の快感に襲われて、歯を食いしばったままメアの中に精を吐き出した。その最奥を濡らす熱さに疼きがぶわりと高まり、メアも喉を反らせてピクン、と果てる。
ダンテの杭は未だ萎える気配がなく、まだ余韻に震えるメアの中を休む事なくちゅぷちゅぷと掻き回し始めた。
そんな行為を繰り返しているうちに、メアの体に注ぎ込める魔力にもそろそろ限界が来ていた。食べるだけ食べたらお腹がいっぱいになるのは当たり前の現象だ。いずれそうなるだろうと判っていたメアは髪の毛をかき上げると白い首筋を晒してダンテに囁いた。
「噛んで欲しいの」
「噛むって、どのくらい」
血がいっぱい出るまで?とメアは笑った。
傷の修復に魔力を消費すれば、まだダンテの魔力を受け入れられるはずだ。
「"私を食べて"?」
不思議の国のアリスのような誘い文句にダンテはくらりと目眩を覚えながら、その甘く香る首筋に強く歯を立てていた。
ごきゅ、と獣の牙が喉笛の肉を突き破り、とろりと温かい血がホットチョコレートのように溢れ出す。
強い痛みと快楽の海でぐちゃぐちゃに揉まれながらも、メアは魔力の流れを傷口に注いでいた。
血の匂いで箍が外れたのか、ダンテは荒く息を切らしながらメアの体を貪ることに夢中になり始めた。
何度吐精しても硬いまま激しく内側を掻き乱す杭の熱さと、首筋に立てられる牙と吐息の熱さがメアの意識を何度もさらおうとして行く。
幾度目の射精かも判らなくなったダンテの熱を最奥に感じながら、メアもぴくんと背中を弓なりに反らせて果てた。
痛みと快感の境界線がどんどん曖昧になっていき、首筋を噛まれただけで脳が勘違いして達してしまう時もあるほどだ。
短く息を切らしながら涙で溶けた目をダンテに向けると、焦点の曖昧な金色の瞳と目が合い、血に濡れた舌が喉の傷口をざらりと舐めた。
そのまま顎を伝って来た熱い舌で口付けをすると鉄の味がじわりと口の中に広がった。
本当に獣になってしまったみたいだ、とメアは笑った。本能のままに貪りあって、理性なんてもうとっくに吹き飛んでいる。
ルージュを引いたような赤に唇と顎を染めながら、ダンテの口元がおもむろに首筋を伝い乳房に辿り着く。白い風船のような柔らかな曲線を手の平がしっとりとすくい、尖った爪が埋もれ、メアは短く息を吐いた。白い丘に赤い血の筋の軌跡がつうと残る。
ダンテの口が尖端を含んでちゅぷ、と舌で乳首を転がすこそばゆい動作をするのを見ながら、ふわりとメアは笑って柔らかい銀髪をゆっくりと撫でた。
「赤ちゃんみたい」
かわいい、と呟く声がひどく掠れる。
改めて彼のことを愛おしく思ってしまった。人と悪魔の境界で揺らぎ苦しむダンテの姿はどうしたって美しくて愛おしい。
双丘を強く揉みしだかれ、筋張った杭で最奥を抉られて嬌声が零れた。そのまま腰をぐちゅぐちゅと振られながら乳首を強く抓り上げられメアはひゃあ、と走った電流のような刺激に声を漏らした。魔力のものとは違う、明らかに甘い痺れだった。
赤い木の実のように腫れ上がった尖端を冷たく鋭い爪の生えた指がくりくりと弄くり回す。
痛みへの切望感に蕩けた中がきゅう、とダンテの杭を締め上げた。
その衝動が伝わったのか熱い息を吐き出しながら、また首筋を深く食まれてメアはダンテの背中に爪を立てる。
ダンテから与えられる痛みがすっかり快楽にすり代わってしまっていた。その暴力的な交わりで正常な判断力すらも汗と一緒に流れ去っている。
「あっ、ふぅ…あ…」
ぬるぬると首筋を伝う血とダンテの牙の熱さに目を細めながら、内側の弱い場所をグリッと擦りあげられてメアは簡単に果てた。
それに引き摺られるようにダンテの杭もぶるり、と震える。
とぷんと新たに精が注ぎ込まれ、とっくに中では受け止めきれず溢れ出した白濁がメアの太ももを酷く汚していた。
ふー、ふー、と荒い息の音だけがしばらく響いたかと思うと、ふとダンテの顎が緩まり、見開かれた金色の目が段々と青い色に戻って行くのをメアは静かに見守っていた。
魔力の暴走が収まったのか、バチン、と一度空気が弾けるような音と共にダンテの腕や顎が元の人の肌に戻っていく。
まだ治療の終わっていない喉の傷をちろちろと舌で舐められてメアはくすぐったさで笑い声をあげた。
「おかえり」
「ごめんな……痛かったよな」
ようやく熱の引いたダンテ自身がメアの中からずるりと抜け落ちるのを感じながら、ぎゅっと抱き締められる。
赤い血と白濁にまみれ、爪で切り裂かれてボロボロになったシーツの上でもつれ合いながらメアは大丈夫とダンテの頭を撫でた。
「ちゃんと気持ちよかったよ」
「嘘つけ」
「ほんとに」
すり、と頭を抱き寄せ音を立ててキスを落とす。
「可愛かったし、ダンテ」
「あんま言うなそれ……」
ふへへ、と笑ってメアは俯いて落ち込んでいるダンテの頬を手の平で包み込んだ。
目を伏せたままダンテは囁く。
「ありがとな」
よりいっそう強く抱き寄せられ体の温かさとお腹の奥に滲む柔らかな温もりを噛みしめながら、メアはそっと目を閉じた。