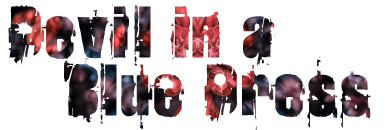色鮮やかな夜のネオン街が窓ガラスの向こうで流線を描いては、次々と横切って行く。
その景色を焦点の合わない視界の内で眺めながら、メアは非現実的な空気に未だ呆気に取られていた。依頼主の厚意で事務所まで迎えに来たリムジンには冷えたスパークリングワインとカットフルーツが用意されている。繊細なカットガラスのプレートに盛られたイチゴをつまみながら、ダンテはメアとは対照的にリラックスした様子だ。
ブラックライトが煌々と光る薄暗い車内は本来十人は余裕で乗れそうだったが、今はメアとダンテの二人きりだった。
どうしてこんな状況になってしまったのだろうと、十秒に一回は考え込んでしまう。
「緊張して吐きそうなんだけど……私場違いだって笑われないかな?」
「そんなに肩肘張っても仕方ねえだろ」
メアはローテーブルの上に置いてあった金の蝋印の割られた封筒を取り上げて、もう一度内容が間違っていないか目を通す。
それは舞踏会への招待状だった。
「前々から悪魔絡みでは有名な男なんだよ。ハズレの可能性は薄いと思うぜ?」
一週間前に届いた招待状に添えられた言葉から厄介な気配を感じ取ったダンテはその依頼にノリ気だった。"自分の感知できない所で闇競売が開かれようとしている"、"出品される品の中には世にも珍しい悪魔も混ざっているらしい"、"私は止める術を持たないのでどうか貴殿の力を貸して欲しい"……そういった旨が滔々と綴られており、ダンテは二つ返事で依頼を引き受けた。
「胡散臭いよな。罠の可能性だってある。でも狩らない訳にはいかないだろ」
様々な懸念はひとまず置いておいて、依頼をこなすのは良しとしよう。しかし潜入する現場は富豪たちが懇親を深める舞踏会である。メアにとっては相手の罠に陥る事よりも、その手前に築かれた"牙城"の方がよっぽどプレッシャーであった。
「お金持ち……こわい……」
「別に会話する必要はねえだろ。パートナー同伴の条件がなかったら、俺だけで来たんだけどな……」
ダンテがちょうどスパークリングワインのボトルを飲み干すと、ゆっくりとリムジンが止まり、運転手によってドアが開けられた。
小一時間ほど走った末に辿り着いたのは郊外の豊かな草原の中に建てられた一軒の邸宅だった。ヨーロッパ風の柔らかなクリーム色と水色の外壁に、ロココ調の装飾が散見できる。右手の奥にはドーム型の温室が見え、端的に表すなら"豪邸"の一言に尽きる趣だった。実際のところ集まる人々は王族でも貴族でも何でもないので、巨大なおままごとのセットにも見えてしまうのだが。
二人一組で来ることと、夜会服を着用すること、今回の舞踏会のドレスコードはただそれだけだった。
ダンテに手を引かれて車から降りる。今晩のメアはオリエンタルブルーの、深いスリットが入ったイブニングドレスにシルバーのハイヒールの装いだった。淡いとはいえ目につくかもしれない腕の古傷を隠すためにレースの長袖があるデザインにしてもらったが、オフショルダーのデザインなので夜気に晒された肩と背中が肌寒く、ストールを準備すれば良かっただろうかと早くも後悔し始めていた。一方のダンテは艶やかな黒色をしたベルベットのディナージャケットと黒いワイシャツにグレーのベスト、そこへ深い臙脂色のネクタイを締めていた。流石にいつもの赤いコート姿では目立つ上にドレスコードをクリア出来そうにもないので、メアのドレスと一緒に見繕ってきたものだ。
ドレスはウエストのレース部分で切り替えされるまで体のラインがくっきりと出てしまう作りをしていて、鳩尾の辺りが既に苦しい。着られれば何でもいいよと投げやりだったメアの代わりにダンテが選んだものだった。
「やっぱり似合ってるぜ。……瞳の色とよく合ってる」
耳元で囁かれた満足そうなダンテの声にメアは赤い口紅を引いた唇を不満げに尖らせた。
「もうちょっと露出が少ないドレスが良かった、かも」
今更ながら、猛烈に恥ずかしくなってきてしまった。
髪を上げているせいで白いデコルテはいっそう際立って映え、タイトな前身頃に押し上げられた豊かな胸の谷間には細い銀のネックレスが窮屈そうに挟まっている。
普段メアがゆるいサイズの服を好んで着ているせいもあってダンテもあまり意識していなかったが、ドレスを選ぶ際一着目を試着して出てきたメアのスタイルが案外良いことに気がついてしまったのだった。
「"あるもん"は見せつけないともったいないだろ?」
「……ダンテのバカ」
「うるせぇ、自分で選ばないのが悪いんだ」
ダンテが差し出したエスコートする手を取り、メアはほうと小さく息を吐く。
「ダンテは何でも似合っちゃうね」
「スーツは肩が凝るから嫌いだけどな……」
いつもの伸びっぱなしの髪に櫛をいれ、ワックスで前髪をラフに横に流しただけなのに、ダンテの顔立ちには気品が感じられた。端整なのは見ての通りだったが、その纏う空気は先天的なのか?それとも素養なのだろうか?とメアはダンテの高い鼻筋の辺りをつい視線でなぞってしまう。
「どうした」
「な、何でもない」
気まずさを押し隠して、屋敷の入口で受付のボーイに招待状を渡すと、すぐに中の広間に案内された。こちらも優美なロカイユの装飾に溢れており、既に集まった招待客たちがぞろぞろと賑やかに談笑している。
グラスのかち合う音、甲高い笑い声と低い猫なで声、種々雑多な香水や酒の匂い、高級な生地の煌めき、膨れ上がった人々の気配に圧倒されてメアは脚がすくみそうになってしまった。こういったパーティーの類を全く知らない訳ではなく、父の手伝いでターゲットの気を引く為に潜り込んだことはあるが、それも一人でのことだった。
「今日は妙に落ち着かないな?」
ダンテに水のグラスを差し出されてメアは何も言わずにこくこくと飲み干した。
深く息を吐きそれから、何でだろう?と考え、
「ダンテといると緊張する」
「んなバカな」
「だってこれじゃあ……、」
言いかけた言葉が恥ずかしくなってメアはごくりと唾を呑んだ。なんだよ、と怪訝そうなダンテを無視してウェイターからもう一杯水を貰って飲み干す。
"恋人"みたいだ、と思ってしまったのだ。それも自意識過剰すぎると思った。
良くいえば寛容、悪くいえば適当なダンテの反応に惑わされてつい忘れてしまうが、自分はただ一時身の安全を守ってもらっているだけの居候である。裏を返せば、彼は父から逃げる為の隠れ蓑に過ぎないのだとメア自身も割り切る必要がある。こうやって悪魔絡みの依頼を手伝うのも逃亡資金が手っ取り早く必要だからであって、ダンテと一緒に居たいからとかそういう訳では断じてない。……はずなのだが。
「具合悪いなら無理すんなよ」
人混みの中でそっと腰に手を回されて人気の少ない壁際に誘導される。丈の長いスカートと高いヒールは決して歩きやすいとは言えず、ダンテのエスコートがあるとホッとした。
「ありがとう」
「お上品なフリは疲れるな」
今にもネクタイを解きたそうに首元を弄りながらダンテは深くため息を吐く。
そこへ人混みをゆっくりとかき分けてくる男の姿があった。くすんだ赤毛を後ろに流し、多くの参加者の中でも一際目立つ艶やかな深紅のタキシードを身にまとっている。これでシルクハットでも被ったらサーカス団の座長に見えなくもないな、とメアは思った。
男はダンテの姿を見つけると仰々しく腕を広げた。
「おお!"この世の中はすべて舞台"」
「……"男も女も皆役者"、ってか」
シェイクスピアの引用を引き継ぎながら、ダンテが口の端を上げて笑う。それに赤毛の男は拍手で返して微笑んだ。
「その銀髪はダンテさんですね。こちらの美しいお嬢さんがお連れの方かな。お似合いですよ、お二人共。今夜はようこそおいでくださいました」
彼は今回の依頼人、マルクス・ベラルディだった。先見の明に優れた、カリスマ投資家としても有名で雑誌やテレビでも度々見かける顔だ。だが一方で裏社会にも関わっているとされ武器や薬物の売買などにも手を染めていると聞く。取り分け捨て置けないのが悪魔の収集家でもあるらしい、という噂だ。
「直接ご依頼に行けず申し訳ありませんでした。いらしていただけて何よりです」
「面白そうなパーティーだったからな。見物するだけでも元が取れると思って」
ベラルディの微笑みは底が見えず、まるでのっぺりとした仮面が張り付いているかのようだった。メアは思わずダンテの腕にそっと身を寄せた。罠の可能性もある、とダンテは行きの車の中で言っていたが。
本題に入りましょうか、とベラルディが声を低くする。
「今回のご依頼はあくまで懸念、なのですが……部下のカルロの動向が最近不穏でして」
ベラルディがそっと示した部下の男・カルロは現在はインカムのイヤフォンを気にしながら通用口で指示を出している。
今晩秘密裏に競売の集会が開かれるという噂を耳にし、それを阻止したいのだが生憎ベラルディは戦力となる人材を持っていないので便利屋のダンテにそれを頼みたい、と彼は招待状にもあった旨をもう一度自身の口から説明した。
ダンテは後ろ手に上着の内側のホルスターに差した二挺拳銃を撫でながら、
「要はアイツを見張っときゃいいんだな?」
「ずばり、そういう事です」
ベラルディは芝居がかった声音と仕草でパチリ、と指を鳴らした。ウェイターの盆から赤ワインのグラスを取り上げながら、
「それでは、よろしくお願いしますね」
「ああ」
鼻歌混じりにベラルディは人混みに紛れていった。
その背中をじっと睨んでいると、ダンテに腕を掴んでいた指を剥がされ、手を握られる。
「そんなハムスターみたいに怯えんなよ」
「だってどっからどう見ても三百六十度嘘っぽいんだもん……」
視界の端で部下のカルロを追いながら、まあ飯でも食おうぜとダンテはメアの手を引いて立食形式のビュッフェエリアに向かう。
「何とかなんだろ」
メアはすっかり緊張で食欲が失せていたのでトマトとチーズのカプレーゼをちまちまとフォークでつつくばかりだったが、ダンテは涼しい顔でメニューを楽しんでいた。全種類コンプリートしてしまうのでは、という勢いにメアは呆気に取られる。
普段から疑問でしかないのだが、よく食べるわりに動かない時は本当に動かない週休六日主義のダンテの様子を知っているので、あの体の引き締まりが恨めしくて仕方なくなった。
そんなメアの心中を知ってから知らずか、これ美味いぜ、と時折横合いからフォークが伸びてくるのでぼんやりと口を開くと、確かに美味しいメニューばかりだった。中でもイチゴのレアチーズケーキは格別で、これは一ピース食べたいとメアが目を輝かせるとダンテがすかさず取り分けて持って来てくれた。
「今日は一段と紳士……どうしたの……」
「うるせえなぁ。普段から紳士だろうが」
えー、と唇を尖らせるとダンテに鼻の頭を軽く指で弾かれたのでメアは大人しく黙った。
「まあ無理矢理連れてきたのは俺だからな。ごめんな」
「え?」
「あんまり乗り気じゃなかっただろうお前」
少し気まずそうなダンテの横顔を見上げながら、そういう風に見えちゃってたかとメアは反省し、落ち込んだ。よくよく考えたらドレス選びに始まり、後ろ向きな発言ばかりしてしまっていた気がして、自分がますます嫌いになっていく。
「ちがうの、お仕事手伝えるのも嬉しいし、こういうパーティーは楽しそうだなと思ってたしダンテと来られて良かったなとは思ってるんだけど……」
メアは息継ぎもそこそこにまくし立てながら、涙腺が緩みそうになるのを堪えるように食べかけのケーキに視線を落とす。
「ダンテの隣が本当に私なんかでいいのかなって、ずっと不安に思っちゃって」
「は?」
「だって私色気ないし大人っぽい場所とか苦手だしガサツだし……!」
高くなってしまった声をあ、と手で押さえ込み、辺りを気にしながらメアは眉を潜めた。
「……ほらね?」
その様子にダンテはふはっ、と息を漏らすと小さく喉を鳴らして笑い出した。
「なんだそんなことか」
「私なんか変な事言った……?」
「いや、ほんと可愛いやつだなって思って」
なっ、とメアは言葉に詰まり、答えに悩んだ挙句、結局俯いて食べかけのケーキを食べる作業に戻った。味覚があやふやになってしまい、美味しいはずなのに頭の中がざわざわとして味に集中出来ない。ケーキを食べ終える頃には、段々と落ち着いてきて、ツボにハマってしまったのか小さく笑い続けているダンテを据わった目でひっそりと見やった。
「笑いすぎでしょう」
「はあー、おもしろ。空気に酔ってんのかなこれ」
その時、おもむろに音楽が流れ始めた。管弦楽団による生演奏で、指揮者のタクトに合わせて優雅なメロディが広間いっぱいに溢れていく。見るとフロアの中央で人の流れが生まれ、ワルツのステップが刻まれだした。
「踊るか。せっかくだし」
その唐突な言葉にコンパクトを覗きながらリップを塗り直していたメアはポカン、と呆気に取られて手元が狂いそうになった。
「私社交ダンスなんて踊れないよ?!」
「ノリで脚動かしてれば何とかなる。多分」
どうだ?と差し出された手にメアはおずおずと手を重ねた。そんなクラブハウスじゃあるまいし、という不安とダンテは踊れるのだろうか?という期待がない交ぜになって心臓が忙しく鳴る。
人の囲みを抜けると四角形に空間が空けられていた。ちょうど曲が切り替わるタイミングだったらしく、踊っていた人たちの入れ替わりの波に乗じて空いている位置につく。
手を取られ、ここに添えろと言われるがままダンテの左腕に手を置いた。腰を強く抱き寄せられるとふわりとムスクとバニラの混ざり合ったような甘い香りがダンテの首元から漂ってくる。今日は香水をつけたのかな、と些細な違いにすら胸がざわめいてしまった。
空気に酔っている、とダンテは笑っていたがメアも充分酔っているようだった。
「右足後ろから引いてスタートだ。三拍子のテンポ」
「そんなこと言われましてもその後は?」
「俺の体の動きに集中すればいい」
低く囁いてからにやりと笑った唇がいつもより近い。ハイヒールを履いたせいで普段は二十センチはある身長の差が十センチまで縮まっているのを忘れていた。もっとちゃんと化粧を直しておけばよかったかなと後悔しつつも、ええいままよ、とメアはダンテの楽しげに光るアイスブルーの瞳にじっと意識を溶け込ませる。
音楽が始まった。柔らかなワルツは耳に心地よい。ダンテの目の動きで一歩目を踏み出した。それから二歩目、三歩目と辿っていく。ワルツのステップなんて映画の中でしか見たことがなく記憶は朧げだったが、ダンテのリードには迷いがなくすぐに体を任せられた。腰に回された手の平は温かく、まるでメリーゴーランドに揺られているみたいだ、と体の強張りが解けて行くのを感じた。その気配にダンテが唇の端で笑う。
「踊れただろ?」
「うん」
様々な美しいドレスを着た男女がくるくると優雅に踊る様子は、子どもの頃夢中で覗き込んだカレイドスコープを思い出させた。天井から見下ろしたらきっともっと綺麗なんだろう。
「"酒と女と歌を愛さぬ者は、生涯馬鹿で終わる"」
ダンテがふと呟いた。
「なあに、それ?」
「この曲のアイディアの元になった言葉……だったかな」
小さい頃クラシックに詳しいやつがずっと傍にいてあれこれ教えてくれたんだ、とダンテにしては珍しく昔話を持ち出した。
記憶の内側に潜ってどこか遠い目をしているダンテをメアはじっと見つめる。
「ダンテにとっては大事な人だった?」
「まあ、な。いけ好かない野郎だったけど」
「踊りもその人に?」
「いいや、ワルツは母さんと少し踊っただけだ。俺もガキだったから、こう……足の上に乗っかってステップを踏んだくらいで」
ペンギンのようによちよちと動き回る幼いダンテと、事務所の写真立てでしか知らないお母さんの姿が脳裏に浮かんでメアはつい笑ってしまった。
「いつか誰かと踊るかもしれないでしょ?って母さん笑ってたんだよな」
本当にこんなことになるとは、と苦笑してからダンテは穏やかな表情で目を細める。
「メアと踊れて良かった」
メアは反射的に否定しそうになった言葉をごくりと飲み込んで、ありがとうと蚊の鳴くような声で呟いた。
「もっと自分に自信持てよ。今夜のお前は他の誰よりも綺麗だ」
耳朶を撫でたダンテの吐息と言葉に、お腹の底から頭のてっぺんまで熱が駆け巡った。顔が火照って、恥ずかしさでぎゅっと目蓋を閉ざした瞬間に乱れた左足がダンテの爪先を踏みつけ、体がぐらりとかしぐ。
あっごめ……っ、とよろけた体を太い腕にすくい上げられ、胸を仰け反らせながらメアの視界は広間の天井の絵画をとらえていた。ちょうど曲が止み、さざ波のような拍手が肌を打つ。
腕と腰を引き寄せられ、視線を上げるとダンテの顎の辺りにおでこがぶつかりかけた。
「ごめんね、足踏んじゃった」
「上手いことキマったからいいだろ」
まるで夢を見ていたみたいだ。映画の中に迷い込んでいたような心地から抜け出せず、笑みに吊り上がるダンテの口元をぼんやりと見つめていると、
「そんなに物欲しそうな顔するなよ」
首を傾げて囁いたダンテの吐息が唇を掠めてメアの顔にまた熱が戻ってくる。ムッと眉をしかめて無言のまま胸板をそっと押し返すと、ダンテは白い歯を見せて無邪気に笑った。
彼のペースに振り回されて調子は狂いっぱなしだったが、どうしても悪い気はしなくてそれがまた腹立たしい。
踊り手が入れ替わる波に乗じて人の囲いの中に戻ると、おっ、とダンテが小さく声を上げた。
「やっとアイツも動き出したみたいだな」
見るとカルロがインカムを外し、静かに誰かとバックヤードに消えていくのが見えた。
踊っている間もダンテは監視していたのだろうか、と浮かれていた自分との差にメアは恥ずかしくなってしまった。気を引きしめないと、とドレスの内側のレッグホルスターに仕舞ったブローニング・ハイパワーの存在を今一度意識する。先日迎えたM27は荷物の容量の関係でお留守番になってしまったので今日はハイパワー頼みである。
バックヤードに続くドアを少し離れたところから観察していると何人かの客がぽつりぽつりと吸い込まれていくのが見えた。
「本当に闇オークションを開くつもりなのかな」
「さあな。入ってみないと判らねえ」
オークションへの招待状なんて都合のいいものは貰っていない。あくまでメアたちはベラルディが招いた客であり、独断で動いているカルロの客では無いのだ。
ダンテは隠していた双子の銃の片方、エボニーを腰から引き抜くと、
「脅してでも招待してもらうしかなさそうだ」
やっぱりそうなるよなと察しがついていたメアはダンテの背中側に隠れるように回った。
ドアを通り抜けると厨房へと続くらしき薄暗い廊下が伸びていた。どこかで見たような気がする絵画が何点か壁に飾られ、赤いカーペットが続いている。
最奥は厨房の明かりと賑わいが漏れ聞こえていたが、途中で地下に続くらしき階段が背の高い彫刻の横にひっそりとあるのを見つけた。大理石で作られた女神の像がたおやかに微笑んでいる。この屋敷の作りはどうなってんだ、と不満を漏らしながらダンテは更に明度の落ちた階段を下っていった。メアもそれに続いて真っ直ぐ降りていくと唐突にぽっかり開いたアーチ型の入口が現れる。垂れ落ちた赤い天鵞絨のカーテンからほの暗いオレンジ色の光が差し、その傍らにはカルロの姿があった。
印象に残らない男だ、と思った。髪は暗く、ダークスーツに身を包み中肉中背でどこにでもいそうな平凡な男だった。彼は無表情のままこちらを薄い緑色の瞳でじっと射抜くように見ると、カーテンをそっと持ち上げた。
「貴方がいらっしゃるのを待っておりました」
後ろ手にグリップを握り込んでいたダンテの手の力が緩むのが見えた。
「随分と気前がいいな。入場料は取らないのか?」
「私からの奢り、ですよ」
ようやく表情筋を動かして微かに笑うとカルロはどうぞ、と二人を手招きした。目配せをして行くしかないな、とダンテが先陣を切った。
中は円形の小さな劇場になっていた。中央の一段高くなった舞台を取り囲むように50席ほどの座席がぐるりと並んでいる。造りの雰囲気は高低差のないミニチュアのコロッセオのようだった。着席している観客たちは皆一様に同じ意匠のヴェネチアンマスクを被っており、目元だけを派手やかに隠した面々が靴音を響かせて入って来たダンテたちの方をぞろりと振り向く。その不気味さにメアは音もなく息を飲んだ。
四方に取り付けられていたスピーカーからふいにガリガリとノイズが吐き出された。
「紳士淑女の皆々様、ようこそおいでくださいました」
変声機を通した甲高い子供のような声だ。ダンテとメアは席にはつかず、入口の壁際に立って傍観することにした。
その奇っ怪な司会者の声に導かれていよいよオークションが始まった。中央の舞台は稼動式だったようで更に真ん中の部分が高くせり上がる。
一つ目の商品として晒されたのは檻の中に入った少女だった。華奢な体には余りある鋼鉄の手枷と口枷を嵌められ、虚ろな瞳で天井を見つめている。
世にも珍しい人狼族の少女だ、という紹介に観客たちがざわついた。裏手から現れたアシスタントが檻の中に向かってワイヤー針式のスタンガンを撃つ。その痛みにパニックに陥った少女が咽び泣いた。体が膨れ上がり、口枷を噛み砕く勢いで牙が剥かれ、ガシャンと一際大きく檻が揺れる。少女のくすんだ金髪から尖った耳が突き出すのが見えた。
「こんな惨い事して何になるの……」
メアは見ていられず床の木目を睨みつけた。
壁に寄りかかって腕を組みながら、ダンテもうんざりしたように吐き捨てる。
「金持ちどもの暇つぶしは理解出来そうにない」
見せ物が終わり、アシスタントが撃った麻酔銃によって人狼化しかけた少女が昏倒すると、客席から乾いた拍手が上がった。
程なくして入札が始まる。
「こんな趣味の悪いヤツらと同類に思われるのは癪に障る」
邪魔してくるわ、という声にメアが返事も出来ないうちにダンテは飛び出していた。
高く跳ね、ステージに飛び乗ると少女が繋がれていた鎖を銃で撃ち壊した。檻の鍵も同じく撃ち壊し、ぐったりとした少女を抱きかかえる。その銃声と光景にヒステリーに陥った観客たちが金切り声を上げ始めた。
「おっと、これは思わぬ手違いが発生してしまったようですね。失礼いたしました」
司会者の宥めすかす声を聴きながら、ステージまで走って追いついたメアにダンテが少女を託す。少女の体は痩せ細り、ひどく軽かった。長い髪の毛は血と汗でべたついており、年の頃が幼いにしてもちゃんとした食事を与えられていなかったのかもしれない、とメアは涙を呑み込む。少女の腕に刺さった麻酔針を抜き、痛々しく肌を擦り切れさせている手枷と口枷を観察した。そんなに複雑な構造じゃないな、と髪の毛のセットに使っていたU字型のヘアピンで解錠を試みることにした。簡単な鍵なら何度か開けたことがある、きっと大丈夫、とメアはふっと息を整える。
ステージ上では裏手からぞろぞろと飛び出してきたアシスタントの男たちに溢れていた。メリメリと皮膚や生地の裂ける音が響き、悪魔に姿を変えていく。ダンテは口笛を吹いてラッキー、と笑いながらディナージャケットのボタンを外した。
「これなら手加減しなくて済む」
双子の拳銃が火を吹いた。死神のような悪魔たちがダンテ目掛けて鎌を振るう。それを左のステップで避けてから革靴で蹴り飛ばし、悪魔の頭上に飛び上がると、銃弾の雨を食らわせた。次々と悪魔たちが砕けていくも、砂ではなく赤い泥のような塊になっていく。何を媒介にして現世に現れているのか、パッと見ただけでは見当がつかなかった。
一方の客席はといえば足早に逃げ出すものも居れば、楽しげに鑑賞しているものもおり、どちらかといえば残った客たちの方が多かった。とち狂ってやがんなとダンテは鼻で笑う。流れ弾に当たって死なれても責任を負いきれないぜ、と舌打ちをした矢先に客が上げていた入札用の番号札が弾け飛んだ。
「順番が乱れてしまいましたが、出品番号八番に参りましょう。本日の目玉商品ーー世にも珍しい半人半魔の青年をご紹介いたします」
嬉々とした司会者の声が響いた。
カチリ、と手枷に続いて口枷を順調に解錠し終えたメアがえ?と唖然としてステージを見上げる。ダンテも似たような反応でスピーカーの方を睨んでいた。
「つまんねえジョークは止めといた方が身の為だと思うがな……」
メアは半人半魔、のキーワードが上手く呑み込めずぐったりとした少女を抱いたまま考えあぐねていた。
返り血と泥に塗れたダンテが不機嫌そうに全てのスピーカーを撃ち壊し、低級の悪魔たちを薙ぎ倒していく。
どこに隠れていたのだろう?と驚くほど敵の量だけが多かった。ダンテは歯応えを感じていなさそうだが、加勢した方が良いかもしれない。
メアはうつらうつらとしている少女を部屋の隅、飲み物が用意されているテーブルの下に運んだ。
「外は危ないから、ここに一人で隠れていられる?」
少女はこくりと頷き、メアの手をゆっくりと握ってから離した。
「いい子だね、すぐに戻るから」
テーブルクロスの内側に少女を隠し、柔らかな頬を一度撫でてからメアは踵を返した。
ステージまで走り寄り、ハイパワーでダンテの背中側から迫る敵を撃ち抜き、前蹴りで踏みつける。鋭利なハイヒールに貫かれた仮面が砕け、金切り声を上げながら悪魔は泥になって溶けていった。
いい加減まずいと感じ始めたのか避難を始める客も増えだす。遅せぇよ、と笑いながらダンテはトリガーを引き続けた。今日のダンテも荷物の関係でリベリオンは"自宅待機"だった。本人曰く"呼べば来る"と酒の席の酔っ払いのような事を言っていたが果たしてどこまでが本当なのだろう。が、実際のところまだ剣が必要なほど手応えがある敵は出て来ていないようだった。
悪魔の持っている鎌を奪い上げ、切り伏せながら、メアはキリがないとボヤく。
「なんでこんなに湧いてくるの?」
お互い背中合わせで戦いながら、メアはドレスの裾を絡げて蹴りを放ち、ダンテは悪魔の頭を掴んで地面に叩きつける。
「……溜め込んでたか、もしくは呼び寄せてるやつがいるのかもな」
その時、悪魔の群れを掻き分けて人影が現れた。彼は血の色をしたタキシードを纏っており、
「スピーカーを壊されてしまったので直接来る羽目になってしまいましたよ」
その声の方向に二人同時に銃口を向けた。
マルクス・ベラルディがチェシャ猫のような笑みを浮かべて立っていた。
「やっぱりアンタの仕業だったのか。怪しすぎんだよ。大根役者め」
「これは失敬。適度に餌をチラつかせた方が貴方のような人の場合釣れ易いかと思いまして」
「……さっきのナメた発言はどういうつもりだ」
悪魔の残骸である赤黒い泥の海を渡りながら、ベラルディは笑う。
「ダンテさん、私はね、悪魔が大好きなんですよ。愛している、と言うべきか」
こいつ狂ってはいるがただの人間のようだな、とダンテは舌打ちをする。逆に手が出せないのが厄介だった。悪魔なら躊躇わずに殺せるのに。
ベラルディはダンテとの距離を詰めながら値踏みするように目を眇めた。
「取り分け貴方は美しいうえに珍しい。あの"伝説のスパーダ"のご子息なんでしょう?」
「さあな、ガセネタだと思うが?生憎あんたのご期待には応えられそうにもない」
「そうご謙遜なさらず。せっかく貴方だけは私が落札しようと思っていたのに」
心底残念そうに眉根を寄せたベラルディから目を逸らしてダンテが忌々しげに顔を歪めた。
その時、黒い影が静かに飛び出して来たのをメアは視界の端に見た。部下のカルロだ。その腕には人狼の少女に使われたのと同じ麻酔銃が抱えられている。
反射的に射線上に飛び出していた。ダンテの背中を庇うように腕を広げながら、メアは狙いを定めてカルロの右肩を撃った。ぐあっ、と呻き声を上げながら彼は倒れ伏して銃を取り落とした。
それと同時に体から力が抜け、メアはがくんと膝をつく。右の肺の辺りに麻酔針が刺さっていた。早くも痺れ始めた手で針を抜き捨てる。
息が上手く出来ない。こんなに苦しいものをあの子は打たれたのか、とメアは少女が隠れているテーブルの方をちらりと見た。
「おい、メア、」
異変に気がついたダンテに肩を揺さぶられてメアは問題ない、と仕草で伝えた。
悪びれもせずにベラルディがああ、と残念そうな声をあげる。
「とんだ女狐の邪魔が入りましたね」
痛めた肩を庇いながら何とか立ち上がったカルロに気が付き、ダンテは彼が拾い上げようとした麻酔銃を撃ち抜いて粉砕した。
「殺したかねえから大人しくしててくれよ」
ダンテはホルスターに銃をし舞い込むと、ベラルディに歩み寄りそのニヤけた顔面を右の拳で殴り倒した。短く呼気を漏らしたベラルディの口から折れた歯が飛んでいき、彼は痛みに顔をくしゃりと歪めた。
「殴らないとは一言も言ってないからな?」
襟首を掴まれ、殺気に近い光を漲らせたダンテの眼光に、ベラルディは口角泡を飛ばしながら待ってくれ、と喉をひっくり返す。
「私に何かあれば"ヤツ"らが動き出すぞ」
「知ったこっちゃねえな。つべこべ言わずに豚箱で大人しく寝てろよ。悪魔へのお熱も冷めるだろ」
「貴方は"レッド・ラム"を知らないのか!」
メアの肩がピクリと震えた。"レッド・ラム"、まさかその単語をこんな所で聞く事になるとは思わなかった。忌々しい記憶が入った箱が開きかけたのを意識の隅で捩じ伏せる。
メアは上半身に力が入らなくなり床にぐしゃりと突っ伏した。赤黒い汚泥が肌とドレスを汚していく。せっかくダンテが褒めてくれたのにな、と後悔が過ぎった。
掴んでいたベラルディの襟首を放すと、ダンテは彼の足首を掴んで荒々しく手繰り寄せた。
「警察が来るまで大人しく我慢な」
足で膝を抑え込み逆に捻り返し、片足の関節を鈍い音を立てて外すとベラルディが情けない悲鳴を上げる。
その声を銃声でかき消すように残った悪魔を瞬時に一掃してから、ダンテはメアの元に戻ってきた。
「歩けるか?」
何とか体を起こそうと腕で半身を持ち上げようとしたが、四肢にほとんど力が入らなかった。無理しなくていい、と泥の中からすくい上げられて横抱きにされる。
そのまま足早に出口に向かおうとしたダンテのネクタイを掴んで、メアはテーブルの方を示した。
「さっきの、女の子が……」
声を絞り出すのも一苦労で、これをダンテが打たれていたらどうなっていたんだろう?と想像せずにはいられなかった。メアほどの強い効き目は見せないだろうが、厄介なことにはなっていただろう。
「隠れてるのか?」
「そう」
ダンテが勢いよくクロスをめくった時だった。中から四つ足の獣が飛び出してくると、ぐるぐると喉を鳴らした。足首の擦り切れた跡から人狼に姿を変えた少女だと分かって、メアはダンテに床に下ろすよう頼んだ。
「もう大丈夫だよ」
腕を伸ばすと狼はしばらく威嚇の姿勢を解かなかったが、メアが手の甲を鼻先に伸ばすとすうっと静かになった。カチカチと伸びた爪の音を立て尾を振りながら腕の中に歩み寄って来た狼を何とか持ち上げた腕でゆっくりと撫でて、メアは大きな頭蓋に頬を寄せた。
「一人で逃げられる?」
狼になっても艶の失われた毛並みと肋骨の浮いた痩せた体に涙が込み上げたが、彼女をどうしてあげたらいいのか今すぐには思い浮かばなかった。
狼は別れを告げるようにメアの頬を一度ペロリと舐めると、先に出口へと向かってよたよたと走っていった。
「もう捕まらないといいけど」
ダンテに再び抱き上げられながらメアはポツリと呟いた。そうだな、と返しながらダンテも階段を登って行く。幼い少女だから一人きりで逃げ切るのは難しいかもしれない、と思ったが口にはしなかった。
「めんどくせえけど通報しとくか」
屋敷の出口に向かいかけたが厨房に踵を返した。
突然入ってきた血まみれの男女二人にコックとウェイターたちは揃って声も上げずに怯えた顔をしている。
「外線の掛けられる電話、借りてもいいか?」
話しかけられたウェイターはぶんぶんと空を切る音を立てて首肯しながら厨房奥の事務室を示した。
「あと車を一台借りたい。明日には返すからさ。鍵も事務室か?」
それにも同じく首肯で返してきたウェイターにサンキュ、とウインクをして礼を言いながらダンテは事務室に向かった。
請求書類に溢れた手狭な部屋にあった黒電話で911にかけると、ダンテはざっくりと事のあらましを伝え、早く人を寄越せと乱暴に通話を切った。
「巻き込まれる前にトンズラしよう」
ダンテは壁にかかっていた配達用らしき車の鍵を拝借した。そのまま裏口を出て鍵の番号と照らし合わせながら車両を探す。
見つけたのはレトロなクリーム色のシトロエンバスだった。移動販売車としてもよく使われる型なのでダンテが思わず吹き出しながら、
「クレープ屋みてえだな」
助手席にぐったりとしたメアを乗せてシートベルトを締めてから、ダンテは大丈夫か?と汗に濡れた額を撫でた。
「……うん、かえろ?」
「そうだな」
ダンテの運転でシトロエンバスは静かに屋敷の敷地を抜け出した。
行きのリムジンよりも飛ばしたので一時間も掛からないうちに事務所に着いた。
片腕でメアの体を抱きながらダンテはエンツォに電話をかける。もう日付も変わる頃合だったが寝ぼけた声でエンツォが電話口に出た。
「悪いんだが明日の朝、事務所の前に停まってる車をこれから言う場所に届けて欲しいんだ」
『んだよまた雑用かァ?手間賃は出るんだろうな?』
「お前が寝過ごさなければな?」
屋敷の住所を伝えて頼んだぞと電話を切ると、腕の中でますます発熱し始めたメアの体にダンテは苦々しい表情で唇を噛む。
「なぁ、本当に医者に診てもらわなくて平気なのか」
「寝て、れば治るよ……っ」
へらっと力の入らない笑みを浮かべるメアの背中を一度撫でて、ダンテは階段を上がった。一瞬悩んでから自分の部屋に入ってメアの靴を脱がし、クイーンサイズの広いベッドに横たえる。
お互いに悪魔の返り血にまみれていたので散々な有様だったが、こんな状態のメアが一人で風呂に入れる訳もない。
セットしていた髪を崩しながらベッドの縁に腰掛けて、どうすっかなとダンテがふうと溜め息を吐くと、くいっと袖を引っ張られた。
発熱は恐らく麻酔薬、極端に強い筋弛緩剤による免疫反応だろう。メアの手はやはり熱かった。
「ドレス、がね……苦しい、の」
「脱がせってか……」
別に童貞でもなければ戯れに娼館の女を抱いたことも一度や二度ではなく、服くらい何度も脱がせたことはあるが、メアをその辺の女たちと比べるのは果てしなくお門違いだと思った。
「後であーだこーだ言うなよ?」
「ダンテなら、いいよ」
それはどういう意味だ?と尋ねたい衝動を噛み殺した。
可愛いこと言ってくれるね、と笑って流しながら糸の切れたマリオネットのような腕を手繰り寄せて背中のホックを外す。抵抗感のある華奢なファスナーに苦戦しながら腰まで下ろして、オリエンタルブルーのドレスの肩を払い落とした。ストラップレスのワインレッドの下着の中で柔らかな谷間がふるりと揺れる。そのまま腰を抱き寄せてスカートの部分を爪先まで引き抜いた。床に放り投げると血を吸った生地がどさり、と重たい音をあげる。
ストッキングとガンホルスターもいらないよな、と太ももに手をかけると白い肌がじっとりと汗ばんでいた。雑念が過ぎりかけたのを奥歯を噛み締めてやり過ごし、ガーターベルトの留め具を外す。ストッキングを破かないように指を沿わせると指の腹に当たるメアの肌の滑らかさと柔らかさで思考が一杯になった。
ガキじゃあるまいし落ち着けよ、とダンテは自我に話しかけながらストッキングを脱がし終え、ブラジャーと揃いのレース素材のショーツの上に巻かれていたホルスターのベルトを取り払った。まるで爆弾解除をしているような気持ちだ。
ふうっ、と息を吐いてメアがありがとうと笑う。
「いや、お前が庇ってくれなかったら動けなくなってたのは俺かもしれないし……ありがとな」
麻酔針が刺さった右胸には青紫色の痣が浮いていた。窓から差し込んでくる月の薄明かりの下にいると、メアの白い肌が一際透き通ってまるでガラス細工のようだ。それでも痛々しく浮き彫りになるのは両腕や両脚に残った切り傷の痕、それから一番目立つのはうっすらと割れた腹筋の横、右脇腹の引き吊れたような古い火傷の痕だった。思わず指を這わせるとメアがくすぐったそうに笑う。
「これも親父さんにつけられたのか」
「ううん……しごとを、手伝ってた時に……私が失敗しちゃって……」
思い出したくない記憶だったのかメアがそっと目蓋を閉じたので、余計なことを聞いたなとダンテは眉を潜めた。
「髪も解くか?」
「おねがいします」
セットしていた髪からピンやヘアゴムを取り外していくと、はらりとアッシュブルネットの髪が肩に落ち、ほとんどいつもの彼女に戻った。まるで魔法が解けたようでもあり、より一層生々しい空気が漂う。
ダンテはひどい目眩に襲われて目頭を手で押さえながら、リクエストを尋ねた。
「他にしたいことは?」
「のど、かわいた……」
水持ってくる、とキッチンに向かいながら窮屈だと思っていた事すら忘れかけていたシャツのボタンを寛げてネクタイを抜き取り、ジャケットとベストをソファの上に投げ捨てる。
ガラスのコップとミネラルウォーターのボトルを持って部屋に戻るとどうにか自力で体を起こしたらしいメアがヘッドボードに寄りかかりながら窓の外を見上げていた。
「ダンテはいつも、この月をみながら寝てるんだねぇ」
そういえばメアの部屋には窓がなかったな、と思い出しながらダンテはグラスに水を注いだ。
あんなに慌ただしい夜だったくせに月だけはいつも通りただただ静かだ。
「飲めるか?」
気だるそうなメアの口元にグラスを添えるとカチリと歯のエナメル質がガラスを食む音が響いた。口に含むまでは出来たのだが嚥下する量の調節と喉の動きが上手くいかないらしく、メアはげほりと咳き込んでしまう。
「んわっ、」
飲み込めなかった水が顎を伝い胸元を濡らした。あー、と息を漏らしながら枕元に放ってあったバスタオルで拭いてやるとメアはごめん、と笑う。
「うまく飲めないから、いいや」
そこからの意識は我ながら霞みがかっていた。都合が良いもんだ、と嘲笑われても仕方ないと思う。
「……少しずつなら飲めるだろ」
と、ダンテはグラスの水を口に含むとメアの汗ばんだ首筋を手繰り寄せた。唇を重ね合わせて、ルージュの引かれた唇を割り開き舌で水を送り込む。一瞬見開かれたメアの瞳が猫のように細まった。ごくりと喉が鳴り、水を飲み込んだのを確認してからダンテはしまった、と我に返る。
たじろいで一歩後ろに引こうとした足が、止まる。メアに掴まれた袖を振り払うことが出来なかった。
「おいしい……もっかい……」
ぼんやりとした熱っぽい目で見上げられて、ダンテは静かにもう一度グラスを傾けた。
メアの咥内はひどく熱かった。冷たい水が一瞬で温くなる。それで余計に喉が渇くらしく、なんども濡れた唇が水をねだる。口移しを終えた舌にメアの小さな甘い舌が絡んできて、油断しているとあっという間に理性が焼き切れてしまいそうだった。
すっかり乱れたルージュを親指で拭ってやってから、もういいだろ、とダンテは眉間に皺を寄せた。
「しんどくなってきた……」
色々な意味で、とため息をついたダンテにメアはごめんなさい、と眠たげに目を伏せた。
きっと寝て覚めたら全部忘れているんだろうな、と何となく思った。結局は薬で朦朧としているようなものなのだ。そんな状態の彼女に手を出した自分も自分だが、と自己嫌悪に陥りそうになるのを堪えてダンテはメアの額を撫でて寝かしつけた。
「もう寝ろ。今日はここで寝ていいから」
俺は下のソファにいる、と踵を返そうとすると人差し指を弱い力でぎゅっと握られた。指一本なんて簡単に無視出来るのに、と思いながらやはりダンテは振り返ってしまう。
「さみしい」
メアの素直な呟きにあーもー、と前髪を掻きむしって、ダンテはシャツのボタンを外した。黒のワイシャツを脱ぎ捨て裸足になるとメアの隣に潜り込む。
「ここで寝るからな?」
朝起きて蹴り飛ばしたりしないでくれよ、と呟くとメアが眠たげに微笑みながら、汗ばんだ熱い体を寄せてきた。その頭を腕に抱きながらダンテは胸の真ん中にじんわりと苦い痛みが走るのを感じていた。
ただの依頼人だと思っていたし、最初は正直鬱陶しかった。それなのにからかっていたはずの自分の方がすっかり引き摺り回されて、翻弄されている。彼女の方が悪魔よりもよっぽどタチが悪い気さえしてきた。
……瞳の色に惑わされているだけだ、とばかり思っていたのに。
まあいいか、と呟いてダンテは考えることを止め、腕の中のメアの寝息を聞きながら目蓋を下ろした。
今夜は久しぶりによく眠れそうだ。