考え事をしながらいつのまにか寝入ってしまったようで、私がホープからの電話で飛び起きた
「はい…」
『ライトさん…またかけちゃいました。』
心が満たされるような優しい声が端末から聞こえ自然と頬がゆるむ
『今何をしていましたか?』
「え…ああ、寝ていた」
私がそう言うとホープは慌てたようにすいません、起してしまいましたか?
と誤ってくるあたり心使いが優しいと思う
『ライトさん…あなたが出て行ってから3日しか経ってませんが…あなたの顔が見たくて仕方がないんですけど…』
「…丁度いいな。私は今はまだ暇だからお前の都合がつき次第会えると思うぞ。それに…」
直接会って話したい話があるんだ とは言えずに口ごもるが ホープの反応に私は安堵した
「本当ですか?やった!僕も予定は特に無いですし、明日でも明後日でもそれ以降でも大丈夫です」
私は立ち上がりリグディからもらっていた予定表を摘み上げた
「私の方は、明日は午前のみ、だな。明後日は…」
予定を読み上げて都合のいい日をあわせる
「あの…すぐにでも会いたいので、どちらも予定の無い明日の午後はどうでしょうか?急で申し訳ないんですが…」
「いいぞ。場所は…」
「僕が行きますよ。」
ホープとの電話を切ればまたも私は温かい気持ちに包まれていた
明日か…明日ホープに会える…
もうこの胸の高鳴りを否定することなど出来なかった
次の日、任務の変わりに軽い病院での検査があった。人間ドックのような物だ。
それを適当に済ませてすぐ家に戻って私服に着替える。
ミニスカートにⅤ字ネックのシャツというラフな格好だ。
昼食を済ませつつ時計に目をやる。
午後に来るとは言っていたが今日は平日だからホープの通う学校でも普通に授業があるだろう。
その後という事は早くて5時か6時位。
ホープが来たらちゃんと話をしよう。このまま引きずるのは
私はそれまで仕事の書類にでも目を通そうとリビングのソファに腰掛ける。
それからどのくらい経っただろう、昼下がりの温かい陽気に照らされて睡魔に襲われた
Hope:side
今日は授業は午前だけだったので飛んで家に帰った。
自分が持っている服の中で一番大人っぽいコーディネートをして鏡の前に立つ
―ライトさんの隣に並んでも不自然ではないだろうか?
常にライトさんは凛としていて僕が隣で歩けば弟に思われる事が多かった。
今でこそ身長は追い越したが雰囲気というものが違うのだと思う。
ライトさんの弟に思われるのは結構傷つく。
昼食もそこそこに僕はエデン行きの電車に乗り込んだ。
もうすぐでライトさんに会える。
今まで4年もよく耐えたと自分で自分に感心だ。
今では数日会えなかっただけでこんなに思いが膨らむのに。
流れる景色はだんだんと首都エデンのものに変わる
パルムポルムとは比べ物にならないような高い建物が所狭しとひしめき合っていていかにも都会を思わせる。
あとすこし…
電車を降りて駅を出る。
足取りは以上に軽くて例えるならばルンルン。だ。
ライトニングが住むマンションが見えた時にはすごく嬉しくて気を抜けば走り出しそうだった。
急ぎ足でエレベーターに乗って家のドアの前までくる。
ライトさんに会えると思うと嬉しくって仕方が無い。
僕はライトニングの完璧なる依存症だ。
家のインターホンを鳴らせば家の中で音がするもライトニングが出てくる気配は無い。
「いないのかな…」
そういえばこの前来たときにドアロック機能に何かあったらと僕のデーターを入れておいたんだった。
僕はロック解除認識気に手を当てる。
案の定カチャっと扉は開かれた。
「ライトさん…?」
少し扉を開いてみればライトニングがいつも履いている靴があった。
おそらく家の中にいるはずだ
「入りますよ?」
断ってから中に入るとすぐにリビングのソファで寝息を立てているライトニングを見つけた。寝てる…?
パルスにいた頃は警戒心がかなり強く少しの風程度でも目を覚ましていた彼女がすやすやと眠っているのを見て僕は一人笑う。
ライトさんもこんな顔するんだ。
あまりにも無包囲な寝顔をさらけ出しているようで僕は衝動に駆られふらふらとライトニングの近くに寄る
ただそれだけで彼女は勢い良く飛び起きた。
警戒心は薄れてないんだ…と僕は苦笑する
「あ…すいません…起すつもりじゃなかったんですけど…」
「いや…私も寝るつもりじゃなかったんだ」
ライトさんは寝てても起きてても変わらず美しい。
ライトニングがちょっと待っていろとソファーから降りてキッチンに向かう。
戻ってきた彼女が持っていた物を見て僕は頬が緩むのを感じた
「ライトさんって甘いもの好きなんですか?」
コトリとテーブルの上に置かれた2つのショートケーキと紅茶を見てたずねる。
2つという事は僕の為にわざわざ用意してくれたのだったら尚嬉しい
「好きじゃ悪いか?」
ケーキを頬張りながらそう言うライトニングがなんと言うか、可愛くて僕はまた笑みをこぼす。
ライトニングいわく甘いものは大好物とまでは行かないがどちらかといえば好きらしい。
一方紅茶は微糖のストレートというところが彼女らしいと思う。
和やかな雰囲気に僕は気になっていたことを尋ねた
「昨日電話したときにライトさん それに…って言いかけてましたよね?あれ、何だったんですか?」
深い意味も無いだろうと思っていたがライトニングを取り巻くオーラが豹変し、持っていたティーカップを置いて視線が僕に向けられた
「…話がある。と言おうとした」
あまりにも冷静な声で言う彼女からは先ほどと打って変わって和やかという表情は感じられない。
どちらかといえば緊張さえも伺えるほどだ。
あまり表情は変わっていないとしてもなんとなく感じ取れるのだ
ソファーに座りなおし僕は直球にたずねた
「話、とは…?」
何か良くないことを言われそうな雰囲気で静まり返った部屋にライトニングの反応をうかがう
「この前お前は私の事を好いているといっただろう?その時に私は考えさせてくれ、と言った」
「はい…」
唐突な話に僕の心臓が飛び上がる
「もっとお前にふさわしいと思う女が他に現れると思うんだ。
その人と幸せになった方がお前のためでもある。
それなのに私がお前の近くにいればその人との関係に支障が出るだろう?
お世辞にも可愛いとはいえない軍人の私なんかを相手にしていてもお前の為にならないと思うんだ」
並べられた言葉に僕は必死に悲しみを隠しつつ言葉を探す
「僕にはあなた以外見えないと言いましたよね?もし僕に相応しい人がいたとしても僕はその人を好きにはなりませんし、幸せにもなれません。
眠っていた間の事だから信じてもらえないかも知れないけど、僕はあなただけなんです。
相応しいとか僕の為にならないとか僕の為を思って言ってくれているのかも知れないけど、そんなの嬉しくないです!」
悲しみから自分ではどうする事もできないくらいに言葉が出てきてしまう。
「僕の為にと言ってそうなってしまうのは嫌なんです。
あなたが僕の事を拒否されるのならはっきりとそう言ってくれた方が気が楽です!」
僕の心は張り裂けそうでライトニングを見ることすら出来なかった
「ホープ…」
「変な期待させないでくださいよ…優しすぎますよ…」
もう全て言い切ってしまった僕は子供のように力なく首を落とした
何て僕はバカなんだろう。ライトさんがらみだとすぐこれだ。
歯止めが効かなくって自爆してしまう。
「拒否などする訳ないだろう。自分の気持ちに…素直になるとしたら…」
ライトニングが明らかに口ごもる。やはり言いにくい事なのだ
「私はお前の気持ちに応えたい」
ライトニングの言葉に僕は顔を上げた
「え・・・?」
良い意味で予想を裏切られて僕はあっけにとられる
「じゃあ…」
「…私なりに努力する」
「…………」
「ホープ…?」
もう嬉しすぎて言葉が出なくて僕はまたライトニングの華奢な体を抱きしめた。
「嬉しいです。すごく…」
以前みたいに遠まわしに拒否されないのを良いことに僕はずっと彼女を抱きしめていた。
手に入れた光を失わないように。
真紅の薔薇を枯らしてしまわないように。
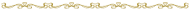
←戻る
1/3