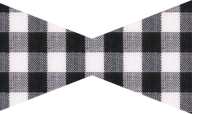
──とある昼下がり、探偵社の建物の一階にある喫茶処「うずまき」にて。
「あら、なまえちゃんいらっしゃい。今日もいつもの紅茶?」
「ありがとうございます。それでお願いします」
「はいよ〜」
昼休み位ゆっくりしていきなさいね〜、と陽気な声で言葉を掛けてくれる店主のおばちゃんに一礼し、いつものカウンターの一席に腰を掛ける。
そこで私は鞄をごそごそと探り、今日一人でこの喫茶処に来た理由であるものを探り当て微かに目を輝かせた。すぐにそれを取り出して手に取り、静かに心を踊らせる。
そう、私が探していたのはお気に入りの本のシリーズの、つい最近出た新刊の小説だ。元々本を読むのが趣味の私だが、矢張り仕事が忙しいと中々読む時間がなくなるのは必然なのである。
今までは、深夜残業をしながら涙を飲む日々を続けていたがそれももう終わりだ。最近の仕事の大きな山場は越えたし、今だって探偵社はこんなに平和だ。今日のこの時位は読んでも罪はないだろう。
そして私は胸を高鳴らせ、一旦運ばれてきた紅茶を一口啜ってからその本の表紙をゆっくりと捲った。そして文字を目に映そうと、その頁の方に視線を落とした、その時。
「やあ、奇遇だねえなまえちゃん、こんな所で会うなんて」
私は少し離れた所から聞こえた声に、急速に嫌な予感を募らせた。もしや、この声は。真逆また……あの人が。
「昨日も帰り道に会ったよね!いやあ、この仕事が忙しい時に、事務員のなまえちゃんとこんなに会えるなんてもしかして運命とかいうやつでは…」
「……あんたが仕事をさぼっていつもオフィスに居るからこうなるんじゃないの」
私は、いつも通り恥ずかしげもなく臭い台詞を言ってくるこの軟派野郎──太宰治の言葉を遮り冷たく言い放った。勿論本から目は離さない。
しかし彼は特に気にする様子も無く、許してもいないのに隣に座って上機嫌に鼻歌を歌い始めた。
……しかも、選曲はいつもの物騒な心中ソングである。
私は暫くは黙って本の文字を目で追うことに集中しようとしたが、数分すると我慢ならなくなり再び太宰治をじろりと睨んで言った。
「……一寸、本を読むのに集中できないんだけど」
「ええー?私が鼻歌を歌っていようがいまいが、なまえちゃんには関係ないことじゃないか。あ、それとも……」
もしかして、私のこと意識しちゃってる?と、にやにやと意地の悪い笑顔を浮かべながら言う太宰に、私は思わずかーっと顔が熱くなっていってしまうのを慌てて振り払った。冷静になれ、冷静になれ、自分。とひたすら言い聞かせ、あくまで淡々と太宰に対して言葉を連ねた。
「……そんなことあるわけないでしょ。大体、何で心中のことばっかり考えてるような変人を私が意識しなくちゃいけないのよ?有り得ないわ、こんな自殺嗜癖」
「まあいいよ、別にそれでも。私は勝手に鼻歌を歌って、本を読んでる美しいなまえちゃんの姿をひたすら拝むだけだからね」
「……一回死んでくれない?」
「なまえちゃんが一緒に心中してくれるなら喜んでそうするのだけど……あ、なまえちゃんが頸を締めて殺してくれるならそれでも全然構わないよ!」
「…………」
これ以上何を言っても無駄だということを悟った私は、仕方ないと大きく溜め息を吐いた。
本当に、この男、太宰治は苦手だ。何故私にここまでしぶとく、何度断られても懲りずに心中の申し込みをするのだろう。
まあ確かに、太宰が女性に心中の申し込みをして断られるというのは探偵社でも見慣れた光景だ。
しかし、大抵は一度断られるとぶつぶつ言いながらも諦めるのがいつものことなのに、何故か私に対してはこうもしつこい。
ちらり、と何の気もなしに横の方に視線を向けてみる。視界に入るのは上機嫌な太宰の横顔。矢張り、顔だけだとあれだけ女性にモテるのにも頷ける位整っている。しかし、何故そんなやつがそんなに美人でもない私なんかに、告白まがいの言葉を繰り返してくるのだろうか。
「あれあれ〜、どうしたの?なまえちゃん。私の顔に何かついてる?」
すると、太宰が再び意地の悪い笑顔を浮かべて顔を急に近づけてきた。私はそれで初めて、今まで自分が太宰のことをずっと見つめていたことに気づき、途端に羞恥が込み上げてくる。
どんどん熱の集まっていく顔を隠そうと、慌てて顔を遠ざけようとしたが、その拍子にカウンターの椅子から落ちそうになって小さく悲鳴を上げた。
やばい、倒れる──そう考えて背中の痛みを想像したその時。腰の辺りを支えられる感覚がして急に動きが止まった。見上げる先には、太宰の整った顔立ち。
「………っ、……」
「危ない危ない……大丈夫?なまえちゃん」
私はその言葉で我に帰り、腰に回っているのが太宰の腕だと気がついて心臓が止まりそうになるかと思った。
慌てて太宰の腕から離れようとしたが、その前に太宰の腕が私の体を引き寄せて身動きがとれなくなる。
「ちょっ、太宰、何してんのよ、あんた……………!」
「だって、なまえちゃんが顔赤くしてるのがあんまり可愛いから」
「は!?な、何言って……!」
すると、私が言い終わる前に太宰の腕が頬に伸びてきて、思わずびくりと体が震えた。
そんな私に太宰はくすりと笑い声を漏らし、本当に愛おしそうな手つきで私の頬を撫で始める。私はそれを振り払おうと必死に努力したが、大人の男の力に私が敵う訳もなく、ふいと顔を背けるだけしかできない。
「あんたね………こういうことは、その、恋人とか、そういう関係の人にしてあげるべきでしょ!?何で私がこんな………」
「そう言われても、私今恋人居ないからなあ」
「だとしても!何で私にこんなことするのよ!!」
「え?そんなの、なまえちゃんを愛しているからに決まってるじゃない」
「……………………………は?」
私は、まるで今日の天気は晴れですよーとでも言うようにぽろっと出てきた太宰の言葉に、思わずぽかんと口を開けて固まってしまった。
「…………は?だ、太宰が、私を?ちょ、一寸何その冗談、笑えないんだけど……?」
「何、冗談じゃないさ、私は、なまえちゃんのことが好きだ、一人の女性として。もし、なまえちゃんがそれに応えてくれるなら、一生幸せにするつもりだよ?」
何回も言ったと思うのだけどねえ、と、こっ恥ずかしいことをあっさりと言ってのけた太宰はそう言って唇を尖らせる。それに対し私は頭がついていけず、呆然と固まった。
え?本気で此奴、私のことを、好きって?まあ確かに、よくよく考えてみたら好きだとか愛してるだとか言ってたような気もしなくもないけど……でも、こいつのことだからてっきり悪冗談だと思って無視していたのに。
「本当、なまえちゃんって鈍感。まあそういうところも好きだけどね。ほら、早く素直になりなよ」
「う、五月蝿いわね!素直になるとか………!私は…………」
私はそこまで言いかけて、言葉を詰まらせた。私は、どうなのだろうか。今まで、太宰は私のことをただのからかいがいのある相手だとしか考えていないのかと思っていた。
今まで見た、太宰の色々な顔が次々に蘇ってくる。思い出す度に湧き上がってくる、様々な感情。
ああ、そうか。私はとっくに──この感情の正体に気づいていたのかもしれない。ただ、それが叶わないのが怖くて、目を背けていただけだ。
私は背けていた顔を意を決して太宰の方に向ける。そして、すぐ近くにいる太宰に向かってこう言い放った。
「太宰!あんたは、自殺嗜癖だし変人だし迷惑噴霧器だし……もう本っ当にどうしようもない奴だけど………でも、そ、その、」
最初はちゃんと言葉にできていたものの、だんだんと頭が真っ白になってきて、どんどん声が小さくなって言葉が不明瞭になっていく。
「あんたのこときらいじゃ、ないから、だから、その……あんたが言うなら、付き合ってあげても…………」
最後の方は恐らく言葉になっていなかったが、でも私にとってはそれだけ言うだけで精一杯だった。太宰は目を丸くして、私の方を黙って見ている。暫しの間、沈黙が二人を包んだ。
「………ああもう!!太宰!!何か言いなさいよ!!!だいたいいつもあんたは……」
沈黙に耐えきれなくなった私が、やっと叫んだ言葉を言い切ることは叶わなかった。
唇には、温かくて柔らかい感触。目の前一杯に広がるのは、太宰の顔。
それは暫くしてちゅ、と微かな水音を立てて離れる。
放心状態で固まる私に、太宰は「あ、ごめん……あんまり可愛かったから、つい」と声を漏らした。
その後のことはもうよく覚えていない。とりあえず私は太宰に一発蹴りを入れてから逃げ去り、慌てて自分のデスクに戻って羞恥に悶えながらも仕事に没頭する他なかった。
しかし、ナオミちゃん辺りが噂を聞きつけて、私逹を質問攻めにするのはきっと時間の問題であろう。
もう全部全部、君の所為だ
しなもん。様リク
リクエストありがとうございます!遅くなって本当に申し訳ないです……それに太宰さんの口調が迷子ですね。そして長い。でもツンデレ夢主を書くうえでの勉強になった気がします。綾辻さんの小説の感想も送って下さり、本当にありがとうございました!
これからもどうかこのサイトをよろしくお願い致します。
prev | next
back