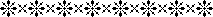 今日は休日だ。 まあ盗賊に休日なんで言い方おかしいんだけど次の仕事の情報がまとまるまで各自待機だ。 そんなわけで僕は部屋で読書をしている。 もちろん団長の部屋だ。 最初こそ嫌々だった住めば都、本もたくさんあるし悪くない。 「ここで終わりだなんてズルいよね」 読み終わった本を置いて溜息を吐いた。 続きが気になるじゃないか。 でもまあ暇つぶしにはなったかな。 ちらりとソファを見ればまだ団長は本にかじりついている。 本の虫だ。 僕も人のことは言えないけど。 「ねぇ団長、お腹すいたんだけど」 「…広間にパクがいる」 それだけ言うと団長はまた本の世界へと没頭。 やれやれ。 まぁいいや、パクにご飯を作ってもらおう。 パンの上に目玉焼きが乗ったやつがいいな。 チーズとベーコンも。 「パク〜、って…あり?」 広場に足を踏み入れるとそこにはフィンクスとシャルとマチ。 なんでこの三人はいつもいるんだろうねぇ。 「パクならいないよ」 「いつ戻ってくるの?」 「さぁ、俺達はお互い干渉しないからね」 シャルはにっこり微笑むけど僕のお腹は空腹を訴えている。 困ったなぁ、いつもパクに作ってもらってたし… 「どうしたんだい?」 「マチ」 「腹空かせてんの?」 「うん、そうなんだ。でもパクがいないし」 「なんか作ってやろうか?」 「え?マチ料理できるの?」 「なっ!当たり前だろ、そこ座ってな。ちょうど昼時だ。作ってやるよ」 なんだ、前にシャルが料理はパクしかできないって言ってたからマチはできないんだと思ってよ。 「待てよマチ」 「なんだいフィンクス」 「あ、ほら。冷蔵庫の中はパクが管理してるだろ、なぁシャル?」 「そうだよ、それに俺まだお腹すいてないし」 二人は引きつったような笑みを浮かべて互いに肘でつつきあっている。 なんだかマチを説得しているように見えるんだけど 「なに、アタシの料理が食べれないっていうのかい?」 「いや、そんなわけじゃないよ!ただ本当に空いてないんだ!フィンクスは減ってるって!」 「な!てめ!いやシャルこそ減ってるぜ!朝からコーヒーしか飲んでねぇんだろ?」 「俺は体動かしてないから糖分で栄養とれてるの!」 「いいから座ってな!三人分アタシが作ってやる」 マチはギロリと睨みを聞かせるとキッチンのほうへ消えていった。 「カグヤ!お前マチに料理させるなんてなんてこと!」 「え?何か不味いのかな?」 「前にマチが作った料理を食べて蜘蛛は全員寝込んだんだよ」 え? 寝込んだ? この頑丈が取り柄みたいなフィンクスも? 「それってただ食材が腐ってたとかじゃないの」 「いやそんなはずねぇ、あの日の食材は俺が盗んできたんだ!」 ふーん でもまぁ、作ってくれるならそれは嬉しいんじゃないかな。 昔一度だけ団長が作ってくれた料理を思い出した。 その日は阿伏兎さんがいなくて、僕と団長二人で。 お互いお腹を空かせて見兼ねた団長が作ってくれた。 キッチンは見事に壊れて部屋も半壊したけど、誰かが僕のために料理を作ってくれたことが嬉しかった。 真っ黒で、硬くて、苦かったけど、涙がでるぐらい美味しかった。 「できたよ、座りな」 そんな昔話しを思い出していたらマチが皿を持って居間に現れた。 逃げ出そうとしているフィンクスとシャルの襟首を捕まえて僕は椅子に座った。 二人は覚悟を決めたのかゴクリとテーブルに並べられる皿を凝視している。 うん、なんだ。 美味しそうじゃないか。 赤、白、黒、緑、紫とカラフルな…炒飯? 「えっと、マチ…これって」 「美味しそうな炒飯だネ」 「だろ?隠し味を使ったとっておきの炒飯だ、さぁ食べな」 「いただきます!」 パクリと口に運ぶとピリッと辛味が僕の口に広がった。 なんだ、美味しいじゃないか。 横を見るとスプーンを咥えたまま白目になるフィンクスと冷や汗をかいてるシャルがいた。 どうしたんだろう。 こんなに美味しいのにネ。 お腹が減っている僕は二人に構っている余裕はないので一瞬で炒飯をぺろりと食べる。 「あー美味しいヨ、マチ!これぐらい辛い方が僕は好きだネ」 「だろ?そう思って辛めに味付けしたんだ、赤いものは辛いだろうからね」 マチは僕が完食して褒めたのが余程嬉しかったのか瞳をキラキラさせて説明する。 あぁ可愛いなぁもう。 チラリと二人を見るとカタカタと震え全然食べていなかった。 本当にお腹すいてなかったのかな? 「ねぇ残すなら僕が食べていいかな?二人と違ってお腹ペコペコなんだ」 そう言うと二人は何だか神を見るような目で僕を見て皿を差し出してきた。 それを美味しくいただく。 そう言えば、団長が作ってくれたのも炒飯だったなぁ。 * 「なぁ、マチ…赤って…何入れたんだ…?」 「唐辛子とトマトまではわかったけど…」 「なんかあの甘酸っぱいのはなんだったんだ?」 「あぁ、あれ苺だヨ。僕が好きだからマチ入れてくれたんだろうネ」 目を見開く二人とお腹がいっぱいで満足な僕。 次の日二人に体調を心配されたけど僕はなんともなかった。 いつも通り健康そのもの。 それから何故か二人は僕に優しくなって数日後二人から別々に高めのお菓子を貰ったのは別の話。 愛こそ香辛料 prev / next top ×
|