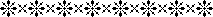 廃墟に戻っても僕の気分は落ちたままだった。 あの赤が消えない。 月の迷い子 姫君 罪人 どういうことだ? あの老婆は迷いなく自決した。まるで伝え終われば死ぬのが当たり前のように。 「カグヤ、これは俺の見解なんだが…」 団長は顎に手を当てて重々しく口を開いた。 「あの老婆は自分のことを案内人と言っていた。それに気付いたかは知らんが老婆の髪色は月色だった」 「月色?」 「お前と同じ色だった。瞳はお前が至近距離で見ただろ?何色だった、俺の見解が正しければ濃い金か月色だっただろ?」 記憶をフル回転させ思い出す、あの時何故気付かなかったのか。 確かに老婆の瞳は月色だった。 濁っていたため金にも見えたが、間違いなく月色だった。 「つまりあの老婆も月の迷い子なんじゃないか?百年に一度堕とされると言っていた。次の迷い子にそれを伝えて使命を果たしたから…」 「自分で命を絶った…?」 「そうだ、そうすると辻褄があうだろ?」 あの老婆も月の迷い子? 僕と同じ… でも 「ならどうして元の世界に戻らなかったのかな?」 「さぁ…死んでしまった今、聞き出す相手はいないからな。あのバーテンダーも何も知らなかったし」 あの老婆も僕も、罪人か。 「くっ…く、ッ…ははは、ははははは」 乾いた笑い声が響き渡る、団長は険しい顔で僕を見るがもうそんなのはどうでもよかった。 「何故笑う」 「団長も見ただろあの老婆の末路、僕もああなるじゃないの?てゆーか、百年生きた末に自決。ただただ虚しい最後だヨ」 熱くなる瞳を押さえる、もうあの赤は消えていた。いや消した。 僕はそんなモノに惑わされていられない。 「戻れないわけじゃない。返せば戻れると言っていた。何か方法があるはずだ。それを見つけ出す、絶対に」 それまではこの世界にいてやろう。 この大嫌いで憎い、修羅の世界で。 泣くように笑う prev / next top ×
|