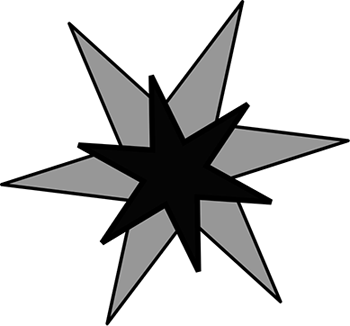「何? あれは常よりの敬服を示さんと民が王へと捧ぐ、献上の品ではないのか」
「もちろん、その意味合いもございましょう」
そのような会話からはじまったのだと、のちに彼女は教えてくれた。
「ただ、一般にバレンタインのチョコレートというものは義理と本命に分けられると聞きます」
「ほう」
「義理とは言葉通り形式的なもの。一方で本命は、慕う殿方への求愛であると」
「ふむ……余への想いが義理であるはずはないのだから、つまるところ本命中の本命であろう。余としたことが、些か無粋な返答をしてしまったな」
「と、申しますと」
「求愛とあらば、応えてやらねばなるまい。ニトクリス、すぐにあやつを呼び戻せ。まだそこらにいよう」
「はい!」
*
天空の女王に呼び止められ、来た廊下を戻ったときすでに予感はあった。
具体的な予感ではない。けれどあの王が一度帰した者をわざわざ呼び戻すなんてよほどのことだし、よほどのことである限り私に拒否権はないのだろうと、それくらいの予想はつく。
「寄れ。許す」
きっぱりと二語、そう発すると、ファラオ・オジマンディアスは手をこまねくでも顎で指し示すでもなく、ただ私の顔をじっと見た。
金色の瞳は、己の言葉の影響力をかけらも疑わない自信と大らかさに溢れている。めったに来ることのない仮想神殿の最深部は、シミュレータと思えないほど濃厚な古代の空気に満ちていた。しんとした石柱の色、黄金の壁画。羅紗の垂れ幕は俗世とのつながりを断つように、すっぽりと神王の閨を覆っている。
私はごくりと唾をのみながら、泰然自若と絨毯で身を休める王の元へ侍った。
「うむ。そう硬くなるな。日頃の邁進、大儀であるぞ」
「あ、ありがとうございます」
何やら機嫌の良いファラオに労われ、杯を傾ける。甘い果実の味が広がって少しだけ気がほぐれた。
「苔桃の果汁だ。子供にはこれがよかろう」
「おいしいです。でもどうして……」
「余は民どもの世事俗事に興味など抱かぬし、余を祀る儀であるならまだしも、異国の慣習に媚び諂ったりはせぬ」
「はあ」
「だが貴様がかまける分には構うまい。女子供が祭りに色めくはいつの世も変わらぬこと。その健気さに免じ菓子の献上を許したが……このような褒美だけでは、些か不充分であったな」
王はそう言って、先ほど私に授けた天然石の髪飾りを指で撫でた。
「じゅ、充分です。すごく綺麗だし、これをつけてると王様の時代を肌身に感じられる気がします」
「愛いことを言う。だが物で返せるのは物の礼だけ。祭りに乗じ余を誘うなど、神をも恐れぬ大胆さではあるが……」
「……へ?」
「赦そう。そのいじらしさ、しかと受け止めてやる」
「あの」
常に朗々と発せられる彼の言葉を聞き損じることはないが、すべて聞こえても何を言われているかわからないときというのはある。いつの間にやら文字通り、目と鼻の先に迫っていたファラオの尊顔にちかちかと目をまたたかせているうち、体は浮遊感に包まれていた。
そのまま迷いのない足取りで寝台へ寄った王は、私の体を優しく降ろし、自身も天蓋の内へと入る。
「ファラオ」
「うむ」
「オジマンディアス王!」
「ふふ、なんだ、もう少し艶っぽく呼ばぬか。寝台の上であるぞ」
「そうじゃなくて!」
はにかむように目尻を下げるオジマンディアス王はとてもかわいらしいが、だからといってこのナイルの濁流がごとき展開に流されるわけにはいかない。
「どうして寝台に運ぶんですか!?」
「何? この場所では不満か。貴様生娘であろうに、なかなか貪欲ではないか」
ごくりと息を飲む王様に悪意がないことはわかる。そして悪意のない者を説得することほど難しいことはないのだ。
「私、そんなつもりでチョコを渡したんじゃありません」
「なんだと? あの菓子は義理であったと申すか!」
「ち、違いますちゃんと心を込めて」
「では王からの寵愛を望んでのことであろう。楽にせよ」
「どうして0か100かしかないんですか!?」
ばさりと羽織りを脱ぎ捨てて覆いかぶさる王様に、必死で抵抗を試みるが力も体格も違いすぎる。押さえつけるまでもなく、覗き込むようにして私の動きを制すと、彼は金色の目を光らせた。
「妙なことを申す。王が誰を愛でるかは王が決めること。ましてや貴様は余を慕う女、拒む理由がどこにある」
「……慕うといってもそれはなんていうか、親愛というか、尊敬というか」
「ならば貴様はそれでよい」
王様の低い声が体の奥までじんと響き、指の先から力が抜けていく。
「そも識らぬものに怯えてどうする? それを忌むかは識ってから決めよ。余に抱かれ、女であることを悔やむ者などこの世にはおらぬ」
いつも真っ直ぐ見開かれているファラオの目が、今は見たこともないほど妖艶に細められている。褐色の肌は天蓋の影を纏い艶めいていた。くっきりと筋の隆起する雄々しい体躯だ。これがいかに生き物として上位で、すべてに勝り、贅沢なものであるかは物を知らぬ私にだってわかる。
「我が神気にあてられ打ち震えるか。素直でよい」
大きな手のひらが迷いなく服の内へと進む。王の言葉も態度もすべて私を納得させるものだ。反論の余地などまったくないと思わされる。きっと抗う私が間違っているのだ。だって彼の存在は、ただそこにあるだけでこんなにも正しい。
「おねがいです、ファラオ」
けれどそんなのは勝手なことだと思う。
「許して」
「赦すと、言っているではないか」
身をぎゅっと縮めて首を振ると、王様は私の体にすべらせていた温かい手を離した。
「そんなに恐ろしいか」
「はい」
「……ふむ」
流されることは簡単だが、それでは私が彼のことを大切にできなくなる。一方的な寵愛で何かを失うのは御免だ。
「チョコのお礼だって言うなら、このまま添い寝をしてください」
駄目元でそんなことを言ってみる。たとえ止めてくれようと、私の体はすっかりふやけてもう起きあがることすらできないのだ。
「まこと、神をも恐れぬ貪欲さとはこのことよ」
王様は少しのあいだ透明な目をしていたけれど、そう言って慈愛をにじませると、私の体を抱えあげ子をあやすよう胸に乗せた。きっとこの人は、本当に私を喜ばせたいだけなのだ。自分という存在そのものが、他者への最大の賛辞であり贅沢であると知っている。
背に添う手のひらはやはり太陽のように温かい。体の奥の、太古の核に、王様の寝物語がしんしんとしみ込んでいく。ナイルのほとりは今日も豊かだ。
2018_02_14