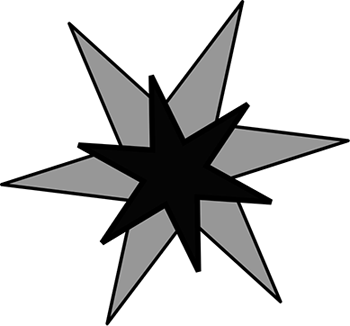短編『1mとすこし』『異星間交遊』の続きです。
お屋敷、といって差し支えないおうちだ。
彼のテンポ感が独特であろうことは予想できたが、手を繋いだ一週間後に親に挨拶というのは想定を上回るぶっ飛ばし具合である。長い板張りの廊下を歩きながらそう思った。
きっとそこまでの深い意味はない。寮で暮らす牛島くんが、久しぶりに実家に戻るという週末に、何気なく話題を振ったのだ。
「牛島くんのおうちってどんな感じ?」
「来てみるか」
骨の髄まで実践派の彼がそう聞いて、私がぼんやりと頷いたことによりおうちデートは二秒で決まった。はたから見ていた天童くんがうひゃ〜と他人事のような声を上げたが、私に突っ込む余裕はなかった。何を着て行こう。何か持って行った方がいいのだろうか。
付き合って初めてのバレンタインに、チョコでなく菓子折りの心配をするとは思ってもみなかった。遠くでバレンタインデーキッスを歌っている天童くんの声がぐるぐると頭の中に鳴り響き──あれよあれよという間に、今に至るというわけだ。
「これ本当に、つまらないものですが」
「あら、息子の同級生の作ったチョコレートがつまらないはずないわ」
言葉の通り、心底面白そうな目を私とチョコレートに向けているお母さんはかなりのツワモノの予感がした。きりっとまっすぐ上を向く眉毛は牛島くんによく似ている。
お祖母ちゃんを入れ四人でお茶をして、学校でのことや、私の家族のことなどを話す。ぽろぽろとひび割れた甘すぎるチョコレートケーキを食べ終わり、牛島くんの部屋へ案内をされるころには背中がぴっしりと固まっていた。彼の姿勢がいい理由がよくわかる気がした。
「疲れたか?」
「緊張したあ」
そんなものか、と頷く牛島くんはいつもと変わらない様子だ。体の大きな彼でも窮屈さを感じさせない、広い和室だった。窓から見える庭の真ん中にはバレーのネットが張られている。彼を形作る様々なものが、いたるところに垣間見えた。
所在なさげにそわそわとする私を見て、牛島くんが首をひねる。無言で手招きをする彼がなんだかおかしくて気が緩んだ。
「ここで、あってる……?」
けれどその安息も長くはつづかない。彼が指差した場所へ座りながら、私は思わずそう聞いた。たしかにどっしりと座った牛島くんの体は立派な座椅子のようではある。けれど初めてきた彼氏の部屋で、いきなり膝の上に座るというのはどうだろう。
「父さんは、よくこうして俺と遊んでくれた」
そういえば、離婚した父は海外に住んでいるのだとこのあいだ学食で言っていた。彼にバレーを教えた父親はさぞ大きな存在だったのだろう。そう言うと、牛島くんは「父さんの背はもう追い越したと思う」と言って手のひらを見た。
「ふふ、そうかもね」
大きな手がそのまま私の頭に乗る。頭ぽん、なんていう長閑なものではない。これは頭ずしりだ。
「ボールより小さいな」
「も、持とうとしないで!」
「すまん」
なんだかますますいろいろな意味で鼓動が高鳴ってきた私は、前を向いたまま大きく一度深呼吸をする。
「どうした?」
「いやなんか、ドキドキして」
「落ち着かないか? 俺はこうされたら落ち着いたが」
「牛島くんは私のお父さんになりたいの?」
「違うな」
私と比べ、彼があまりに落ち着いているものだからついいじわるを言ってしまった。その自覚があるのか、牛島くんも少しむっとした顔でこちらを見下ろしている。申し訳なさと少しの怖さに、心臓が脈打った。でも、こんな顔も嫌いじゃないと思う。知らない表情を見るために、彼の心にちょっとした爪を立てるのは無謀だろうか。虎に戯れる猫のようなものだと許してほしい。
「お前といると……」
「うん?」
「自分に驚くことが多い」
「わ、私もそう」
「そうか」
相手にも驚くが、なによりも自分に驚く。同意しながら見上げた先に、牛島くんのまっすぐな目があった。ここぞという時に躊躇いを持たない彼の性格は、バレーの試合を見ていればわかる。思いの外、私たちの進度は早いようだ。こんなことが天童くんにばれたら大変だ。またエンドレスであの歌をうたわれてしまう。
「若利」
廊下の向こうから声が聞こえ、私たちの背中はまたピンと伸びる。牛島くんがとっさに私の肩を掴み置物のように隣へずらしたため、私は正座をしたまま畳の目に沿って一メートルほど移動した。牛島くんにも、親に対する照れや後ろめたさのようなものはあるらしい。
襖を開けて何かを話したあと、彼は素知らぬ顔でまたこちらへ戻って来る。こんなときにポーカーフェイスは得だと思う。
「お隣に林檎を届けに行くそうだ」
「ああ、はあ」
「俺が」
「うん?」
「バレー以外に疎いことは自覚してる。間違ってたら言ってほしい」
「わかった」
相変わらず臆面なく状況確認をするこの人は、きっと少しだけ誤解をしている。
「でもあのね、私もそんなに詳しいわけじゃないんだよ」
「そうなのか」
「うん」
「それは……困ったな」
子どものように笑う彼の顔は、あまり困っているように見えない。そんな顔を見せられると私の方が困ってしまう。照れをごまかそうと、私は畳に置かれた彼の手に自分のそれをぱしりと重ねた。
彼と唇を合わせるには、たとえ座っていたってうんと上を向かなくてはいけない。この背伸びを私はあと何度するのだろう。牛島くんと一緒にいると、私の背筋はどんどん伸びる。いつか少しくらい、距離は縮むだろうか。
2018_02_14