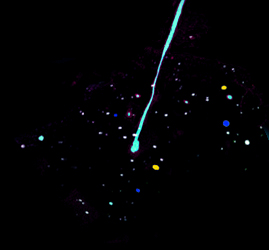
「なんだか随分と」
塗りつぶされたような薄闇色の髪をなびかせて、彼が診察室に入ってきたとき、私は思わずそう口にした。
「感じが変わりましたね」
「そうかい?」
六番目の異聞帯からストームボーダーが帰還してすぐ、盾の喚びかけに応えたのは白銀の髪を持つ妖精の王だった。ノウムカルデアで彼らの帰りを待っていた私は、報告書に目を通す暇もなく疲弊しきったマスターや、デミサーヴァントであるマシュ・キリエライト、キャプテンや技術顧問、加えて瞬間的な顕現ですらその身に厄介な呪いを負ったカルデアのサーヴァントたちの治療に追われ、ろくな情報整理もできていなかった。元からメンタル面の解析及びフォローといったものはすべてマスターらに任せ、自分はサーヴァントのフィジカルのみを診れば良いのだと割り切っていたこともある。
なので、新たに召喚されたサーヴァントが異聞帯に由来するものであると知っても、その詳細を尋ねることはしなかった。彼はすべての検査に協力的で、また態度も柔らかく、気性の荒い英雄や、突飛な言動の絶えない神霊らと比べれば格段に診やすかったのだ。
それゆえに──今日再びバイタルチェックに現れた彼、妖精王オベロンが、別人のように変容しているのを見て驚いた。再臨段階により容姿や装束が大きく変わるサーバントは珍しくない。けれど、彼の場合はそれとは少し違うように思えた。
そうしてすぐに、納得する。
味気ないと言われるかもしれないが、私がここで診るのは構造だ。彼らを形造る霊基の状態であり、その中心にある霊核の安定性だ。
「容姿も能力も大きく変化していますが……霊基はさほど変わりませんね」
「変わらない?」
「はい。プリテンダーという特殊なクラスで現界したあなたの霊基は、元から極端に不安定で、それゆえに安定していました」
私の言葉を意外に思ったのか、以前とは異なる鋭い目つきでオベロンはこちらを睨みつける。瞳の形は変わらない。けれど内面を反映するかのように、それはうっすらと剣呑に細められていた。
「不安定なのに安定? よくわからないな」
「あなたの霊核は……診る角度によって、くるりと違うものに見える。色合いも、形も。あくまでイメージの話ですが」
「それじゃ安定とは程遠いじゃないか。自分で言うのもなんだが、そんな出鱈目な構造のサーヴァントが、人類史を守るカルデアにおいてまともな戦力になるのかね」
「なりますとも。同じ質量の霊子体においては、表出面などさしたる問題ではないのです。コインには裏と表がある。けれど、どちらを上にしたところでその価値は変わらない」
「……なるほど。良い例えだとは思うけど、どこか癪に触るな。コインのように薄っぺらな男だと言いたいわけ?」
オベロンであるはずの男は、そう言うと捨てばちな様子で頭の後ろに手をやった。
「そんなつもりはありません」
「だろうね。君から悪意は感じられない」
遊ばれているのだろうか。打ってかわってにこりと笑う彼の表情に、私はやや混乱する。再臨どころか、秒単位で印象の変わる男だ。私は一つ咳をして、自分のペースを取り戻す。
「一騎のサーヴァントにも多面性があります。情報を固定化されたサーヴァントの在り方とは一見矛盾しているようですが……己の人生を再臨状態により段階的に補完するサーヴァントは案外珍しくありません」
「ふうん」
「つまり、表出している部分が変われど、本質は変わらないということです。こと臨床面においては微々たる誤差と言えます」
「そりゃ、霊核や霊基のレベルで見たらそうなんだろう」
オベロンはつまらなさそうに鼻を鳴らすと、反らせていた体を前に倒し、回転椅子をわずかにこちらへ近づけた。
「じゃあ君は、以前から僕の悪性に気づいていたということ?」
「悪性……ですか」
私は手元のカルテに目をやって、そのあと先ほど抽出した彼の霊基情報を思い出す。
「悪の属性を持つ反英雄はカルデアにも多くいます。けれどあなたは……それとは少し違うのでしょうね」
「どう違う? 善良そうな君の口から、ぜひ率直な意見を聞きたいね」
「反英雄とも違う。反転とも違う。あなたの本質は」
破滅の具現化。虚空の象徴。諦観の成れの果て。世界への嫌悪の行き着く先──。様々な言葉が浮かんだけれど、どれもが的を射ているとは思えず口ごもる。
私にとってオベロンとは、シェイクスピアの戯曲に登場する王であり脇役だ。それがここまで禍々しく化けたというのだから、ブリテンの繁榮と崩落というものは凄まじいものであったに違いない。
「先ほどあなたは、私から悪意は感じられないと言いましたが」
「話を逸らすなよ。俺が聞いてる」
「すみません。けれどあなたを見ていたら言わずにはいられませんでした。私にも、悪意はある。すべてを辞めてしまいたい。何もかも終わってしまえばいい」
枯れ木のような、獣のような左手が視線の先でぼんやりと光っている。とある世界のなごりを映し出すように、青く、哀しい色だ。
「命をかけて戦う少女たちの背後で、そんなことを思うことがある」
いつの間にか、私は下を向いて言ってはならないことを口走っていた。多くを失い、全てを捨て、生き残ったこの世界とも呼べないものの端っこで幾度、終焉を夢見たか知れない。
「崩落の化身、オベロン。いつか終わりたいと思ったときには、一緒に落ちてくれますか」
「もちろんさ! ……と言いたいところだけど」
彼は大きく手を広げ、私の願望を受け入れるジェスチャーをしたあとで、今思い出したというふうに白々しく首を振る。
「心中相手は決めているんだ。まだ見ぬ人だが、会う前から裏切るわけにはいかない」
「そうですか」
「けれど、夢想になら付き合うよ。柔らかなベッドの上で、ともに甘美なる終末の夢に微睡むことはできる」
彼がまさにシェイクスピア劇の一節のようなことを言うものだから、私はおかしくなって顔を上げた。大仰で、ロマンチックで、悲劇的でいて、どこか喜劇的でもある。偶然か必然か、そういった人物を私はもう一人知っていた。
「まるでどこかの夢魔のようなことを言いますね」
「やめてくれ」
己の雑念を振り払うように軽口を叩き、私はデスクに目を戻す。再臨後のバイタル異常なし。霊基安定。魔力供給率、高度維持。
「でも女性を口説くのは、下手になりましたね」
「おかしなことをカルテに書くなよ」
私の言葉がよほど心外だったのか、彼は立ち上がり薄い翅を震わせた。ハグロトンボのように繊細で美しい光沢だ。
本来マスターに任せるはずの心的交流を、意図せずしてしまったことに自分でも驚きながら、その背を見る。
ペンを置いた拍子にディスプレイが通知音を響かせて、一つのポップアップを映し出した。
「ああ、今あなたの新たな霊基情報が届きました。ヴォーティガーン」
宙のようなマントを揺らし、妖精はカルデアの白に浮く。
「オベロン・ヴォーティガーン。これからもよろしく」
顔を顰めるように笑い、彼は一つ、長いため息を吐いた。
「こっちではそれを名乗ってないんだけどな」
ここではすべてが曖昧な夢だ。だから私は形を診る。確かな物を確認して、誰もが安心したいのだ。そうでなければどこまでも落ちてしまう。