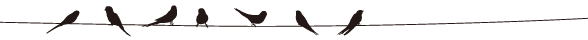
「真ん中の鳥が飛ぶよ」
彼の言ったとおり、真ん中にいたヒバリが追いやられるように空へ逃げた。彼のそうした予言が魔法というよりも手品じみて見えるのは、常に何かしらのタネを仕掛けて回る男だと知っているからだ。
「鳥にタネなんて仕込めるわけないだろう?」
「わかってますよ」
こんなのは偶然だ。彼は運が良いのだ。そもそも頭が良くて運動神経が良くて顔も良い、そんな遺伝子を持って生まれたこと自体相当運が良い。そしてそんな男に引っかかっている私は相当に運が悪かった。
「偶然っておそろしいですね」
「偶然じゃないさ。ちょっと観察してれば鳥の行動パターンくらい猿でも掴める。こんなのには大した運も頭もいらないよ」
そうですか。私はぼそりと相づちをうってぶどうジュースを傾けた。陽の傾いた喫茶店でなぜかハウスワインを頼んだ折原さんは、私にも同じものを、と言おうとして小さく笑った。結果私はワイングラスでぶどうジュースを飲んでいる。とろりと濃くておいしいけれど、少しきつい。べたべたと甘すぎるジュースは嫌いだ。
「それで、春からのことだけど」
切り出した折原さんの言葉に肩が揺れる。彼はまたくすりと笑ってから、私の手のひらに自分のそれをそっと重ねた。緊張をほぐそうとしてくれているのかもしれないけれど逆効果だ。逃がさないと捕えられている心地だった。
「そんなに堅くならないでよ。なにも脅そうってわけじゃない」
「……」
「引き続き援助は切らないでおくよ。ここで手を引いたら意味がないしね」
「ありがとう、ございます……」
高校の学費を出してくれたのは折原さんだった。見栄を張って入学した私立の名門校で、私のような庶民ははじめから浮いていた。二年になったころ出て行った父親は多大な借金を抱えていて、加えて体の弱かった母は無理がたたり入院。絵に描いたような不幸だった。あっという間に退学へ追い込まれた私に、救いの手を差し伸べてくれたのがこの人だ。父の知り合いだと言った彼は、父の失踪に自分が噛んでいることを白状し、これ以上追求しないことを条件にポンと分厚い封筒をくれた。これからのことを考えて高校くらいは出ておきたかった私には、渡りに船だった。促されるまま、彼の言う金額を学園の口座に振り込んだのだ。寄付金も多分に入っていたと思う。除け者にされがちだった私の学園生活は様変わりして、こうして卒業まで無事こぎ着けることができたわけだが──果たして正しい判断だったのかは甚だ疑問だ。けれど一度乗った船はもう岸辺へ戻ってくれないようだった。入院中の母には叔父の援助だと言ってある。どうせ連絡など取らないのだ。
「そのまま進学するんだろう?」
「はい。高校の担任が推薦書を書いてくれました」
「君は成績優秀だったからねえ」
エスカレーター式の学内進学はおどろくほど簡単で、私はただ口座にお金を入れるだけでよかった。パトロンのような役割をしている家はいくつかあるみたいだけれど、そのどれもが企業家であり資産家であり私でも知っているような有名な会社のご令嬢家だ。「あなたのおうちは何をやっているの?」と屈託なく聞いてきたクラスメイトの問いは、おそらく勤め先を尋ねるものではない。彼女たちの親は雇う側なのだ。
「でも私、ほんとうに何も……」
「できなくていいのさ。君はあの学園に籍を置いて、寄付金を払い続けてくれればそれでいい」
「……」
「さしづめ俺はあの学園の株主みたいなものさ」
彼があの学校とどのような関係にあって、あの学校が裏でどのようなことをしているのかは知らないが、何かあまり良くないことに手を貸していることはわかった。けれど私には退路がない。いや、本当に捨て身になれば進学せずに就職して、入院費を稼ぐため夜の副業に身を投じるくらいは出来るのだ。しかし勇気が出なかった。彼の言うことを聞いていればお金の工面はすべてしてくれる。いつか盛大なしっぺ返しが来るとしても、怯える自分と弱った母を守るため、得体の知れないものの片棒を担ぎ続けるしかなかった。
「折原さんは、いくつなんですか」
「俺のことが知りたいの?」
「……お世話になっているわりに、あまりに知らなさすぎるので」
「そうだね。じゃあ一日一つずつ教えてあげよう」
「……」
「そうしたら、俺に会うのが楽しみになるだろ?」
彼はそう言って甘い笑みを顔に貼り付けたけれど、そもそもの元凶は自分なのだと私に白状したことを忘れているのだろうか。もっとも、たとえ彼が原因だとしてもそれに乗ったのは父なのだろうし、今更どうこう言う気はない。そもそもが母の体調も省みず体裁ばかりを取り繕う嫌な人だった。家計が破綻したことは許しがたいが、縁が切れたことにはほっとしているくらいだ。
「あなたが犯罪者ぎりぎりの人間だということくらいは知ってます」
「何度かお手伝いしてくれたもんね。けど、ぎりぎりと思ってくれてるんだ」
クラスメイトの写真をくれだとか、とある教室にこの鞄を置いてほしいだとか、そんなレベルの手伝いをさせられたことはあった。あやしいのは明らかだけれど、知らない振りをしていれば迷惑行為止まりだし言い訳もできる。そんな仕掛けで彼が大金を手にしているのだとしたらやはりそれは魔術師でなく手品師、いや詐欺師ペテン師の類いである。
「私は折原さんの悪行については、何も知りません。知りたくもないです」
「それが賢いね。じゃあ代わりに俺のプライベート情報を一つ。好きな色は、黒だ」
そんなことは聞かなくてもわかるし、知りたくもない。けれど一日一つと言った以上もう何を聞いても教えてはくれないのだろう。
「もっと、年齢とか経歴とか、そういうことが知りたかったです」
「歳は二十三。来神の高大卒だよ」
教えるんかい。と思わずつっこみそうになったのをグッと堪える。彼はのうのうと「初回サービスだよ」なんて言いながら笑っていた。よく笑う男だ。彼の笑顔についてはいくつか知っている。単純に楽しいときだけでなく、人を誑かすときや油断させるときなどにも浮かべるのだ。そしてこんな風に笑うのは、私をバカにしているときだ。
「私は……A型の牡羊座、十八歳、春から大学生です」
「知ってるよ」
「好きな色は、」
「青」
「……」
「だからそれくらい、猿でもわかるって」
折原さんはグラスをくるりと回しながら器用に指を立てた。目を逸らして、窓を見る。端っこの鳥が飛ぶだろうと思った。
「飛ばないよ。二羽増える」
言うが早いが、どこからか飛んできたヒバリが両脇に一羽ずつとまった。甘すぎるジュースを飲み下し彼を見据える。赤茶けた目が揺れている。この元凶にして恩人のペテン師に、次に会うのはいつだろうか。それまでに入院費を振り込んで、母の見舞いに行こうと思った。娘はそれなりに元気にやっています。あやしげな棒を担ぐのにもすっかり慣れてきました。なんてことはとても言えないけれど。
2016.1.10
最終クールスタートお祝い!
最終クールスタートお祝い!