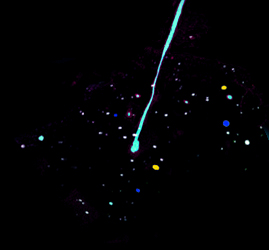
「チョロすぎ」
マーリンとの関係をこの男に報告する義理はないが、思いがけずアクシデントに巻き込んでしまったオベロンには、その後の流れを伝えておいてもいいだろう。そんな殊勝な思いが半分と、あとはちょっとした反抗心だった。
「ほんっと君って、真面目なようで流されやすくてお硬いと見せかけて貞操観念ゆるゆるな中身のない女だよな」
「そこまで言います?」
彼は息継ぎもなく罵詈雑言を吐くと、膝に足首を乗せ肩をすくめる。私の話でなく、これはオベロンへの当てこすりであったのだ。マーリンは私を見捨てたのでなく、またあなたのことをそれなりに信頼しているのだと、話の本題はそこであったはずだ。
けれどそれとは別に──オベロンの忠告は半分当たっていたとも言える。私は一連の流れを思い、カルテを見つめる。マーリンの額をしたたかに打った、透明なバインダーに挟んだカルテだ。マーリンに対する自分の気持ちが胡乱であることは事実だ。彼という存在自体には親しみを持っているし、彼の能力や、立場に対して敬意を抱いてもいる。話しているときは楽しいし、助けられることも多くある。彼なりに私のことを気遣ってくれていることは、日常の中でも端々に感じる。
「マーリンは頼りになるし、感謝もしています。でも、彼と関係を持つことにどれくらいの抵抗感があるのか、自分でもわからないんです。とても畏ろしい気もするし、大して問題がない気もする。それに……」
「それも、奴の夢魔としての力のうちの一つなんだろ。己の欲望のためなら他人の感情すら操り、惑わし、掌握する」
オベロンは言いよどむ私に自らの言葉を被せ、ここで時折りそうするように、椅子の背を大きく軋ませた。
「手のひらの上で転がされ、最終的にぺろりと喰われるのがお前だ」
おしまいおしまい、とにこやかに言われてしまえば、もはや返せる言葉はなかった。彼が終わりというのならこの話はここで終わりなのだろう。
「ところで、さっき何か言いかけた?」
そう思ったのに、オベロンは耳聡く私のどもりを追求した。
「それに、私にだって性欲はあると言おうとしたんです」
「……まあ君の性欲に対して特別な感慨は抱かないけど、俺の前で公言しないでくれない? 気味悪いから」
「だから言いかけてやめたんですよ!」
一体何を口走っているのだろうと、爛れ続けるこの部屋の空気にため息をつく。
「でもそれなら、ちょうどいいじゃないか。まさにwin-winだよ。互いに夢の中で猿のように発散し合えばいい」
「だから、心と体は別の問題だと何度言えば……」
そこまで言いかけて、私は勘違いに気づいた。連日続く赤裸々な会話を、気づかぬうちに混同している。
「いえ、これを言ったのはあなたじゃなかった」
「は? ……まさかとは思うけど、俺を誰と間違えたって?」
「似てるんですよ、たまに。存在は対照的ですらあるのに、局所的にイメージが重なる。どうしてでしょうね」
そう返した次の瞬間には、聞いたこともないような音と衝撃が走り、目の前に四本の爪が生えていた。
「取り消せ。今すぐに訂正しろ。そしてもう二度と言うな」
バインダーと紙カルテを貫いて、青黒い爪先がぎらぎらと光っている。対面している相手がサーヴァントという桁外れの膂力を持つ存在であることを思い出し、私は慎重に息を呑み込んだ。
「……ごめんなさい。嫌っているのを知っていて、無神経でした。もう言わない」
「思うのもやめろよ。不快だから」
爪はぞんざいに引き抜かれ、四つの穴がカルテに残る。随分といわく付きのバインダーになってしまったものだとぞっとしながら、私は廃棄を決意する。
「オベロンは……」
話を逸らそうと思ったわけではない。それは全く別のことであるのに、まるで同じ話である気がしたのだ。
「見つかりそうですか?」
「見つかる?」
「心中相手は決めているって言ってたでしょう」
彼が覚えているように、私だって彼、ヴォーティガーンと初めて話した日のことはよく記憶している。
「まだ見ぬ人と言っただろう。きっと永遠に見つかることはない。見つけてしまえば、俺は世界を憎めなくなるかもしれない。そんなのは俺としても御免だからね。ああ、どこまでも矛盾していて、そのくせ堂々巡りだ。生き物としての構造が狂ってるよね」
「そんなことはないと思う。だって──」
見つけることと認めることはきっと違う。思うことと言うことが違うように。彼は彼でいるために、永遠に隠し続けるのだ。大切なものを、大切であると。
「反対でしょう。大事な物のない人が、世界を壊したいなんて思いますか?」
「反対なものか。大事な物がないからこそ、壊したいと思うんだろ」
「本当に嘘つきですねえ」
「わかったような口きくなよ。バーカ」
私はまた、鐘の音を遠くに聞いた気がして、それから赤茶色の髪を思った。二人の少女は私の中で重なり合い、一つの輝かしい星となる。
「ごめんなさい。何というか少し、腹が立って」
「はあ? なんだそれ」
こんなにも愛に溢れた男が、穴の空いたような顔をして笑っていることが悔しかったのだ。彼は私よりもずっと多くのものを持っている。大切な人を知っている。なにせ彼は数千年ものあいだ文明を乗せ、育んだ島の写し身だ。
「君、もしかして俺が好きなの?」
「焦がれています」
「それは不幸だ」
大きなものになりたい。すべてを飲み込めるほど大きなものに。
世界を飲み込み終わらせるということの意味を、私は今さらながらに理解して目を閉じた。だってそれはどうしようもなく、一つの愛だ。
愛の種類を学びながら、私は彼らに焦がれている。
なんだか貰うばかりのようで、それがとても悔しい。