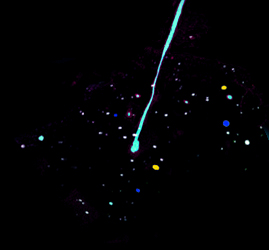
心地の良い感覚がする。マーリンだろうか。
私はくぐもった意識の内側で、夢であろうそれを受け止める。頬に落ちる髪の毛。交わされる口づけ。瞼は重く、手足も重く、目の前の人物の形を確かめることができない。けれどいつもあるものが今日はなく、不思議に思った。
香りも、感触も、花の気配ではないのだ。
さらりとしたシーツに指を這わせ、夢ではない、と思ったところで私の意識は落ちる。
どこまでもどこまでも、底のない眠りが続いている。
*
「起きてるならそう言えって」
その一言に肩が上がってしまったため、決定的に狸寝入りがばれてしまった。
この視界は二度目だ。白いブラウスはゆったりとくつろげられ、目と鼻の先にボタンが見える。なにがどのようにしてこうなったのか、自分なりに予想することはできた。けれどあくまで予想であり、事実かどうかはわからない。どうか私の思うそれよりいくらかマシなものであってほしいと願いながら、問われた言葉に返事をし損ねていると、首に爪が這った。
「起きてます」
「で、何か言うことは」
「言うことはありませんが、聞きたいことが十個ほど」
「十個で足りるのかなぁー」
嫌な口調で返されて、私は喉を詰まらせた。診察室に彼が入ってきたところまでは覚えている。薬の作用に耐えきれず、頭上で交わされる会話を聞き流しながらぼんやりとしているうちに、目隠しが取られたのだ。そうして見たものが、花の色をしていなかったことも、かろうじて記憶していた。
「たしか、霊薬の効果はオベロンに向いてしまって……」
「そうだよ。それにしてもあの魔術師、薄情なもんだよな」
「マーリンが?」
「あとはごゆっくりって、俺を残して帰ったよ。君本当に、ただの食料としか思われてないんじゃないの。他人にシェアされても問題ないみたいだ。まあ夢魔に貞操観念を求めるのも馬鹿らしいけど、ここまであからさまだと流石に哀れになるよな」
「……」
「ところで君、俺に何したか覚えてる? とても十個じゃ足りないけど、十に絞って答えてやるから聞いてみなよ。まあ知らない方が良いことも世の中にはあるだろうから、聞きたくないって言うなら俺が勝手に選んで教えるけど」
よく喋るオベロンの声が次から次へと耳の中に落ちてきて、私はまたもや返事ができなくなった。彼は問いに答えがないことを嫌うが、何かを言おうとするとおでこの辺りが熱くなって、喉がうまく動かない。恥ずかしくて、情けなくて、悲しくて、その理由もわからずに私は息を止めた。
「は……え、泣いてんの」
泣かないために止めていたのに、彼がそう聞くものだからうっかり唇が震え、なんとか目の端にとどめていた涙がシーツの上に落ちてしまう。今度は普通の息ができなくなり、私は喉の奥で引きつる呼吸を押しとどめた。けれど、一度溢れた涙はどうやっても止まってくれない。
「は、なに……俺のせい?」
オベロンは聞いたことのない声で矢継ぎ早に聞いてくる。私の背を囲っていた手のひらが落ち着きなく動き回り、ちくちくと痛む。とうとう漏れた自分の嗚咽が頭にこもり、耳がとても遠くなった気がして、彼が焦っているのか怒っているのかもよくわからない。
「ご、ごめんなさい……オベロンまで巻き込んで」
「……巻き込まれたのは君も一緒だろ」
「ほとんど覚えてないけど、きっと、あなたに酷いことをした」
「君の方がそれを言うの?」
不安や困惑、それに人前で泣いていることの羞恥が混ざり合い心の中がぐずぐずに溶けていく。私は布団の下で背を丸め、なんとか平常心を取り戻そうと不恰好な呼吸を繰り返す。指先が震えるので強く握りこみ、胸に当てた。まるで小さな子どもに戻ったようだ。見ていてほしくないし、一人になりたいのに、オベロンはよりにもよって優しく肩を撫でる。そして駄目押しのように大きなため息をついた。
「腹が立つな。君ごときが俺に大したことできるわけないだろ。それより逆を心配したら?」
「……何かしたの?」
「しないよ。俺にはどこかのクソ野郎と違って、意識のない女を犯す趣味はないからね。ただまあ……」
彼はそこで言葉を止めて、しばらくのあいだそのまま私の背をさすった。獣のような手のひらでも、こんなに優しい仕草ができるのだと意外に思いながら、鼻を啜る。袖口で涙をぬぐい、ふやけた顔を見られたくなかった私はいつかのように寝返りをうった。
「まあ、なに?」
いつまで経っても続かない彼の言葉を問えば、オベロンは打って変わって晴れやかな声を出す。
「いやまさか、何もしてないよ。本当さ」
「何したの……!!」
「酷いなあ、疑うの?」
勢いよく起き上がった私の横で、オベロンは肘をつき呑気に寝そべっている。どの口が言うのかと怒りが混乱を上回ったところで、涙が嘘のように引っ込んだ。
もう一度追求しようと開いた口に、ぴたりと爪の先を当てられる。彼は固く鋭いそれで先ほどのように慎重に私の唇をなぞり、それからわずかに侵入して、舌に触れた。とある感覚がよみがえり、それ以上何も言えなくなった私の体を、彼はシーツに引き倒す。
「意識のない女を犯す趣味はないって言ったけど、君はいま意識があるわけだし。このくだらない茶番劇に一晩付き合ったんだ。それなりの見返りがあって良いと思うんだけど。君はどう思う?」
「見返りもなにも……あなたは私のことが嫌いなんでしょう」
「わかってないな。嫌いな女にする嫌がらせほど楽しいものはないだろ」
「さ、最低ですね」
確かに、媚薬の作用にまかせてやみくもに誘惑したのだろう私に、手を出さないでくれたことはありがたい。彼の言うことがどこまで本当かはわからないが、抱かれたかそうでないかくらいは自分でもわかる。何せこれは夢でなく現実なのだ。
オベロンは私の上に跨ると、ゆっくりと背をかがめ、首を吸った。以前のように噛まれるのではと反射的に身構える。けれど彼はごく一般的な愛撫を続けるだけで、歯を立てる様子も爪で掻く様子もない。それはそれで困るのだけれど、どうしてか拒むきっかけを作れずに、私はその手が服の中へ入ってきたところでようやく「待って」と制止した。
「よかった。このまま止められなかったらどうしようかと思ったよ」
「……本当に性格が悪いですね」
「お互い様だろ」
服を整えながら、またもやシャワーを浴びていないことに気づく。どうして彼とはこんなことばかりなのだろう。
「そろそろ自室に戻ってください。今日もサー・ガウェインと楽しい種火周回でしょう」
捨て台詞を吐きながらベッドを降りれば、彼は舌打ちをして「やっぱヤっちまえば良かったな」とこぼした。仮にも妖精の王だというのになんて口が悪いのだろう。シャワーを浴び終えてもまだそこに寝ていたら、蚊取り線香でも焚いてやろうと企てながらバスルームのドアを開ける。