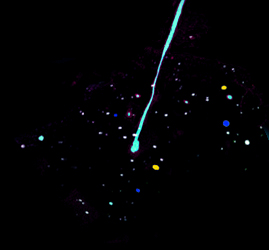
「それでこれ、どういうこと?」
いつもより少しばかり、枕が高いと思ったのだ。首の下に感じる温かさは生き物のそれである。薄っすらと目を開けた先に見えたのはブラウスのボタンだった。妖精王オベロンの着る中性的でいてどこか懐かしい、童話のような白いブラウスがすぐそこにある。上から二つ分、くつろげられた胸元があられもなく晒されているのを見て、私はようやく状況を理解した。理解はしたがそれゆえに動けず、硬直したまま彼の胸の内で煩悶する。
「起きてるんだろう。君本当に、人の質問に答えないよな。俺を自室のベッドに連れ込んで、どうするつもりだって聞いてんだけど」
可愛げのかけらもない刺々しい声が耳に刺さる。そのわりに私のことを押し退けず、腕枕をしたままなのはなぜなのか。そもそも私からこのような体勢をとった覚えはない。彼は確かに枕元で眠っていたが、たとえ小型化を解いたところでこうはならないだろうと思う。何らかの大いなる陰謀を感じる。
「つ、連れ込んでなんか」
「寝て起きたら女の部屋とは……カルデアってのは恐ろしいところだなあ」
大げさに吐かれた溜息が私の前髪を揺らし、とうとう我に返り切った私はすぐさま起き上がろうと身じろいだ。
「まあ待てよ。そんなに急ぐことないだろ」
けれど彼の両腕にがっしりと囲われているため、逃げ出すことも叶わない。これは完全に油断をした。純白の小妖精である彼の寝顔があまりに健気で、か弱く、慈しみ深く見えたため、つい湧き上がる庇護欲のままに行動してしまったのだ。
「なんなの? お前は学習能力がないわけ? それともやっぱり誘ってる? 早く質問に答えないと俺が勝手に決めるけど」
そう言われてしまえば返す言葉もない。愛らしい姿に気を抜いて、まんまと背後をとられたのはごく最近のことだ。私は自分で思っているよりも忘れっぽく、流されやすいのかもしれない。彼に言えば、今さら何をと蔑まれるだろうが。
「オ、オベロンが倒れてて、ブランカが……っ」
なんとか昨夜の状況を伝えようと言葉を探すも、彼が背すじにそって尖った指先を滑らせるため、おかしな刺激が体中にかけぬけて思考がまとまらない。
「待って、頭がうまく」
「待たない。それで?」
「ガウェインが、探しに来たから思わず匿って、私も疲れていたからそのまま……」
ガウェインの名前を出したところで、オベロンは指先の動きをぴたりと止め、小さく舌打ちをした。
「あの太陽バカ、しつこすぎるだろ。妖精國におけるアレはアレで目も当てられない愚か者だったが、本家と比べればだいぶマシと言わざるをえない」
彼の気がそれたのを見計らい、私はひとまず至近距離で向かい合ったこの状況から逃れようと、体の向きを反転する。少しだけ息がしやすくなるも、密着度はそう変わらず事態はあまり改善しない。虫酸が走ると言ってのけた女とベッドの上でくっついて、オベロンは何が楽しいのか。否、彼のことだから嫌がらせとしてこの上なく楽しいことなのかもしれないが。
「ふーん」
何に納得したのか、オベロンは私のうなじの髪を掬うと、潜ませたような思わせぶりな声を出した。
「で、君は毎晩、夢魔とよろしくやってるくせにまだ物足りないわけだ」
「……マーリンは最近、夢に現れません」
「じゃあ、これなに?」
「これって」
「お前さ、本気であいつのこと信じてるの?」
「どういうこと?」
「記憶を消せるって言われたんだろ。だったら何を根拠にそう言える?」
矢継ぎ早に問われ、私の思考はまたも混乱する。何をと言われたって、根拠はないが感覚でわかるのだ。
「マーリンが夢に現れたときは、起き抜けに余韻があるから……」
「だから、それこそがあいつの張るブラフだって言ってんの」
先ほどよりも耳元でオベロンの声がする。夢の中ではないはずなのに、私の心身はどんどん不自由になるようだ。
「本当にお人好しの馬鹿だよな。力量の差もわからずに善良だとかなんだとか……夢の中の記憶なんか夢魔にかかればいくらだって操作できる。大体、お前がその余韻とやらを感じ始めたのだって、わりかし最近のことだろう」
「……」
「じゃあその前は? あいつはいつからお前に目をつけてた? いつから、なにを、どこまで? 何もわからないだろ。あいつは完璧に記憶を消すのがつまらなくなって、たちの悪い遊び方を覚えただけだ」
オベロンの言葉を真に受けてはいけない。とくにマーリンについての話なら尚更だ。オベロンは印象や偏見で彼を語っているにすぎない。私はマーリンの声や温度や、その輪郭を知っている。
「マーリンは言わないことも隠すことも多いけど、私に嘘はついていないと思う」
「じゃあ良いことを教えてやるよ、二日前だ」
「なに、が」
「最後にお前があいつに抱かれた日だよ」
「どうしてあなたがそんなこと」
「あ、妖精王としての能力とかじゃないからね。痕を見れば誰だってわかる。しかしこんなところにマーキングとは念の入ったことだ。一体誰に対する牽制だか」
肌に傷をつけないすれすれの加減で、うなじをなぞられ体が震える。なぜこんなにこの場所が弱いのだろうと、嫌になったところで何かを思い出しそうになった。彼の言葉の意味を理解したときには、ぷつりと爪が肌に食い込んでいた。そのままシャツの布をちりちりと引き裂かれ、背中がだんだんと空気に触れていく。そこに立てられたものは、今度は爪でなくしめった犬歯だ。
「いたい、オベロン……!」
「妖精國における性交はすべてが快楽のためだ。妖精たちに生殖機能はない。人の真似をしているうちに、無意味に肌を擦り合わせる形だけの行為の虜となった。気持ち悪い限りだよねえ」
侮蔑しながら女の肌に口をつけるこの男は、自虐に他人を巻き込む最低の男だ。むかむかと腹が立った私は、考えうる限りの反抗を試みる。
「オベロン、あなたは向こうの妖精とは違うでしょう……汎人類史の物語に最愛の妃を置いてきたあなたは」
「そうだ。あのクソ野郎の生み出したオベロンは、いわゆる大衆の思う王であり、夫だ」
彼を揺さぶるのなら、そのアイデンティティに狙いを定めるのが一番だろう。吉と出るか凶と出るかは分の悪い賭けだが、このまま良いようにされているわけにもいかない。
「つまり男女の営みのなんたるかくらい、わかってるつもりだけど」
オベロンはそう言ってシャツを裂く指を止めると、私の体を裏返し、真正面からこちらを見下ろした。そうしてあろうことか、再度大きな溜息をつく。
「残念ながら君はティターニアじゃない」
「……わかってますよそんなこと。でもそれ、今ここで言うことですか」
心底げんなりとした私は、もはやこの茶番にまともに付き合うことすら馬鹿らしくなり、脱力する。同じように思ったのか、彼も目から凶暴な光を消して私の上から退いた。
乱れた息と動悸を整えるため、私はベッドの端に座り込み深呼吸を繰り返す。
「で、何か言うことは」
「……シャツ代、弁償してください」
「ほんっと、かわいくないな」
そんなことはお互い様だ。目覚まし時計のアラーム音が鳴り響き、彼が背後でそれを消す。考えてみれば昨夜からシャワーを浴びていないから、早く帰ってくれないだろうか。
*
悪い冗談のような夏の夜を過ごしたのち、私たちの関係がどう変わったかと問われれば不明だ。定期検診の時期も過ぎ、もうしばらくはこの場所で彼と会うこともないだろうと思っていた矢先に──オベロンは自ら私の元を訪れた。
「どうしましたか。メロンの食べ過ぎでお腹でも壊しました?」
さきんじて憎まれ口を叩けば、彼は何も言わずに回転椅子へと腰かける。
いつものように倍ほどの皮肉で返されると思っていた私はやや拍子抜けをし、訝しみながら彼を見た。
「……珍しくブランカが拗ねていてね。彼女に乗れないと俺も困る」
一言、そう呟いたオベロンの声はいつになくバツが悪そうだ。髪は黒いがいつものマントは羽織っておらず、ブラウスの背から薄い羽だけが伸びている。
「それは……私と仲直りをしに来たという意味であっていますか?」
「そういうことじゃないの。知らないけど」
私たちがベッドの上で揉めているとき、彼女の姿は見えなかったけれど、あの部屋のどこかにいたのだとしたら怯えさせてしまったかもしれない。ブランカがオベロンのことを大切に思っていることは知っている。そして彼女が心優しいことも。
「わかりました。私もオベロンも大丈夫だって、伝えておいてください」
思わず笑うも、彼はやはり無言のまま目を伏せている。
「ええと……オベロンは大丈夫じゃないのでしょうか」
「うるさい」
霊基の乱れはなさそうだ。これはきっと心持ちの問題だろう。長いこと形ばかり診てきたものだから、こんなときにどうすればいいのか皆目わからず、私は途方にくれた。彼のカルテを取り出しながら温かいお茶でも淹れようかと考えていると、オベロンは少しだけ顎を上げ、薄暗い目をこちらへ向けた。
「君が最初に、口説いたんだぜ」
"一緒に落ちてくれますか"
私は二度目の診察の日に彼へ告げた、自らの言葉を思い出し動きを止める。壁の白が急に目の前に迫った気がして、一つ、二つ、まばたきをした。
それは魔が差してこぼれた無責任な言葉ではあったけれど、確かに一つの本音であった。
漂白された地表を見たとき──ちょうどいいと思った。
きっと疲れていたのだ。
長く続いた人理修復の工程を終えたのち、ようやく戻った正常な時間軸に待ち受けていたものは、現実という過酷な世界だった。非現実を乗り切った私に、現実と向き合う力はもう残されていなかった。私の心はとっくに燃え尽きて、取るに足らない不要物として世界の端に追いやられていた。
あの最果ての森に身を寄せて、最後には焼き払われた虫たちのように。
だからきっと、抗えない大きな力により世界が終わるというのなら、ちょうどいいと思ったのだ。そして私は、自分の心に絶望した。
「──そうでした。でも勝手なことだけど、あの言葉を口にした時点で、私はすでに救われていたんです。あなた以外には言えない言葉だった。だってそんなのは、とても……酷すぎて」
もうやめたいだなんて、どうして私が言えるだろう。傷を傷のまま受け入れて、痛みを痛みとして抱え続ける若きマスターの後ろで、どうしその背から目をそらせるだろう。
「向けるのなら、前を向きたい。私はまだ、あの子たちを……」
私は世界も自分も救えないけれど、彼女たちの手助けならわずかばかりできる。そのことが今ここで生きる理由だ。
「オベロン。あなたがカルデアに来てくれてよかった」
カルテとペンを机に置き、私は彼の前に膝をつく。
「いつでも滅べるから、ではないですよ。私はあなたを、いざというときの首吊りロープのようには思いたくない。誰かを切り札とするのなら、それはできるかぎり、前へ進むためでなくては」
切らずに済むに越したことはない最後の一枚。いつか夢で聞いた言葉を思い出し、やはり似ているのだと思った。そこにいるだけで意味のあるもの。私たちの心をぎりぎりで繋ぎ止める、かつての終末装置。
「結局、君も変わらないな」
彼はうつむいたまま、小さく言う。
「間違いなく俺の嫌悪の対象だ。今すぐこの世から消えてほしい。お前のすべてを闇に葬ってやりたい」
これはきっと彼の本音だ。本音であり、つまりどこまでも虚言なのだ。
「ありがとう。あなたにそう言われているうちはきっと頑張れます」
「嘘つきの言葉を糧にするなよ。腹が立つ」
「いいんですよ。どちらにしろ、確かなものは形だけです」
私は垂れる黒髪に手を伸ばし、その奥の瞳を覗き込む。
「少し触れてもいいですか」
答えはないが、拒まない彼の頬にそっと触れ、輪郭を確かめる。
オベロンは沼底のような目を少しだけ潤ませて「反吐が出る」とこぼした。
その気持ちはよくわかる。けれど私は同意しない。もう二度と、私は破滅を望まない。きっとそのために彼と出会ったのだ。