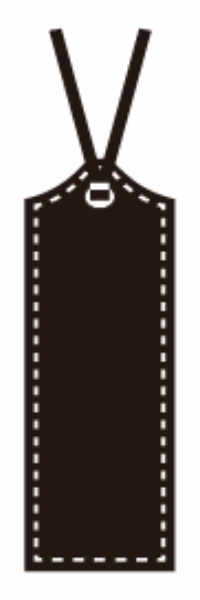奇妙な関係 ② 律さん
空美は静かにしていたい
部屋の奥の壁にもたれていた自転車を起こす。前輪と後輪をつなぐミントのフレームが滑らかに波打っていて、いかにもお洒落でしょと言いたげな自転車──幽協の傘下にある重工業の大手、冨嶽技研が世に送りだす小径車『Everyone』を。
この子とは半年前に仙童フロントで出会った。本当は紹介屋のための関東圏マップをとぼとぼと探していたのに、まさかのひと目惚れ。なにぶん優柔不断な私のこと、いくつかの車種に目移りはしたものの、やっぱりひと目惚れの力は大きく、なけなしのライヴポイントも顧みずに購入した。典型的な衝動買いと言っても過言ではなかった。
だけど、窃盗をおそれて乗っていない。繁華街によってはごくあたりまえのように盗まれる現実を、よりにもよって購入してから思いだした。だから衝動買いって怖いよ。
ただ、仙童フロントはまだ治安がよいほうだ。今日はその街へ行くことに決めた。道のりだって平坦だし、サイクリングにももってこい。
「ジゼルも行く?」
ダメ元で尋ねてみたが、やっぱりダメだった。彼女は相変わらずコカコーラの背もたれに落ち着いたっきり、ご主人さまからのデートのお誘いを完全に無視。うつむきがちにして目もあわさず、ぴくりとも動かない。
「かわいくない!」
案の定の遠吠えを口にしつつ、愛車を玄関へと牽引。その脇、いつ遊びに行きたくなってもいいようにと設置したジゼル専用の小窓を開けると、いよいよそとへと出て玄関扉を閉める。それから、3桁の数字錠で施錠。パスワードは「715」。ソラミを音階にし、Aから何番目にあたるのかを数えたもの──「GAE」→「715」となる。これは、テトさんや万里さんなど、ごく一部の知人だけが知っている。
「さて、と」
戸外は、いまはしんと静まりかえっている。15分ほどまえに奏さんの演奏も終幕、ようやく本格的な朝の静けさが目を醒ましている。それこそ虫の音も聞こえないぐらいの静けさだ……というか、そういえば昆虫の幽体は鳴かないんだった。もう繁殖の必要がないので彼らは鳴かない。その場にじっとしていることが多い。ちなみに猫の幽体も発情の鳴き声は発しない。
「夜会巻きにでもしてもらおうかな」
奏さんに触発されたらしい、静けさに肖りながら思案。カリスマ髪結屋である並木想葉夏さんのお店も仙童フロントにある。
いったん自転車を脇に抱えあげ、屋上と下階をつなぐ階段を踏む。さすがは重工業の大店『冨嶽技研』、貧弱な膂力の私にもあつかえるほどの軽量化を実現している。やはりトップ企業はクオリティが違う──根拠のない感動をも抱えながら15階へ。
そこは、相も変わらずの群青色だった。気休め程度にブルーライトを点灯しているかのような、とてもヘルシーとはいいがたい鬱屈した空間。
試しに天井を見あげてみる。まっ白な蛍光灯が爛々と照っていた。とうに見慣れているはずの、考えるまでもない光景なのに、いまだ、どういう目の錯覚なのかと訝ってしまう。もしや、自分の心をあらわす鏡なのではないかと。
サイコロジーの長廊下へと降り立ち、ここで、エレベータースペースのある右手ではなく、私は住居の並んでいる左手を向いた。
1501号室の鉄扉を手前にし、奥へ向かって部屋番号が歳を重ねていく。また、各部屋の扉と扉の間にもスチール製の小扉が吊りこまれ、どうやらメーターボックスのものであるらしい。
すべての扉に純白のブルーライトが染みこみ、まるで堅牢な刑務所のよう。
窓はない。ここは冷たいコンクリートの匣のなか。
と、その、長廊下の中央のあたり──ちょうど1507号室の門前のあたりだろうか、玄関扉と向きあう格好でコンクリートの壁にもたれかかっている人影があった。ひび割れたプラスチックタイルの床に体操座りし、ひとりの若い女性が、一心不乱に文庫本を読んでいる。
そして、泣いている。
小説を読みながら、泣いている。
鼻を啜りながら、泣いている。
とても静かに泣いている。泣き声はなく、その代わりに、すん、すん──と鼻を鳴らしながら歔欷している。
律さんだ。
読んでいるのは、江戸川乱歩の『芋虫』。
はじめて彼女を見たときには、その異様な雰囲気にただただ圧倒されるばかりだった。しかし、なにしろ毎朝のようにおなじ文庫本を読んで落涙している、次第に小説のタイトルに関心が向くようになり、遠目から装丁と厚みを観察、あの世の書店を調べまくり、最近になってようやく短編集『芋虫』であることが判明。
じつは、お家の書架にも並んでいる。小夜ちゃんに彼女のことを話したところ、後日、サプライズのプレゼントをしてもらった。ありがたいことに、まったくおなじ装丁のものを。
江戸川乱歩──『人間椅子』と『屋根裏の散歩者』しか読んだことがなかった。もちろん、私好みの作風をする怪奇小説家ではあるものの、あまりにも有名人すぎるから触手を広げられずにいたんだ。夢野久作・夢枕獏・折原一・遠藤徹・P. D. James・Jack Ketchum など、その奇才によってコアなファンを獲得しつつも、かといって有名人すぎもしない小説家のほうが私の琴線に触れやすいらしい。私って天の邪鬼なのかな。
いずれにしても、この短編に深い感銘を受けたことは間違いない。私も、須永中尉のあの核心の言葉に思わず目を潤ませたひとりだ。昭和14年、反戦的であるとして警視庁検閲課から発禁命令を受けたものの、のちに乱歩本人が「夢を語る私の性格は現実世界からどのような扱いを受けても一向に痛痒を感じない」と述べているように、あの当時の日本国のイデオロギーとはまったく無関係、人間のエゴや醜さ、ゆえなる美しさを純粋に探求した作品だとわかる。秀作なんだ。逸品なんだ。尊い物語なんだ。
たぶん、律さんもあのあたりのシーンで泣いている。右の指先にまとめられるページの厚みで、なんとなくわかる。
毎日の習慣なのかはわからないが、たいてい、この時間帯に泣いている。15階の長廊下、ブルーライトの滴る床に座りこみ、冷たい壁にもたれ、小柄な身体をさらに小さく折り畳んで『芋虫』に没入している。
すん、すん──小まめに鼻を啜り、静かに泣いている。そうやって、調律している。
★ 調律 [ ちょうりつ ]
涕泣が生体の心身に良い影響をあたえることはすでに衆知の事実。認知神経学や心理学などの諸科学においても、ある程度までの効果的立証は為されている。鎮静作用があることはもとより、解毒作用や抑鬱作用もあるとして、泣くことを幅広く利用するのがヘルスケアの近道だと提唱されている。実際、涙は「天然の麻酔薬」と呼ばれているぐらいなのだし。
「我慢せずに泣きなさい」という専門家の勧告に対し、なかには否定的な意見を持つひともいるけれど。例えば、
「人間はひとりで生きているわけではなく、常に第三者と接触し、干渉し、協力しあいながら社会を構築しているのだから、我慢すべき場面でおいおいと泣かれてはこちらが迷惑だ!」
という意見。なるほど、ひとたび社会活動のなかへと足を伸ばす際には、行動をわきまえ、慎み、第三者を慮らなくてはソーシャルモラリティの歯車が破綻しかねない。涕泣は、あくまでもプライベートで試すこと。そこを分け隔てず、なんでもかんでも一絡げに勧告するのは混乱の原因──あまりにも端折りすぎている専門家の表現に不快をおぼえる気持ちも理解できる。要するに「泣くことを我慢してしまう日本人の民族性に対する明確な警鐘であるべきだ」とか「我慢を怠りなさい──と受け止められかねない不完全な表現は慎むべきだ」ということなのだろう。
閑話休題。
自己犠牲か自己解放かの議論は扨措き、すくなくとも、涕泣に関する大局的医学的な有用性の是が覆ることはもうないだろう。生体の涙はそのように肯定されつつある。
ただ、これはあくまでも生体のお話。
すでに生命という概念の備わっていない幽体のほうはどうか?
じつは、幽体も泣く。生体と同様に、嬉しいとき、悲しいとき、苦しいとき、感動したときには、ちゃんと泣くことができる。
なにしろ、幽体はメンタルの塊だ。肉体という器に精神という水が注がれている生体とは違い、幽体は、精神という水だけですべてが構成されているようなもの。ある意味、RPGのスライムのようなものなのかも知れない。だから、ちょっとしたことで簡単に倫力が減少する。慟力の強さはひとそれぞれなりに、減るものは減り、0になればラストする。ひいては、アップルシンドロームが起き、物言わぬ虜囚霊となる。
幽体には、あらかじめ、そうなってしまわないための反応作用が備わっている。それが以前に紹介した『保存性条件反応;PMCR』だ。
PMCRはいくつかの種類が認定されている。例えば、憂鬱になったときにため息が出る、唖然としたときに瞼が瞬く──など。もうそれをする必要なんてないのに、ベクトルからの後押しもあって一連の現象が起きることがある。そうして、精神状態が安定へと向かい、活動の保持が為される。
ちなみに、リペルした際のドキドキ感は、あの世でいうところのアレルギー反応に近い。いわば「これに懲りて2度と抜かるなよ?」という警告みたいなものか。とはいえ、これはかなり特殊な事例であり、元来的に、やはりPMCRが幽体の活動を保持するために存在していることは間違いない。ラストさせることが目的ではないんだ。
で、PMCRのなかでも、涕泣という反応が最も保持に適しているらしい。消耗した倫力の回復に大きく貢献するらしい。
だから、幽体だって泣く。心が動いたときにはちゃんと泣くことができる。涙腺のタフネスこそ個人差があるけれど、泣いて心を鎮静させ、安寧を得て倫力を回復することができる。そこのところだけは生体の涕泣行為と大差ない。
ただし、生体の涙は水分でできているけれど、幽体の涙には水分などというサイエンスが微塵も係らない。なにしろ、幽体は物理世界には存在しない存在なのだから。
じゃあ、幽体の涙の成分はなんなのか?
おかしな話だけど「倫体の一部が溶けて流れている」とされている。
溶けたら、いずれ無くなるんじゃないか?
それは、やはりあの世にかぎったお話。だって、幽体にはサイエンスが係らないのだから、倫体が溶けたって決して無になることはない。例えば、格闘技漫画のキャラクターがいくら闘気を放ったところで、その容姿までもが霞んで消えるわけではない──という状況によく似ている。ここでいう「溶ける」とは、あくまでも比喩表現にすぎず、実際に溶解するわけじゃないんだ。サイエンスが係らないのになぜか涙のヴィジョンがあらわれるものだから「源泉はどこ?」という奇妙な議論が巻き起こり、迷走のすえに「倫体が溶けるという比喩状態をクリアして涙があらわれる」という謎めいた定義が為されてしまった。わざわざ定義する必要があったのかと思う。わからないのならば「わからない」って、言えばいいのにな……。
なにはともあれ、作用的には生体の涕泣行為と大差ないが、現象的には明らかな相違点がある。そこで、学界では「すべての面においてあの世に倣っては誤認や誤解を招く」と危惧し、差別化を図るために、この、幽体が泣くというPMCRについて確固たる専門用語を定めている。
それが『調律』。
某学者が、産方にピアノの調律師だったという大親友から想を得て造語したのだとか。個人的に好きなエピソードだ。あくまでも学術用語なので「泣く」という表現でも通用するんだけど、でも私は、この『調律』という言葉をさらっと言えるようなイキな大人になりたいと密かに思っている。
涕泣が生体の心身に良い影響をあたえることはすでに衆知の事実。認知神経学や心理学などの諸科学においても、ある程度までの効果的立証は為されている。鎮静作用があることはもとより、解毒作用や抑鬱作用もあるとして、泣くことを幅広く利用するのがヘルスケアの近道だと提唱されている。実際、涙は「天然の麻酔薬」と呼ばれているぐらいなのだし。
「我慢せずに泣きなさい」という専門家の勧告に対し、なかには否定的な意見を持つひともいるけれど。例えば、
「人間はひとりで生きているわけではなく、常に第三者と接触し、干渉し、協力しあいながら社会を構築しているのだから、我慢すべき場面でおいおいと泣かれてはこちらが迷惑だ!」
という意見。なるほど、ひとたび社会活動のなかへと足を伸ばす際には、行動をわきまえ、慎み、第三者を慮らなくてはソーシャルモラリティの歯車が破綻しかねない。涕泣は、あくまでもプライベートで試すこと。そこを分け隔てず、なんでもかんでも一絡げに勧告するのは混乱の原因──あまりにも端折りすぎている専門家の表現に不快をおぼえる気持ちも理解できる。要するに「泣くことを我慢してしまう日本人の民族性に対する明確な警鐘であるべきだ」とか「我慢を怠りなさい──と受け止められかねない不完全な表現は慎むべきだ」ということなのだろう。
閑話休題。
自己犠牲か自己解放かの議論は扨措き、すくなくとも、涕泣に関する大局的医学的な有用性の是が覆ることはもうないだろう。生体の涙はそのように肯定されつつある。
ただ、これはあくまでも生体のお話。
すでに生命という概念の備わっていない幽体のほうはどうか?
じつは、幽体も泣く。生体と同様に、嬉しいとき、悲しいとき、苦しいとき、感動したときには、ちゃんと泣くことができる。
なにしろ、幽体はメンタルの塊だ。肉体という器に精神という水が注がれている生体とは違い、幽体は、精神という水だけですべてが構成されているようなもの。ある意味、RPGのスライムのようなものなのかも知れない。だから、ちょっとしたことで簡単に倫力が減少する。慟力の強さはひとそれぞれなりに、減るものは減り、0になればラストする。ひいては、アップルシンドロームが起き、物言わぬ虜囚霊となる。
幽体には、あらかじめ、そうなってしまわないための反応作用が備わっている。それが以前に紹介した『保存性条件反応;PMCR』だ。
PMCRはいくつかの種類が認定されている。例えば、憂鬱になったときにため息が出る、唖然としたときに瞼が瞬く──など。もうそれをする必要なんてないのに、ベクトルからの後押しもあって一連の現象が起きることがある。そうして、精神状態が安定へと向かい、活動の保持が為される。
ちなみに、リペルした際のドキドキ感は、あの世でいうところのアレルギー反応に近い。いわば「これに懲りて2度と抜かるなよ?」という警告みたいなものか。とはいえ、これはかなり特殊な事例であり、元来的に、やはりPMCRが幽体の活動を保持するために存在していることは間違いない。ラストさせることが目的ではないんだ。
で、PMCRのなかでも、涕泣という反応が最も保持に適しているらしい。消耗した倫力の回復に大きく貢献するらしい。
だから、幽体だって泣く。心が動いたときにはちゃんと泣くことができる。涙腺のタフネスこそ個人差があるけれど、泣いて心を鎮静させ、安寧を得て倫力を回復することができる。そこのところだけは生体の涕泣行為と大差ない。
ただし、生体の涙は水分でできているけれど、幽体の涙には水分などというサイエンスが微塵も係らない。なにしろ、幽体は物理世界には存在しない存在なのだから。
じゃあ、幽体の涙の成分はなんなのか?
おかしな話だけど「倫体の一部が溶けて流れている」とされている。
溶けたら、いずれ無くなるんじゃないか?
それは、やはりあの世にかぎったお話。だって、幽体にはサイエンスが係らないのだから、倫体が溶けたって決して無になることはない。例えば、格闘技漫画のキャラクターがいくら闘気を放ったところで、その容姿までもが霞んで消えるわけではない──という状況によく似ている。ここでいう「溶ける」とは、あくまでも比喩表現にすぎず、実際に溶解するわけじゃないんだ。サイエンスが係らないのになぜか涙のヴィジョンがあらわれるものだから「源泉はどこ?」という奇妙な議論が巻き起こり、迷走のすえに「倫体が溶けるという比喩状態をクリアして涙があらわれる」という謎めいた定義が為されてしまった。わざわざ定義する必要があったのかと思う。わからないのならば「わからない」って、言えばいいのにな……。
なにはともあれ、作用的には生体の涕泣行為と大差ないが、現象的には明らかな相違点がある。そこで、学界では「すべての面においてあの世に倣っては誤認や誤解を招く」と危惧し、差別化を図るために、この、幽体が泣くというPMCRについて確固たる専門用語を定めている。
それが『調律』。
某学者が、産方にピアノの調律師だったという大親友から想を得て造語したのだとか。個人的に好きなエピソードだ。あくまでも学術用語なので「泣く」という表現でも通用するんだけど、でも私は、この『調律』という言葉をさらっと言えるようなイキな大人になりたいと密かに思っている。
すん、すん──毎朝のように調律しているから、私のほうで勝手に『律さん』と名づけた。勝手に名づけ、勝手に心のなかで呼んでいる。
鼻を啜って泣いている。幽体は、涙こそ出るけれど洟までは出ない。でも、彼女は鼻を啜る。私も啜る。そのほうが泣いている感じになりやすくなり、心が盛りあがりやすくなり、つまり落ち着きやすくなるから。ということは、これもPMCRの一種なのかも知れない。いや、ただのベクトルなのかも知れない。だから、涙をこぼすだけで調律を完了させるひともいるのかも知れない。
不躾なことだとも省みず、エレベーターを呼ぶことも忘れたまま、私は律さんに見入っている。毎度のことながら、つい見入ってしまっている。
観相は20代前半だろうか、若く見える。まるで伸ばしかけのように重みのあるボブヘアには緩くウェーヴがかけられてあり、ハーフアップを軽くお団子に。その色はオレンジアッシュだろうか、とても明快。服はといえば、ハーフ袖にフリルのあしらわれる灰色のヘザーシャツに、紫がかった青のオーバーオールを着ている。裾の折りかえしはピンクで、そのしたに履いているのは紅色の薔薇が咲く黒いサンダル──大胆さを感じさせ、でも脱力系でもあるエアリーコーデ。典型的なジャパニーズガールズスタイルだ。
面立ちも若い。整えただけだろう自然な太さの眉、ささやかながらにマスカラの乗る円らな目・低くて小さな鼻・上下にぽってりしている唇が、面積の狭いホワイトアイランドのうえで健やかに息をしている。同性向けのナチュラルメイクで、確か、こういう趣のことを「青文字系」と呼んだような気がする。
自由が丘のあたりを散歩していそうな雰囲気の女性が、仄暗い廊下に体操座りし、江戸川乱歩の短編小説を捲りながら静かに泣いている。異様といえば異様な光景だ。でも、不思議と似合ってもいるのだから興味深い。なるほど、Björk『Hidden Place』がフィットする空気を彼女が持っていることを加味すれば、この光景が似合うのも腑に落ちるというものか──ひととなりを知りたければフィットする音楽を照らしあわせてみるにかぎる。
陽的な陰──文学的な律さん。彼女がどういう産方を歩み、起因を拾ったのか、私は知らない。もちろん、対話をしてみればいずれ知られるのかも知れない。ひいては、彼女のコミュニティに仲間入りし、新たな人生を得られるのかも知れない。でも、私は彼女と対話しなかった。すくなくとも、いま以上の接点を持つことなど望んでいない。
と──不意に、律さんが顔をあげた。
いったん『芋虫』を離れ、潤んでいるとわかる瞳を目のまえの煤けた玄関扉へと向ける。向けるも束の間、今度はゆっくりと右を向いた。そこには、自転車を脇にしてたたずむ私がいる。
目が合った。
八の字の眉といい、ちょこんと突きでた下唇といい、泣き顔が愛らしい。いや、美しい。もしや「可憐」と表現したほうが正しいのかも知れない。なんだか守ってあげたくなるような、純粋無垢な幼女を連想してしまう。だけど、純粋無垢ということは、つまりは、強いということでもある。
そう、大人が子供を守ってあげたくなるのは、かつての、汚れのない自分のオマージュだ。弱くなってしまった現在を戒め、かつてのように強くあろうと志向するデトックス運動でもある。
律さんにも、そうさせる面影がある。だから、こうして彼女と目があうたび、私はドキッとする感覚に襲われる。たいそう大人びてしまった望月空美を再発見してしまい、なんだか気恥ずかしくなり、なのに、不思議と愛しくもなってしまう。
私にも、あんな日があったんだろうか。それを、だれに向けていたんだろうか。母親だったろうか。父親だったろうか。クラスメートだったろうか。担任の先生だったろうか。憧れのミュージシャンだったろうか。いや、そもそも私には、ひとに愛された日があっただろうか。守りたく思われた日はあっただろうか。愛しく思われた日はあっただろうか。そのとき、私は幸せだっただろうか?
でも……思いだせない。
単に忘れてしまったのか、もともとそんな日が1日もなかったのか、それさえも思いだせない。だいたい、自殺なんて愚かな真似をしてしまった私だ、思いだしたいという思いがない。
なのに、思わず思いだそうとしている。
思い出も、思いも、ないのに。
知らず知らずのうち、自転車のハンドルを握る両手が力を帯びていた。いつものこと。いつも、私は彼女と目があい、ドキッとし、愛しくなり、産方をふりかえり、なんにも思い出がないことを知り、にわかに焦り、ついには力んでしまう。
律さんの泣き顔は、魔法だ。
いつの間にやら上目づかいになっていた顎で、私は会釈。ミリ単位の会釈。
すると、やにわに律さんが顔をほころばせた。えへへ──といわんばかりの、屈託のない笑顔。飾り気のない笑顔。まぁるい笑顔。
泣き顔を見られて照れたというような、苦笑いの類ではなかった。自然の摂理のままに花びらが開いたかのような、無理のない笑顔だった。
なんて綺麗。
見惚れてしまう。見惚れ、私のほうまで笑みを浮かべてしまう。
なぜこうして律さんが笑むのか、その真意はわからない。わからないけれど、他意も悪意もないことだけはわかる。理屈じゃなく、たぶん、律さんという人はそれができちゃうひとなんだ。
長く、じつは短い時間をおたがいに笑みあっていたものの、ふたたび、彼女のキラキラと輝く双眸は小説のなかへと戻っていった。
自然と、名残惜しいような感情が湧いてくる。
でも、これ以上を希ってはならないと心の奥が悟っている。これ以上のコミュニケーションは、却って望まないコネクションしか生まず、しかも、もともとのコミュニケーションを根幹から壊してしまうものだ──と。
律さんの魔法が好き。それから、屈託のない笑顔によって魔法が解ける瞬間も好き。産方の思い出にひたろうとする自分が、まるで肯定されたように感じるから。このカタルシスは偉大だ。
なんで自殺なんかしたんだろう?──そう思うこともある。しかも、感傷ではなく理屈でもって。そして、そんなロジカルな自分を無機質なもののように思うこともある。あげく、リセットされたベクトルのせいだと責任転嫁することも。
産方があるから、私があるのに。
「もっと過去をふりかえってもいいんだよ」と、律さんに諭されているのかも。思いだそうとするあなたもあなただし、もしも思い出がなくても、それもあなたなんだよ──と。
すべてを肯定してもらった気持ちになる。
ベクトルという概念のせいで、みんな、1度はみずからの産方を顧みる。クールに、ドライに、ロジカルに顧みる。私も例外ではない。いや、みんなと違い、何度も何度も顧みている。でも、まったく思いだせず、何度も何度も冷めた様子であきらめている。そんな自分を、アンドロイドのように思うこともある。ほんのちょっぴり人間っぽさをインプットされた、ターミネーターのように。
いずれ、なにからなにまでもあきらめてしまうのかも知れない。あきらめ、滞り、物言わない虜囚霊か、覇気のない浮浪霊になってしまうのかも。
幽体には、きっと自己肯定が必要なのだろう。だから、それができているのだろうテトさんも、万里さんも、雲母さんも強い。円蛇さまも、お綾さんも、シュガーさんも強い。まだまだ幽体歴の浅い飛鳥さえも。
私は、弱い。
産方に対して冷めている自分が怖い。
弱いくせに冷めている自分が危うい。
危惧に足踏みするとき、こうして律さんが認めてくれる。肯定してくれる。背中を押してくれる。たとえそれが勘違いの先入観であったとしても、私にとっては真実に違いない。
彼女の笑顔を見たいんだ。産方を思いだせずに力む──そのエネルギーをも認めてくれる笑顔を見たいんだ。彼女によってもたらされるダブルの感傷で、自分を調律したいんだ。
これって、わがままかな?
でも、私には律さんがいてほしい。一瞬の、ただ見つめあって笑いあうだけの、コネクションとはなりようもないこの関係が、私には大切で、絶対で、必要なんだ。
この、奇妙な関係が。
だってほら、また今日も私は、なんだかあたたかな心地になり、ふたたび涙している律さんに敬意の背中を払うと、ほっこりした指先でエレベーターを呼んでしまったんだから。
| ≪ | 表紙に戻る | ≫ |