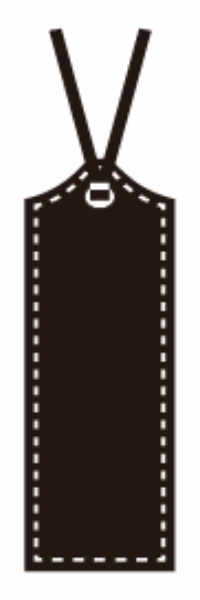的士屋のアデライーダ
空美は静かにしていたい
まっ黒なロング丈のワンピーススカート、まっ白な 頭巾、白と黒の2重のヴェール、数珠のネックレスの先端に金色の十字架があしらわれるロザリオ、素足にまっ黒なローファー──修道用スカプラリオはまとっておらず、とてもシンプルな修道女の衣装。
なのに、食いあわせが悪い。なんというか、いろんな冒涜を感じる。蓮の台に結跏趺坐──百歩譲ってここまでは流しこめるとしよう、でも、どうして修道女ファッションなのか。私には、仏教や基督教に対する冷笑的な食いあわせと思えてならない。神も仏も単なるコスチュームにすぎなかったのだ──と嘲笑うかのような。
いや、やっぱり冒涜なのだろう。だって、
「ガ、ス……」
フルフェイスの、まっ黒なガスマスクをかぶっている。口もとから斜め下へとわずかにバルブが伸び、缶詰めのような形の巨大なフィルターが1個だけついている。ふたつのアウターレンズがゆいいつの赤で、大きく、まん丸。まるでアリクイと昆虫を足したような不気味なフォルムで、確か、ゲーム版のバイオハザードの隠しキャラがこんなようなガスマスクをかぶっていたような気がする。
目は……見えない。アウターレンズの赤がドギツく、大世界の闇とも相俟って人相がまったくわからない。頭巾もぴっちりとかぶっていて1本の髪の毛さえも認められないし、ひととなりを探りあてるための原始的なヒントが皆無。
修道女の衣装にガスマスク、そして蓮のドローンに結跏趺坐──仏教や基督教に対する敬意など微塵も感じられない。やっぱり彼らへの冒涜か、揶揄か、皮肉なのだろう。
「小僧よ」
おそらくは小柄で、身体の線も細く、わずかながらに胸の膨らみもあって、だから女性だとは思う。でも、完全に面立ちが隠匿されてあるので断言まではできない。
容貌も性別も年齢も、そもそも人間なのかどうかも判然としない悪趣味なひと。わかることがあるとすれば、どうやら雲母さんのお知りあいらしいということ。
「朗報だ」
おもむろに両手を腰へあて、晶片小僧に背中を向けたまま、なおも彼女は囁く。愉快そうに、ひとりごちるように。
「アーダはいま、機嫌が悪い」
「え?」
「客にドタキャンされてな」
「それ悲報……」
「徒足を踏んでカンカンだ」
唄うように言い放った、その直後のことだった。
「オ客様ハ神様デスカ!?」
「ぉえ!?」
視界の端、びくッと戦慄する飛鳥。もちろん私も。
「神様デスカオ客様ハ!?」
唐突に修道女が叫んだのだ。いや、ドローンが叫んだのかも知れない。とにかく、壊れかけの拡声器を通したかのような、音割れしたノイジーな女の声が、修道女のあたりから鳴り響きはじめた。
「オ客様ハ神様デスカ!? 神様デスカオ客様ハ!?」
秋葉原の家電量販店かパチンコ屋のアナウンスを思わせる巨大な声。肉声にしては大きすぎる。やっぱり拡声器? 録音?
「オ客様ハ神様デスカ!? 神様デスカオ客様ハ!?」
「お、落ち着……」
特大のリフレインは晶片小僧の台詞もかき消し、
「オ客様ハ神様デスカ!? 神様デスカオ客様ハ!?」
そして蓮の台は、
「オ客様ハ神様デスカ!?」
急発進でこちらに向かっ、
「神様デスカオ客様ハ!?」
て来た。
──そこから先のことは、記憶が定かではない。あまりにも一瞬の出来事だったし、劇場的だったしで、唖然茫然としてしまった。飛鳥とともども、たぶん目を丸くして立ちつくすばかりだっただろう。
断片的に憶えていることといえば、ドローンが颯爽と私たちを通り越し、ふりかえったときにはもう、
『ちょちょちょちょちょ……!』
周章てふためく声とともに晶片小僧が中空を舞っていて、確か、ドローンから触手のようなものが出ていて、それが彼をがっちりとホールドしているらしく、そのまま、拿捕したまま、蓮の台と結跏趺坐の修道女は滑らかな弧を描きながら上昇していって、そうして、瞬く間もなく大世界の闇夜に消え去った。
まだ、遠くのほうでは、
「オ客様ハ神様デスカ? 神様デスカオ客様ハ──?」
謎の問責が響いている。
そういえば、晶片小僧が拿捕される寸前、ぱんッという音が聞こえたような気がする。破裂音のような、銃声のような、害獣対策用の電子爆音機のような大きな音。あたり一帯に鳴り響く音なので出所は定かではないけれど、ドローンの拡声器にまぎれて聞こえたような。それで、その直後に晶片小僧の身体が宙に飛び跳ね、タイミングよくドローンがキャッチしたように見えた。
あの飛び跳ね方……なんか、リペルのフッ飛び方に似てた。
「オ客──神──スカ──様──カオ──ハ──?」
まだ聞こえてる。すごい音量だとわかる。
修道女のあらわれたほうに身体を向け、消え去ったほうに頭だけをふり向かせ、大世界の夜空を唖然と仰ぐ。その視界の端には、私とまったくおなじ体勢を鏡像対称にしたかのような飛鳥の姿。
なにが起きたのか、いや、なんだったのかが理解できない。晶片小僧の登場、雲母さんの登場、ガスマスクの修道女の登場──立てつづけの出来事に思考が追いついていない。この身体全体が、目で見て耳で聴くばかりの単なる感覚器へと降格している。
「晶片小僧はご帰宅だ」
おもむろに、満足したような音色で雲母さんがつぶやいた。発作的に彼女を見やる。先ほどまでの不気味な笑みこそ失せていたものの、まだわずかに口角があがっている。
ドローンのアナウンスはまだかすかに聞こえているけれど、それ以外は静寂。呆気に取られている精神状態も相俟ってか、次第に完全無欠の無音とさえ錯覚していく。左右の、何屋かもわからないお店からひとが飛びでてくることもないし、もしや夢でも見ていたのだろうか?──この望月空美という感覚器を疑ってしまうほど。
しばらくの間、身動ぎできずに茫然とたたずんでいると、
「あ、あの」
ようやく、飛鳥が声を絞りだした。
「い、いま、のは、あの……」
彼女もまた呆気に取られている。ぼそぼそと、ひとりごとのよう。
「なん、だったの、でしょう? あの、ガス、マスクの、ひと、は……?」
「アデライーダ・ヴォルコヴァ」
飛鳥にも劣らないわずかな声量で雲母さんがこたえた。でも、
「愛称はアーダ」
消え入りそうなリコーダーの音とは違い、こちらは胸の内側を貫くヴィーナ。
「彼女はあたしの友人。旧ソ連人の的士屋だ」
「的士屋!?」
私の口から、思った以上に大きな声が出た。
「あんな、ああいう、的士屋って、いらっしゃるん、ですね。はじめて、見ました」
★ 的士屋 [ タクシーや ]
大世界は広い。東京・千葉・埼玉・神奈川を足したほどの面積を誇る。さらに、高層ビル内部や地下空間を加えれば、関東地方全域と比喩しても過言ではなくなる。
自動車や電車が通行できる場所もあるにはあるけれど、都心部よりも建造物が密集している大世界のインフラ事情を考えればそれも稀有な場所には違いない。となれば、幽体の移動手段は、徒歩か、せいぜい自転車ということになる。
でも、やはり大世界は広い。いかに肉体疲労を抱えることのない幽体とはいえ、遠方移動ともなれば途方に暮れてしまう。慟力の消耗は時間の問題。
タクシーが必要となるのは自明。
というわけで、あの世とおなじく大世界にもタクシーが存在する。組合で商売するケースもあれば個人営業もあって、これもあの世と大差ない。違いがあるとすれば、商売道具が自動車ではないというところか。
多くの場合が二輪車、次いで三輪自動車──いわゆるオートリクシャーやトゥクトゥクと呼ばれるもの。これらが、狭い路地を遠慮なく駆け抜けていく。遠慮がなさすぎて通行人が轢かれることもよくある。どうせ死なないし自動車も壊れないし──という心理でも働くのだろうか。事実、轢かれても死なないのだから道路交通法という概念へと展開されるはずもなく、仮に訴訟を起こしたとしてもまったくの無意味。どこ見て走ってんだ!──その場で喧嘩になるだけ。物騒といえば物騒な話かも。
タクシーを利用する手段は主に3種類で、これもあの世とほぼおなじ。街中を走っているところを呼び止めるか、大世界に点在する営業所へと立ち寄るか、ホーネットで予約して来てもらうか。ただし、3つ目の場合は注意が必要。そもそもホーネットの回線状態が悪く、予約完了へと行き着くまでにかなり時間がかかるから。いっそのこと街に出てタクシーを探したほうが早い──とまで言われているほどだ。
ちなみに、なぜ「タクシー」ではなく「的士」と表記するのかといえば、中華的なテクスチャに寛容なのが現在の大世界の風潮だから。そういう表現を取るところにアート性を感じるという、妙な深層心理が土着しているから。渡来系弥生人を自負している古の幽体がどれだけいるのかはわからないけれど、すくなくとも大陸の強引な感受性が大世界を支配していることだけは確かだから。
大世界は広い。東京・千葉・埼玉・神奈川を足したほどの面積を誇る。さらに、高層ビル内部や地下空間を加えれば、関東地方全域と比喩しても過言ではなくなる。
自動車や電車が通行できる場所もあるにはあるけれど、都心部よりも建造物が密集している大世界のインフラ事情を考えればそれも稀有な場所には違いない。となれば、幽体の移動手段は、徒歩か、せいぜい自転車ということになる。
でも、やはり大世界は広い。いかに肉体疲労を抱えることのない幽体とはいえ、遠方移動ともなれば途方に暮れてしまう。慟力の消耗は時間の問題。
タクシーが必要となるのは自明。
というわけで、あの世とおなじく大世界にもタクシーが存在する。組合で商売するケースもあれば個人営業もあって、これもあの世と大差ない。違いがあるとすれば、商売道具が自動車ではないというところか。
多くの場合が二輪車、次いで三輪自動車──いわゆるオートリクシャーやトゥクトゥクと呼ばれるもの。これらが、狭い路地を遠慮なく駆け抜けていく。遠慮がなさすぎて通行人が轢かれることもよくある。どうせ死なないし自動車も壊れないし──という心理でも働くのだろうか。事実、轢かれても死なないのだから道路交通法という概念へと展開されるはずもなく、仮に訴訟を起こしたとしてもまったくの無意味。どこ見て走ってんだ!──その場で喧嘩になるだけ。物騒といえば物騒な話かも。
タクシーを利用する手段は主に3種類で、これもあの世とほぼおなじ。街中を走っているところを呼び止めるか、大世界に点在する営業所へと立ち寄るか、ホーネットで予約して来てもらうか。ただし、3つ目の場合は注意が必要。そもそもホーネットの回線状態が悪く、予約完了へと行き着くまでにかなり時間がかかるから。いっそのこと街に出てタクシーを探したほうが早い──とまで言われているほどだ。
ちなみに、なぜ「タクシー」ではなく「的士」と表記するのかといえば、中華的なテクスチャに寛容なのが現在の大世界の風潮だから。そういう表現を取るところにアート性を感じるという、妙な深層心理が土着しているから。渡来系弥生人を自負している古の幽体がどれだけいるのかはわからないけれど、すくなくとも大陸の強引な感受性が大世界を支配していることだけは確かだから。
まさか飛行物体を商売道具にしている的士屋がいるとは。いかにも現代的なお話で、便利そうでもあるけれど、
「蓮の台……とは、なかなか、エキセントリックな、ひと、です、ね」
修道女の衣服とガスマスクで装う意図がわからない。爆音のアナウンスを搭載している意図もわからない。アナウンスの文言の意図もわからない。
『オ客様ハ神様デスカ!? 神様デスカオ客様ハ!?』
私には、ぜんぜんわからない。
「趣味だ」
ぶっきらぼうにこたえ、雲母さんは引きかえした。ちょうどアデライーダが登場した角を折れて姿を消す。でもすぐに戻ってくると、
「あの乗り物はあたしがつくった。彼女に依頼されてな」
「ど、どうりで」
「上品なヤツをつくりたかったのだが」
「アーダさんの趣味、だったんですね」
「不本意だ」
「はぁ」
「不本意だ」
特に不本意そうでもなく、いつもの無表情で私たちの隣に並んだ。
「それにしても、相変わらず空美はよく知っている」
「え?」
「蓮の台──ムダ知識」
「はぁ」
「あまり欲しがらないことだ」
「はぁ」
「キリがない。捨てることになる」
「……はぁ」
生返事をしながら、ふと、雲母さんの背後に目を向ける。
直方体のなにかが、彼女へと迫ってきている。
やや大きめのキャリーバッグを思わせる箱だった。縦は1mほど、幅は50㎝ほど、奥行きは30㎝ほどか、駅や空港でよく見る形状。大世界の闇のせいで瞭然とはしていないものの、全体が毒々しい紅色をしていて、ジュラルミンケースのようなくすんだ輝きを放っていることはわかる。そんな謎の直方体が、車輪もないのに雲母さんの背後へと近づいてくる。
「こ、れ……は?」
「荷物だ。気にするな」
よくよく見ると、箱のすみにオレンジ色のロゴが読めた。あぁ、なるほど、だとしたら彼女の私物に違いない。
そう、由良雲母の製品群は『キラーシリーズ』と総称されている。ロゴは『K!ller』。自営業ながら、かなり広くこの世に知られているブランド。懐中電灯などの小物からフォークリフトのような重機まで幅広く製作、独立独歩にして新進気鋭、閑散期を知ることのないエッセンシャルブランド。
なぜかTシャツまでつくっている。いま、彼女の着ているものがまさにそれ。ちなみに我が家にもある。初対面の際にもらった。近未来的なバイクにスケルトンが跨がり、マグマ地帯を爆走している絵柄のTシャツ──梱包する透明なビニル袋はいまだにパンドラの箱。
「あの」
地上からわずか3㎝、音もなく、まるでリニアモーターカーのように浮いているバッグを後目に尋ねた。
「お仕事、ですか?」
そしてふたたび雲母さんの顔を見る。
先ほどの騒々しい出来事がまるで嘘だったかのように、彼女は涼しい顔で、
「これから2件目だ」
艶やかなボブをかきあげた。それから、横目でちらと私を見るとしばしの沈黙。そして、左の口角をわずかにあげ、おもむろに、雲母さんはこんなことを提案してきた。
「2件目を」
「はい?」
「職場体験」
「は?」
「してみるか?」
「しょく……え?」
「飛鳥も、一緒に」
「職場、体、験?」
「行ってみるか?」
「行、く?」
「幽霊屋敷に」
「ゆ?」
「入るだけだ。現場に入り、見ているだけ」
「ゆ……」
「職場体験してみるか?」
「ゆうれいやしき!?」
「ゆうれいやしき!?」
飛鳥との、一糸と乱れぬ斉唱だった。
とたん、嫌な予感が全身を駆けめぐる。厄日かも知れない。天中殺かも知れない。今日はいろんな人と出会う。いろんなことが重なる。こんなことって滅多にない。1日1人・1日1件であってほしい。だって私は、静かな街を、山紫水明の地を、
「幽霊屋敷の調査だ。紹介屋としてのブラッシュアップ──おまえたちにもそろそろ必要だろう?」
ただ遊山していたいだけなんだ。
| ≪ | 表紙に戻る | ≫ |