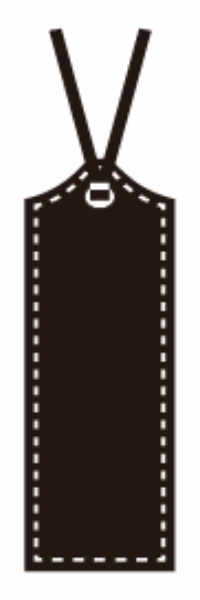奇妙な関係 ① 奏さん
空美は静かにしていたい
二胡の音色が、聴こえる。
いや、ずっと聴こえてはいた。聴こえはじめてから、かれこれ1時間半は経つだろうか。演奏のはじまりから、ずっと私の耳はパフォーマンスをとらえていた。
ただ、半分だけ寝ているような状態でもあったため、はじまりから聴いていたわけではないともいえる。こんなところが、幽体ならではの説明が難しいところ。
なにせ、幽体には睡眠欲がない。食欲も性欲もない。生命維持活動も子孫繁殖能力も必要ない。緩和されなかったベクトルによっては恋愛感情のような情緒を抱える幽体もいるが、しかし学術的には所有欲の類と見るのだそうで、やはり種の保存という概念はリンクしない。やはり、すでに死んでいるのだから生きる必要などなく、すでに死んでいるのだから遺す必要もないということになる。だから、どんなに頑張って眠ろうとしても、生体のようには眠れない。睡眠状態に入ることができない。
ただし、うとうとすることはできなくもない。それは、例えば、電車のなかで立ったまま眠っているような状態に近いだろうか。いまにも膝が落ちるか落ちないかの、寸でのところで意識が保持されているぎりぎりの状態。むろん、ぎりぎりの状態の向こう側に行くことはできない。それは眠っている状態なのであり、幽体がこの境地に達することは未来永劫に叶わない。あくまでも生体にとってのぎりぎりの状態を「幽体の眠り」と方便し、この眠りでもって倫力の回復に努めることはできる。
ちなみにテトさんは眠らない。万里さんや雲母さんもあまり眠らないのだそう。たぶん、九十九さんやオチバさん、円蛇さまも同様なのだろう。飛鳥がたまに重点的に眠るぐらい。そうすると、定期的に眠るのは私だけなのかも知れない。
いや、ひとりいる。頻繁に寝ている男が。
まぁ、それはいいとして。
今日も、私は眠った。4時間ぐらいだろうか。もちろん、生体にとってのぎりぎりの状態である以上、完全に聴覚を遮断していたわけではない。でも意識のボリュームはさがっており、だから、なんとなく遠くのほうで音を聴いていた。聴いているようで聴いていないような、とても曖昧な、微睡みのような耳だった。
毎朝、欠かさず流れてくる二胡の音色。
馥郁19號の向かいに建つマンションからだ。
奏でるのは、たぶん、中国人の女性。タブンというのは、彼女とまだ1度もコミュニケートしたことがないから。だから、外見と雰囲気からくるおおよそのイメージでもって中国人だろうと推理している。日本人にはない大陸的な彫りを美貌に刻む、青龍刀のようにしなやかな印象の女性だ。
二胡の調べも巧者そのもの。ゆったりとうねる大海原のようにダイナミックな旋律を奏でたかと思えば、森林を口遊ませる微風のようにソフトな旋律となり、ときには小鳥の囀りをほうふつさせるトリッキーな旋律まで熟してみせる。とはいえ、うるさくはない。むしろ、未踏の大陸を遊山しているかのような神秘の空想にふけらせてくれる。まさに、永えなる魔法の調べ。
「この曲……」
記憶が確かならば、これまでではじめて耳にする。なのに、私はこの曲を知っていた。
『空山鳥語』
劉天華という音楽家が1928年に編んだという、二胡の名曲だ。草花や野鳥の目醒める朝陽の森をイメージしたという、伝統と革新を両立させた、即興性の豊かな曲。
なぜ私がこんなマニアックな民族音楽を知っているかといえば、生来の空想癖が高じ、お小づかいを貯めては世界中の民族音楽のCDを片っ端から聴き噛るさなかに出会っていた曲だから。確か、小学校の中学年ぐらいのころだったろうか。すでに情緒的な記憶はなくなっているが、なんとなし、理屈を超えた懐かしさをおぼえる。
『空山鳥語』──ふたたび耳にするとは思ってもみなかった。なるほど、人生はなにが起こるかわからないものだ。
奇妙な感慨にふけりながら、のそりと上半身を起こす。小さな枕と漆黒のマット以外にはなにも敷かれていない、ただ横たわるためだけに置いた群青色のパイプベッド、このうえにしばらくあぐらをかいてすごす。
昨日は厄日だった。いたずらに倫力を消耗するばかりの、無力を痛感した日。九十九さん・小夜ちゃん・アダム・円蛇さま・テトさん・万里さんたちのおかげでどうにか持ちなおすことができたけれど、この人生を永遠の生命と思えば、できれば避けて通りたかった日。
だからか、身体が疲れているような気がする。幽体には体力という概念がないから、たぶん心のほうが疲れてる。全身が怠く感じるのは、たぶん錯覚。病は気から──言い得て妙。
でも、それも二胡の音色が次第に癒していってくれる。幽体ってのは単純な生き物だな。いや、メンタルだけでできているからこその、必然的な現象なのかも知れない。
あぐらをほどき、コンクリートの土間へおりる。裸足にスリッパを履かせ、草花に囲まれる惰眠スペースを脱出。そして、昨晩、テトさんと万里さんの寛いでいたリビングスペースへ。
「おはよ」
コカコーラのベンチ、その背もたれにジゼルがとまっていた。隼の仲間である長元坊のジゼル。斑模様の毛並みは美しく、顔立ちも美人だ。鳥類愛好家の間では、確か、雌雄と関係なくすべての長元坊のことを「お嬢さん」と呼ぶのだったか。ならば、美人なのはあたりまえなのかも知れない。
「お、は、よ、う」
なのに、ジゼルはぴくりとも反応しない。この気弱なご主人さまをちらと見ることもせず、円らな瞳を窓辺へと向けたまま。愛想の欠片もなく、残念ながら懐いていない。事実、昨日も助けにきてはくれなかった。ホント恨めしい。
「……薄情者」
遠吠えをつぶやきながら彼女のベンチを迂回、ベニヤ板を重ねあわせてトタンで補強しただけの質素な玄関扉を開けた。
戸外の一面に闇が広がっている。まだ午前中のはずだけれど、そもそも大世界には太陽が存在せず、だから永遠の闇黒しか拝めない。当然、ここには朝の匂いがなく、ということは夜の匂いもなく、錆や油などの有機的なスメルしか漂っていない。おなじ人工の街でも、みなとみらいのほうがはるかに自然の匂いに満ちあふれているほどだ。
そとへと出るなり直進、屋上の際に立つ。家内の灯が足もとまでまっすぐに流れ、雨水の通り道と排水溝の錆を橙色に浮きあがらせる。赤茶けた錆──いくら金束子でこすっても落ちなかった。やむなく見なかったふりをし、代わりに、眼下のビル群へと視線をわたらせる。
「相変わらず、なにがなんやら」
闇の濃度が高い。建物の1棟1棟の輪郭が読み取れず、街灯や各部屋の灯だけが点在している。白・蒼・碧・朱・茜・黄──まるで天地が逆さになったようだ。太陽と同様、大世界には星も月も瞬かないので、なるほど、これが航空業界に聞く「バーティゴ」という現象か。メンタルを強く保っていなくては墜落してしまうことウケアイ。
「それとも、地獄なの?」
「獄」とは「囚人を監禁しておくところ」という意味。または「裁き」そのものをあらわすこともある。そう考えると、この世が地の獄であってもおかしくはない。私たちは、永遠の生命という獄に臥し、永く裁かれているようなものなのだから。
「だから、充実が必要?」
この世の摂理からあたえられた、いつラストするかもわからないという薄氷の秩序を生きつづけるためには、もしや揺るぎない充実が必要なのかも知れない。抜かりなく、常に充実の精神を保っていなくては、いつか必ず墜落する日が訪れるのかも知れない。その最たる予防法こそ、弛まぬ労働に他ならないのかも知れない。
実際、恪勤主義ってそういう思想だったっけ。
「一日一番……かぁ」
そういうことなのかも知れない。
いっそのこと、ラストしたほうが気楽なのかも知れない──とさえ思えてくる。
でも、
「聴いてたい」
この二胡の音色を。ラストしてしまえば永遠に聴くことができなくなる。さすがに、そんなのはイヤだ。
でも、だから働く、の?
「うーん」
それもイヤなんだよなぁ。すくなくとも、紹介屋稼業を延々とつづけていくことは精神的にムリ。きっと、そのうち限界がくる。限界のすえにラストしてしまうかも知れない。
「私になにができるんだろう?」
バーティゴを耐えつづけ、永遠に墜落しないでいられるための方法ってなんだろう。私にできる方法ってなんだろう。
『ダメよ? 充実をしない幽体では』
『幽体の感覚には限界がある。限界は限界。そのさきはない。ないんだ』
『仕事を放棄したところで、まともに生きられた幽体はおらん』
ホントにそうなのかなぁ。労働でなくてはダメなのかなぁ。趣味ではダメなのかなぁ。静けさに寄りかかっているだけではダメなのかなぁ。
「あのひとは、どうだろう?」
どう考えているんだろう。あの、目のまえに建つ8階建マンションの、7階の角部屋に住んでいるらしい、朝になると必ずや二胡を奏でる、あの、まるで青龍刀のようにしなやかな女性は。
「奏さんは、どう考えてるんだろう?」
窓の桟に腰かけ、半身をこちらに向け、美しい横顔で弓を操っている。あれが彼女のいつものスタンスだ。ああして、欠かすことなく穏やかな朝を奏でている。
闇の支配する大世界には、朝も昼も夜もない。私にとって、彼女のパフォーマンスは朝の訪れを報せてくれる鐘の音でもある。
「奏さんは、どうすごしてるんだろう?」
朝しか知らない。昼と夜をどのようにすごしているのかは知らない。仕事をしているのか、無職なのか、どういう趣味や信条を持っているのか、私には知りようがない。もちろん興味は尽きないものの、だからといって尾行するのは違うような気がする。あるいは、話しかけてコミュニケートすることさえも。
この関係を壊したくないんだもん。
奏さんとの、この奇妙な関係を。
スリッパを脱ぐ。しゃがみこむ。屋上の縁に腰かける。両足はマンションの側面に投げだす。怖くない。落ちても死なないし。どうせ闇だから地上なんて見えやしないし。そもそも高所恐怖症なのかどうかも憶えてないし。というか、高所を体験することなく死んでしまったんだし。
眼下には街の灯の星々。そのひとつ、奏さんの部屋の瞬きへと目を凝らす。
うつむきがちに弓を操る姿。
綺麗。
濃紺の長袖マキシワンピースをまとっている。リネン素材と思われるもので、ボタニカル柄か、白い小花がドット柄のように全体にあしらわれている。詰め襟であり、その右に斜めのスリットが入っていて、どうやらチャイナドレス風のワンピらしい。かわいらしくも気品のあるファッション。
黒髪は、夜会巻き。後頭部のあたり、長い髪を黄金の髪飾りでぴたりと留めている。とはいえ、カッチリと固めすぎず、さり気なく鬢をおろしている。なんとなし気さくな印象。
ここから20mほどの距離があるし、しかも横顔なので、面立ちまではわからない。しかし、目鼻立ちがしっかりしていて、凛々しいということはわかる。観相は20代後半~30代前半ぐらいか。典型的な東アジア人の顔ではあるものの、日本人特有の小ぢんまりとした造型ではなく、大陸的な、確固たる主張のありそうな大人な面立ち。だから私は、たぶん中国人か、もしくは中国系のひとなのだろうと踏んでいる。
特に、目が印象的。切れ長で、やや吊りあがり気味の眦が鋭く研ぎ澄まされていて、天野喜孝の女性画をほうふつ。力みのない、幼稚な目をしている私が憧れない理由はない。
なんて綺麗な女性なんだろう──いつものことながら、そう思う。
イルマ姉さんとも違う、万里さんとも雲母さんとも違う、お綾さんとも円蛇さまとも違う、でも、間違いなく彼女たちにも匹儔する美人だ。系列でいえばイルマ姉さんの顔貌に近いけれど、もちろん彼女のようにヤサグレている印象は微塵もない。理不尽な霊圧を感じさせないぶん、私にとってはきわめて安心感のあるアジアンビューティ。
ずっと見ていられる。見てたい。
でも、すぐに私は奏さんから視線を外した。そして、ふたたび遠くの星々を見わたす。二胡の音色をBGMに、混沌の大世界を一望。きっと、奏さんもそれを望んでいる。演奏に刮目するのではなく、ゆったりと耳を傾けていてほしい──そう望んでいるような気がする。
大世界──二胡の音色がよく似合う。なにしろ、遣隋使を派遣していた時代を生きた幽体、中国大陸文化を輸入していた飛鳥~平安時代を生きた幽体、メイド・イン・チャイナが物流のエンジンだった経済成長期を生き抜いた幽体、また、中華大人民国から移民したのち、日本と中国のルーツ的なつながりを拠り所にして幅をきかせている幽体──などが政治的実権を掌握しているせいか、中華的なテクスチャやレトリックに対しては寛容な世界。だから、路地のいたるところに漢字のロゴやタグが刻まれ、多くの繁華街がチャイナタウンの様相を呈している。横浜の中華街をイメージさせる街もあれば、いまはなき九龍城寨をイメージさせる街もある。ごく一部、本来の日本文化を取り戻そうとシュプレヒコールをあげている団体もあるけれど、やはり大陸のパワーは生半なものではなく、いまだ復権のフの字にもいたっていないのが現状。
でも、私は大世界の持つ独特な風情が嫌いではない。もちろんグリーンのころには大いに戸惑ったものだけれど、慣れてしまえば愉快のほうが勝る。老太フロントのドライな商魂さえ省けば、どこにいても異国情緒が胸をくすぐり、飽くことのない空想世界へと没入させてくれる。チープで、でもディープな夢心地へと。
奏さんの調べも相俟って、昨日の、無力の霧が晴れていく。可憐な囀りが心を煽り、インドアな私をアクティブな気持ちにもさせてくれる。繁華街にでも足を伸ばしてみようかな?──図らずもそう計画する望月空美と引きあわせてくれる。
数十層にも連なる地下街『南蓮フロント』か、それとも、骨董街『仙童フロント』にでも行ってみようかな?
店舗の数の豊富さや各店の中華的な外観で圧倒させてくれるのは南蓮フロント、でも、ちょっと遠いんだよなぁ。平坦な道のりだから自転車でも行けちゃうのが仙童フロント、でも、異国情緒は薄いんだよなぁ。
さて、情緒を取るか利便を取るか──彼女のおかげで、図らずも画策してしまっている。なんて愉快な画策なんだろう。
うきうきしながら、ふと、視線を落とす。
奏さんと、目が合った。
ちょうど、彼女も顎をあげたところだった。
軽く会釈。すると、眼下の美しいひとがわずかに私を微笑んだ……ような気がした。もちろん遠目だからわからない、けれど、水の波紋のように円みのある曲線を青龍刀の面に感じ取った。感じ取った直後、私の頭のなかをよぎる単語はいつも、なぜか「Rock'n'Roll」。
鋭さの中心にある円やかさが、私にはロックに感じるんだ。逆説的ロック。政治や民衆心理など、世のなかの不可逆観念に唾を吹きかけるソリッドな古典ロックではなく、吹きかけすぎて却って凝り固まってしまった不可逆ロックを微笑みの熱で溶かすような新時代のロック。Kelly 于文文『Want You Back』を思わせる、優しくも潔いロック。
だからか、すぐに彼女は顎をおろした。
ほんの一瞬の出来事だった。
一瞬だけど、毎朝の出来事。
不意に目が合い、私が軽く会釈をし、奏さんが微笑み、そしてまたおのおのの想いへと戻る──こんな毎朝。
ただそれだけの関係。
静かな関係。
美しい関係。
奇妙な関係。
ロックな関係。
壊したくはない関係。
だから、私は奏さんとコミュニケートしない。尾けない。話さない。知り得ない。プライベートサークルに入らない。
だから、彼女の名前も知らない。
毎朝、欠かすことなく二胡を奏でているから、私のほうで勝手に『奏さん』と名づけた。勝手に名づけ、勝手に心のなかで呼んでいる。
奏さんは私のことをどう思ってる?──それはわからない。コミュニケートしないのだから、そんなのわかりようがない。
いや、わからないのがいいんだ。
おたがいにわかりあわず、なのに、なんの支障もなく、寂しくもなく、ストレスもなく、むしろ、穏やかで、円やかで、静かな関係なのがいい。
こういう関係も、いい。
1年半ほどまえにあの角部屋へ越してきたらしい奏さん。はじめて彼女の二胡へと耳を傾けた日も、今日とおなじコミュニケーションだった。会釈し、微笑みをかえすという、ただそれだけのコミュニケーション。鬱いで寝込む日もあったけれど、でも、ほぼ毎日のようにつづいている。
失いたくない理想の関係。世人からは奇妙だと嘲笑われ、もしや眉をひそめられるかも知れないこの奇妙な関係もまた、私を安らかに活動させてくれるかけがえのない潤滑油なのだから。
| ≪ | 表紙に戻る | ≫ |