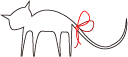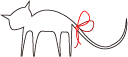プリペット通り四番地に住むダーズリー夫妻は、「おかげさまで、私どもはどこからどうみてもまともな人間です」と言うのが自慢の、おおよそまともではない人たちだった。
不思議とかそんな非常識はまるっきり認めない人種で、摩訶不思議な出来事が彼らの周辺で起こるなんて、ましてや彼らの大事な愛息子が彼らの言うまともではない人間になるなど、とうてい考えられなかった。
そんな彼らの愛息子の話をしよう。
その前に、彼らのことを少しだけ紹介しておくと、ダーズリー氏は、穴あけドリルを製造しているグラニングズ社の社長で、かなりの肥満体型の巨大な口ひげをもった豚。
奥さんの方はペチュニアといって垣根越しにご近所の様子を詮索するのが趣味の、悪趣味な痩せたブロンドの鶴といったところだろうか。
正反対の体型をした二人だが、息子については、どこを探したってこんなにできのいい子はいやしない、という親バカな意見は一致した。
実際息子のダドリーは勉強も運動も歌も絵も、何だって誰よりも上手くやってみせたし、誰も知らないようなことも知っていた。
まさに天才、神童と言われ、周りにはいつも人がいた。
ダーズリー夫妻が彼を可愛がる理由はそれだけではなく、とても二人から産まれたとは思えないほど見目麗しい子だったのが一番の理由ではないだろうか。
ニキビ、しわ、しみ、傷一つない白く陶器のように綺麗な肌にエメラルドの大きな瞳、桃色の小さな唇。
まるで女の子のような容姿だ。
綺麗なプラチナブロンドは男の子らしく多少短めに切られてはいたが、それも女の子がショートカットにしているようにしか見えず、彼のファンの女の子の間ではショートカットが流行った。
標準より背は低いがスタイルも良く、まさに天使といっても過言ではないほど可愛らしいダドリーは皆から大変愛されている。
たとえ、その天使のような容姿からは想像もつかないほど口が悪く、性格が悪くても。
ダドリーがどんなに皆から愛されていても、そうは思わない人間だって少なからずいるわけで、そんな連中から度々陰湿な嫌がらせをされていたダドリーは、先生に言いつけるでもなく、親に言いつけるでもなく、いつも自分自身の力で解決した。
悪口を言われれば言い返し、嫌がらせをされればまったく同じことをやり返した。
目には目を、歯には歯を、有名なハンムラビ法典である。
そんなわけで、彼をいじめるような愚かな真似をする者はいなくなり、同時に彼の性格も広まった。
それでも彼の人気は衰えることはなく、それどころかますます熱狂的な者が増えるという結果に終わったが。
彼には共に住んでいるハリー・ポッターという従兄弟がいる。
真っ黒な髪でダドリーと同じ色の瞳の丸い眼鏡をかけた痩せた男の子。
交通事故で両親を失い、額に一生消えない傷までできてしまった憐れな少年だと、ダドリーはペチュニアから教えられていた。
しかしダドリーは彼の両親が交通事故で死んだのではないことを知っていたし、彼が何者かなんて教えられずともわかっていた。
彼の両親はヴォルデモート卿によって殺され、彼の額の傷もまたヴォルデモート卿によってつけられたもので、彼は生き残った少年であることも、彼が復活したヴォルデモート卿を再び倒すことも何もかもダドリーは知っているのだ。
昔話をしよう。
彼は産まれる前は遠い東の島国に住んでいた。
その国の頂点はころころと忙しなく変わり、彼がいた頃は昔掲げた誓いすら破りかねない法律を作る愚かな者が頂点に立っていた。
しかし、住みやすく、四季がはっきりしている美しい国であった。
そこに住んでいた頃のダドリーは今と変わらず、本が好きな賢く美しい人気者で、やはり性格もよろしくはなかった。
一人が好きな彼はよく部屋で本を読み、いろんな知識を取り入れた。
図鑑、小説、漫画、ジャンルも様々で、ミステリー、ギャグ、歴史、スポーツ、ホラー、本当にいろいろな種類の本を読んだ。
その中でもダドリーが一番好きだったのがファンタジーだ。
ファンタジーと言ってもいろいろある。
まるっきり全てが不思議な世界であったり、現実に少しだけ潜んでいたり。
ダドリーが一番好きな本は不思議な世界と現実が半々に別れ、読む者を本の世界に引きずり込むような不思議でおもしろい本だ。
一つは、はてしない物語という、現実世界があるから不思議な世界もある、そんな二つの世界を幼い子供に両立させようとするお話。
この感想はダドリーのものであるから鵜呑みにしてはならない。
この、はてしない物語の上巻と並んで好きな本がハリー・ポッターだ。
彼の従兄弟と同じ名前で、容姿もとてもよく似ている。
本人なのだから当然だが。
それはさておき、昔のダドリーは若いうちにあっさり死んでしまった。
死因は交通事故だか病気だか、本人はそんなことに興味はなかったから覚えちゃいない。
彼にとって重要なのは死んだ後、自分が"生まれ変わった"世界がハリー・ポッターの世界であるということと、自分が"生まれ変わった"人物がダドリー・ダーズリーであったということ。
その二つだ。
原作のような容姿になどなってたまるか!
あんな喋る豚にブロンドのかつらをつけたような姿はまっぴらごめんだ。
一歳2ヶ月のダドリーは人知れず決意した。
ママがどれだけ口元にスプーンを持ってこようが必要以上は食べなかった。
元々ダドリーの許容量は人より少ないので食べられなかったというのが正しいが。
そんな彼の努力?が報われ、昔と然程変わらない姿で彼は今日、11歳の誕生日を迎えた。
もう原作が始まっている!
そう考えるだけでダドリーの胸は踊った。
目の前に山と積まれたプレゼントより、これから始まる物語の方が彼にとっては最高のプレゼントだ。
たとえ自分が魔法を使えない、ホグワーツに行けないポジションにいても、ハリー・ポッターの物語を本人の口から聞ける。
ダドリーとハリーの仲は悪くないどころか良好であったから、聞かずとも詳しく話してくれるだろう。
手紙がくるのはいつだったか。
きたら最初に僕が取って読んでやろうか。
一度も怒られたことはないけれど、そんなことをしたらさすがにパパは顔を真っ赤にさせて激怒するだろうな。
そんなことを考えて唇を歪める一方で、夏休みが終わってからのことを考えるとダドリーは憂鬱でたまらなかった。
夏休みが終わればハリーは魔法使いの名門ホグワーツ魔法魔術学校に行くのに、ダドリーときたら私立スメルティングズ男子校に行くことになっているからだ。
パパの話を聞く限り野蛮でつまらなそうな場所だ。
なぜそんなところを名門と呼んでいるのか、そこで一体何を学べるというのか、ダドリーは甚だ疑問だった。
まだ公立ストーンウォール校に行って先輩の頭をトイレに突っ込む方が面白そうな気さえした。