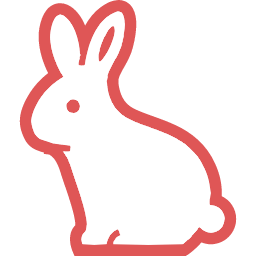ずばんっ!! ぼふっとベッドに落ちてきた。一瞬の出来事に、優希は茫然と目を見開いていた。知ってる動きだった。確かに、ログで見た通りの動きだったのに。
『次、はいって』
菊地原の声に、慌ててもう一度入る。視界に広がる世界が、ブース内から仮想訓練のための街中へと変わる。菊地原がこちらに走ってくる。優希はぎゅっと強く踏み込み菊地原を避けて回り込む。
「!」しかしその瞬間、菊地原の腕から生えたスコーピオンが優希の胴に深く刺さった。そのまま腕を振り切られると、胴がすっぱりと斬れてしまった。『トリオン体活動限界』無機質なその声を聞き、すぐにまた優希は簡素なベッドの置かれた部屋へと戻された。
スコーピオンの特徴を優希も気を付けていたはずだ。先ほど避けたときに優希はそのままフェイントを使って相手の懐に入ろうと考えていたのに。菊地原の動きは、あまりにも早かった。
もうリーチだ。どうする、どうする。考えながらも、まだ勝負の途中だ。キィィ……と独特な音でランダムに街中に転送される。今度は、道路のど真ん中だった。チームで戦うランク戦とは違い、個人ランク戦は相手の近くに転送されるため菊地原の姿をすぐに発見した。と同時に、彼からも発見される。
逃げ、なきゃ。菊地原と目が合った瞬間、優希はそう判断した。地面を蹴って菊地原と違う方向に走り出す。「ちょっと!」一対一の戦いだというのに逃げた優希に菊地原が不満そうに言った。
ただ動き回るだけの機動なら、こちらも速い。範囲内なら、ルール上移動して逃げても平気なはずだ。
なんでだ。なんで菊地原はこんなに速い。優希は走り回りながら頭を回転させた。
機動ならこっちだって分があった。だから優希はそれを活かしてフェイントをした。フェイントの動きが単調すぎた?それにしては、対処が早すぎる。
フェイントのこともそうだが、菊地原の動きが、ログで見たときより随分と速く感じる。思えば、ログで見た菊地原に負けた相手も決して遅いわけではなかった。むしろ、速い方なはずだ。なのに相対するとどうしてこんなに。勉強したログの内容が間違っていたのだろうか。本当は、もっと早く動けるのか?
……違う。どれだけ状況が悪くても、戦闘中は自分を疑うな。やってきたことは間違ってない。速いなら、理由がある。
理由。優希は顔を上げて地形を見た。それから、強く地面を踏んで立ち止まる。
「……逃げ回るのは、終わり?」
「お……終わり……!」
速いなら理由がある。理由、理由、それはわからないけど、きっと彼は。迷いが、ない。フェイントは利かない。それなら、戦い方は変える。
わたしは速い。さっきの菊地原くんが追い付けないくらいに。速いなら、やることは決まっている。わたしは一位。菊地原くんがいた時だって、訓練は一位だったんだ。ここは_____訓練と同じ地形だ。
地面を蹴って、隣の建物の壁をまた蹴って、上へ上へと上っていく。菊地原も上ってくるが、上は取った。そのまま建物を蹴って勢いよく下に落ちる。上に向かってくる菊地原と激突するときが、たぶん終結のときだ。
「!」
ぶつかる直前、ぎゅぱっ!と久野の両手からスコーピオンが伸びた。片手は菊地原を狙い、もう片方は____近くにあった壁を。
菊地原は自分に向かうスコーピオンを壊す。両手に一本分のスコーピオンを割いているのだから当然、耐久性は負ける。だけど、これでいい。ぎゅんっ!スコーピオンが壁を斬る重みで体を引っ張り、そのまま体を壁に引き寄せた。視界から消えた優希を追う菊地原。だが、一手遅い。追った瞬間、今度こそ伸びてきたスコーピオンに、胸を貫かれた。
「4対1……」
結局、取れたのはたったの一本だけ。試合結果を見ながらため息をつく優希の後ろから「不満なわけ」と菊地原が声をかけた。
「ふ、ふふ、不満という、か……最初の、2本が、あの、ちょっと……」
「まあ、最初はほんと出来の悪い試合だったしね」
「そ、そ……そう……」
一本取ったあとは、粘ったもののやはりあと一歩のところで負けてしまった。それでも、最初に比べればいくらかましだった。
「……あ、あの、」
「なに」
「あ……あい、あり、が、とう」
「……なんで?」
「た、たたかっ、くれて……」相対していたときは戦闘中ということもあり緊張しなかったが、試合が終わるとやはりうまく話せない。優希がどもりながら言うと、「僕から誘ったはずなんだけど」と菊地原に返される。
「い……いや、あの、わたしなんか、と、菊地原くんがた、たたた、戦ってくれて……」
優希の言葉に、菊地原がぐっと眉を寄せた。
「す、すぎょ、すぎょい、参考に、なったから……」
「ああそう」
うんざりとした顔をする菊地原に、う、うん、そう……と優希が小さく頷く。それから、二人の間に少しの沈黙が流れた。な、なにか言ったほうがいいのかな……優希が菊地原の様子を伺っていると、「久野」と名前を呼ばれた。
「ふ、えっ」
「なに」
「な、名前……」
「はあ? 知ってるでしょ。同じクラスなんだけど」
「そ、そそ、そうだけど……」と優希がごにょごにょと小さく言った。同じクラスだからって、名前を覚えてくれていたことは嬉しい。
「お前、B級に上がったならもっとそれなりの態度取りなよ。まだ上がれてない奴もいるのに、腹立つ」
「ご……ごご、ごめんなさ……」
「……」
「あの、で、でも、わたしはやっぱり……き、きくちはら、くんとは、く、比べ物にならない……から……」
「当然でしょ。Bに上がったばっかでなに言ってんの。これから上に行こうって人間が、なにびびった態度してんのって話」
「う、うえ、は……上がれない……」
「はあ?」
苛立ったような声だった。向上心もないわけ、と不愉快そうだ。
「お前、訓練頑張ってたし、そこそこ根性あるのかと思ってたけど、そんなもんなわけ」
「た、たた、隊、組めない……から……」
「隊?」
「隊なんて、そ、そんなのやっていけるわけない……B、B級、も、や、やってける、じじ自信、なくて」
だから……上には……。口にしながら、じわじわと自分の駄目さを再認識する。そのまま、じわじわと目に涙が溜まってきた。ボーダーに入ってまで、なにを言ってるんだろうか。こんな、訓練を受けさせてもらえる立場にまでなっておいて、今更。「……なにそれ」と菊地原が言うのが聞こえた。
「そんなもん、ソロでやってけばいいだけじゃん」
何言ってんの?とでもいいたげな言い方だった。しかし優希からすれば、菊地原こそ何を言っているのだろうと思った。「……そ、ろ?」聞き覚えのない言葉に、優希が聞き返した。
「なに、あんだけデータ調べて知らなかったわけ? ボーダーにはソロの隊員だっているし、そんなことが上に行けない理由なんて、甘えだね」
「ソロ……ひ、ひとりってこと……?」
「ソロって言ってんでしょ。一人にきまってるじゃん」
菊地原の言葉は、相変わらずとげとげしい。だけどそのときの優希には、まるで天使のような言葉だった。
「ひ、ひとり……! わ、わたしでもやれる……!?」
「……だから、さっきからそう言ってるんだけど」
「あ、あ、あ、ありがとう菊地原くん!!!」
ばっ!感動のあまり優希が菊地原の手を取った。その瞬間、「えっ」と菊地原が身を引く。しかしその手は、優希の両手に包まれたままだった。
「よ、よ、よかったぁ……わたしでも足手まといにならない……!」
「う、うれしい、うれしいよおおお……」と泣き出しながら大事に菊地原の手を握りしめる優希に、「な、なんなの、なんなのお前!」と焦った菊地原が言っていた。