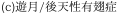花びらが降る。雪のように、ひらひらと、音もなく。
淡い色をした花びらは、街中をひっそりと流れる小川の水面に落ちてゆく。こんなふうに水に浮かんで流れてゆく花びらを花筏(はないかだ)と呼ぶのだと、教えてくれたのは彼女だった。
ざあ、と、風が吹いた。
僕は堅牢な橋の上から、風になびく花筏をぼんやりと眺めた。水面がゆらゆらと揺れる。花びらは、後から後から降りしきる。
「チアキも、ちゃんと次の恋してね?」
あの夜、彼女はそう言って淋しく微笑んだ。別れを切り出したのはそっちなのに、と、僕は少しだけ釈然としないまま彼女を見ていた。開け放した窓の向こうに浮かぶおぼろ月。春の宵闇は桜の匂いがする。
「じゃあね。鍵、返すね」
ことり。古びた狭いテーブルに、僕の部屋の鍵が置かれた。ふたりで食事するにはちいさすぎるね、なんて、あたたかなお皿を並べながら彼女は笑っていたのに。だけどチアキらしくていい部屋だよねと言いながら、狭い浴室や使い勝手の悪いキッチンに佇む彼女を、こんなにも鮮烈に思い出せるのに。
遠ざかる。遠く、遠くへ。
窓の外を見やると、オレンジ色の街灯の下、迷いなく歩いていく彼女が視界のはじに映った。はらり、桜がひとひら、夜風に乗って部屋に舞い込む。僕は花びらを指先で摘まむと、春の夜にそれを返した。
「どうしたの、ぼんやりして」
遠慮がちにシャツの袖を捕まれて、僕はあっという間に現実に引き戻された。
「何でもない。行こう」
桜の花は容赦なく飽きることなく毎年毎年咲きつづける。花びらが降る。僕の肩に、君の髪に。僕は君の手を引いた。
「ねえ千暁」
君が、僕を見つめて呟く。
「あのね。千暁が誰を想ってたって、わたしは千暁が一番好きだからね」
なんちゃって、と照れくさそうに笑って、君は僕の手をするりと離して二三歩先を歩く。風に舞う桜の中、僕はゆっくりと深呼吸した。
「…ありがとう」
ぐいっと腕を引き寄せて、僕は君を抱きしめた。あたたかい。君の優しい匂い。
…ああ、君と出会って、それまで茫漠と色を失っていた僕の世界は嘘のように色鮮やかに甦ったんだ。これ以上、僕は何を望めばいい?
「君がいてくれて、良かった」
聞こえるか聞こえないかの掠れた声で言った僕の背を、君は子供にするみたいにとんとんと撫でた。
「…ずっと、一緒にいられるかな」
「勿論。千暁が望むなら、百年でも千年でも」
花びらが降る。雪のように、ひらひらと、音もなく。
そうだ、花びらが水に浮かんで流れてゆく様を花筏と呼ぶのだと、今度は僕が君に教えてあげよう。
僕は降りしきる花の雨の中、そっと、君にキスをした。

さいごがきみでよかった
-END-
▼愛葬謌様に提出
┗さいごがきみでよかった