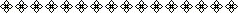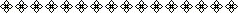冷えた視線
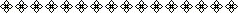
街角に立ち、青葉や他の少年たちとたわいも無い話をかわす。
今の所は街中も特に何事もなく、だから自分たちもただの子供達として笑い合っていられる。
そんな日常の平和な時間が貴重な物なのだと理解したのは、結局の所は非日常を味わってきたからだろうか。
逆に今では平和な日常の方が非日常に感じられる。
大分また感覚がずれてきているな、と帝人は思いふっと息を吐いた。
背中にちりちりと視線を感じる。いつの間にか慣れてしまった、強い圧力。
受け流して、無視して、どれ位それを繰り返しただろう。
姿勢を変えないまま、そっと前の建物の窓に目をやれば、見慣れてしまったバーテン服とサングラスの組み合わせが紫煙を燻らせている姿が映っていた。
ダラーズを抜けると言い放った時と同じ、どこか冷えた視線。
「…青葉君、ボク今日はそろそろ帰るよ。」
えー、とかまだそんな時間じゃないでしょーとか言う不満の声に用事があるからと笑って手を振り、背中を向ける。
視線はまだ感じる。追いかけてくる気配。
怖い、と思う。
結局の所友人の知人止まりで、ちゃんと交わした会話ときたら、あの喧騒の中のやり取りだけ。なのに、今更何の用があると言うのか。
分からないから怖い、怖い…楽しい?
最後の感覚に対してまた息を吐く。吸う。整える。
こちらを気にしているというのなら、接触する切っ掛けを作ってみるのも悪くない。
そんな事を考えながら、帝人はビルとビルの間の細い路地へ足を進めていった。
小さな背中を追いかければ、日の光が遮られるコンクリの谷間に小さな靴が落ちていた。
拾い上げて、視線を巡らせれば小さくもう片方の靴が大分先の方に佇んでいるのも見えた。
二つ目の目印を拾い上げて、持ち主を探す。追いかけていると言う感覚よりも誘われていると言う事実に昂揚する。
靴を置いていくなんてシンデレラか、等という胸の内の独り言は、曲がり角の先に落ちているネクタイによって、ヘンゼルとグレーテルの方が良いかと上書きされる。
森に2回も捨てられた子供は、1回目は小石を、2回目は千切ったパンを目印に落として。
鳥に食べられて家路を見失い、人食い魔女のお菓子の家へと辿り着く。
なら、俺は何なのだろう?
目印を食べる鳥というにはでか過ぎるから、赤頭巾を狙う狼あたりが似合う気がする。
そこまで考えて、また落ちていたものを拾う。シンプルなストラップの付いた、見覚えのある携帯。
くすくすと笑う声が聞こえて、それに振り向く前にサングラスに手を伸ばす。外して胸のポケットに仕舞う。
「お久しぶりです、静雄さん…何か僕にご用事ですか?」
白々しくそんな言葉を吐きながら、積み上げられたビールケースに座り込んで少年が笑う。
軽く膝を組んで座り、、薄暗い中ではその裸足の白さが妙に目立つ。
「…落し物だ。」
どう切り出すべきか分からずに、取り合えず腕の中の物を示す。
ありがとうございます、と礼を言いながらも動く気配の無い相手に、一歩踏み出して押し付けるように突き出す。
それでも動かない。
そのままじっと見上げてくる視線に痛みさえ感じる。錯覚だと分かっているそれに、少しだけ愉悦を感じる。
「…僕の事見てましたよね?」
何でです、と答えを強請る声。
何の関わりも無い自分を見上げて、信じられないと叫ぶ様に感情の冷えていったあの時の瞳が、今また自分を見上げている。
自分の言葉が、この子供を揺さぶる力があると気づいたのはあの時だ。欲しい、と思ったのはその後だ。
感情を硝子越しに押し込めて、伏せた獣が獲物を追う様に見つめ続けて。
凪いだまま見上げてくる冷えた視線に、剥き出しにした熱を絡めた言葉を吐き出す。
「…お前も、落し物か?」
拾っても良いか、好きにしても良いかと屈みこんで覆いかぶさる様に問えば、くすくすと笑ってお好きにどうぞとうなじへ手が回る。
引き寄せられる口づけは下から、噛み付くような口付けは上から。
そのまま帝人を抱き上げて、静雄は路地を後にした。
ちなみに、近場のラブホテルと自分の家、どちらがここから近いだろうかと静雄が思案している事を、裸足のままの帝人は知らない。
シンデレラの罠に狼が嵌ったのか、それとも魔女を狼が食べてしまったのか?
その答えは闇の中。
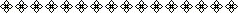
●肉食系静帝企画さまに提出させて頂きました。
●素敵企画に参加させて頂き、嬉しかったです。
●ありがとうございました!
戻る