「冷静に考えて、エッ、これ終わらなくない?」
脳味噌が一瞬空白になるという、絶望状態に陥る前に来る瞬間は、日付もとうに越え、学校始業日になってしまってから1時間47分と約23秒後に訪れた。
目の前のテーブルには、参考書と解答集とペンケースが広がる。テーブルを跨いだ向こうには、全く同じセットが反対方向を向いて広がっている。向かいに座る靖友くんの分だ。
「ハア?なに言ってンだオメー」
「や、靖友くん?これ、絶対に終わらないよ?あと始業式まで、えーっと…」
私から見て後方に当たる壁に掛かった時計を見るためにわざわざ体を翻し、
「…12時間ないよ!?」
と、計算ができなかったことを誤魔化すように慌てて言った。
「はいはい、計算できなかったんだナ」
だけれど靖友くんにはあっさりバレていた。こっちをちらりとも水に、手元の数Bの復習ワークにぐりぐりと文字を書きこんでいた。いつもと変わらず(今この状況だけで考えるといささかのんびりしすぎだと感じてしまうくらいに)、彼のペンが動いていた。
「なんでそんな靖友くんは落ち着いてんのよお」
力ない声を上げる。カーペットの上にある他の教科のワークやプリントを見つめると、気が遠くなった。
「終わると思ってるからに決まってンだろ」
「ええ、嘘」
「ほんとだほんと。ぼやぼやしてる暇があるなら早くやった方がいいんじゃナァイ?」
ジトっとした目で見られながら正論を言われたので、咄嗟に喉元から出かけた言葉をなんとか飲み込んで、手元の問題に目を落とした。XとYとマークシート番号が踊っている。
なぜ私たちがこんなものに悩まされているのかと、根本的な話をしよう。年末と正月をスキップと鼻歌交じりに満喫した私を待ち受けていたのは、数日後に迫ったセンター試験と言う魔物と、その魔物を倒すために学校から授けられたセンター試験対策用の問題集たちだった。言ってみれば王様からもらった剣と盾みたいなものだ。なのに、それらが私の首を締めてくるのだから笑えない。
年末に、塾で最後の授業を受けたときに他校の子と話したところどうやらその子の学校には三年のセンター前のこの時期、当たり前だけれど宿題と言うものは出ていないらしい。こちらの事情を話すと「えー、箱学宿題あんのー最悪だねー」と、正真正銘他人事を言われてしまった。そりゃあ私だって終業式を迎えるまであるとは思わなかったさ。宿題というダークホースなんて。ただ、それがどうやら我が校の伝統らしく、試験まで学校が全力でサポートするという方針らしい。こちらからするとやらなければいけないことが二倍に増え、はた迷惑な話だ。
「…ねえ、靖友くん。あとどれくらい?」
蚊の鳴くような声が出てしまった。我に返るともちろんワークは全然進んでいなかった。依然として数字と記号が紙上を踊り狂っている。
靖友くんは集中しているのか、返事をくれなかった。心が折れかけたが、仕方ないと諦めペンをしっかり握り直す。
ちゃんと考えれば分からないような、難しい問題ではないのだ。いや、確かに突如応用レベルの設問が出たりするけれど、基本的に基本レベルの問題しか出ない、出ない、出ないはず。
なのだけれど。
次のページをめくると、問の設問1から解法の全く予想できない問題が出て、ペンを握る手が止まってしまった。
「やっぱり無理だ…」
思わず弱音を口に出してしまう。
「なにブツブツ言ってンだなまえ」
突然の声に、びくっと体を震わせた。問題集から顔を上げると、ため息をつきながら靖友くんが私を見ていた。
「え…なんにもないよ」
その目つきが怖くて、思わずそんな言葉を返す。
「嘘つけェ、なんにもなかったらそんなだらだら弱音吐かねえダロ」
もう一つ大きなため息をついて、靖友くんはペンから手を離した。「どうしたの?」と聞くと「休憩だ休憩!」と返された。
すっかり静まり返ってしまったリビングに行き、お茶の入ったボトルを冷蔵庫から取り出す。部屋に置きっぱなしのコップに注ぐために、ボトルを持ったままなるべく静かに扉を閉めて、自室に戻った。
「お茶持ってきたよ」
帰ると、靖友くんはベッドに寝転んで、私の少女漫画を読んでいた。すっかりくつろぎモードのようだ。靖友くんは、メリハリのある性格と言うか、メリハリがありすぎる性格と言うか…とにかくはっきりしている人だ。つまり、休憩とか骨休めが上手と言うことで、私はそれができないのでいつもすごいなあと思ってしまう。
「おう、サンキュー」
漫画から視線を外した靖友くんは、体を起こしてベッドに腰掛ける。トポトポと言わせながらコップにお茶を注ぎ、そのまま靖友くんに渡した。
「疲れたなあ」
私は靖友くんが腰掛けるすぐ横のカーペットに腰を下ろした。ベッドを背もたれにして体を預ける。
「なまえはほんとよくくよくよすんなァ」
「そんなことないよ、普通だよ」
「ていうかこの漫画面白い」
「そ、そう?持って帰ってもいいよ」
靖友くんはこう見えて結構少女漫画もお読みになられるのだ。私は麦茶を煽った。火照った体に冷たい麦茶が気持ちいい。
「おばさんたち寝てんのか」
「うん、ぐっすりしてるみたいだよ。あー私も寝たいよ。眠いよ」
「そんなんオレも一緒だっつーの」
机の上に広げられた宿題を見やる。
「…靖友くん、本気でアレが終わると思ってる?」
「アァ?当たり前だろバーカ」
首を限界まで後ろに傾けて上を向き、ベッドの上にいる靖友くんを見ると、剣呑な顔をして人差し指で鼻を潰された。地味に痛い。
「まじスか」
「まじだよ」
大真面目な靖友くんの答えを聞いてため息をついた私は、そのままベッドに頭の全体重を預ける。部屋の真ん中についている電灯の光が眩しくて、思わず瞳を閉じた。私には、今どうしたって明るい未来が見えないのだから、困ってしまう。
宿題が終わらないどころか、数日後に迫ったセンター試験だってそうだ。それから、本試験だって。大学に行けるかどうかも、その先も、私にはきちんとその図が描けない。四月からも靖友くんの隣で、私は笑っていられるのだろうか。
「…ハァ、なんつー顔してンだなまえ」
いつの間にかしわの寄った私の眉間を靖友くんの指が伸ばす。直前まで麦茶の入ったコップを支えていたその指はひんやりと冷たかった。
「…靖友くん。私、」
私が震えそうな喉を抑えながら、言葉を発しようとすると、
「ストーップ、その先はいったん保留だ」
と、靖友くんがその大きな手で今度は私の口を塞ぐ。
「むごふご」
びっくりした私は声をあげたが、くぐもった声が音になっただけで意味のある言語にはならなかった。
「あー…お前さァ、どうやってオレと付き合ったんだァ?」
唐突な質問に戸惑う。ゆっくり手が私から離れて、口が自由になる。
「えー…あー…告白した。好きです、付き合ってくださいって」
当時のことを思い出す。同じクラスでもなんでもない私は、当時自転車に夢中だった靖友くんとの面識が全くと言うほどなく、完全に私の片思いだったわけだ。それをなんとかしようと、ある日なんとか彼を呼び出して、学校内で告白した。確か放課後の、夕日が差した廊下だったと思う。
「そうだろ?でもオレ、それまでなまえのことあんまり、っつーかまったく知らなかったんだよな」
「うん、そうだね」
告白したとき、あんぐりと口を開けた靖友くんはその場でフリーズしてしまった。いたたまれない沈黙のあとに靖友くんが発した第一声は「お前、相手勘違いしてんじゃナァイ?」だった。手紙ならまだしも、直接告白しているのに勘違いするも何もないだろう。後から聞いたところ、東堂君や新開くんに告白する子たちの伝達をすることがしばしばあったらしい。
「だから、もしオメーが告白してこなかったら、気付かないままだったわけだろォ?オメーのことも、オメーの『好き』も」
「…確かに、そうだねえ」
そんな世界があったのかもしれないと思うと、今の私はぞっとする。最後のインターハイのことや、練習の合間を縫って行ったデートとか、図書館での勉強や、こうやってテスト前にカンヅメすることや、そういうことが少しも起こらない世界だ。
頭を起こして靖友くんの方を体ごと振り返ると、腕がにゅっと伸びてきて、ぐいっと引っ張り上げられた私はベッドに座ることになった。靖友くんと体ごと顔を見合わせる。
ふぁ、と。靖友くんが大きな欠伸をした。気が抜けて顔が緩む。
「それでいいンだよ。なまえ、さっきから怖い顔ばっかだぞ」
自分の目を擦りながら、靖友くんが言う。そんな顔をしていただろうか。だけれどそんなこと言ったって、靖友くんは普段から怖い顔ばかりだ。
「だから、オレが終わるっていったら終わるンだよ」
「はあ」
突然話が飛んだので、靖友くんの言うことがうまく汲み取れなくて、気のない返事をする。
「…言葉にすることがどれだけ力になるか、お前もうよく知ってんだろ?」
だって、大好きなオレに好きになってもらってンだもんナァ?
靖友くんの目が途端に細い線になる。その顔をじっと見つめる間もなく、細くて筋肉質の腕がにゅうと伸びてきて、私の背中に回る。ぐいっと引き寄せられて気付けば私は靖友くんの胸の中に倒れこんでいた。
顔がべしっと潰れたけれど、不満を言おうとした顔がどうしても緩んでしまう。靖友くんはなんでか、時折甘いミルクみたいな匂いがする。目を閉じたらいつの間にか眠ってしまいそうな、優しい匂いだ。
「じゃあ、絶対終わるね。宿題」
「おお」
くぐもった相槌が頭上から聞こえる。
「それに、絶対上手くいくね。センターも、受験も」
「そうだ。オメーはオレと一緒に四月から洋南大生に決まってんダロ」
後頭部の辺りに痛みが走る。どうやらデコピンをされたみたいだ。
甘い雰囲気にもう少し酔っぱらっていたかったが、机の上に置かれた麦茶の氷がカランと音をあげて融解した。
「…宿題、がんばりますか」
「そーだナ」
ベッドから飛び降りて、二人でカーペットの上に座った。ペンを握って、馬鹿みたいに二人で笑い合った。私は今だって、馬鹿みたい靖友くんにドキドキしている。ペンを動かしながら、付き合い始めたころからのことをのぼんやり思い出す。靖友くんから教えてもらったことが山のようにあって、それをずっと靖友くんのおかげだけだと思っていた。しかしそれは、私が作り上げたものでもあったのだ。言葉にすることはとても強かったのだ。まったく、靖友くんには教えてもらうことばかりだ。だけれど、だから私は、願う。
これからも願い続けるために、戦うのだ。
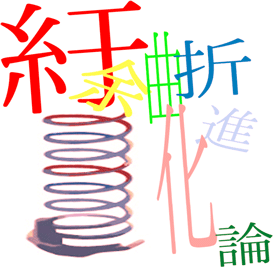
受験生の皆さん、どうかどうか頑張ってください!
(140112)