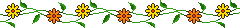殺し屋探偵学生時代話
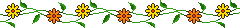
「はじめまして、君とパルトネルを組むことになったナナシです。よろしく」
「・・・S・スクアーロだぁ。いいかぁ、俺の足を引っ張りやがったらテメェをたたっ切るからなぁ!!」
「はぁ」
これが当時13歳のナナシと10歳のスクアーロが初対面の際に交わした会話であった。
『工場』と呼ばれるナナシとスクアーロが通う学校には、パルトネル授業というカリキュラムがある。不定期に行われるそれは、学年を問わない男女のペアで与えられた課題をこなすというものだ。卒業間近であるナナシの最後のパルトネルが、小生意気で自分より3歳年下のスクアーロだった訳である。パルトネルは事前にくじで決められており、相手がどのような落ちこぼれであってもパルトネルになった以上は協力して課題を行わなければならない。その点は、ナナシもスクアーロも優秀な生徒であったので、全く問題はなかった。
「あらスクアーロ!久しぶりじゃない、私以外のパルトネルはどうだった?」
「・・・・・・テメェか。さっさと俺の前から消え失せろぉ!」
「酷いわねスクアーロ。2年前のパルトネルにそんなことを言うなんて」
美女ではあるが如何せん化粧の濃い女がスクアーロの腕に自分の腕を絡めてきた。彼女の名前はリジーナ、以前のスクアーロのパルトネルである。殺しだけなら女生徒で一番と言われているが、自分勝手でヒステリックなその気性と咄嗟の判断力の無さが災いしてスクアーロの足を引っ張ることしかしなかった。当の本人はスクアーロから頼りにされていたと思い込んでいるのだから、スクアーロからしたら腹立たしいにも程がある女だ。
「あなたの今度のパルトネルは・・・あぁ、ナナシ・ジャッロね。チビの変わり者だって有名な」
「あ゛ぁ?」
「そいつの家ってミラノでは有名な資産家らしいわよ。そんな家に生まれた人生の勝ち組がわざわざこんな人間のクズ予備軍の集まるこの学校に来るだなんて、とんだ物好きよね」
そのあとのリジーナの話はスクアーロにとってはどうでもいいものだったので聞き流していたら、言いたいことを言い終わったのかさっさと別の男のもとに去っていった。相変わらず顔のいい男とあらば見境のない奴だ。
「・・・ケッ、俺と同じようなもんじゃねえかぁ」
スクアーロはリジーナの後ろ姿を一瞬睨みつけて、さっさと昼食を食べに行った。
「スクアーロ君ってシチリア出身?」
「あ゛ぁ?それがどうしたぁ?」
「いや別に深い意味はないけど。シチリア訛りだから、そうなのかなって」
2人のパルトネルとしての初めての授業の説明を受けている最中、ナナシはそう言った。もとより授業の説明を真面目に聞く者などいないのでそこら中で話し声が聞こえる。自分のイタリア語は訛りが強いことくらい誰もがわかるので、スクアーロは特に思うことはなかった。
「あと、スクアーロ君ってそれなりに良い家の生まれでしょ」
ナナシがさも当然のように言った言葉に、スクアーロは思わずぎくりと身体を強張らせた。馬鹿な、何故わかった?
「う゛お゛ぉい、何故・・・」
「剣を使ってるのは左手なのに文字を書くのは右手。殺しの手段を利き手じゃない手で扱うだなんて思えないし、両利きならスクアーロ君だったら二刀流にするだろうし。恐らく本来の利き手は左手なんだろうね。でもスクアーロ君の文字は利き手じゃない手で書いたとは思えない程綺麗。そこまで徹底的に矯正させる必要があるのは、周りの目が集まりやすい良家の人間くらいなものでしょ」
全て事実だからスクアーロは驚いた。確かに自分はシチリアじゃそれなりに権力のある地主の生まれで、他人に見られる時に恥をかかないようにともともと左利きだったのを矯正して右手でも利き手並に動かせるようにさせられた。しかし剣を使う時は本来の利き手じゃない手で扱うと剣にムラが出る為、左手で扱うようにしている。
「あと、所作」
「所作だぁ?」
「わざと乱暴にしてるけど、わかっちゃうんだよね、もともとの綺麗さが。背筋とか真っ直ぐで綺麗だし、立ち姿も様になってる。そういう家って、立ってる姿勢だけでもいちいち色々言われるんだよね」
「・・・成る程、テメェも同族だからわかるって訳か」
自分のことばかりが勝手に相手に知られて腹が立ったスクアーロはお返しとばかりに言い返してやった。ナナシはキョトンとした顔を浮かべてスクアーロを見返す。・・・さほどダメージはないようだ。
「知ってたんだ。ま、隠してる訳じゃないから別にいいんだけど。私もそういう教育受けてきたから、自然とわかっちゃう訳」
「・・・シャーロック・ホームズを相手にしてる気分だぜぇ」
「私はホームズよりポワロ派なんだよね」
「知るかぁ!!」
どうでもいい主張に腹立ちながらもスクアーロはナナシに一目置いた。この女は、少なくともリジーナなどよりも、ずっと優秀なパルトネルだ。
「・・・卒業課題めんどくさ・・・」
ナナシは大量の課題を前に崩れ落ちた。この1年を終えれば卒業であるナナシら最上級生は、とてつもない量の卒業課題をこなさなければならない。その内容はどれもこの先必要なのか疑問に思えるものなのだが、卒業後に殺し屋になろうが密売人になろうが今現在は名目上は学生である。学生の本分は勤勉である、だなんて古臭い戯れ事を盲目的に信じるような殊勝な考えをナナシは持っていない。如何に楽をしてこの卒業課題をこなすか考えていると、大量の課題の向こうの椅子に見覚えのある男が座った。課題越しに銀色の髪が見える。
「う゛お゛ぉい、これは一体何なんだぁ!!」
「卒業課題。スクアーロ君も3年後にやることだよ」
「何なんだそりゃあ?ここはハイスクールかぁ?」
「名目上はね」
パルトネルとなってから1ヶ月、スクアーロが自分を信頼しつつあるのをナナシは感じていた。同じように、ナナシもスクアーロを信頼しつつある。なかなかいいパルトネルなのではないかとナナシは思った。過去2回行ったパルトネル授業の歴代パルトネル達がどれほど使えなかったか、スクアーロの優秀さを見ているとよくわかる。
「そうだスクアーロ君、これ手伝ってよ」
「あ゛!?」
「これはスクアーロ君でもできると思うからさ。さすがにこの量を卒業までに終わらせるのは無理だよ」
「う゛お゛ぉい!!!知るかぁ、テメェでやれぇ!!!」
「これを終わらせるのに精一杯で、パルトネル授業に集中できなかったら嫌だし。お願い」
「・・・・・・・・・・・・このドカスがぁ!!!」
「ありがとう、スクアーロ君」
なんだかんだで卒業前の1年を、このパルトネルと有意義に過ごせそうだ。ナナシはそう感じた。
香様からのリクエストでした。リクエストありがとうございました!