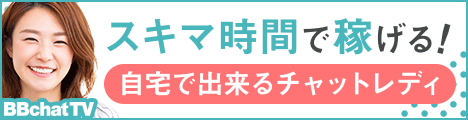部活から帰ってきた兄の詩(うた)をすぐさまリビングのソファーに押し倒して、栄太(えいた)は胸元に顔を埋めて深く息を吸い込んだ。
Tシャツに染み付いた土っぽい匂いや汗の匂いが入り交じった詩の匂いを堪能して恍惚とした吐息を吐き出す。
「帰ってきたとたん盛ってんじゃねーよ…っ」
「…はぁ…、だって…兄ちゃんすぐシャワー入っちゃうから。この匂いが嗅げなくなるなんてもったいないじゃん」
「知るか…っこの変態が」
うんざりとした声を気にせず栄太は詩の首元へと顔を寄せた。
胸よりも一段と濃くなった詩の匂いにますます吐息が熱くなる。
「いい匂い…」
「…っ!ん…!…くっ…」
うっとりと呟いて栄太は耳に舌を伸ばした。
耳のふちをつぅっとなぞり、軟骨を緩く噛む。
そんなくすぐるような愛撫に合わせて詩はビクビクと肩を震わせた。
「っは…ぁ、あっ…!」
濡れた舌は凹凸を丁寧になぞって耳の穴まで優しく舐め上げていく。
熱く柔らかな快感と、ピチャピチャと鼓膜から脳に直接響く水音が詩の情欲を揺すり起こしていく。
「くっ…、そんな…っ耳ばっか舐めんなって…!」
「…ん…? 早く他のところも舐めてほしいの?」
「ばか!そんなこと言ってねーだろ!…っんん…!」
耳を舐めながら栄太は詩のシャツをまくり上げる。
指先に触れた硬い腹筋にはしっとりと汗が滲んでいた。
思わず「美味しそう」と呟いて、体を起こした栄太はすぐさまその腹筋に舌を這わせた。
ビクビクと痙攣する筋肉をじっくりと何度も舐め上げて、へその窪みを舌先でぐりぐりとえぐり、そしてあえて乳首をはずして胸部を舐め回す。
汗と詩の匂いを味わいつくし、栄太の興奮は最高潮に達していた。
息を荒げながらやや乱暴気味にシャツを脱がせると、栄太は腕を上げた詩の脇にむしゃぶりついた。
「ひあぁっ!」
気持ちよさよりもくすぐったさが勝っている感覚に詩は堪らず身をよじらせる。
しかし、脇なんてあられもない所を舐められているという羞恥心がその刺激を快楽へと変換していってしまう。
甘い快感と栄太の熱情に飲まれて詩もすっかり上気させられてしまっていた。
「…兄ちゃんの体、どんどん敏感になってくね。もう全身が性感帯になったんじゃない?」
「お前の…っせいだろ…!毎日毎日こんな舐め回しやがって…!」
「ふふっ…こんな体じゃもう女を抱くことなんてできないかもね」
「うるせっ…ふぁあ!」
睨み付けてきた詩に構わず栄太はずっとおあずけにしていた乳首を舌でぐりっと押し潰した。
とたんに強い快感が弾け、詩は表情を崩して甘ったるい悲鳴を漏らしてしまう。
「あっ、くぅっ、んんぁ…っ!」
尖らせた舌先で左右にゆさぶり、ちゅっ…と吸い付いて軽く引っ張りながら唇を放す。
もともと固く立ち上がっていた乳首は更に膨張して赤く色づいていく。
栄太の舌や唇、さらには指で弄ばれるたびに詩は体のあちこちをビクつかせて淫らな喘ぎをこぼす。
「っは、あ…!ぁ…っえ ぃた…ぁっもう…苦し…っ」
執拗なまでの乳首の刺激に悶えながら詩は悩ましげな声を上げた。
散々欲情を煽られ、下半身が痛いほどに張りつめていたのだ。
腫れ上がった肉棒から競り上がる疼きに耐えきれず詩は涙のたまった目で栄太を見つめる。
苦しそうに必死に訴えかけてくるその蕩けた兄の顔を見るのが栄太は大好きだった。
「堪え性がないなぁ兄ちゃんは。……うわ、パンツどろっどろ。嫌そうなふりして、俺に舐められてこんなに興奮してたんだ」
ジャージを脱がされあらわになった下着にはすでに大きな染みができていた。
肉棒は形がくっきりと浮かび上がるほど剛直してドクンドクンと脈動を繰り返している。
発情をありありとさらけ出してしまっている下半身に栄太の視線が突き刺さり、再び羞恥心をぶり返した詩は顔を歪めて唇を噛みしめる。
だが発情しきっているのは栄太も同じだ。
ペロリと舌なめずりをすると、栄太は急く気持ちを押さえて下着の染みに鼻先をつけ、深く息を吸った。
性器特有の青臭さ。汗や尿。下着の中に充満している雄の匂いが栄太の意識をとろけさせていく。
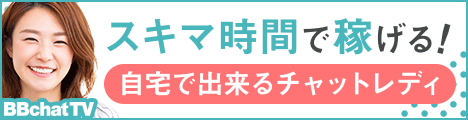 
「…はぁ…、ヤバい…」
うわ言のように呟きながら下着を引き下ろして、今度は肉竿の根本に鼻をつけて匂いを吸い込む。
濃厚な香りとともに性器の鼓動や熱を感じて栄太は我慢できず自分の性器を掴んでしごき始めた。
「この匂いだけでイけるかも…マジ兄ちゃんの匂い最高」
「はっ…、気持ち悪いこと言うなよ…!」
悪態をつきながらも、詩は早く自身をくわえてほしくてたまらなかった。
先端からは止めどなく蜜が溢れ、自らの腹を濡らしていく。
栄太の息が吹きかかるたびにゾクッと疼いて全身が震えた。
早くくわえて、めちゃくちゃにしゃぶってくれ。今すぐにそう叫びだしたかったが、羞恥とプライドが邪魔をして詩は唇を噛んで待ちわびることしかできなかった。
「っふぁ…!ぁ…!ぅぅ…っ!」
ようやく伸ばされた栄太の舌。しかしその動きは詩が望んだものよりもはるかに優しく、緩やかだった。
「くっ…ぅぅ…っ!」
根本から先端へ。熱や味を確かめるようにゆっくりと舌を這わせ、そして先端から再び根本へと戻っていく。
それを何度も繰り返して唾液まみれになった竿をやっと口に含む。
だが上下に動いたりはせず、栄太は口いっぱいに含んだまま動きを止めてしまった。口内中に広がる香りに恍惚としているのだ。
煮え切らない快感に苛まれ続け、詩はもはや限界だった。
顔をくしゃくしゃにして栄太を見つめ、熔けきった吐息とともに口を開く。
「栄太…っ!もう、焦らすな…!早く…っイかせて…!」
「んっ…!あぁ!ごめんっ。兄ちゃんの匂いに夢中になってた。焦らすつもりはなかったんだけど」
詩の言葉で我にかえった栄太は、へへっと照れくさそうに笑いかけた。
そしてまた竿をくわえ、望み通りに深く強く詩の欲望をしごき立てた。
「あっ…!くぁっ!あぁあっ」
極限まで焦らされた肉竿は栄太からの熱い刺激を受けて打ち震えた。
瞬く間に快感が駆け抜けて詩の頭が真っ白に染まっていく。
自らも下着を下ろして激しく自身を掻き立てながら栄太はガチガチに反り返る肉棒を唇でしごき、亀頭をぐるぐると舌で磨き、本能のままに喰らいつくす。
限界はあっという間に訪れた。
一気に煮えたぎった欲望が迫り、背筋がビリビリと甘く痺れて詩は激しく仰け反った。
「いくっイク…!あっぅああ!出る…っ!あぁあああっ!」
勢いよく放たれた精液。それを口内で受け止めて栄太はそのまま自らをしごき続けた。
口いっぱいに広がり鼻を突き抜ける精液の匂いに熱情を焦がし、そしてほどなくして際限まで高まった欲をドクドクと解き放った。
「んっ…く」
こぼれないようにゆっくりと竿から唇を離し、口内に溜まった精液を名残惜しそうに飲み込む。
散々弄ばれたのと部活の疲れもあったのか、詩はいつの間にか深い寝息を立てて眠ってしまっていた。
口の端から少しこぼれてしまった白濁を舐めとりながら栄太は詩の肩を軽く揺すってみる。
「兄ちゃん…兄ちゃん?」
詩は起きる様子がなく、詩は今日はねちっこくやりすぎたか…?と反省した。
…だがすぐに、あ でも兄ちゃんが起きるまで好きなだけ匂い嗅ぎまくれるじゃん。よっしゃ。
と、あっさり気持ちを切り替えてニタリと微笑んだ。
「しばらく起きないでね…?」
そんな勝手な願いを囁いて、栄太はそっと詩を抱きかかえて詩の部屋へと向かった。
end

先生、キスして、Hして。玩具好き先生と夜の教室で初H(マンガ)
|