by Lewis Carroll
不穏なマーリン | 表面上は甘ほの、心内は不穏な感じ

「じゃあ、俺ちょっとご飯食べてくるね」
必要な資源を得るためのレイシフト周回、その隙間時間で栄養を摂るべく藤丸立香は食堂へと向かった。それを見届けたマーリンは、さて自分はどうしたものかと考える。一般的にサーヴァントは人間的営みを必要としないが、このカルデアに置いては凡その活動は「嗜好」として許されている。食事もその一つだ、料理好きというサーヴァントがいることもあり、カルデアの食堂は人理焼却事件が起こる前よりも賑わっているように思う。
「あら、こんにちは夢と花の妖精さん」
「やあナーサリー・ライム、そんなに急いでどこにいくんだい」
「赤い小人さんからお菓子をいただいたのよ」
くすくすと笑いながら、秘密を教えてくれるようにしてナーサリー・ライムが隠し持っていた包みを開いて見せてくれた。中には色形様々なクッキーが詰まっており、まるで小さな宝石箱のようだった。
「この子たちは臆病だから、こうしてわたしが隠してあげるの。でも好奇心旺盛でね、悪いひとに唆されてどこかに飛んで行ってしまったら大変だわ」
「ああ、それが良いだろう。クッキーたちには、君から親の言いつけは守るようにと言いきかせておくれ」
「ふふ、ええもちろん。そうするわ、ねえ妖精さん」
小さな手が屈んで欲しいと手招きするので、マーリンは彼女の前に膝をついた。ナーサリー・ライムは包み紙からひとつ、ハート型のクッキーを取り出した。
「オイスターの子どもたちでは足りなかったのね、わるいセイウチさん」
クッキーをマーリンの唇に挟みながら、「だけどもう太陽の沈まない夜は明けてよ」とナーサリー・ライムが歌う。雲の合間をジャンプするような軽やかな足取りで友人たちのもとに走っていく小さな最中を見つながら、マーリンは唇で挟んだクッキーを指で口の中へと押し込んだ。バニラが香るクッキー生地も、アイシングの甘みも何も感じない。さくりと何かが砕ける感触、砂が口に入ったような不快感。押し殺して呑み込めば、口の中が乾いて滲むように唾液が分泌される。
____(おなか、すいた)
小さな、マーリンが言う。
気が遠くなるほどの昔、彼方に封じ込めた冬の記憶。薄汚れた灰色の髪に淀んだ瞳の子どもが視える。本来彼が必要とする栄養の一切を与えられず、骨と皮だけの身体。こけた頬、窪んだ目元、血が滲む布で“まあるい”耳。聞くに堪えないしゃがれた声で、子どもが繰り返す。
お
な
か
が
す
い
た
「あれはぜんぶ、ぼくがたべていいんだよね」
子どもが指をさす、その先に何があるかマーリンは良く解っていた。子どもの言葉が頭の中をめぐる、口の中がまるで餓えた獣のように涎で溢れていた。獲物を前にステイを強いられた空腹のペットのように体が震え、たらりと口の端から欲が零れ落ちる。
「だって、ぼくのためにうまれてきたんだから」
返事の代わりに、ごくりと喉が鳴った。無いはずの胃が、空腹を訴えて泣いている。その音はまるで、どうしようもなく醜い生き物の咆哮のように聞こえた。
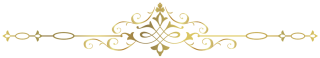
(_______これで、最後かな)
本日のレイシフトで収集した資材のチェックが終わり、専用の機械に入れて魔力品質を確認する。確認には1時間程度かかるので、仕事はこれでひと段落となる。ひつきは手持ちのバインダーを机に置いて、ぐいと背伸びをした。
今日は収穫量が少ないので、いつも二人係で熟しているチェック作業だが問題なく終わりそうだ。ドーム型の機械に並べられた禍々しい蛮神の心臓と渾沌の爪、呪獣胆石。規定水準を満たした素材なら、品質確認後に保管庫へと移動となる。それ以外なら既定の手順に従ってリサイクル、規格外でも上質な魔力リソースに変わりないのでサーヴァントにとってはおやつがわりになると言っていたがどうなのだろう。
とてもではないが、このままのビジュアルでは食欲が湧いてこないなあ。ドームのガラス越しに素材を見つめていると、ふわりと優しい香りがした。覚えのある芳香に嫌な予感を感じた次の瞬間、後ろから圧し掛かるようにして現れた男に、ひつきの身体はあっけなく機械の上へと押しつぶされた。
「へぶ」
「_____ばあ! 頼れるマーリンお兄さんの登場だぞぉ、おどろいたかいひつき」