暴食少女と喧嘩人形(平和島静雄)
矢包ひなみは、食べることが好きだ。
何時からそうであったのか定かではないが、物心着いた時には既にそうであった。一日三食、一時はCM効果で一日五食など騒がれていたひなみの基本は一日八食プラス間食が基本だ。誰かが止めなければ取り敢えず食べる(あるいは寝ている)ひなみを、流石に心配した親が一度かかりつけの病院に診て貰ったことがある。話を聞いた医師は、幾つかの検査をした後に言った言葉と言えば『成長期、ですから…』
ひなみの親は愕然とした。医者は苦笑いをして誤魔化した。その後ろで、当時小学校3年生のひなみは飴がいっぱいつまったビンを両手に幸福そうに砂糖玉を転がしていた。
『いずれ、落ち着いて来ますよ。今の時期はその、体とか心とか、とても伸びる時期ですから』
そう言って医師はその場をごまかした。結論から言えば、…ひなみは4年経っても、10年経っても、その異様な食欲が衰えることはなかった。むしろ助長した、と言っても過言ではない。ひなみは食べた、嫌いなものや口に合わないもの以外を食べ続けた。暇なとき、暇ではない時でさえ食べていた。
幸いというべきか、ひなみはその食欲が外見に比例するタイプではなかった。ひなみは人の倍以上食べている癖に、身長は女子の平均以下で止まった。体重も平均以下から上下しなかった。頼りない程細い手足の肉付きは変わることなく、引きこもってばかりだったので体力もなくなった。そんなひなみを友人は『燃費が悪すぎ』と罵った、まったくもってその通りだと思う。ひなみ自身、どうして自分がこうなってしまったのか解らない。
ただ、食べずにはいられない。___食べないと、とても切なくて泣きたくなるのだ。少しでも空腹を覚えたなら食べるしかない、五分もそのままだと体が崩れて動けなくなるから。食べることが嫌いかと言われれば否だ、だけど決して好きという訳ではない。そんな次元、とおの昔に通り過ぎた。ひなみはまだ死にたくない、だから食べるのだ。
ひなみにとって生きることと、食べることはどうしようもなく同義だった。
だからこそ、それを害されることは『死』そのものであった。
「………」
ひなみはコンクリートの上に落ちるそれから目が離せなかった。美味しそうな生クリームカスタード、カリカリふわふわのシュー生地、ささやかながらの粉砂糖にチョコレートのトッピング。神だ。何が罪といえば、その魅惑のフォルムと内側に隠した仕様のない極楽…つまりソレの存在そのものと言っても過言ではない。
「…」
数秒前まで、それはひなみの手の中にあった。そして、食べられるのを今や今かと全身を震わせて待ち望んでいたのだ。なのに、なのに…シュークリームは死んだ。横からすっ飛んできたナニかの爆風に巻き込まれて。
状況を…説明しよう。
矢包ひなみは朝が苦手だ、死ぬほど苦手だ。だが、今日と言うこの日…あ、今日は渋谷にあるとある有名な私営店のお店が限定200個のオリジナル・シュークリーム(※通常売られているシュークリームとは異なる、年に一度しか販売しない素材にも拘った最上級の一品)の販売日なのだが…その為に、何時もより早起き(※早朝4時起床)をして、シュークリームに顔見せできるようにオシャレ(※気持ちの問題である)をし、通勤ラッシュにもまれながらも渋谷に到着。開店4時間前(※既に列が出来上がっていたが、経験の上に導いたまだ購入可能であると見て判断)に並び、空腹をローソンで購入したアレやソレやで紛らわせていたが及ばず。仕様のない空腹に涙まで浮かばせながら、どうにか購入したオリジナル・シュークリーム(※お一人様お1つ限定)!待ちきれずに歩きながら開封し、すわかぶりつかんとした瞬間______ゴミ箱が目の前を通過した。流石のことに驚いて唖然としていると、見知らぬオジサンが駆け寄り『大丈夫か?』と声をかけてくれた。そして気づいた。シュークリームが、無い。
「……」
シュークリームが落ちてしまったコンクリート、そこを凝視して俯き黙り込んでいるひなみにオジサン(仮)は気まずそうに頭を掻いた。泣いている、そう思ったのかもしれない。その顔は、年頃の少女の扱いに手を請真似ている大人のそれだった。ある意味で、オジサンの推測は正しかった。…ひなみが『なぜ泣いている』という原因の点を除けば。
「あーっ…嬢ちゃん、恐い思いさせちまったな。ケガぁないか?」
「…」
「この辺、危険だから。あっち行っとけ、な?おじさんの忠告は聞いとけって」
「…」
「な?」
「…」
全く持って、不愉快であった。
何故、なぜこの瞬間、この場所で、ひなみが、ひなみのシュークリームがこのような終わりを迎えないといけないのか。何故?何故?何故?何故____っ?
きゅるりと、腹が鳴った。その音に、オジサンは目どこか呆れたように笑う。
「あー、シュークリームだけど…残念だったな。こりゃぁ新しいの買うしかないべ。な?運が無かったんだって」
「トムさん…、」
「おー静雄、……もう良いのか」
「ッス …ご迷惑おかけしました」
「いーっていーって、ありゃああっちが悪いべ。お前ぇがキレても仕方ねー連中だよ」
「…ッス。 …知り合いッスか」
「いや、お前の投げたごみ箱の被害者。シュークリーム落としちまったみたいで__」
続きは無かった。正確には遮られたのだ、目の前でがくりと座り込んでしまった日南に。
「おいっ_」
「なっ」
「っ―――――!!!」
次の瞬間、ひなみは声のない声で叫んだ。その慟哭は深く、暗く、絶望の色に染まって、昼間の渋谷に響いた。音のない、子どもの様な鳴声は皮肉にも秋の澄み切った青空によくそぐうそれだった。
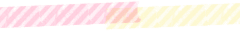
1年後、秋。
ひなみはスキップ交じりに行列の波から抜け出した。一年前より伸びた髪をくるりと巻き纏め、フリルのスカートを揺らしながら胸に愛らしいラッピングのケーキボックスを抱えていた。それにとろんと眠たそうな瞳にキラキラとした光を宿し、ひなみはパンプスの踵を鳴らした。
「ひなみ」
きょろきょろと朝の池袋の人混みの中で視界を巡らせていると、彼の方が先に見つけて声をかけてくれた。
「買えたか、目当てのモン」
「うん、ほら」
そう言って胸に抱いていた白いケーキボックスを掲げる日南に、彼は「掲げなくても見えるっつーの」と笑う。何時も通りの眠たそうなやる気のない顔なのに、嬉しそうに頬を桃色に染めているひなみに、彼は少し呆れたように言う。
「ホント食うの好きだよな、お前」
「好きっ 大好きっ 世界一!」
「そりゃ言い過ぎだろ」
歓喜のあまりくるくる回り出したひなみを適当にあしらいながら「っし。じゃあ帰るか、目当てのモン買えたし。いい加減、眠みぃわ」と早口に提案した。
ひなみに付き合い早朝から町に繰り出していた彼の眠気は、既にピークである。
「ほら、行くぞ」
「まって」
欠伸をかみ殺して歩き出そうとした彼の裾を、ひなみは摘まんで引き止める。なんだと振り返る彼を他所に、ひなみはごそごそとボックスを開き始めた。
そこから現れたのはシュークリーム。ひなみも、彼も、一年ぶりに目にした素敵に無敵なフォルムのオリジナル・シュークリームだった。
「…と、」
ひなみはそれを手に取るとぶつりと半分にした。カリカリふわふわの生地から、美味しそうな生クリームカスタードがあふれてくる。それをこぼさないよゆにそうっと、彼に差し出す。
「はんぶっこ、ね」
「良いのか? お前、ここのシュークリームすげぇ楽しみにしてただろ」
「いい。 …一緒に食べた方が、きっと美味しいから」
その言葉に目を丸くする彼に、ひなみは続ける。
「はんぶっこ、しよ。静雄」
「……しゃーねぇな」
ぶっきら棒に返しながら、彼__静雄は、日南からシュークリームを受け取った。あふれそうになるクリームごと大きな口でシュークリームにかぶりつく静雄を見て、ひなみも満足そうにシュークリームを口にする。
それは、一年と少しの間にはじまった___シュークリームみたいに甘い、恋のお話し。