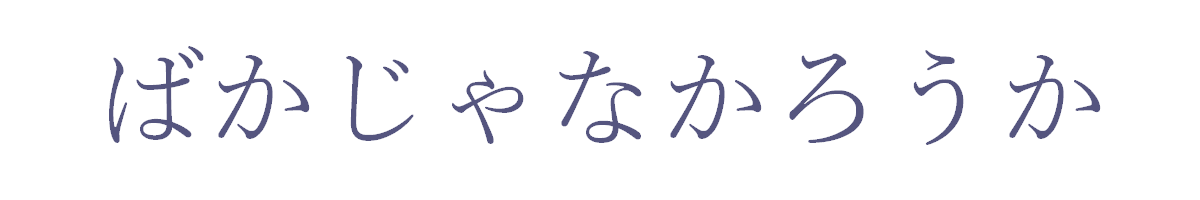
おいていかれる、という恐怖を、いったいどれだけの人間が認知しているのか、俺はふと気になることがある。 置いて行かれる。老いて逝かれる。置いて、老いて、措いていかれる恐怖を、いったいどれだけの人間が真に迫って恐怖しているのだろうか。ふと、そんなとりとめもないことに思考が巡る時がある。それは俺の場合、決まって夏野とセックスをした時に逡巡する。自分より二つ三つ下の、少年らしさをふんだんに含んだみずみずしい肌を啜ったあとに思考する。ああ、俺はおいていかれるのだな、と、実感する。さっきまで汗だくになりながらお互いむさぼっていたというのに(……本当に、そうだろうか。お互い? 本当に?)その熱を、がらすがひび割れるほどの温度差をもって夏野は冷却する。今だってそうだ、先ほどの熱量なんて忘れたようなすまし顔で数ⅡBのテキストを開いている。高校一年生で数ⅡBなんてやっただろうか。数学の授業なんてただの数の羅列としか(ときどきわけのわからない記号も出現するけれど)認識していなかった俺の海馬をどれだけまさぐってもその答えは出なかったので、俺はおとなしく本の虫と化した夏野のきれいな背骨を一つ一つなぞる。最中はぴくりぴくりとかわいらしく跳ねていたその身体は、今は石膏のように凝り固まっている。ぺたりと掌をくっつけてみるも、平熱に戻ってしまった夏野の肌は汗以外の情事の痕跡を全く残していなかった。それにまた、俺は悲しくなる。そして、考える。人は、どういったときにおいていかれると、恐怖するのだろう。自分を作った父親の腰が曲がったときだろうか。自分を生み出した母親の顔にしわが深く刻まれたときだろうか。兄弟が自分の背を抜かしたときだろうか。姉妹が化粧づいたときだろうか。親友が、自分をまったく見ていないときだろうか。 時間が止まればいいのに。 と、そう思えればまだ楽だったのだ。 時間が止まればいいのにと。この気難しい少年と永遠に一緒にいられたらいいのにと、そう切に願えたならば、神に祈れたならば、きっと俺たちは間違えずに済んだのだ。こんな生産性のない、馬鹿らしいことなんてせずに済んだはずなのだ。背骨を最後まで数え切って、いよいよ臀部へ、となったところで、ようやく夏野がぱちりと瞬きをした。剣呑な色をまといながら、その両目が俺を射る。まだやるき、と夏野はだるそうに言った。首を振る。別に、もう一度しけこみたいだなんてそんなことは毛頭、思っていない。性に花咲く十代といえど、二度も出してしまえばいい加減性欲よりも疲労感のほうが勝ってくる。そしてああ、俺のこれはいわゆる賢者タイムというやつなのだろうか、とぼんやり思った。さっきまであんなに欲情した身体を面倒に思ったり、先刻まで振っていた腰に羞恥や後悔を抱いたり。そういったことの一環なのかもしれない。なつの、とその名を呼んだ。夏野は数式から俺に視線をずらしたまま、なんだよと言った。俺はもう一度、夏野を呼んだ。なつの、なつの、なつの。 夏野。 うるさい、としまいにはテキストで頭をはたかれた。それなりの重量を持ったそれは、そのくせ軽い音をさせてからっぽな俺の頭を振動させた。鈍く痛む頭皮をそのままに、俺は夏野の痩躯にそっと腕を回す。夏野は大仰なため息を一つ吐いて、同じように俺の背中に手を回してくれた。あんなに勉強しているのにペンだこ一つない、綺麗な指だ。その指が俺の背中を泳ぐようになぞる。ちらりと視線をずらせば、俺と夏野の距離を絶対ゼロにさせまいとする分厚い参考書が目に入った。 人はおいていかれると、いつ恐怖するのだろうか。 人はおいていかれる時、何に恐怖するのだろうか。 夏野の黒髪に顔をうずめる。シャンプーの匂いが香った。それが俺の好きではない香料だということにして、自分の吐き気に適当な理由をつけた。 時間が止まればいいのに。 そう思えたら、どれだけ楽だったのだろう。今日も今日とて、馬鹿な俺は夏野を引き留めることも、神に祈ることも、結局できないのだ。 |