ME ONLY FOR YOU!!
-2-
個室居酒屋、メンバー三人だけの定例会。
灰皿に吸い殻を押し付けながら考えごとをしていたら、太ももの上のスマホが震えた。俺はすぐさま画面を確認する。そして肩を落とす。画面に表示されたのはただの、友達登録してあるショップからのお知らせだった。
「…でー、×◯ちゃんっているじゃんちょっと前から来てくれるようになった子。ビックリだよ△△ちゃんと繋がっててさぁもうさぁ諸々筒抜け。こっわー」
●●がテーブルの向こう側で熱弁を繰り広げているが、俺はずっと右から左へ聞き流していた。内容はたぶん毎度同じ、ファンの子とのナンダカンダだろう。●●は俺たち三人の中で唯一、かなり下が緩い。
「ああーたぬきで叩かれるー…俺スレが火を吹くー…やだー…」
「叩かれたところでお前全然懲りないしな」
◯◯が空になった皿を重ねながら小気味良く相槌を入れる。
「懲りる懲りないではないわけよ、わかる?向こうから来るわけよ、断ったら可哀想なわけよ」
「知らねえよ、ボコボコに叩かれて謝罪動画でまた頭丸めて炎上でもしとけば」
「あっお前そういうこと言う、わかったそしたらお前の本カノたぬきで晒したるからな」
「やめろ殺すぞ」
二人の会話に参加しないまま、俺は他に何の通知も寄越さないスマホの画面をぼんやり眺め続けた。どれだけ待ち続けても、やっぱり連絡は来ない。
「臣を見習えよ、爪の垢煎じて飲ましてもらえばお前」
◯◯が俺の名を挟むから「ん?」と聞き返したが、なにが気に入らないのか、●●は大袈裟なため息を吐いて眉間に皺を寄せた。
「いいよねー愛されセンターのおみみ様はぁー」
「すまん、あんまり聞いてなかった。何の話?」
「叩かれたこともなきゃファンサも上手いし?照れ屋で?ちょっと音痴で?かっこいいのにかわいんだもんねーはいはいみんな大好き大好き」
「ああ、はは。いいよな●●は歌上手いから。羨ましいよ」
「ハイお世辞一丁いただきやしたーアザーッス!」
世辞ではないのに、不貞腐れてしまった●●は素直に受け取ってくれない。居酒屋店員の口調を真似ながら「ハイ生追加ー!」と続け、卓上のタッチパネルを操作する。
「●●のトークが上手いから、それきっかけでファンになってくれた人だってたくさんいるじゃないか。俺にはないよ、その器用さ」
俺の言葉に◯◯が小さく頷いて「まあ、それはある。それだけしかないけど」と付け加えた。
「ねえどっち?褒めてんの?なんなの」
「褒めてない全然」
「あ、晒す?本カノ晒すよ今、いいんかお前コラ」
「……」
二人の小競り合いを他所に、またタバコの火を点ける。
最近、本数がやたら増えた。来るのか来ないのかも分からない便りを待つのは不安で、やたらと長くて、いつも手持ち無沙汰になる。
「…なんでくれないのかなぁ…」
呟いた一言を、◯◯は「なにが?」と拾ってくれたが、正直に打ち明ける気にはならなくて笑って誤魔化してしまった。
連絡が来ない。ずっと、待ってるのに。
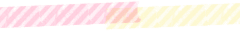
「polaroid」を結成して一年半が経つ。
ずっと前のことだ。三人で一つずつ、メンバー誰かを連想させるものとして持ち寄った「ポメラニアン」「ボカロ」「パパラッチ」という、グループ名の候補の単語。どれも本当にふざけてたよな、思い出すと苦笑してしまう。
適当に混ぜて適当に語感を拾って適当に決まった「polaroid」という名前は、だけど、気づけばずいぶん目と口に馴染むようになった。
口が上手く顔も広い●●に広報とSNS管理を任せ、webやDTMに強い◯◯には楽曲とサイトの制作を。そして「体がデカイ」という理由だけで何故か、センターは俺が担うことになった。専門時代に仲良くなった三人で始めた半ば冗談みたいな活動は、思っていたよりずっと上手く軌道に乗ってしまったし、思っていたより何倍も稼げた。
●●は「天職」と言ってこの活動を謳歌しているし、◯◯も、彼女との結婚資金を貯めたいからと相手公認で活動を続けてる。二人とも辞めたいとは、どうやら思ってないらしい。だから俺もずっと言わないでいる。…言えないままだ。「辞めたい」の言葉を。
ああそうだ、明後日はレンタル会議室で配信をするんだったか。どんなことを発言してどんなことには口を噤もうか、なんとなく決めておかないとな。●●みたいな器用さも、◯◯みたいな頭の良さも俺にはない。向いてないんだ本当に。…憂鬱だな。
二日後、約束していた時間に十分遅れで●●がやってきたところでようやく配信の準備が完了した。配線やカメラ位置を◯◯が微調整し、話す内容を三人で最終確認する。
「はいオッケ、じゃあ臣っち、いっちゃって」
●●に促され、エンターキーを押す。その途端画面には視聴者からの挨拶の言葉が流れ、課金アイテムもいくつか投下された。
「えーと、こんばんは。polaroidです。今日も観に来てくれてありがとう」
俺が最初の挨拶をするとまたコメントが沢山更新された。速くて、ちっとも目で追えない。速読して逐一拾うのは●●の役目だ、俺はただカメラを観ながら穏やかに喋っていれば良いらしい。
「この前のライブから始めたグッズなんだけど、知らない人もいるかもしれないから、一応、宣伝ってことで」
グッズをカメラに映して、●●に託す。今度は●●が中央に代わってグッズの詳細を説明した。
どうしてこう、次から次へと淀みなく言葉を思いつくんだろうな。●●の説明に感心しながら画面を見ていると、ちょうどその時課金アイテムが投下されたのが目に止まった。
「…あ」
配信中、ということも一瞬忘れて、予定にはない声をあげてしまった。メンバーの二人に訝しげな顔をされ、視聴者からも「???」「なにー?」「おみみどしたの」とコメントを送られる。
慌てて口をつぐんだが、もう遅い。困った、どうしようか。
「…いや、番組…観たかったヤツ。あの、録画してないなって、はは…急に思い出して」
笑いながら途切れ途切れに言ったが、もちろん嘘だ。これは配信中やステージ上、なにか困った時に使えるからと●●に教えてもらった方便の内の一つだった。
コメントはまた高速でリロードされる。「wwwww」「なぜいま笑」「おみみきゃわ」俺が目視できたのはその三つだけだ。
「はいおみみくんの突発ボケがかまされた訳ですけど。ちょ、みんなグッズの話だからね今!はいこっち注目!聞いて!」
●●がうまいこと注意を自分に引きつけてくれるので助かった。◯◯もチョップの真似事をして、何人かの視聴者がそれに笑ってくれている。
小さく笑いながら、さっき課金アイテムを送ってくれた人のID名を思い返す。「taichi_770」。たいちくんだ。
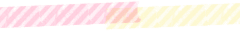
たいちくんは、三ヶ月くらい前からライブに来てくれるようになったファンの一人だ。男の子が一人で来るなんて珍しいなと思ったのを、よく覚えている。
ステージの上、たいちくんと目が合った瞬間だった。涙目で俺を見つめるものだから、あんまりかわいくて困ってしまった。誰推しかと●●に聞かれて、壊れた機械のように喉を詰まらせるものだからこっちまで動揺した。
彼の口からこぼれた最初の一文字は「お」だった。だから、俺は嬉しかった。本当に、すごく嬉しかったんだ。
「……俺?」
焦ったくて、急いた。自分を指差して尋ねるとたいちくんは何度も頷いた。その仕草が、その顔が、今も忘れられない。何度も思い出しては胸が高鳴る。愛しいなと思った。勇気を出して、きっと不安を抱えながら、それでも俺たちに、いや俺に、会いに来てくれたのだ。
それまでちっとも理解できなかった●●の気持ちが、ようやく自分にも分かった。
「かわいい子に推されたら普通に無理じゃない?」
…ああ、分かる。無理だ。かわいい。
健気でウブなファンの人が今まで一人もいなかったわけじゃない。中にはうちわを振りながら泣いてくれる人も、チェキの時に足が震えてしまう人だっていた。
でも自分の心はいつも不思議なほど凪いでいた。嬉しいとかありがたいとは思っても、それ以上の気持ちは一度も生まれたことがなかった。
「うーん、かわいいとかかわいくないとか思ったことが、あんまり…みんな同じに見えるんだ」
●●にそう言ったら、彼は腕を組み真剣な顔をして数秒後こう言ってのけた。
「無自覚ゲイなんじゃね?」
あの時は、笑って流した。背中を小突いて「バカ」くらいは言った気がする。でも今同じことを言われたら、神妙な顔をしてしまう。頷いてしまう、かも、しれない。
俺は、たいちくんみたいな子が好きなんだと、たいちくんに出会って初めて気づいたんだ。
物販販売の時、自分の列に並んでくれたのも嬉しかった。目深に被ったキャップと俯く角度のせいでちっとも顔が見えなくて、目が合わないのがもどかしかった。屈んで覗き込んで、半分無理やりだったかもしれない。だけどやっと間近で見れたたいちくんは、ステージの上から見るよりもっとずっと、胸にきた。
震える手で小銭をばら撒いてくれて、俺はあの時ラッキーだと思った。どさくさに紛れて手を握れる。たいちくんに触れたかった。俺の手を知って欲しかった。
握った感触を忘れない。意外と骨張っていて、薄くて広いたいちくんの手。また胸にきた。指を絡めたいと思ったんだ。
行き過ぎた接触に怯えさせたかもしれないと、その後のチェキ撮影会では少し不安だった。俺の列に並んでくれなかったら。撮影しないで帰ってしまったら。でも列の半ば辺りで現れてくれたからそれがすごく嬉しくて、安堵した。おかしいだろ、俺はずっとあの日一喜一憂してたんだ。初めてだったんだ、そんなの全部。
ピースサインしかリクエストしてくれないからちょっとガッカリもした。どうせならハグ、いや本音をこぼすならエアキスくらい言って欲しかったのに。
直立不動と宛なく彷徨う両手がかわいくて、思わず腰を抱いた。引き寄せたたいちくんの体は他の誰より心地よかった。何度目だろう、また、胸にきたんだ。帰したくないと思った。でも引き留めておけるような誘い文句なんて俺は一つも知らない。せめてもの気持ちで名前を聞いて、たいちくんとのチェキにメッセージと、それから裏面に電話番号を書いておいた。
その日の夜ずっと、たいちくんからの連絡を待った。でもタバコを一箱空けても尚、便りはなかった。
終わった。そう思った。もう多分会えないんだろうと。嫌悪感を与えたに違いない。最悪の印象を与えるには充分な言動ばかりだったんだ、俺はきっと。
「そんな人だなんて思ってなかった」。目を閉じると俺にそう吐き捨てるたいちくんがくっきり浮かんだ。弁解しようにも、俺はたいちくんのことを何一つ知らない。こんなこと、誰にでもしてる訳じゃない。初めてだったんだ、本当に…信じて。たいちくんが初めてなんだ。
謝りたい。勝手に手を握ってごめん。腰に手を回してごめん。強引で、ごめん。たいちくんが一定の距離を保って俺たちの応援をしたいんなら、俺はそれに従うから。やり直させてくれないか、次は間違えないから。
…なに言ってんだ。次なんてもう、ないのに。自分を呪った。なんて馬鹿な真似をしたんだと後悔した。俺はきっとこれからもたいちくんをステージの上から探して、その度に肩を落とすんだろう。ああ辞めたい。こんな過ちを犯すくらいだったら最初から、活動なんてしていなければ良かった。
だけどビックリだ。次のライブ、だって客席の前から数えて数列目。目深に被ったキャップの彼を見つけたから。
幻滅されたのかと思っていたが、どうやら違うみたいだ。そのライブでもたいちくんは物販販売の時わざわざ俺の列に並んだし、撮影会でも当然のように俺と撮ってくれた。…一体どうして。個人的な連絡はしたくないけどファンとしては変わらず楽しませてよ、と、そういうことなのだろうか。
「おっ、お……あの、あ、臣クン今日も超かっこよかったッス!」
チェキ撮影の時、髪色に負けないくらい顔を真っ赤にしてそう言うから、不思議な子だと心底思った。
「…ありがとう、嬉しいよ」
お礼を言えば涙目で笑う。たいちくんの言動一つ一つから俺への「好きだ」という気持ちが溢れているように感じられて仕方ない。俺は、とにかく混乱した。
どうしようか。どうしたらいい?たいちくんは何を望んでる?わからなかった。二人きり、誰にも聞かれない場所でそれをしっかり聞きたいのに、たいちくんは俺と二人きりになろうとは極力してくれない。撮ればサッサと捌けてサッサと帰ってしまうのだ。…なあ、一体どうして?二回目のチェキ撮影も、結局リクエストはピースサインだけ。俺の頭はハテナマークで溢れかえった。
そうか、電話番号というのが良くなかったのかもしれない。そうだよいきなり電話はハードルが高い、馬鹿だラインのIDにしておけば良かったんだ。やっと考えが至って、だから二回目のチェキの裏には自身のラインIDを書いた。これなら連絡が来るに違いない。たいちくんのことだ、きっと最初は簡潔な一文とスタンプとか。そんな感じで始まりのテープを切ってくれるんだろう。
「……どうして……」
その夜、俺はタバコを二箱空にした。たいちくんからの友達申請もトークも、空が薄白くなって尚、結局なんのリアクションもなかったのだ。
「あのさ、●●よく言ってるヤツあるだろ、「たぬき」って。…それに、俺のこと書いてる人とか、いないか…?」
たいちくんと出会って一ヶ月。相変わらずライブには来てくれるのに個人的な連絡は一切くれない彼のことを考える日々が続いていた。もしかして裏で俺のことを叩いているのではと不安になり、それとなく尋ねてみたが●●は首を横に振って不思議そうな顔をしただけだった。
「え、なして?なんかやっちゃったの臣」
「いや、あー…やっちゃったかやっちゃってないのか、自分でもよく分からないんだ」
「なんそれ」
「いや、うん…。いいんだ、なんでもない」
自己嫌悪に陥る。たいちくんがそんなことをするようには見えないのに、もしかしたらと疑ってしまった。…いやでもまだわからない。俺たちの目が決して届かぬ場所で、そういうことを書き連ねてるのかもしれない。今この瞬間も、俺の悪事を裁こうとしているのかもしれない。
ライブ後日からの日々はいつもこうだ。たいちくんへの疑念と自身の行いへの後悔で項垂れる。それで、絶望の渦中で次のライブの日がやって来て、会場にたいちくんの姿を見つけては面食らう。俺に釘付けになって、俺の名前を書いたうちわを振って、俺のソロパートで必ずコールするたいちくんを見ては、分からなくなる。
たいちくんのことが未だによく分からない。…どうして?どうしたい?どうするのが、一番いい?
「あっ、あの、あの!…きょ、きょ今日は指ハートで……」
「……それだけ?」
「えぁっ、は、ははハイッス、え、えっと……」
「そっか、残念」
「……」
答えが出ないまま、今日もまたたいちくんとチェキを撮る。今度こそと願って、裏面には誰にも教えていない作りたての、Twitterの個人アカウントIDを書いた。
『連絡してほしい。待ってる。』
縋るような気持ちで添えた一言を、たいちくんはどう受け取ってくれたのだろう。
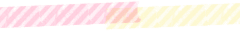
「…いいよな●●も◯◯も。羨ましいよ、俺」
ライブ終了後、誰もいなくなった会場内での撤収作業中だった。後は物販の売れ残りを片すだけというところでいよいよ手が止まり、まだ閉じていなかったパイプ椅子に力なく座る。思わずこぼれた俺の本音に二人は目を丸くした。
「っはー。なにその唐突な嫌味のジャブ」
「嫌味じゃない。本当にそう思ってるから言ってる」
焦燥感と不安感で苛立つ。今日もきっとたいちくんからの連絡はない。タバコの箱をいくつ空にしてもきっと、俺のスマホはくだらない通知をよこすだけに決まってる。
狙った子と毎回必ずいい関係になれる●●も、結婚の話ができるほど好きな人と良好でいられる◯◯も、俺は羨ましくて仕方ない。二人ともどうやったらそんなに上手くできるんだろう。センターの役も長蛇の列もいらないから、俺だっていいなと思った子と、好きな人と…他でもないたいちくんと、関係を築きたい。
「…どした、悩みあるなら聞くけど」
◯◯が俺の肩を一度、軽く叩いた。きっと本気で心配してくれているんだろう。…そうだよな。だって撤収作業を途中で放り投げるなんて今まで一度もしたことなかった。
「…はは。器用さもないし、考えも足りなくてさ…いいとこ無しだよ俺」
言葉にして一層落ち込む。つまり不器用で馬鹿というわけだ、俺は。たいちくんも呆れたんだろうか。本当の俺を知ってなんて愚かなんだと、チェキの裏面を見ながら見損なっているのだろうか。
「…あのさ臣、お前に足りないもん教えたろか」
●●が俺の前にしゃがみ込み、まっすぐ俺を見上げる。珍しいと感じるほど、それは芯の強い眼差しだった。
「…ああ、頼むよ」
「酒だ」
「うん。……うん?」
聞き返すのと同時に●●は立ち上がり、そして場の空気を一掃する為にパンパンと二回手を鳴らした。
「飲み行こ今日!臣ちゃん珍しくキちゃってるから!」
「いや、あの待って●●、そんなつもりで言った訳じゃ」
「もうね拗らしてるから。これ完全に拗らしちゃってる」
「いんじゃない、お前が話聞いてあげれば」
「いやあの…」
「大丈夫、任せな。要はめんどくさい子に手ぇ出しちゃったんしょ?揉めそうなんしょ?俺が今後のこと一緒に考えてやるから」
「違うんだよ…」
聞く耳を持ってくれない●●に困り、助けを求めて◯◯に視線を送るが、彼は一人淡々と撤収作業を再開してしまっていた。偶然に目が合っても「そうそう」と声に出さず頷くだけ。…だから。違うんだってば。
完全撤収の時間を二分オーバーし、俺たちは会場を後にした。●●はすっかり飲む気満々だし◯◯も間に入ってくれようとしない。困った、このままではお悩み相談と銘打って●●が熱弁を振るってしまう。
「…あれ?」
階段を登り切ってすぐ、◯◯が何かに気付いた。彼の視線の先を遅れて追いかける。そこには電柱に背を預け座り込むたいちくんがいた。
「……たいちくん」
「あっ!!うぉ…あ、あの、あの!お、お疲れ様ッス!」
俺たちに気付くなり立ち上がって何度も頭を下げるたいちくんに、◯◯が「あのさ待っててもらって悪いんだけど、出待ちは一応禁止になってるから次からやめてもらっていい?」と注意したが、それを●●が「いーじゃんかたいこと言うなや」と笑いながら遮る。対応の違う二人に、たいちくんはただ「うぉ」とか「ひょあ」と言いながら狼狽えていた。
「…中に、何か忘れ物?」
俺が尋ねると、たいちくんは慌てて紙袋を差し出した。
「いっ、あの違くて、あっ、ごめんなさい出待ちしちゃって!次からは気をつけるッス!あの、えっと、これ、あのこれ、渡すの忘れて!あ、忘れてって言うか忘れた訳じゃないんスけど、あの、タイミング分かんなくて」
差し出された紙袋の中身を覗く。中には、恐らく菓子屋で買ったものなんだろう。白い小さな箱が三つ入っていた。
「あの……あの!箱の下のとこ…●●クンと◯◯クンと臣クンの、名前書いてて」
紙袋から取り出してみる。たいちくんの言う通り底の面には俺たちの名前がそれぞれ書かれていた。
「これ、あのっ…賞味期限が…あれ?消費?だっけ?えっと、とにかく期限が今日までであのっ…すごいメッチャ美味しいって有名なケーキ屋さんの!シュークリーム!色違いで三つあって、あのっ…メッチャ美味しいって有名らしくて!」
「……」
必死で言葉を紡いで、力を込めて両目を瞑って、拳を握って、体中を硬くして、焦って、慌てて…たいちくんの全てがまた胸にきた。かわいくて愛しくて、歯軋りしたくなった。
「…ありがとう。嬉しい」
『臣クンへ』と書かれた箱を両手で受け取り、たいちくんにお礼を伝える。俺が笑うとたいちくんも満面の笑みで笑った。生きてること全てが報われたみたいな顔で笑ったりするから、もう、ほらまた。胸にくるんだよ。
「あ…えと、じゃあ俺っち、あ間違えた俺!行きます!お疲れ様でした!」
部活のようにキャップの脱帽までして頭を下げると、たいちくんは小走りで駆けて行ってしまった。背中が一瞬で遠くなる。待っての一言すら待ってくれない。たいちくんはいつだってそうだ。
「……」
追いかけろと、俺の背中を押す俺の声が、その時たしかに聞こえた。
「……俺、用事あったんだった」
呟いて、それから駆け出す。俺に取り残された二人が背後でなにか言ったが、聞き取る余裕も聞き返す暇も当然なかった。
「えっと…すまん!祖母が危篤で!!」
振り返って大きく手を振る。二人は声を揃えて「はー!?」と言ったが、それでも手を振り返してくれていた。ごめんな、ありがとう。説明はまた今度改めて。だって俺、これを逃したらいよいよ本物の馬鹿になっちまうから!
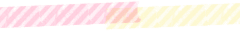
無駄に体がデカくて良かった。だって俺の一歩は他の人よりデカい。たいちくんを見失う前に追い付けたのはそのおかげだって言うなら、無駄なことなんて一つもないじゃないかって、そんな風にすら思える。
「待って!」
やっと捕まえた手首を強く掴んで、息を乱しながら「たいちくん」と名前を呼んだ。足を止め、たいちくんがこちらへ振り返る。事態を飲み込めていないのか、その口はあんぐりと開かれていた。
「……話す時間をくれないか?十分…五分でもいいから」
「………」
「…だめ?嫌か?嫌ならはっきり言って」
「……へっ…」
「こういうのが迷惑ならそう言ってほしい。…言ってくれないと分からないんだ」
「………」
どれだけ待っただろう。数十秒、いや数分。たいちくんは俺に手首を掴まれたままその場に突っ立っているだけだ。
「…なあ、たいちくん」
「……へぁ…」
「俺に幻滅した?」
たいちくんの本心に自ら指先を伸ばす。怖くてたまらない。頷かれたら俺は、一体どうすればいいんだろう。でもはぐらかしたくない。誤魔化したくない。たいちくんの本当の気持ちを、俺は知りたい。
「……」
たいちくんはオロオロと迷いながら、けれどゆっくり首を横に振った。顔中にハテナマークを貼りつけて、一歩間違えれば泣き出しそうな顔で、今度は首を傾げている。
「…え、あ…お、俺っち馬鹿だから……わ、わかんない……」
「…自分の気持ちが?ってこと?」
俺の問いに、また首を横に振る。意識を向ける余裕がないのか、俺に掴まれた手首には何の力も入っていなかった。
「お、臣クンに…聞かれてる内容が、あの…わかんない……」
「……」
どこが分かりにくかったんだろう、えーと…ああダメだ、俺もよく分からない。分からない俺ができることはただ一つ。正攻法で、当たって砕けるしかない。
「たいちくんが好きだ」
俺の言葉に、たいちくんの両目が見開かれる。
「…誰にでもこういうことしてるとか、思われたくない。信じて欲しい。…どうやったら信じてくれる?」
「………」
「辞めたら信じてくれる?だったら俺、辞めるから。◯◯と●●に今連絡するから、聞いててくれるか?」
信じてもらわないことには何も始まらないのだと、そんな当たり前に俺は気付いた。どんなに言葉を連ねても、イベントの中で特別な態度を取っても、チェキの裏にいくら想いを込めても。証明しなくちゃ意味がないんだ。俺は、順番を間違えていた。
ラインを立ち上げてpolaroidのグループトーク画面を表示する。けれど通話のマークをタップするのとほぼ同時だった。たいちくんが今度は俺の手首を掴みそれを阻止した。
「っだあああぁぁっ!!!!??」
「……」
「や、えっ辞めるってなに!?おっ…臣クンがpolaroid辞めるってことッスか!?」
たいちくんは顔面蒼白だった。信じられないものを見るような顔で、彼は俺にそう尋ねた。
「ああ。大丈夫、二人なら真剣に話せばわかってくれると思う」
「まっ…まーままま……まっ、待って!!?な、なに!?なんで!?」
「証明できる方法、他に思い付かないんだ。いいんだ気にしないで。元々辞めようって考えてたし」
「まっ、まっ、いや待っ……なっ…ダメでしょ!!」
たいちくんが俺の手からスマホを取り上げ、それを後ろ手に隠す。まるで自殺を止める警察のようだ。たいちくんは俺の目を見ながら「絶対ダメ!」と叫んだ。
「臣クンが辞めたら…ど、どんだけの人が泣くと思ってんスか!!」
「そんな人いない。返して、たいちくん」
「ダメ!絶対ダメ!!臣クン辞めるとか有り得ない!!」
「どうして?だって、今のままじゃたいちくんに信じてもらえない。俺のこと最低な奴だって…幻滅したって、思ってるんだろ?」
「思っ…ハァ!?思ってないよそんなこと!!最高だよ臣クンは!最高じゃなかったことなんか一回もないよ!!世界一かっこよくて世界一キラキラしててっ…世界一大好きだよ!!」
「だからどうして…そうやって思わせぶりなことばっかり…」
たいちくんの目が、言葉が、さっきからずっと胸にくる。くるから、分からなくて崩れそうだった。もう嫌だ。決定的な言葉でいっそ打ちのめしてくれよ。なあ俺をからかってるのか?楽しいか?初めての恋に右往左往する情けないザマが、そんなに?
「……だったら何でっ…連絡くれないんだよ!!」
荒げた声にその時一番驚いていたのは誰かって、それは俺だった。ただビックリした。こんな声を俺は出すのかと、生まれて初めて知るような衝撃だった。
「……」
どれくらいの静寂が続いただろう。遠くで車のエンジン音や若者の笑い声が聞こえる。夜の柔らかな風が二回ほど俺の頬を撫でた後、ようやく言葉を発したのはたいちくんの方だった。
「……連絡くれないって…なに……?」
「……」
たいちくんを見る。この期に及んでとぼける気なのかと、信じられない気持ちでたいちくんの目を見る。だけどわかった。ああ、やっとわかった。たいちくんはとぼけている訳でもはぐらかしている訳でもない。…なかったんだ、ずっと。
「……たいちくん、裏側」
「え、う、裏側?えっ、裏側!?」
慌てふためきながら、その場でキャップや自分の服を確認し始める。終いには自分の背中を見ようと必死に頭を捻るから、おかしいとかわいいと愛しいで、俺の心は滅茶苦茶になった。
「チェキの裏側にずっと、今まで毎回書いてたんだ」
「へっ、あ、チェキ?…え、チェキ!?えっ、裏!?!えっなに…」
「今日のやつにも。…見てみて」
俺に促されたいちくんがリュックからチェキを取り出す。ジップロックとその上からクリアファイルに守られたチェキを、たいちくんは恐る恐る、手の中でひっくり返した。
「………ひ…」
「…そっか、気づいてなかったのか。はは、納得した」
「…ひょあ…え、これ…お、お、臣クンの…個人アカ…?」
「そうだよ。たいちくんの他に誰も知らない」
「…だっ……へぁ……」
その場でヘナヘナとしゃがみ込んでしまうから俺も一緒にしゃがみ込む。いつも俺たちの視界を邪魔するたいちくんのキャップ、そのツバをつまんで、そっと取った。
「……連絡、ずっと待ってたよ。初めて会った時から」
「……う、うそ…え、えぁ…な、ななな…なん…」
「たいちくんが好きだ。…今度は、信じてくれる?」
「………」
たいちくんのことをこんな至近距離で、こんなに長い間見つめるのは初めてだった。今、目の前で本物の呼吸をしてる。本物の涙を浮かべてる。それだけで震えるほどの幸せが俺を襲った。たいちくんだけの俺になりたくて、俺だけのたいちくんになってほしいと、強く、強く思った。
「……お、俺、俺……」
「…うん」
たいちくんの震える声に吸い寄せられる。額をくっつけて、綺麗なその目に自分を映す。もういらないよ、いらないんだ。俺たちの間には何も。
「え…個人的な、い、いいねとか、リプとかしても…良いんスか……」
「……」
たいちくんに捕らわれた俺のスマホを、たいちくんの手ごと今度は俺が攫う。全部握って、全部閉じ込めて、俺は今から、たいちくんだけの俺になるんだよ。
「…電話もラインもしてくれなきゃ困る。ずっと待ってたんだから」
たいちくんが好きだ。想いを込めて、胸を締め付けながら、俺は目の前で震えるたいちくんにキスをするんだ。