ME ONLY FOR YOU!!
-1-
不定期で開催される生配信。次回ライブのチケット予約開始日時は、この配信でいつも告知される。席指定もない立ち見のライブだしそんなに急がなくたって売り切れる心配はないけど、予約日初日、その開始時間五分以内にチケットを購入するというのが、気付けばマイルールになっていた。
今日は勇気を出して課金アイテムの投下ができた。今まで勇気が一歩足りなくてできなかったから念願だった。よくやった頑張ったぞ俺。えらい。
『……ー。それじゃあ、みんなに会えるのを楽しみにしてるよ。またな』
画面の向こうで臣クンが笑って、撮影用のカメラをオフにするため手を伸ばす。こちらに向かってくる指先を最後までしっかり見届けてから、俺はゆっくり息を吐いた。
「はぁ…今日もかっこよかった……」
溢れる息が熱を持つ。こんな俺を人類の半分以上は「馬鹿だ」って言うんだろう。
それでも止められないんだ、馬鹿なことは自分だってわかってる。わかってるからなんにも言わないでほしい。お願い。
臣クンが、好きだ。
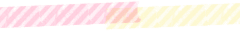
伏見臣。三人組の男性アイドルグループ「polaroid」の、センターに立つ人の名だ。
…え?そんなグループ見たことも聞いたこともないって?そりゃあ当たり前ッス。だって彼らは知る人ぞ知る…つまり、知ってる人しか知らない「地下アイドル」なんだから。
彼らのファンは総称して「ポラー」と呼ばれる。ポラーの一員になって早三ヶ月。圧倒的に女の子が多いこの集団の中、最初はおっかなびっくりだった俺も今ではすっかりメンタルが強くなった。前から五列以内でステージを拝む強靭さも手に入れたし、うちわだって振れるようになったし、臣クンのソロの時は「臣クン」とコールできる強さを身につけた。
知ったきっかけは、話せば誰もが「偶然」と言うかもしれない。だけど俺だけはこっそり「運命」だと思ってる。
TikTokで「踊ってみた」をたまに投稿してる俺のアカウント。その「おすすめ」の一覧に、ある日polaroidの動画がひょっこり現れた。
流行りの歌を踊る三人組を、なんの気無しに見てた。なんなら始めの数秒は「俺の方が上手いし」なんて思った。でも、臣クンが真ん中に立ってカメラ目線で踊り出した瞬間、目から脳、脳から全身へ、電流が一瞬で流れた。
かっこいい。こんなかっこいい人がこの世にいていいのか。笑った顔が優しい。傾げた時の首の角度が完璧。さりげないウィンクは殺戮兵器だし、指先の動きは死角のない芸術だった。
だ、誰だこの人。こんな人見たことない、出会ったことがない。
それは、一目惚れだった。そう一目惚れだったんだ間違いない。ああそうか生まれて初めての「一目惚れ」は、この人の為にあったんだ。液晶越しがなんだ。フィルター加工がなんだってんだ。「会ったこともないくせに」なんて言葉、会ったこともない第三者に言われたって屁でもないや。
この人が好き。俺、この人のことが好きだ。
アカウントのトップに飛んでプロフィールを見る。「三人組アイドルユニット-polaroid-」。貼ってあるリンク先も全部飛んだ。SNSアカウントは速攻フォローして、オシャレセレクトショップみたいなオシャレデザインのエモいホームページもすぐさまブクマした。
ブログ、つぶやき、ディスコグラフィー、インフォ、全部全部読み漁った。伏見臣。ふしみおみ。臣クン。臣クンかぁ…かっこいいな。会ってみたいな。遠くからこっそりで良い、生の臣クンをできるならいつかこの目で…。
そう思っていた矢先だ。メンバーの一人がツイッターアカウントで呟いた、あるツイートが目に止まった。
『ライブのチケットまだまだ余ってます!よろしくお願いします!』
チ、チケット。うわ買わなきゃ。買わない手はない、買うっきゃない。ツイートに貼られたリンク先へ風の速さで飛び、俺はわずか数秒後キャリア決済を完了させていた。液晶に映る「支払いが完了しました。」の一文を息切れするような気持ちで見つめる。
会える。臣クンに、会える。お金を出せば会える人が恋の相手なんて、俺はどれだけラッキーなんだと心から思った。だって、いくら望んだって願ったって叶わない想いが、この世にはきっとごまんとあるから。
なんてこった、お札数枚を差し出せば俺は臣クンに会えるのだ。会ってしまえる。すごい。こんな奇跡みたいな幸運があって良いのか。
その日の夜は興奮してちっとも眠れなかった。だって瞼を閉じると暗闇の向こうに臣クンの姿が浮かんで、優しく笑うのだ。俺に向かってウィンクするのだ。心臓が何度も止まりかけるから、ベッドの中でその度に呻いた。家族に「うるさい!」と怒られたけど、そんなの全然、どうだっていい。だって俺はもうすぐ、恋の相手に会えるんだから!
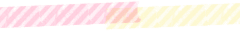
数週間後、ついにその時はやってきた。今日はpolaroidのライブ当日。俺が生まれて初めて臣クンに会える日だ。
「……ふー…」
大丈夫。ネットで沢山調べたし大事なことは全部メモに書いたしそのメモは胸ポケットにちゃんと忍ばせてる。最前交渉、コールアンドレスポンス、キンブレの振り方、チェキ禁止事項、鍵締め狙い厳禁、その他諸々etc。しっかり頭に叩き込んできた。大丈夫、俺はきっと大丈夫。
もしかしたら男性客は俺の他にはいないかもしれない。周りに白い目で見られるかもしれない。陰口を叩かれるかもしれないし後ろ指を刺されるかもしれない。
それでも俺は俺の意志で決めたんだ。どんなことがあっても臣クンと会うことを諦めたくないって。この強い意志さえあれば俺は絶対に大丈夫な筈だ。…筈なのだ、うわヤバい緊張で口の中と目がパサパサになってきた。
電車を乗り継いで会場に向かう。同じ駅で降りる女の人たちが全員ポラーで全員臣クン推しだったらどうしよう、会場に着く前に牽制されたらどうしよう。次から次へとネガティブな妄想が浮かぶけど、俺の足はそれでも会場へとひたすら向かった。
スマホのマップと睨めっこしながら辿り着いた会場は、少し狭い階段を降りた先に入り口がある造りだった。階段には既に十数人のお客さんらしき人々が列を作っている。被ってきたキャップをここぞとばかり目深にして、最後尾の女の子の後ろにそっと近づく。背負ってるリュックにpolaroidメンバーの缶バが付いてたから間違いない。この列の人たちこそがポラーだ。
目立たないよう、必殺・気配消し(※俺が編み出した技。ポスターや看板などを観察してるフリをしたり、スマホで調べ物に夢中になってるフリをすることの総称。周囲の人と目を合わせないのがコツ)をして、キンキンとうるさい心臓をやり過ごす。前後から聞こえてくる会話に時折「おみみ」という単語が飛び出すから、その度に息が少し止まった。
開場スタートの時刻。列が急に動き出す。俺は内心アワアワとテンパりながら、その流れに従った。階段を降りつつ前方の様子を伺う。うわぁやっぱ女の子ばっかり。し、しかもこぞってかわいい。全員漏れなく可愛い。テスト前、自分以外の皆が頭良く見えるあの現象なのかもしれない。俺は自分だけが場違いな気がしてきてもはや泣く手前だった。
でも、会場外より会場内に入ってしまった方が緊張しないもんなんだなと知った。中は思ってたよりずっと薄暗くて、列に並んでいた時より人の目が気にならないのだ。
ステージに一番近いスペースには、イベント関係者何人かと恐らくベテランのファンの人たちが群がっていた。ベテラン勢同士の熱心な最前交渉を遠巻きに眺めながら、とてもじゃないけどあの中に入っていくのは無理だなと悟る。だって、うわ…か、かわいい子ばっかり。
目深に被ったキャップをちょっとだけ押し上げて、前方の女の子たちを見る。あのツインテの、地雷系の子。超細くて超白くて超かわいくて超ツヤツヤ。カバンから取り出したうちわに大きく「おみみ」って書いてあるから、俺は一人こっそり打ちのめされてしまった。
あんなかわいい子が、臣クンを好きなんだ。…ねえもしかしなくても俺、やっぱりメチャクチャ場違いなんじゃない?勘違い野郎なんじゃない?こんな、俺みたいな、ポッと出のそれも同性のファンなんかが会場にいたら、臣クン迷惑なんじゃない?
「………」
あんなに強かった筈の意志が、まるで嘘みたいだ。恥ずかしい。俺、自分のことしか考えてなかった。臣クンがもしもステージの上、俺を見るなりギョッとしたらどうしよう。瞼の裏、あんなに何度も浮かべた臣クンの優しい笑顔が、ウィンクが、急に凍って動かなくなる。
嫌がられたらどうしよう。引かれたらどうしよう。そんなの嫌だ、想像だけで泣きそうだ。
そうやって涙目になっていた時だ、会場に開演前のSEが響き渡った。ステージ前の曲として選ばれたのは、polaroidの中で俺が二番目に好きなヤツ。これから好きな子とデートするぞ!って気持ちを歌った、楽しくて明るいラブソングだ。
周りの人たちがそれぞれに口ずさんだり、ハモったりし始める。みんなの目が、キラキラしてる。
「…きみと過ぅごすー…今日はハッピーハッピーデーィ…」
自分の喉から微かに漏れた歌声が、SEとしてかかっている歌と重なる。臣クンのソロパートとシンクロする。…そう。そうだよ、今日は待ちに待った日。会いたくて仕方なかった人に会える奇跡の日。
会いたくて来たんだよ、俺。見つけてもらえなくていい、気づかれなくていい、目なんか合わなくていい。俺は臣クンを見たくて、臣クンを好きだって気持ちでこの時間を過ごしたくて、勇気を出してここまで来たんだ。
悲しい出来事がもしも起きても、もういいんだ。そんなのは起きてから喰らえばいいんだ。キャップのツバを思い切り上げた。ステージをまっすぐ見上げた。リュックからキンブレを取り出して両手に握った。SEの音量がだんだん小さくなる。ステージの照明が明るくなる。黄色い歓声に包まれながら、三人がステージに上がる。
真ん中に立つ人を見た瞬間、網膜から伝った雷が全身を一瞬で駆け抜けた。
ねえ、世界中の人がなんて言ったって、間違いないよ。ないんだ、絶対。
これが恋だ。臣クン。
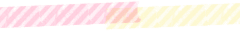
照明が織りなす虹色と何重にもなった歓声を浴びながら、polaroidの三人は歌って踊った。あの時の五感の全部を、俺は生涯忘れないだろう。
体が動かなくて、目は釘付けで、息もできなかった。瞬きすら自分の意思では自由にできなくて、まるで金縛りみたいだって思った。金縛りって恋のど真ん中に落ちた時もなるんだなって、俺は初めて知ったんだ。
臣クンはセンターで、国宝みたいな美しさでダンスを踊った。時たま、お客さんの声援に相槌や微笑みで応えながら、神様みたいな神々しさでステージを染めた。
最初の二曲くらいずっと続いていた金縛りは、三曲目の前に設けられたトークタイムでやっと解け始めた。トーク担当は主にpolaroidの右側、●●クンの担当。●●クンはメチャクチャ面白いし笑い方も豪快で気持ちいい。会場中を盛り上げながら、軽快に告知と宣伝をこなした。
臣クンは、ちょっと口下手。●●クンに質問を振られても「うーんと…」とか「あー…」とか煮え切らない相槌を打って、困った顔で笑うんだ。そんなところも大好き。他の同担もみんなそうなんだろう。臣クンが照れながらはにかむ度に、前方客席の方から「かわいいー」「おみみー」って声が飛び出す。
●●クンのトークでちょっとだけ体の力が抜けた俺は、三曲目からは勇気を出してキンブレを振った。臣クンのソロパートでは控えめに「おーみみ、おみみ」とポラー伝統のコールもしてみた(コールアンドレスポンスはTwitterで誰かがあげてた過去ライブ動画でバッチリ予習済みだ)。
液晶越しにしか見たことのなかった臣クンが、今、すぐ近くで本物の呼吸をしてる。本物の汗をかいてる。それだけで震えるほどの幸せが俺を襲った。今日いまこの会場の空気をどうにかして持って帰れないかって、そんなことを真剣に考えながらラスサビを小さな声でハモった。
ライブ終盤、また●●クンのトークが間に挟まれた。内容は物販とこの後のチェキの概要。常連には説明不要なんだろう、だから●●クンは「知ってる人は寝ながら聞いててね」と付け加えて、会場の笑いを誘ってた。
「……と、まあ、そんな感じで。あれやそれやとやらせてもらってる訳でしてね、ありがたいことにねホント僕たち」
●●クンの話し方に「芸人みたいだな」と、左側の○○クンがツッコむ。真ん中の臣クンが「あはは」と笑う。イケメン三人が仲良く笑い合ってるだけで涙腺に謎に来るから、ナニコレと内心慌てた。
「いつも来てくれる皆には聞き飽きた内容だった訳ですが…あっ、ちなみに今日初めましての人!!」
●●クンが思い出したようにそう言って片手をまっすぐ上げる。お客さんの挙手を促してるようだ。
心臓がキンと鳴って、唾の塊が喉を滑り落ちた。あ、あ、これ、もしかしてこれ、俺が手を挙げなきゃいけない時?じゃない?もしやまさかもしかして。
そっと動かした腕は、ガチガチに固まって手首しか動かない。三人に気づいてもらえる訳なく、動け動けと思ってるうちに前の方のお客さんが「はーい」と軽やかに手を挙げた。
「はいー百度目ましてですね今日も来てくれてあざーす」
クスクスと笑い声が溢れる。あ、そっか今の、常連サンの冗談ってことか。
「……」
笑い声が遠くで聞こえてるその隙に、ゆっくりひっそり手を挙げた。三人は気づかないかもしれない。もしそうならそれはそれで、別にいい。そんな気持ちで、爆弾みたいな心臓と雨みたいな冷や汗と共に、無言で挙手をした。
「…あ」
マイク越し、最初に声をこぼしたのは臣クンだった。
臣クンに肩を叩かれ、●●クンが俺に気づく。それに続いて他のお客さんも俺の方を見るのがわかった。あ、ヤバ、息が、息が吸えないし吐けない死ぬ。
「わー初めまして!男の子だ!嬉しいですありがとー!」
●●クンが明るく笑う。俺は無言でコクコク頷く。周りの視線が自分に向けられて、体の表面は熱いのに内側が氷みたいに冷えていく。暑いのか寒いのか全然分からなくて、俺の体温調節機能はこの瞬間に満を辞してご臨終した。
「へへ。誰推し?とか聞いてもオッケー?良かったら教えてください」
●●クンの問いに、俺は口をパクパクさせながらキンブレを壊れるほど強く握った。
「…ぉ……っ、おっ、お、おっっっ……」
ダメだ喉がぶっ壊れた。まともに喋れないもうダメだ死んだ。俺は死んだ。
そして、それまで●●クンの少し後ろに立って黙っていた臣クンが、ゆっくりステージ前方へ進んで、俺を見ながら優しく笑った。あり得ない。神様みたいな御光が差してた。
「……俺?」
臣クンが自分を指差して首を傾げる。ああダメ、やっぱりその傾げる角度完璧。その声反則。その垂れ目凶器。
大好き、大好き臣クン。
「………」
使い物にならない喉のせいで、名前を呼べない。だから代わりに何度も何度も頷いた。伝われ届けと思いながら必死で頭を縦に振った。謎に涙が滲んでジワジワ歪む視界の向こう、それは俺の見た幻覚だったかもしれない。もうよく分からない。だけど臣クンはその時、すごく嬉しそうな顔で、俺だけを見つめて、笑ってくれた。…ように見えたのだ。
「…嬉しい。ありがとう」
口元に充てていたマイクをわざわざ手で覆って、臣クンは肉声だけを使って、そう言った。
「………」
俺は突っ立ったまま、その場で気絶した。…いや気絶したかどうかは定かじゃないんだけど、だってどう思い出そうとしてもこの時の記憶だけ曖昧なんだもん。キャパオーバーで脳みそが停止してたんだろう、当たり前だ。臣クンはやっぱり殺戮兵器だった。
トーク終了後、数曲の歌を披露してpolaroidのライブは終了した。ステージから三人が捌けて会場内が明るくなる。
俺は慌ててキャップを目深に直して、キンブレをリュックにしまった。この後は物販とチェキ。アレとアレとアレを買うことと、チェキは一回だけしようと心に決めてた。
物販はメンバー達本人がお会計をしてくれる。三箇所の会計列はどこも長蛇だったけど、やっぱり臣クンの列がちょっとだけ、一番長い。
ドキドキしながらその列に並んだ。できるだけ俯いて、誰とも目が合わないようにした。こういう時間のぼっち参加の心細さったらない。周りの楽しそうな会話に紛れて自分の喉が何度も「ゴク」って鳴るから、恥ずかしくて苦しくて仕方なかった。
物販の机がだんだん近づいてくる。臣クンとお客さんのやりとりが少しずつ見えてくる。臣クンはお客さん一人一人に、ありがとうの言葉と優しい笑顔をセットで送っていた。でもきっと、早く捌かないとこの後が押しちゃうんだろう。その対応は一律で淡々としているように感じた。
俺の前のお客さん達が一人また一人と会計を終えていく。一つ前のお客さんの時に緊張が最高潮になって、また心臓がキンキンと鳴り出した。臣クンの「ありがとう」がすぐ近くで聞こえる。もうすぐ俺がその「ありがとう」を直接受け取る番だ。どうしよう死ぬ考えただけで気絶しそうだ。
「お待たせしました」
臣クンの優しい声が物販の机越し、俺に送られた。緊張がメーターをぶち破って、頭のどこかから「ピー」というエラー音が鳴った。
「…あ、さっきの」
臣クンがそう言う。続けて「今日はありがとう」と言う。距離、およそ1メートル。俯いたまま固まった俺の目線は臣クンの胸あたりしか見てなくて、ああもうバカ俺のバカ動け喋れ「こちらこそ」くらい言え。
「……」
視界の先、臣クンが俺の顔を覗き込んできた。背の高い臣クンはわざわざ体を屈めて、俺と目が合ったことを確認すると「はは」って、歯を見せて笑った。
「はじめまして。伏見臣です」
はじめまして、七尾太一です。
「今日は来てくれてありがとう」
こちらこそありがとうございました。最高でした。
「どれを買いますか?」
これとこれとこれを買います。
う、嘘だろ。一つも声にならない。
「……」
後ろがつっかえてるし、臣クンにだって迷惑をかけてしまう。半泣きになりながら三回、これとこれとこれ、と指を刺した。臣クンは俺の差した三つを重ねて手提げビニールに入れると、優しい声で「××円です」と言った。
自然に動かせない体で財布の中から金を出そうとしたせいで、机の上に小銭をばら撒いてしまった。もう無理だ無理、もうやだ、バカ俺のバカ。
「………」
ぎこちない動きで小銭をかき集めようとしたら、100円玉をつまむ俺の手を、臣クンが上からそっと握った。
「っ…!!…!?……???……!?!?」
頭から煙が出てる気がした。機械の壊れる音がした。俺は間もなく爆発するんだと思った。
「…チェキで待ってるから」
「………」
「俺と撮って」
臣クンの声が、目が、握られた手が、まっすぐ俺の心臓を貫いた。臣クン以外の全てが視界から消えた。好きで、この人が好きで、誰にバカだって笑われてもいい。
俺は、好きの気持ちだけでもう、死んだっていい。
「……は、はい」
やっと動いた声帯、震える俺の声をちゃんと受け取って、臣クンは優しく、本当に優しく笑ってくれた。
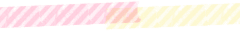
イベントの大トリ、いよいよチェキ撮影会。やっぱり一番長い臣クンの列に、俺は緊張しながら並んだ。券を購入する時、前の人も後ろの人も十枚以上買ってたからちょっとビックリした。一枚だけ、なんて、俺以外にはいなかったのかもしれない。
臣クンとツーショットのチェキなんて間違いなく家宝だ。受け取ったら持ってきたジップロックにすぐ入れて、クリアファイルに挟んでからリュックに丁寧にしまって、帰ったら自分の机の上に置くと決めてる。毎日見るんだ。それだけでこの先三年は幸せに暮らせる自信がある。
ポーズは、考えて考えて考え抜いた結果、一緒にピースしてもらうという無難なものに決めた。だってキツめのリクエストをして怪訝な顔をされたくない。隣に並ぶ、それだけで俺には有り余るほどの幸福だ。
並んで十分ちょっと、ようやく臣クンの姿が前方に見えてくる。お客サン達は予想通り、結構過激なリクエストをしてるみたいだった。肩を抱いてもらったりおでこをくっつけるなんてのは序の口で、すごい人はなんとお姫様抱っこで臣クンの首元に顔を埋めたりバックハグされながら臣クンにお尻を押し付けたりもしていた。す、すごい。なんて過激なんだ、それもみんなみんな可愛い。あ、さっきの地雷系のツインテの子。臣クンにハグされながら可愛い顔で指ハートしてる。すごい。あんなことされたら俺失神して撮られるどころじゃなくなっちゃうよ。
ちなみに臣クンは、いたって平静。穏やかな笑顔を崩すこともないし女の子の行動に動揺する素振りもない。こ、これがアイドル。これがメン地下。これがセンターたる貫禄。すごい。だってあんなにかわいい子が腕の中にいたら、俺は間違いなくフリーズする自信がある。
俺の前の人が、手を繋いで、空いてる方の手同士でハートを作るポーズを撮影した後、いよいよ俺の番がやってきた。心の中で拳をこれでもかと握る。さっきは一言も返せなかったんだ、まずは第一声「ありがとうございます」を臣クンに伝えるんだ。いいか俺絶対だぞ、絶対だ。
「次の方どうぞ」
臣クンの淡々とした声に促され、俺はいよいよ撮影ポイントとして示された白テープのバッテン印へと進む。臣クンは俺に気づくなり「あ」と言って、また嬉しそうに笑った。だめその笑顔見ると心臓が止まっちゃうよ。
「来てくれた。ありがとう」
「あっ、あ、あ…あの、あの、あのっ…」
「うん」
臣クンが優しく微笑む。もう俺たちの間にはステージも物販の机もない。もう気を抜いたら倒れそうだ、どこかに捕まりたい。アワアワウロウロと彷徨う両手に臣クンはすぐ気付いて、それから、強く握ってくれた。
「あっ…ひぇっ……あ、あっ…ありがとうございました!」
や、やっと言えた。言えた、やっと言えたよくやった俺。言えたことに安心した途端涙目になってしまって、臣クンの姿が滲む。だめだ、泣くな、早くリクエストしてササッと撮ってもらって、ササッと捌けなくちゃ。
「うん。俺もありがとう」
「……あ、あの、えと…」
「はは。まさかこれで終わり?指定して。ポーズ」
「あ、あ、はい、はいッス。あ、えっと、あの、ピース……」
「ピースだけ?」
「ひょ、あ、ピ、ピースだけ、そ、そうッス、ピースだけ」
ブンブン頷いて、震える手でピースサインを作る。ガチガチの顔面は笑顔を作れるわけない。もう俺の写りはどうでもいいんだ、早く終わらして早く捌けなきゃ。
「…それだけ?残念」
臣クンが俺にしか聞こえない声で、そう言う。え、ど、どういう意味。頭の中で臣クンの言葉の意味を咀嚼しようとした矢先、臣クンが唐突に俺の腰に手を回して体をグッと引き寄せた。
「名前は?教えて」
「へっ」
「名前。教えてくれないかな。後でチェキに書くから」
あ、お、俺の名前。俺の名前を聞かれてるのかそうか。そう、俺の名前。俺の名前は。腰に回った臣クンの手にちょっとだけ力がこもる。ダメ待って無理気絶する。
「たっ、なっ、なたぉっ、七尾太一ッス」
普段から何気なく使ってしまう「ッス」って語尾。ちょっと恥ずかしくて今日は封印しようって思ってたのにダメだ、出ちゃった。
「うん」
臣クンが俺の腰を抱いたまま、微笑む。ピースサインを作って撮影者であるスタッフさんが構えるチェキカメラの方を向く。臣クンはカメラを見つめながら、俺の顔に自分の顔を近づけた。
「…かわいい、たいちくん」
あ、ダメ。もう、ダメ。
シャッターが光って、俺の心臓はその瞬間に止まったんだと思った。ああ臣クンを好きな気持ちで死んじゃった俺。ああ思ってたよりずっと幸せ。棺桶にはこのチェキを一緒に入れてもらわなきゃ。
「終わりでーす」
スタッフさんの声でハッとして、俺の意識はなんとか現世に舞い戻った。慌てて臣クンに頭を下げて急いでその場から捌ける。危ない、いま立ったまま気絶してた。
撮影の合間合間、現像された写真に臣クンはサラサラとサインを書く。俺が撮影してから数分後、臣クンと俺のチェキは無事手元にやってきた。
『たいちくん、ありがとう。ふしみおみ』
流れるように書かれたマッキーペンの曲線に見惚れながら、俺はジップロックにしまってクリアファイルに挟んで、中で折れたりしないよう慎重に厳重にチェキをしまった。家宝を、ついに手に入れた。これで向こう三年の幸せが約束されたのだ。
会場を出る手前、最後に臣クンを振り返る。まだまだ列の途絶えないチェキ会、臣クンはやっぱり笑顔を崩さずお客さん一人一人といろんなポーズで撮影をしていた。
「………」
ちょっと遠い方が、じっと見つめていられることに気づいた。近くだと許容範囲を超えちゃって、そういや全然まともに見ることができなかったな。バカだ俺、チャンスは有限なのに。穴が開くほど見まくれば良かった。後悔を胸にしながら今焼き付けよう、臣クンの姿を。瞼の裏にいつでも思い描けるように。
たぶんその時、俺はよっぽど間抜けな顔をしてたんだろう。臣クンは撮影と撮影の一瞬の隙間、俺に気づくとおかしそうに笑った。
ヤバ、俺いま口開いてた。慌てて会釈して駆け足で会場の外へ出る。
階段を登り切って、通りの空気を吸い込む。肺の中に新しい風を目一杯送って、俺は薄暗い空を見上げた。
「……か、かっこよかった……」
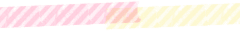
そして、あの日から三ヶ月。配信やSNS更新を全力で享受しながらpolaroidライブに足繁く通い、俺はポラーとしてほんのちょっとずつ成長していったのだった。
初めて行ったライブの日では考えられないほど前列に行けるようになったし、コールの時はずいぶん大きな声が出せるようになったし、キンブレの振り方も様になってきた。
それでチェキは、やっぱり今でも一回のライブにつき一枚っていうのをマイルールにしてる。何度も撮ってもらうのは気が引けるし、自分の後ろの人の待ち時間を少しでも減らしたかったからだ。
でも、絶対、一回。絶対に一回撮って、大切に持って帰る。
最初はピースサインをリクエストしていた俺も気づけばずいぶんと大胆になってしまったもんだ。今では指ハートをリクエストするほどに図々しくなった。信じられない快挙である。同性の俺がハートのリクエストなんて一歩間違えれば「キモい」に分類されちゃうかもしれないっていうのに、快くオッケーしてくれる臣クンはまさに神対応だ。しかも決まって「それだけ?」って言ってくれる。優しい。本当はパフォーマンスとチェキ会の長蛇の列に疲れているだろうに、俺の気分が良くなるように「残念だな」って言ってくれるのだ。
臣クンの優しいところが好きだ。かっこいいところも大好き。たまにステージの上ではにかむ照れ屋サンなところも大好き。もうマジで全部全部大好き。
誰がなんて言ったって、屁でもない。俺は出会ってからずっと恋のど真ん中にいる。
臣クンが好き。想いを込めて、ドキドキしながら、今日も俺はチェキの中に写る臣クンにキスをするんだ。