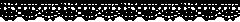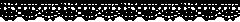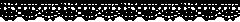
最初は確かに隣に並んで歩いていたはずで、なのに今はいつの間にかずっと前を歩く姿を見つめるだけ
なのに、どうして手を差し伸べるのか
キス一回で許してやる
(ありがとうか好きか)
「てことで、今日からお前は俺の彼女って事で」
顔だけなら童話の中の王子様も顔負けの幼なじみは、私からすればまるで死刑宣告のような事を、本当に嬉しそうに笑いながらそう告げた
それからまるで恋人同士がするように、自分の指を私の指に絡めて家へと歩いたその翌日
学校は私と健司の噂で持ち切りだった
健司のファンは有り得ない位に多い
何時呼び出されるのかと身構えていたら、昼休みに屋上へ呼び出しコール
「あんた藤真君の何?」
「何って・・・ただの幼なじみですけど」
そしてお決まりの言葉を吐かれる
怒りの篭った瞳は受けて気持ちが良いものじゃない
何で私の人生に、こうも藤真健司という男は関わってくるのだろう
(元はと言えば、健司がこうなる事を考えずに変な事を言い出すから!)
「ちょっと聞いてるの?!」
「あ、」
健司に対する怒りで、目の前の集団の存在をすっかり忘れてた・・・
私のそんな態度が気に食わなかったのか、顔を歪めるリーダー格の女の子
「あんたふざけてんの?!」
ヒステリックな声をあげて、続けざまに乾いた音が鳴る
頬に走る鈍い痛みで、自分が殴られたのだと理解出来た
「藤真君とさっさと別れなさいよ」
(こっちは健司のジャイアニズムのせいで、友達とは遊べないし、こんな目にまであってるのに!)
理由なく殴られてやる義理はないし、やり返そうと手を振り上げる
・・・・・・でもそれが出来なかったのは
「おい、何やってんだよ」
地を這うように低い健司の声が聞こえたから───
健司の眉間に寄せた皺と、その瞳が怒りを表していた
「藤真君、ち、違うの!」
「うるせぇ、さっさと失せろ」
女の子達の弁解を遮って、顔も見たくねぇ、と吐き捨てるように告げる健司に、女の子達は今にも泣きそうな顔をしつつも驚いている
(無理もないか、健司は翔陽の王子様だったんだから)
逃げるように去っていく健司のファンの子達の足音だけが、やけに大きく感じた
「もうやだ・・・」
全身の力が抜けて、その場に座り込む
「おい、名前大丈夫か?」
同じように健司もしゃがみ込んで、紅くなっている私の頬に手を添えた
「あー、紅くなってんな」
痛い?だなんて珍しく優しい健司と、頬に添えられた健司の細く長い指先がらしくなくて笑えて
「何だよ」
「別に」
相変わらずの不器用な優しさが嬉しい
「・・・なぁ、」
「何?」
少しの沈黙の後で、先に口を開いたのは健司の方
続きを促せば、真剣そうな瞳と目が合った
「助けてやったよな?お前のせいで、俺が今まで守り続けて来たイメージがパーなんだけど」
「なっ!」
真剣そうな顔で何を言い出すかと思えばそんな事を・・・
こうなったのも健司のせいじゃん!、と返そうとしたけど
「そうだよな?」
「・・・はい」
そんな事を言ったら後から何されるかわからない
渋々認めると、ニヤリと健司が笑う
「名前のせいで、俺の長年の努力が水の泡だしなー」
「・・・」
「てなわけでキス一回で許してやる」
(心配して見に来た、何て言えるかよ。なぁ、名前、早くしろよな。言葉より態度で示せって言うだろう?)
Title:確かに恋だった
END
←