まだ俺が国の王子だったころ、2年間くらい、パーティ用の踊りを教えられていたことがある。大会に出るわけじゃないし、所詮簡単なステップだけの踊りとは呼べなさそうなものだった。俺もジルも先生に教えられたことは1週間もあれば確実にモノに出来たし、何か鍛えたりすることも必要とされてはいなかったから1年でひととおりのステップと身のこなしは覚えてしまった。残りの1年は国の至る所のお嬢様と練習がてら踊ってみるだけ。毎回レッスンが終わるたび、あいつはこのステップが下手だとか靴踏まれただとか、ジルといわゆる悪口を言い合ってお嬢様を笑い者にしては暇つぶしをしていた。踊りってまあそんなもんだと思っていた。 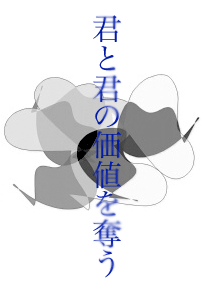 あるパーティに潜んでいる踊り子の女を殺せという任務だった。彼女はある大きなファミリーに入り込んだスパイらしく、もうじきファミリーを抜けて情報を持ち去るだろうという危惧による任務だった。運悪く一番任務の少なかった俺にその仕事が回ってきた。今日は扉を開けるのも廊下を歩くのも正直面倒ごとがついて回る日だから、外に出れるだけまあマシだと思った。「誕生日任務」だとかいう変な名前をつけてオカマは俺の口にケーキを詰め込むと、「早く帰ってらっしゃ〜い!」という無駄に大きな声で俺を屋敷の外へ突き飛ばした。俺は、誕生日のくせに災難だけ振りかけやがってと舌打ちをすると資料を一通り見、まあ1時間が妥当だなと適当にあたりをつけた。目をつぶってでも出来そうな任務だった。行きの車の中で大きな欠伸をして一眠りした。それくらいどうでもいい任務だった。 会場は思ったより広く、明るく、陽気だった。端で様子を伺おうと思っていたが何しろ明るすぎて「端」がない。頭の隅のほうで何かがちくりとしたが気づかない振りを決め込んだ。諦めてぶらぶらと会場の中を回った。ボーイに渡されたシャンパンはまだひと口も飲んでいない。景気のいいファミリーだ。なんとなく、なんとなくあの城を思い出すから気分が悪かった。早く殺してここを出よう、と、楽屋へと続く廊下の扉へ近づいたときだった。 それは本当にうっすらとしたミニマルミュージックだった。俺がそれに気づいたのは俺が暗殺者だからではなかった。どこかで聴いたことのある音楽だったのだ。 はじめは誰も気がつかなかった。俺がステージへ目をやると、俺の側で談笑していた腹の出たおっさんがちらりとステージを見ただけだった。俺は自分の中で何かが思い出されそうなもどかしさを感じた。鑑賞会で聴いたわけでもない、どこかのパーティで聴いたわけでもなかった。勿論あのダンスの練習でも… ステージの黒幕からはだしの女が出てきたとき、俺の心臓は一瞬止まった。ダンスで聴いたんだ。あの退屈なダンスじゃなくて、俺が最初で最後に見た、コンテンポラリーだった。 女はまずゆっくりとステージを歩いた。会場は徐々にステージに釘付けになっていった。ゆっくりとした歩みが曲とともに速くなり、またゆるやかになり、そして自然な流れで彼女は前を振り返った。そのとき会場は水を打ったように静かになり、ほんのりと音楽が踊りに合わせて流れているだけになった。 俺はあいつを殺すのか。 この会場にはおそらく3000人以上の人間が居て、多分ステージから一番離れた位置からは、彼女の顔なんて殆ど見えないだろう。だけど皆ステージから目が離せなかった。彼女は何をも恐れずに宙を舞った。 俺はあいつを殺すのか? 俺にあいつを殺す権利があるんだろうか? 昔から美術とか音楽とかは全部ただの暗記科目だと思っていた。教養、その二文字で片付けられる膨大な知識はただ詰め込めばいいものだとばかり思っていた。だけどこの踊りはあの頃と変わらず俺を真っすぐに貫いた。あのとき見た踊り子は誰だっけ。確かあの国の人間で、革命軍の反乱に巻き込まれて死んだという話を聞いた。あの踊りをもう一生見ることが出来ないんだとその晩自然と涙が出た。そのくらいあの踊りは俺の中で印象強く刻み込まれている記憶だった。そして今目の前で舞っている彼女はその佇まいを思い出させた。 ミニマルミュージック、曲は単調だった。しかし踊りには波があり、盛り上がりがあった。俺ははっとして後ろを振り返ると、3000人がゆっくりと横に揺れていた。ばらばらとした動きだった。僅かな動きだった。“みんな踊っている”。俺はまたステージへと視線を戻した。 踊りが終わった時、3000人は誰からでもなく美しい拍手を彼女に送った。彼女は一礼するとさっとはけていった。俺はシャンパンを置いて楽屋へ向かう。シャンパンに映った俺の顔はただの観客だった。 「なあ、お前本当にスパイなわけ?」 楽屋で髪飾りを外した女は首を傾げて笑った。 「さあね。踊ったら忘れちゃった」 「俺お前を殺しにきたんだけど」 「正直ね」 彼女は腕を組んでまた笑った。そして一息置いて、 「ねえベルフェゴールくん、覚えてない?」と口の端を持ち上げた。 「は?」 「…覚えてないのね。私の母もダンサーだっていったら思い出すかしら?」 俺がさっきまで見入っていた女は、昔ダンスの練習で俺の靴を蹴りまくり踏みまくった女だった。貴族だった彼女らが何故ここでこんなことをしているかといえば全て俺のせいだった。俺が国をぶっ壊したせいだった。俺は無理矢理に笑った。 「ぜーんぜん」 「そう」 彼女はそれに対しては特に言及しなかった。寂しそうに眉を下げる以外はなにも表さなかった。 「そういえば王子様、あなた今日が誕生日じゃなくて?」 「…あー、そうかも」 突然の話題に間抜けな声が出た。くすくすと女が笑った。 「何か欲しいもの言ってみなさいよ。私の命だけかしら?」 「…、死ぬ前にもう一回だけ踊って」 楽屋の向こう側ではまた新たなパフォーマーがステージを賑わせていた。彼女は一歩一歩俺へと近づくと、俺の手を柔らかく握った。そしてこう囁いた。 「私はもう踊ってるわ。 そしてあなたも踊ってるのよ。人間は生まれた時からずっと踊ってるの」 20111222 ごめんなさい(訳:王子誕生日おめでとう) |